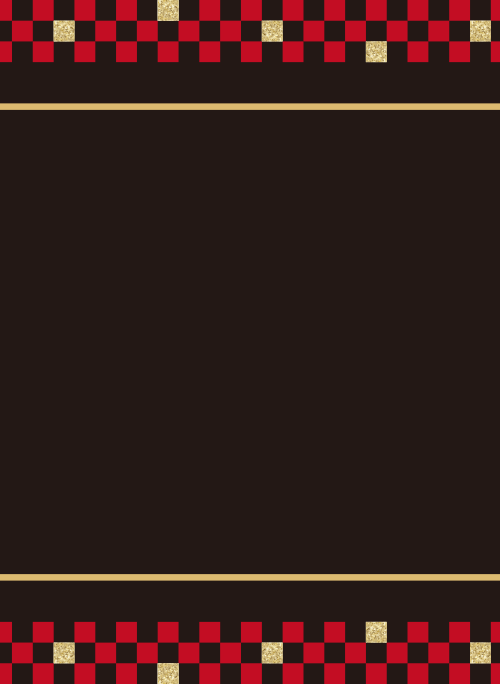名医は、馬であろうと一撃で眠らせるらしい。獏は癪(しゃく)だったが、ひそかに舌を巻いた。
それから、酒で傷口を洗う。薬草をあれこれすり鉢で混ぜ合わせ、それを傷口に塗ると、針と糸で縫合した。
先程の縫い口とは比べ物にならない、美しい縫い目だった。
仙人は無駄(むだ)のない動きであっという間に完成させると、「他に怪我してる場所もみてやるよ」と娘の腰帯を解く。
獏はこの場にいないほうがいいと察すると、戸で隔てられた隣の部屋へ向かう。・・・が、「なんじゃこりゃ!」と仙人が叫ぶので、思わず引き返してしまった。
「どうした」
「どうしたもこうしたもねぇよ。おまえ、この子をどこから拾ってきた? 家畜よりひでぇあつかい受けてたみてぇだ、笞(むち)でこんなに殴るなんて!」
獏はそっと覗き込み、息を呑んだ。
娘の背には、おびただしいミミズ腫れの後が広がっていた。中には皮膚が裂け、血が滲んでいるものもある。
暴行を受けたのは最近ではないらしい。殴られたままろくに治療も受けず治ってしまった数々の古傷は痛々しく、胸をえぐられるような光景だった。
獏のこころが、ドクンと脈打つ。同時に、あの日泣いていた本当の理由が、手にとるようにわかった。小柄な背中は痩せ細り、風で吹き飛ばされそうなほどだというのに。どうしてこんなことができるのか。
立ちすくむ獏にかまわず、仙人は「クソッタレが!」と吐き捨てた。
小さな拳を震わせ、怒りに任せた視線を獏にぶつける。
「おい、このまんまなにも報復しない、なんてことねえだろな!?」
なかば脅しじみた口調で問う。
獏は無言のまま考えた。
あのとき、娘の顔の痣が気になって、声をかけた時。
あの花がほころぶような、いじらしく愛おしい笑顔が、脳裏をよぎる。
硬い岩場に打ち捨てられ、無惨に雨に打たれていたところも。
それから、娘が自分に抱きつき、大声で泣いた姿が、鮮明によみがえった。
(この娘を、人の命を、何だと思っている!)
――このままでは終わらせない。
獏はしばしの無言の後、厳かに言った。
「――私が、手を下す」
それは事実上の、村人たちへの死刑宣告だった。
獏を怒らせれば、命はない。人間どもは超えてはならない一線を越えた。人の命をもて遊び、たやすく奪った神罰が、下されたのだ。
仙人は「それでこそだぜ!」と朗(ほが)らかにいった。
それから、酒で傷口を洗う。薬草をあれこれすり鉢で混ぜ合わせ、それを傷口に塗ると、針と糸で縫合した。
先程の縫い口とは比べ物にならない、美しい縫い目だった。
仙人は無駄(むだ)のない動きであっという間に完成させると、「他に怪我してる場所もみてやるよ」と娘の腰帯を解く。
獏はこの場にいないほうがいいと察すると、戸で隔てられた隣の部屋へ向かう。・・・が、「なんじゃこりゃ!」と仙人が叫ぶので、思わず引き返してしまった。
「どうした」
「どうしたもこうしたもねぇよ。おまえ、この子をどこから拾ってきた? 家畜よりひでぇあつかい受けてたみてぇだ、笞(むち)でこんなに殴るなんて!」
獏はそっと覗き込み、息を呑んだ。
娘の背には、おびただしいミミズ腫れの後が広がっていた。中には皮膚が裂け、血が滲んでいるものもある。
暴行を受けたのは最近ではないらしい。殴られたままろくに治療も受けず治ってしまった数々の古傷は痛々しく、胸をえぐられるような光景だった。
獏のこころが、ドクンと脈打つ。同時に、あの日泣いていた本当の理由が、手にとるようにわかった。小柄な背中は痩せ細り、風で吹き飛ばされそうなほどだというのに。どうしてこんなことができるのか。
立ちすくむ獏にかまわず、仙人は「クソッタレが!」と吐き捨てた。
小さな拳を震わせ、怒りに任せた視線を獏にぶつける。
「おい、このまんまなにも報復しない、なんてことねえだろな!?」
なかば脅しじみた口調で問う。
獏は無言のまま考えた。
あのとき、娘の顔の痣が気になって、声をかけた時。
あの花がほころぶような、いじらしく愛おしい笑顔が、脳裏をよぎる。
硬い岩場に打ち捨てられ、無惨に雨に打たれていたところも。
それから、娘が自分に抱きつき、大声で泣いた姿が、鮮明によみがえった。
(この娘を、人の命を、何だと思っている!)
――このままでは終わらせない。
獏はしばしの無言の後、厳かに言った。
「――私が、手を下す」
それは事実上の、村人たちへの死刑宣告だった。
獏を怒らせれば、命はない。人間どもは超えてはならない一線を越えた。人の命をもて遊び、たやすく奪った神罰が、下されたのだ。
仙人は「それでこそだぜ!」と朗(ほが)らかにいった。