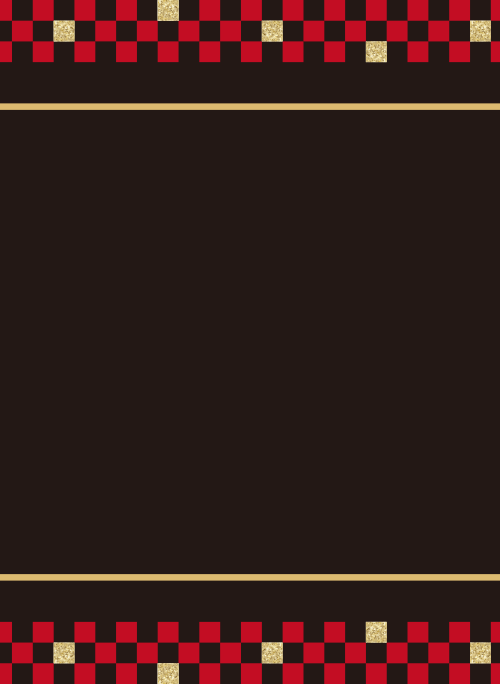豪雨は死者の憎しみを煽(あお)るように、麓の村へふりそそぐ。
白い衣を身にまとう女の遺体は、ぽつんと現場に残されていた。
もう誰も戻ってこない。
だれも娘をさがさない。
そのうち彼女の存在は人々の誰からも忘れ去られるのだろう。
――だがひとり。彼女を案ずる男がいた。
獏は清水村へ降りていた。
今夜も蛍の泉で待っていたが、待てども来なかったのだ。
我ながら滑稽(こっけい)だと思うが、どうにも気になって、村へ行ってみたのだった。
ほとんどの民家は留守だった。
村人総出で、なにか大事が起きているのか。
――『五年に一度、生贄を求めて・・・』
娘の言葉。
嫌な予感が頭をよぎる。
「お助けくださいっ!!」
と叫ぶ女の声がした。
獏ははっとして振り返った。
奴婢なのだろうか。あの娘と同じ汚れた服を着ている。
女は山へ向かってふらふらと、でも必死になって向かっていた。
「その娘はわたしの子なの! お嬢様じゃないのよ!!」
――わたしの子?
獏は瞬時に悟った。この女人はあの娘の母親か。
急ぎ事情を聞くと、獏の推理はあたっていた。
危惧したことが現実になってしまったことも。
獏は天界から従者を呼んだ。
母親をあずけ、みずから探しに出る。
もう少しはやく気づいていれば。
獏は歯噛みする。
今神輿はどこまで進んだのだろう。まだたどり着いていないことを切に願う。
――だが、希望は粉微塵(こなみじん)に砕け散った。
「遅すぎた・・・」
獏は娘の遺体の前で立ちすくんだ。
白い布は血で染まっている。
冷たくなった頬は雨にうたれ、つるりと青白い。
投げ捨てられた血のついた小刀。
殺され、谷底へ落とされた男の血は、雨で薄められてはいるが、ただならぬ不気味な余韻を残していた。
事故がおきたのか。
殺害されたのか。
今は、普段のように冷静に判断することは難しかった。
獏は、白い袖が泥に汚れるのも構わず、膝をつく。
娘のきゃしゃな体を抱き起こした。
ちいさな手をにぎる。
「・・・つめたい」
青白い頬。
あのふわりとわらう顔とは、似ても似つかなかった。
獏はガッと拳で岩の地面を殴りつけた。拳から血が滲み、雨に溶かされてゆく。
「――私は・・・・・・・・・!」
もういちど、娘の笑顔が見たかった。
ただそれだけ。
それだけだったのに。
――自分とかかわった女性は、皆、不幸になってしまう。
白い衣を身にまとう女の遺体は、ぽつんと現場に残されていた。
もう誰も戻ってこない。
だれも娘をさがさない。
そのうち彼女の存在は人々の誰からも忘れ去られるのだろう。
――だがひとり。彼女を案ずる男がいた。
獏は清水村へ降りていた。
今夜も蛍の泉で待っていたが、待てども来なかったのだ。
我ながら滑稽(こっけい)だと思うが、どうにも気になって、村へ行ってみたのだった。
ほとんどの民家は留守だった。
村人総出で、なにか大事が起きているのか。
――『五年に一度、生贄を求めて・・・』
娘の言葉。
嫌な予感が頭をよぎる。
「お助けくださいっ!!」
と叫ぶ女の声がした。
獏ははっとして振り返った。
奴婢なのだろうか。あの娘と同じ汚れた服を着ている。
女は山へ向かってふらふらと、でも必死になって向かっていた。
「その娘はわたしの子なの! お嬢様じゃないのよ!!」
――わたしの子?
獏は瞬時に悟った。この女人はあの娘の母親か。
急ぎ事情を聞くと、獏の推理はあたっていた。
危惧したことが現実になってしまったことも。
獏は天界から従者を呼んだ。
母親をあずけ、みずから探しに出る。
もう少しはやく気づいていれば。
獏は歯噛みする。
今神輿はどこまで進んだのだろう。まだたどり着いていないことを切に願う。
――だが、希望は粉微塵(こなみじん)に砕け散った。
「遅すぎた・・・」
獏は娘の遺体の前で立ちすくんだ。
白い布は血で染まっている。
冷たくなった頬は雨にうたれ、つるりと青白い。
投げ捨てられた血のついた小刀。
殺され、谷底へ落とされた男の血は、雨で薄められてはいるが、ただならぬ不気味な余韻を残していた。
事故がおきたのか。
殺害されたのか。
今は、普段のように冷静に判断することは難しかった。
獏は、白い袖が泥に汚れるのも構わず、膝をつく。
娘のきゃしゃな体を抱き起こした。
ちいさな手をにぎる。
「・・・つめたい」
青白い頬。
あのふわりとわらう顔とは、似ても似つかなかった。
獏はガッと拳で岩の地面を殴りつけた。拳から血が滲み、雨に溶かされてゆく。
「――私は・・・・・・・・・!」
もういちど、娘の笑顔が見たかった。
ただそれだけ。
それだけだったのに。
――自分とかかわった女性は、皆、不幸になってしまう。