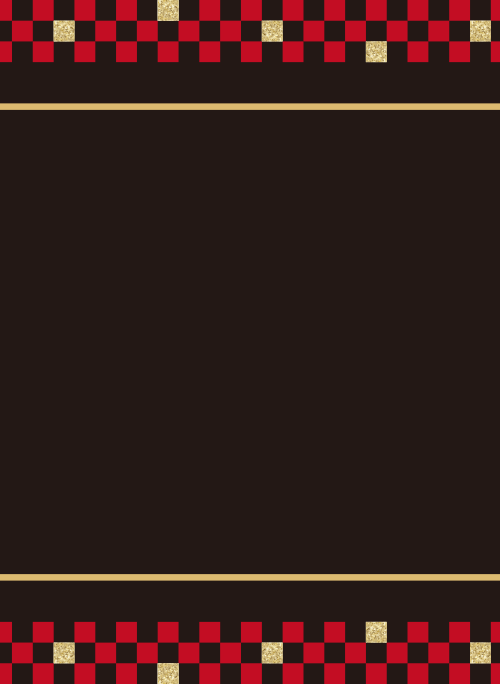奴婢(ぬひ)の娘は、裸足で夜の深い森の中を駆けていた。手には体より大きな壺が重そうに握られている。お仕えするお嬢様が突然、山の湧き水が飲みたいと駄々をこねたのだ。
今は真夜中。しかし断れば、きつい折檻(せっかん)をされる。
やむなく、月明かりを頼りに、獣が潜む危険な山道を行くはめになった。
娘は骨が浮き出るほどに痩せこけていた。髪にも顔にも泥がこびりつき、ぼろ雑巾のような一枚の布で体を隠している。泥や草の露の他にも、よく見れば血液のようなものすら混じっていた。
昨日から、まともな食事にありつけていない。村では宴(うたげ)が開かれ、奴婢たちは寝る間もなくこき使われている。
豪勢な食事も、酒も、すべて用意したのは奴婢たちだが、手をつけることは許されていない。
酒や雑談に夢中な村長たちはのんきなもので、奴婢の一人や二人、のたれ死んでもかまわないとすら思っているだろう。
奴婢は名前を付けることすら許されていない。
壺を抱えてひた走るこの娘には、名前がなかった。
生まれた時から奴婢だったこの娘は、自由の意味すら知らないのだ。
――無論、恋など、生涯無縁のはずだった。
無愛想なカタブツ幻獣と、ばったり出会うまでは。
森の奥深く、ぽっかりと空いた泉の淵に鎮座する岩。そこに男が腰掛けていた。
「っ」
娘は一瞬、妖怪が出たのかとたじろいだ。
それも無理はない。男は、夜の闇の中、淡い光を帯びていたからだ。
「にん、げん・・・?」
娘は食い入るように見つめる。
男は、ゆったりとした真っ白な異国の袍(ほう)を身にまとい、腰に翡翠(ひすい)の佩玉(はいぎょく)と金の鋏を挿した革袋をさげていた。
よく見れば袖に呪詛(じゅそ)のような文字が銀の糸で細かく刺繍(ししゅう)されている。
彼はゆっくりと、娘の方へ視線を投げた。
ふわり、短い黒髪がゆれる。
男の白銀の瞳と娘の目が、ぱちっとあった。
「・・・人間の小娘か」
抑揚のない声で彼は言った。
顔周りの髪を顎のあたりで切りそろえている。二十歳そこそこのようにも見えるが、感情の一切を封じ込めたような無表情は冷ややかだ。
恐ろしいほど冷静沈着に、目の前の娘をとらえていた。
妖怪か。はたまた神様なのか仙人なのか。娘はごくりと息をのんだ。
どちらであれ、見つかってしまった。妖怪であれば喰われてしまうし、神様であれば・・・・・・どうなるか見当もつかない。
しかし男が娘に興味を示したのは一瞬だった。
ふいと視線をそらされる。まるで野良猫を相手にしているようだ。
いてもかまわないし、邪魔しなければ危害を加えない。そう言っているようだった。
娘はほうと息を吐いた。どうやら死なずにすむらしい。
だが、この泉の水は汲んで帰らねば。
痛いほどの沈黙。
森の木々の葉をぬるい風が抜けた時、娘は意を決し口を開いた。
「あのっ。こ、この水を少しいただいても、よろしいでしょうかっ?」
緊張でうわずった声がでた。顔を真赤にして返事を待つ。
彼は無言だった。こちらを気にする風でもない。
(これは、了承、と思ってもいいんだよね?)