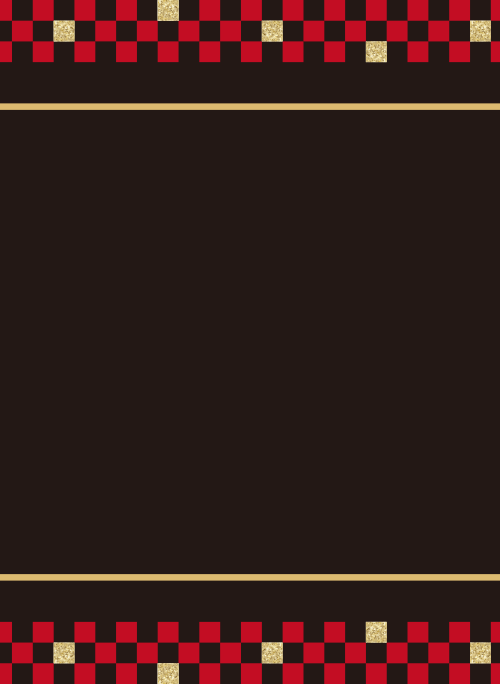「あの奴婢は、私と歳も背格好も対して変わらないわ。彼女には悪いけど、私の身代わりになってもらうのはどうかしら?」
『死』が宣告された。
あぁ・・・。やっぱり。
体から五感が消失していく。
こうなる日が来るのを、心の何処かでわかっていた。それは先日、村長に笞(むち)で打たれたのだって。
咲紀は賢い娘なのだ。
ただ奴婢をいじめるためだけに、宴を台無しにしたわけじゃない。
人々の前で命を助けることで、村人へ慈悲深い印象をあたえるとともに、奴婢に貸しを作り、いざという時の捨て駒にするつもりだったのだ。
さっきのうろたえぶりから察するに、白羽の矢までは予測できなかったようだが、いつか有事の際にいつでも身代わりにできるよう、日頃から気を配っていたに違いない。
それがたまたま、今日だった。
(わたしは、いつの日か殺されるために、咲紀に生かされていた・・・・・・)
はは、と乾いた笑いが口から漏(も)れた。
自嘲(じちょう)とも違う。
無論、咲紀を称賛しているわけでもない。
己の運命を、こんな小娘におもちゃにされた。それが妙に笑えてしかたがない。
それに気づかず、村人たちは意見が真二つに割れていた。
「村長! いくら娘が可愛いからって、それはだめだ!」
「そうよ、天罰(てんばつ)が降り掛かってきたとき、あなたは責任を取れるのですか!?」
「みんな、身を裂く思いでこれまで生贄を捧げてきたんだ。自分だけ助かろうなんて、虫が良すぎる!」
反対の意見。
しかし、咲紀に思いを寄せる若い男たちは違う。
さっきまで他人のふりだったのが嘘のよう。急に咲紀を擁護(ようご)しはじめた。
「この奴婢は、咲紀に命を救ってもらった恩があるはずだ!」
「奴婢の一人や二人、死んだってかまわねぇだろ!?」
奴婢の命は、塵(ちり)よりかるい。
いつか言われた村長の言葉だ。
幼い頃から犬のように何度も〈躾(しつけ)〉されてきた。逆らわぬよう、〈言葉の首輪〉で繋(つな)がれて。
その手綱(たづな)を握るのは、決まって咲紀たち親子だった。
(わたしは、人間ですらないのか・・・?)
娘はひそかに拳(こぶし)を握る。
手が震えた。
悲しみのせいか。
それとも、噴き出すどす黒い殺意をこらえているのか。
そして若者の、最後の一言が決定的となった。
『死』が宣告された。
あぁ・・・。やっぱり。
体から五感が消失していく。
こうなる日が来るのを、心の何処かでわかっていた。それは先日、村長に笞(むち)で打たれたのだって。
咲紀は賢い娘なのだ。
ただ奴婢をいじめるためだけに、宴を台無しにしたわけじゃない。
人々の前で命を助けることで、村人へ慈悲深い印象をあたえるとともに、奴婢に貸しを作り、いざという時の捨て駒にするつもりだったのだ。
さっきのうろたえぶりから察するに、白羽の矢までは予測できなかったようだが、いつか有事の際にいつでも身代わりにできるよう、日頃から気を配っていたに違いない。
それがたまたま、今日だった。
(わたしは、いつの日か殺されるために、咲紀に生かされていた・・・・・・)
はは、と乾いた笑いが口から漏(も)れた。
自嘲(じちょう)とも違う。
無論、咲紀を称賛しているわけでもない。
己の運命を、こんな小娘におもちゃにされた。それが妙に笑えてしかたがない。
それに気づかず、村人たちは意見が真二つに割れていた。
「村長! いくら娘が可愛いからって、それはだめだ!」
「そうよ、天罰(てんばつ)が降り掛かってきたとき、あなたは責任を取れるのですか!?」
「みんな、身を裂く思いでこれまで生贄を捧げてきたんだ。自分だけ助かろうなんて、虫が良すぎる!」
反対の意見。
しかし、咲紀に思いを寄せる若い男たちは違う。
さっきまで他人のふりだったのが嘘のよう。急に咲紀を擁護(ようご)しはじめた。
「この奴婢は、咲紀に命を救ってもらった恩があるはずだ!」
「奴婢の一人や二人、死んだってかまわねぇだろ!?」
奴婢の命は、塵(ちり)よりかるい。
いつか言われた村長の言葉だ。
幼い頃から犬のように何度も〈躾(しつけ)〉されてきた。逆らわぬよう、〈言葉の首輪〉で繋(つな)がれて。
その手綱(たづな)を握るのは、決まって咲紀たち親子だった。
(わたしは、人間ですらないのか・・・?)
娘はひそかに拳(こぶし)を握る。
手が震えた。
悲しみのせいか。
それとも、噴き出すどす黒い殺意をこらえているのか。
そして若者の、最後の一言が決定的となった。