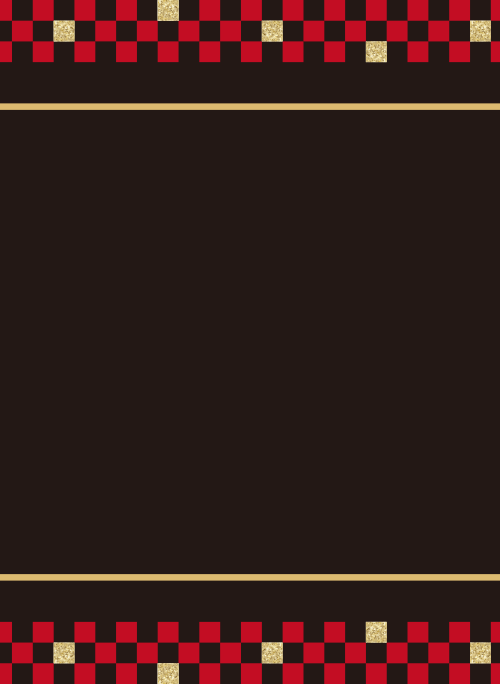この風習は百年もの間、続いていた。
拒めば、村は洪水に襲われると伝承されている。
そして今回、村長の娘に白羽の矢が立った。大蛇が咲紀を気に入り、欲しているのだ。
「いやぁっ! ねえ、お父さま! なんとかしてよ!」
咲紀は髪を振り乱し、半狂乱(はんきょうらん)で父の裾にしがみつく。
「咲紀・・・」
「私を差し出したりしないでしょう!? そうよね?」
父親は、ぐったりと肩を落としていた。まさか想像もしていなかっただろう。手塩にかけた娘を、生贄に出すはめになるなんて。
親子を取り囲む村人は、ヒソヒソと、しかし聞こえるようにしゃべる。
「大蛇さまの神託(しんたく)は絶対だ。破ったらどんな災が降りかかるか!」
「この前は、村一番の美人だったよな? あれも家族が可愛そうだった・・・」
「咲紀さまはお美しい。大蛇さまがお気に召すのも当然だね」
「村長には悪いが・・・、村を救うためだ。致し方ねえ」
・・・・・・つめたい人たち。
奴婢は、心のなかで、ぽつりとつぶやいた。
普段から、咲紀を称賛するものは多い。
気立てがいいとか。美人だとか。
輪をかけて村長の娘だから、求婚者は引きも切らない。それが咲紀の取り繕(つくろ)ってきた仮面だとしても。
今はどうだ。
求婚してきた男どもは皆、誰も父親に懇願しようとしない。
己の身を危険にさらしてまで咲紀を愛する度胸が、なかったということだ。
死にたくない咲紀は、歯を食いしばり、天を睨(にら)み殺さんばかりに呪っていた。
だがそんな姿を見ても、奴婢の娘は心が晴れない。
嫌な予感は増すばかりだ。
「そうだわっ! お父さま、思いついたわ!」
とつぜん、それまで絶望に打ちひしがれていた咲紀が、手を叩いた。
「名案があるのか!?」
父親は食い入ってその肩を抱く。
咲紀は生気を取り戻し、美しい唇を歪めた。蛇のような笑みだ。いや、蛇よりも恐ろしいかもしれない。
女は、たっぷりと妖艶(ようえん)な笑みを浮かべると、父親に腕を絡ませた。
「――――・・・っ!」
あろうことか、その視線は、こちらへ向いている。
(わたし、を、見ているの・・・?)
嫌な脂汗がでた。
ゆっくり時間をかけて頬をすべり落ちる。
それは、まるで神託のように。
咲紀は娘を、まっすぐ指さした。
拒めば、村は洪水に襲われると伝承されている。
そして今回、村長の娘に白羽の矢が立った。大蛇が咲紀を気に入り、欲しているのだ。
「いやぁっ! ねえ、お父さま! なんとかしてよ!」
咲紀は髪を振り乱し、半狂乱(はんきょうらん)で父の裾にしがみつく。
「咲紀・・・」
「私を差し出したりしないでしょう!? そうよね?」
父親は、ぐったりと肩を落としていた。まさか想像もしていなかっただろう。手塩にかけた娘を、生贄に出すはめになるなんて。
親子を取り囲む村人は、ヒソヒソと、しかし聞こえるようにしゃべる。
「大蛇さまの神託(しんたく)は絶対だ。破ったらどんな災が降りかかるか!」
「この前は、村一番の美人だったよな? あれも家族が可愛そうだった・・・」
「咲紀さまはお美しい。大蛇さまがお気に召すのも当然だね」
「村長には悪いが・・・、村を救うためだ。致し方ねえ」
・・・・・・つめたい人たち。
奴婢は、心のなかで、ぽつりとつぶやいた。
普段から、咲紀を称賛するものは多い。
気立てがいいとか。美人だとか。
輪をかけて村長の娘だから、求婚者は引きも切らない。それが咲紀の取り繕(つくろ)ってきた仮面だとしても。
今はどうだ。
求婚してきた男どもは皆、誰も父親に懇願しようとしない。
己の身を危険にさらしてまで咲紀を愛する度胸が、なかったということだ。
死にたくない咲紀は、歯を食いしばり、天を睨(にら)み殺さんばかりに呪っていた。
だがそんな姿を見ても、奴婢の娘は心が晴れない。
嫌な予感は増すばかりだ。
「そうだわっ! お父さま、思いついたわ!」
とつぜん、それまで絶望に打ちひしがれていた咲紀が、手を叩いた。
「名案があるのか!?」
父親は食い入ってその肩を抱く。
咲紀は生気を取り戻し、美しい唇を歪めた。蛇のような笑みだ。いや、蛇よりも恐ろしいかもしれない。
女は、たっぷりと妖艶(ようえん)な笑みを浮かべると、父親に腕を絡ませた。
「――――・・・っ!」
あろうことか、その視線は、こちらへ向いている。
(わたし、を、見ているの・・・?)
嫌な脂汗がでた。
ゆっくり時間をかけて頬をすべり落ちる。
それは、まるで神託のように。
咲紀は娘を、まっすぐ指さした。