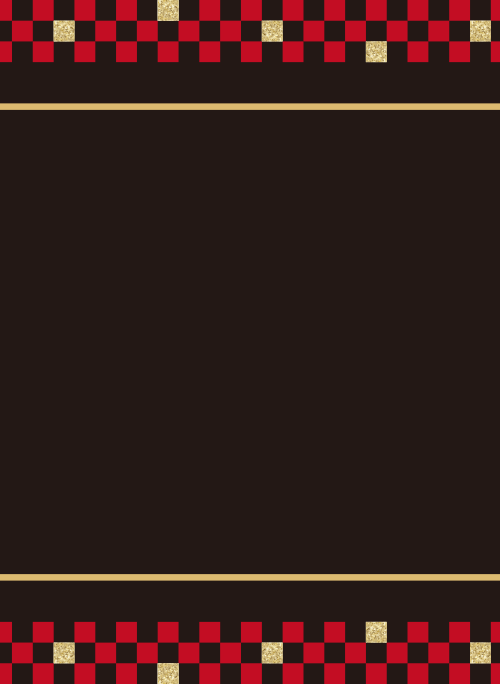深夜。
夢夜は獏の私室を訪れた。いや、例のごとく狐牡丹に連れてこられたのだ。
怪我を負わせた手前、彼女に頭が上がらない夢夜は、おとなしく従う。
獏も、いつも通り寝台から離れた場所で茶を飲んでいた。
「・・・・・・」
ちょっと手を止めて、獏はちらりと娘を見た。
「・・・なんだ、その物欲しげな顔は」
獏は夢夜のじっとりとした視線に気づいたらしい。やや警戒しながら逆に睨み返す。
「ご用はないですか」
「ないな」
「・・・帰っちゃいますよ」
「帰らぬのか」
獏は湯呑をことりと置いた。夢夜は懲りずに言う。
「さみしくなりますよ、一人枕を濡らしますよ?」
「添い寝は結構だ」
獏は立ち上がると、つかつかと距離を詰め、夢夜を追い出しにかかった。
ぐいぐい背を押す。
「年頃の娘が、はしたない。節度を持ちたまえ」
「やだっ。ここにくるまで、どれだけ勇気が必要だったと思っておられる・・・の、で・・・?」
あらがう娘は急にこちらを振り向く。・・・いきなり、ぱちりと絡まる互いの視線。
間近に息がかかるほど迫った互いの距離。
窓からは青白い月光とやわい風がふわり舞い込む。その風にのって、娘の体から湯上がりのいい香りがほわりと香ってきた。
あとすこし、あと一歩踏み出せば確実に唇が触れる距離。昼間とはまったく違う娘の美貌に獏は目を見開いた。
夢夜はそっと目を閉じる。
この意味を、わからぬはずがない。
獏はごくりと息を呑んだ。
その手には乗らん。乗るものか。自分はあくまでも紳士でありたいのだ。
だいいち、天上界で生まれ育った獏は、美人など見慣れている。天女たちは咲き乱れる花のよう、めいめいの美しさを持っているのだ。
だというのに。
夢夜はそのどの花たちとも当てはまらない。髪の色が変わっても、夢夜は変わらず輝きを失わない。
(・・・私にとって、この娘は特別な華なのか・・・)
今さら、そんな当たり前のことに気づくとは。我ながら間抜けだ。
一拍。
二拍・・・。
とくんとくんと、鼓動は急かすように。
ごくり、つばを飲み下した。