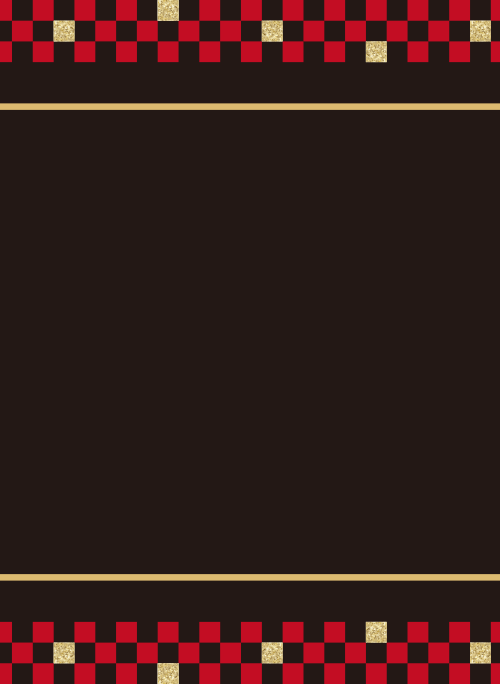ぷつん、と。
「あ・・・」
譲葉は崩れ落ちるように倒れた。その体を獏は支える。
彼女はことんと、眠りに落ちていた。土気色だった唇には色が戻り、落ち着いた呼吸をしている。
獏は彼女を地面におろし、膝に抱えると、その額に唇を寄せた。
これは最後の口づけ。
もう触れることも許されない、愛するひとへの、見送り。
「ずっと言いたかった。君のことが、好きだ」
しょっぱい口づけの味。さよならさえ言えず、最後に口にした言葉は、彼女に届くことはなかった。
あれから、いくつもの夜を見送った。
数年が立った頃。
彼女との思い出をたどって現世の蛍の泉へ獏は降りた。
ふと、村の様子が気になり、山を降りた。
――眼の前の光景に、息が止まった。
譲葉がいた。
見知らぬ男性と歩いていた。
彼女の腕には、幼い娘が抱かれている。
三人はとても幸せそうで。〈家族〉というぬくもりを得ていた。
獏は木陰に身を潜める。三人が通り過ぎるまで、浅い呼吸を繰り返した。
隠れる必要もないのに。なんて馬鹿なのだろう。
こうなることはわかっていたのに。じわり目頭が熱くなる。
――糸さえつながっていれば。隣を歩くのは私のはずだった。
(誰よりも君を愛していたのは私だ。そこにいるのは私のはずだったのだ)
――君は、ちゃんと約束を護った。幸せな道を、選んでくれたのに。
獏は我にかえった。
夢夜を助けるため、現世に向かう。
(あの日から、私は空っぽになった。満たせるものはなく、君ほど素晴らしい女人と出会えるはずもなく。私だけが、孤独で過ごしている気がしてならなかった)
――君を手放したことで、君は幸せになれた。
――君を手放したことで、私は孤独が増した。
獏は思う。
知らなかった。君が、羽衣を手放してまで、家族を守ろうと死を選んだなんて。
知らなかった。その娘や孫が、過酷な仕打ちを受けていたなんて。
なにも知らなかったのだ、私は・・・。
自責の念は留まるところを知らず、剣で刺すように心を貫く。
(すまなかった。譲葉・・・)
獏は繰り返す。
すまなかった。私は弱くて、憎まれ役にすら、なれなかった。
でも。
君は残してくれた。大切な宝物を。
わたしに、夢夜を残してくれた。
「あ・・・」
譲葉は崩れ落ちるように倒れた。その体を獏は支える。
彼女はことんと、眠りに落ちていた。土気色だった唇には色が戻り、落ち着いた呼吸をしている。
獏は彼女を地面におろし、膝に抱えると、その額に唇を寄せた。
これは最後の口づけ。
もう触れることも許されない、愛するひとへの、見送り。
「ずっと言いたかった。君のことが、好きだ」
しょっぱい口づけの味。さよならさえ言えず、最後に口にした言葉は、彼女に届くことはなかった。
あれから、いくつもの夜を見送った。
数年が立った頃。
彼女との思い出をたどって現世の蛍の泉へ獏は降りた。
ふと、村の様子が気になり、山を降りた。
――眼の前の光景に、息が止まった。
譲葉がいた。
見知らぬ男性と歩いていた。
彼女の腕には、幼い娘が抱かれている。
三人はとても幸せそうで。〈家族〉というぬくもりを得ていた。
獏は木陰に身を潜める。三人が通り過ぎるまで、浅い呼吸を繰り返した。
隠れる必要もないのに。なんて馬鹿なのだろう。
こうなることはわかっていたのに。じわり目頭が熱くなる。
――糸さえつながっていれば。隣を歩くのは私のはずだった。
(誰よりも君を愛していたのは私だ。そこにいるのは私のはずだったのだ)
――君は、ちゃんと約束を護った。幸せな道を、選んでくれたのに。
獏は我にかえった。
夢夜を助けるため、現世に向かう。
(あの日から、私は空っぽになった。満たせるものはなく、君ほど素晴らしい女人と出会えるはずもなく。私だけが、孤独で過ごしている気がしてならなかった)
――君を手放したことで、君は幸せになれた。
――君を手放したことで、私は孤独が増した。
獏は思う。
知らなかった。君が、羽衣を手放してまで、家族を守ろうと死を選んだなんて。
知らなかった。その娘や孫が、過酷な仕打ちを受けていたなんて。
なにも知らなかったのだ、私は・・・。
自責の念は留まるところを知らず、剣で刺すように心を貫く。
(すまなかった。譲葉・・・)
獏は繰り返す。
すまなかった。私は弱くて、憎まれ役にすら、なれなかった。
でも。
君は残してくれた。大切な宝物を。
わたしに、夢夜を残してくれた。