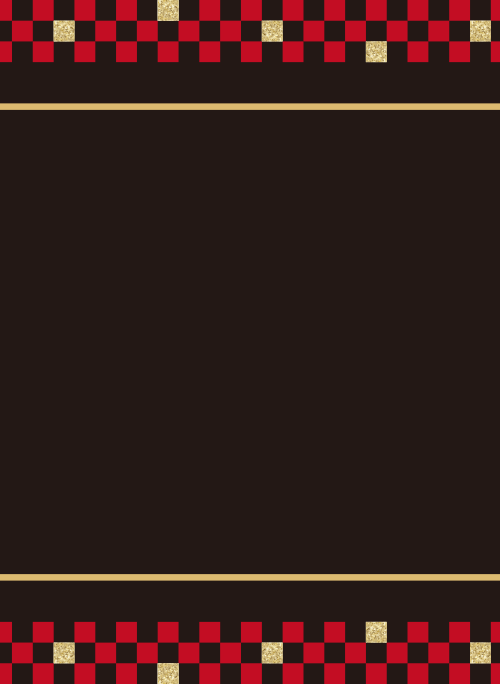目覚めると、枕元に中年女性が立っていた。狐牡丹だ。
「おはようございます。お嬢様」
相変わらず、きりりと引き締まった顔。口調。背筋にいたってはこれでもかと弓のように美しい曲線美である。
「お、はよう、ございます。狐牡丹様。――あ、あはは・・・」
夢夜は笑いかけたつもりが、ほほが引きつった。行儀作法の化身のような彼女の目には、きっと夢夜など野ネズミのように野蛮で小汚く見えているに違いない。
千年の悠久を気高く生きてきた妖狐は、その大きな黒い瞳でじっくりと夢夜を観察した。
「相変わらず、寝相が複雑怪奇ですね。上下逆さまではないですか。そんなありさまでは、旦那様と共寝した時、どちらかが床で寝るハメになりますよ」
「う。す、すいませ」
「ようやく庭ではなくご自分の部屋でお休みなさるようになったのは進歩ですが。寝台は狭いのですよ。落ちなかったのは奇跡ですね。冷たい床で寝ていたら、風邪をひくところでした」
よくもまあ、朝からぺらぺらと言葉がうかぶものだ。夢夜は尻だけで後退り、ささやかな抵抗をみせたが、侍女頭が見逃すはずもない。
「逃げてもムダですよ。今日はわたくしがつきっきりでお世話せよと、旦那さまより命じられております。さあさ、お顔を洗いますよ」
「ひえええっ!」
あらがう暇さえあたえられない。あれよあれよと夢夜はあわただしく身支度を整えさせられた。
狐牡丹は手際よく髪に櫛を入れる。
「だんだん艶が出てきましたね。まったく、わたくしがお手入れしなければ、今もお嬢様の毛なみは犬ころの毛以下でしたよ。感謝してくださいな」
〈毛なみ〉と言われ、夢夜は苦笑いしてごまかした。
毒舌の狐牡丹だが、手つきはやさしい。〈野生児〉の夢夜を〈お嬢様〉と呼ぶにふさわしくなるまで徹底的に磨き上げたのは彼女だ。
初めて風呂に放り込まれた夜を、きっと生涯忘れない。
頭からぶっかけられたお湯は激しかったが、温かい風呂は気持ちよかった。狐牡丹は背中の古傷にも眉一つ動かさず、体をぬか袋でこすってくれた。・・・タワシで磨くようだったのは、気のせいだと信じたい。
やがて髪を整えると、夢夜はいつもの簡素な着物ではなく、獏のぶかぶかの袍を着せられた。
「ほ、ほんとに着るんですか?」
「冗談だと思ってらしたのですか? 本気ですよ、旦那さまは」
純白のまばゆい袖からは、彼の香りがふわりと鼻をくすぐり、抱きしめられているような錯覚を起こす。朝っぱらから、刺激が強い・・・。
狐牡丹はさり気なく袍の下に桃色の衣を着せてくれた。袍は男性用でも、ひらりと蝶の羽のような襟袖が覗くだけで、可憐に見える。
ぎゅっと帯を締められ、息苦しさに耐えながら、身支度は終了した。
身なりをきちんとしていても、暇なのは変わりない。
夢夜は庭に童のようにしゃがみ込むと、棒でなにかをつつきはじめた。
「お嬢さま。何をしておられるので?」
狐牡丹は背後からひょいと覗き込む。
夢夜は、カマキリと戯れていた。
棒でつつくと、カマキリはかまを振り回す。
「・・・なんだか獏様に似ていると思って」
「え。どのへんでございますか!?」