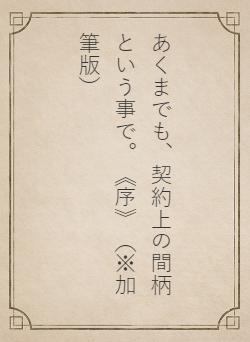「はーい!それでは皆さん見えてますでしょうかー!」
用意してもらった履き物を履いて庭に降りた彼女は、適当に広さがある場所に立つと、居並ぶ貴族達と御簾の内側で見ているであろう帝に呼びかけた。それこそ「良い子の皆〜!」といった類の呼びかけではないが、必要だと思ったのでやっている。
戸惑いを隠せないながらも数名が頷く様が見えたので、彼女は大きく深呼吸をした。両足を肩幅に開いて重心を安定させて立ち、背筋を伸ばす。胸の前に上げた左手を開いて、掌に右手を添えて意識を集中させる。
彼女の意識に応じるように神紋が光った。掌からまず柄が出てきたので掴み、横一文字に一気に引く。陽の光に輝く銀刀の出現に、控え目ながらも「おお」と声が上がった。
『見ての通りだ』
光と共に、銀大神が顕現した。彼女に寄り添うように肩に手を置く。
座っているのに腰を抜かす者もいる貴族達と、御簾の内側すら見透かすように睥睨すると、銀大神はよく通る声で告げる。
『汝等が銀の姫と呼ぶこの娘こそが、私の唯一の使い手だ。異郷からの稀人なれど、無碍に扱う事は許さぬ』
「あのー。私がこの世界で行なうべき事を、こちらの大神様に訊いておいたんですけど」
恐れ慄いたように銀大神に平伏する一同だが、彼女はマイペースに問いかける。
そう。常時顕現はしないようにと、彼女から銀大神に頼んでいたのである。
まず巫女達に導かれた場所は、どうしても女性のみだった。男性の姿、何よりも神が姿を現していたら巫女達が落ち着かないと思い、顕現を解いてくれるように頼み込んだ。しかし未顕現状態でも俗に言うテレパシー、要するに言葉を使わずとも会話はできたので、身支度等の合間合間に、『鞘』である自分の役割を聞き出していたのだ。
「おわかりになる方に伺いたいんですけど。『幽世』でしたっけ?生きている人達の世界、つまりこちらと幽世の境界が曖昧になっていて、向こうの空気が毒みたいに変質して、瘴気となってこちらに流れ出していると聞きました」
「え、ええ。その通りです」
顔をあげたさゆらが、何とか頷いた。
「わたくし達も陰陽寮の者達も総出で封じ込めにかかっていますが、焼け石に水。瘴気を絶ち清める事ができるのは銀刀のみですが、如何なる術者でも剣豪でも、抜く事が叶わなかったのです」
陰陽師もいるんだなと彼女は思ったが、話がずれそうなので胸の内に留めておいた。
「で、誰が銀刀の使い手になり得るか、さゆらさん達で占っていたそうですね。大神様はその占いの力に乗じて、使い手になり得る人…つまり私を連れてきた、との事です」
「そうだったのですか」
初めて顔を合わせた時の状況が繋がったらしく、さゆらは合点が行った顔になった。
彼女は「ここからが本題なんですけど」と前置きする。
「皆さんが私に望む事は何ですか?銀刀の使い手として、瘴気を浄化していく事ですか?」
銀刀の顕現を彼女に命じた貴族が、御簾の内側と素早くやり取りをした。彼女に向き直り、口を開く。
「銀の姫に命じる。銀刀をもって瘴気を祓い、葦原の中津国に平穏を取り戻すのだ。これは勅命である」
「いいですよ」
勿体ぶった、聞きようによっては頭ごなしな物言いであったが、彼女はあっさりと承諾した。まあ帝だし一番偉い人だし、命令する事が当たり前だよなと思ったので、特に気分は害さなかった。
異世界で起こっている事なのだから、自分には無関係だと言ってしまえば、それまで。でもそんな風に切り捨ててしまうのは、あまりにも冷た過ぎると彼女は思ったのだ。何より、特定の誰かしか解決できない困り事に対して、その解決できる誰かがそっぽを向いてしまったら、絶望感が凄いだろうとも思ったのである。要は自分の立場に置き換えて考えた上での承諾だ。
「その代わり、必要なものはお上の権限で、きちんと用意して下さい」
「…申してみよ」
聞く姿勢は見せてくれた事に安堵しつつ、彼女は続けた。
「まず、私が活動する上で拠点となる場所を用意して欲しいです。それと、私はこの葦原の中津国の事は全然知りませんので、社会の構成や状況を教えてくれるお師匠さんが必要です。あと、こちらは私の世界とは文字や言葉の使い方が異なると思いますので、読み書きのお師匠さんも付けて下さい。更に一つ。申し訳ありませんが、私は刀剣の扱いは素人です。剣の指南役も付けて下さい」
「女子が剣を?」
「あらだって必要でしょ?きちんと持ったり振り回したりできるようになりたいです」
現に、真剣は重い。例えば瘴気を絶つにしても、刀をまともに持ち上げる事すらできなければ話にならない。貴族達はざわめくが、彼女は至極当然の事を言っているだけという頭である。
これまた御簾の内側と素早くやり取りをした貴族は、気を取り直すように咳払いをした。
「委細承知と、お上は仰せである。銀の姫の身は、確かに保証しよう」
「良かった。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ。とりあえず、銀刀はしまっちゃいますね」
下げた頭を上げた彼女は、左の掌を銀刀の柄に当てる。するすると吸い込まれるように消えていく銀刀を見た貴族達は、また驚いたのであった。
用意してもらった履き物を履いて庭に降りた彼女は、適当に広さがある場所に立つと、居並ぶ貴族達と御簾の内側で見ているであろう帝に呼びかけた。それこそ「良い子の皆〜!」といった類の呼びかけではないが、必要だと思ったのでやっている。
戸惑いを隠せないながらも数名が頷く様が見えたので、彼女は大きく深呼吸をした。両足を肩幅に開いて重心を安定させて立ち、背筋を伸ばす。胸の前に上げた左手を開いて、掌に右手を添えて意識を集中させる。
彼女の意識に応じるように神紋が光った。掌からまず柄が出てきたので掴み、横一文字に一気に引く。陽の光に輝く銀刀の出現に、控え目ながらも「おお」と声が上がった。
『見ての通りだ』
光と共に、銀大神が顕現した。彼女に寄り添うように肩に手を置く。
座っているのに腰を抜かす者もいる貴族達と、御簾の内側すら見透かすように睥睨すると、銀大神はよく通る声で告げる。
『汝等が銀の姫と呼ぶこの娘こそが、私の唯一の使い手だ。異郷からの稀人なれど、無碍に扱う事は許さぬ』
「あのー。私がこの世界で行なうべき事を、こちらの大神様に訊いておいたんですけど」
恐れ慄いたように銀大神に平伏する一同だが、彼女はマイペースに問いかける。
そう。常時顕現はしないようにと、彼女から銀大神に頼んでいたのである。
まず巫女達に導かれた場所は、どうしても女性のみだった。男性の姿、何よりも神が姿を現していたら巫女達が落ち着かないと思い、顕現を解いてくれるように頼み込んだ。しかし未顕現状態でも俗に言うテレパシー、要するに言葉を使わずとも会話はできたので、身支度等の合間合間に、『鞘』である自分の役割を聞き出していたのだ。
「おわかりになる方に伺いたいんですけど。『幽世』でしたっけ?生きている人達の世界、つまりこちらと幽世の境界が曖昧になっていて、向こうの空気が毒みたいに変質して、瘴気となってこちらに流れ出していると聞きました」
「え、ええ。その通りです」
顔をあげたさゆらが、何とか頷いた。
「わたくし達も陰陽寮の者達も総出で封じ込めにかかっていますが、焼け石に水。瘴気を絶ち清める事ができるのは銀刀のみですが、如何なる術者でも剣豪でも、抜く事が叶わなかったのです」
陰陽師もいるんだなと彼女は思ったが、話がずれそうなので胸の内に留めておいた。
「で、誰が銀刀の使い手になり得るか、さゆらさん達で占っていたそうですね。大神様はその占いの力に乗じて、使い手になり得る人…つまり私を連れてきた、との事です」
「そうだったのですか」
初めて顔を合わせた時の状況が繋がったらしく、さゆらは合点が行った顔になった。
彼女は「ここからが本題なんですけど」と前置きする。
「皆さんが私に望む事は何ですか?銀刀の使い手として、瘴気を浄化していく事ですか?」
銀刀の顕現を彼女に命じた貴族が、御簾の内側と素早くやり取りをした。彼女に向き直り、口を開く。
「銀の姫に命じる。銀刀をもって瘴気を祓い、葦原の中津国に平穏を取り戻すのだ。これは勅命である」
「いいですよ」
勿体ぶった、聞きようによっては頭ごなしな物言いであったが、彼女はあっさりと承諾した。まあ帝だし一番偉い人だし、命令する事が当たり前だよなと思ったので、特に気分は害さなかった。
異世界で起こっている事なのだから、自分には無関係だと言ってしまえば、それまで。でもそんな風に切り捨ててしまうのは、あまりにも冷た過ぎると彼女は思ったのだ。何より、特定の誰かしか解決できない困り事に対して、その解決できる誰かがそっぽを向いてしまったら、絶望感が凄いだろうとも思ったのである。要は自分の立場に置き換えて考えた上での承諾だ。
「その代わり、必要なものはお上の権限で、きちんと用意して下さい」
「…申してみよ」
聞く姿勢は見せてくれた事に安堵しつつ、彼女は続けた。
「まず、私が活動する上で拠点となる場所を用意して欲しいです。それと、私はこの葦原の中津国の事は全然知りませんので、社会の構成や状況を教えてくれるお師匠さんが必要です。あと、こちらは私の世界とは文字や言葉の使い方が異なると思いますので、読み書きのお師匠さんも付けて下さい。更に一つ。申し訳ありませんが、私は刀剣の扱いは素人です。剣の指南役も付けて下さい」
「女子が剣を?」
「あらだって必要でしょ?きちんと持ったり振り回したりできるようになりたいです」
現に、真剣は重い。例えば瘴気を絶つにしても、刀をまともに持ち上げる事すらできなければ話にならない。貴族達はざわめくが、彼女は至極当然の事を言っているだけという頭である。
これまた御簾の内側と素早くやり取りをした貴族は、気を取り直すように咳払いをした。
「委細承知と、お上は仰せである。銀の姫の身は、確かに保証しよう」
「良かった。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ。とりあえず、銀刀はしまっちゃいますね」
下げた頭を上げた彼女は、左の掌を銀刀の柄に当てる。するすると吸い込まれるように消えていく銀刀を見た貴族達は、また驚いたのであった。