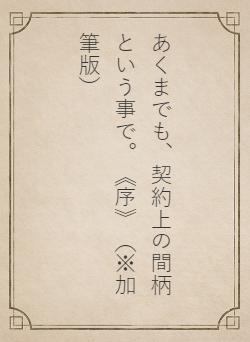彼女がひょっこりと顔を出すと、居並ぶ巫女達は一様にぎょっとした顔になった。一番前にいる1人が鋭い誰何を投げかける。
「な、何者です!ここは銀大神を祀る場所!一体何処から…!」
彼女はマイペースに「こんにちは」と頭を下げた。
「突然すみません。この刀を管理している方達ですか?」
彼女はひょいと軽く銀刀を持ち上げて問いかけた。
「私、いつの間にかこの奥にいて、この刀を抜けたので持ってきてしまったんですけど」
「銀刀を抜いた…!?」
言った途端、巫女達はざわつき始めた。彼女に最初に問いかけをした巫女が、信じられないものを見る目を彼女に向ける。
「その銀刀は、扱う資格を持つ者しか抜く事が叶わぬ霊刀。本当に貴方が…?」
『如何にも』
応じる声と共に、銀大神が彼女の側に顕現した。通路の出口も近くなった所で、一回姿を消していたのである。こういう存在は関わった本人、つまりこの場合は彼女にしか視認ができないのが相場だと思っていたが、どうやら全員が視認できるらしい。巫女達一同が声なき声を上げたのが、彼女はわかった。
銀大神は巫女達を見渡し、彼女の肩に片手を置いて朗々と宣言した。
『この者こそが、銀大神と汝等が呼ぶ、私が認めた使い手。私と在り私を振るう、我が鞘である』
「らしいんですけど、先程からずっと気になっていたんですが、どなたかこれの鞘知りませんか?ここの奥にはそれらしき物が無かったので」
抜き身のままでは危険だし、刀剣自体にも良くないので訊いたのだが、巫女達はただ呆然とするばかりである。静寂の中、銀大神は彼女に目線を合わせて優しく言った。
『言ったはずだ。そなたこそが私の鞘であると。手を出してみよ。心之臓に近い、左手が良い』
「はい」
怪訝に思いつつも、彼女は素直に左手を広げてみせた。銀大神が片手の指先を彼女の掌に向け、すいと動かす。すると掌と手の甲に、赤い紋様が浮かび上がった。
彼女は驚いたが、鋭さと優美さを併せ持つデザインをすぐに気に入った。銀大神は「おお」と声を上げる彼女に、銀刀即ち自分の本体を指して告げる。
『神紋を我が本体にかざしてみよ』
「わかりました」
右手で持つ柄に左手をかざすと、銀刀は紋様に吸い込まれるようにして、するすると彼女の左手に収まっていった。彼女は目を瞬き、左手の掌と甲に刻まれた紋様をまじまじと見る。
「『鞘』って、生身の人間に刀を収める事だったんですね。神様の力で」
『そうだ。私を扱う者しか、私を収める事はできぬ』
銀大神は微笑み、彼女の左手の紋様を指した。
『我が本体が必要になれば、ただ念じれば良い。神紋からいつでも我が本体を顕現できる』
「だそうです。お騒がせしてすみませんでした」
彼女に最初に問いかけをした巫女が、ゆっくりと首を横に振った。
「…銀大神の顕現、銀刀を収める神紋、まさか目にする事になるとは」
「うーん。刀剣ですので、然るべき管理者にきちんと渡すつもりでいたんですけど。私に収めていてよろしいんでしょうか」
「勿論です。わたくし共は、貴方を待ち望んでおりました」
進み出た巫女は、彼女に丁重に頭を下げた。
「お名前があるかとは思いますが、銀の姫とお呼び致します。わたくしは巫女長のさゆらと申す者」
「さゆら様、と仰るんですね」
巫女さん達の中でも偉い人のようなので敬称を付けたのだが、「いえ」と慌てられてしまった。
「わたくし共に『様』は付けなくてもよろしいのですよ」
「うーん。でも何も付けないのもどうかと思いますので、さゆらさんと呼びます。他の皆さんも」
彼女は他の巫女達を見渡し会釈をした。巫女達も戸惑い気味に礼を返す。完全に彼女のペースだが、さゆらは気を取り直すように咳払いをした。
「銀の姫が現れた事は、お上に報告しなければなりません。どうぞこちらへ。帝への目通りの為に、身支度を致しましょう」
「姫という柄ではないんですけど、わかりました。よろしくお願いします。お世話になります」
どうやら自分はかなり重要な立場らしい。この世界の現在の社会情勢、例えば公家が機能しているのかだとか、幕府が存在するのかだとか、はたまた自分が学んできた日本史とは全く別の社会形態なのかだとか、わからない事ばかりだが、いきなり帝に対面とは大変な事態なのだと思う。
正直、緊張はする。しかしまあ、歓迎されていない訳ではないみたいだし、こうして案内してくれる人達もいるから大丈夫かもしれない。
何より、『あえて一旦姿を消してから巫女達の前にわざわざ顕現してみせる』『彼女が鞘である即ち銀刀を扱える人間であるという事実を実証してみせる』というやり方で、銀大神は事情を知らぬ人間達に彼女がいち早く受け入れられるようにしてくれたのだろうなと、彼女は解釈していた。
さゆらを始めとする巫女達に導かれ、彼女は石室を後にした。
「な、何者です!ここは銀大神を祀る場所!一体何処から…!」
彼女はマイペースに「こんにちは」と頭を下げた。
「突然すみません。この刀を管理している方達ですか?」
彼女はひょいと軽く銀刀を持ち上げて問いかけた。
「私、いつの間にかこの奥にいて、この刀を抜けたので持ってきてしまったんですけど」
「銀刀を抜いた…!?」
言った途端、巫女達はざわつき始めた。彼女に最初に問いかけをした巫女が、信じられないものを見る目を彼女に向ける。
「その銀刀は、扱う資格を持つ者しか抜く事が叶わぬ霊刀。本当に貴方が…?」
『如何にも』
応じる声と共に、銀大神が彼女の側に顕現した。通路の出口も近くなった所で、一回姿を消していたのである。こういう存在は関わった本人、つまりこの場合は彼女にしか視認ができないのが相場だと思っていたが、どうやら全員が視認できるらしい。巫女達一同が声なき声を上げたのが、彼女はわかった。
銀大神は巫女達を見渡し、彼女の肩に片手を置いて朗々と宣言した。
『この者こそが、銀大神と汝等が呼ぶ、私が認めた使い手。私と在り私を振るう、我が鞘である』
「らしいんですけど、先程からずっと気になっていたんですが、どなたかこれの鞘知りませんか?ここの奥にはそれらしき物が無かったので」
抜き身のままでは危険だし、刀剣自体にも良くないので訊いたのだが、巫女達はただ呆然とするばかりである。静寂の中、銀大神は彼女に目線を合わせて優しく言った。
『言ったはずだ。そなたこそが私の鞘であると。手を出してみよ。心之臓に近い、左手が良い』
「はい」
怪訝に思いつつも、彼女は素直に左手を広げてみせた。銀大神が片手の指先を彼女の掌に向け、すいと動かす。すると掌と手の甲に、赤い紋様が浮かび上がった。
彼女は驚いたが、鋭さと優美さを併せ持つデザインをすぐに気に入った。銀大神は「おお」と声を上げる彼女に、銀刀即ち自分の本体を指して告げる。
『神紋を我が本体にかざしてみよ』
「わかりました」
右手で持つ柄に左手をかざすと、銀刀は紋様に吸い込まれるようにして、するすると彼女の左手に収まっていった。彼女は目を瞬き、左手の掌と甲に刻まれた紋様をまじまじと見る。
「『鞘』って、生身の人間に刀を収める事だったんですね。神様の力で」
『そうだ。私を扱う者しか、私を収める事はできぬ』
銀大神は微笑み、彼女の左手の紋様を指した。
『我が本体が必要になれば、ただ念じれば良い。神紋からいつでも我が本体を顕現できる』
「だそうです。お騒がせしてすみませんでした」
彼女に最初に問いかけをした巫女が、ゆっくりと首を横に振った。
「…銀大神の顕現、銀刀を収める神紋、まさか目にする事になるとは」
「うーん。刀剣ですので、然るべき管理者にきちんと渡すつもりでいたんですけど。私に収めていてよろしいんでしょうか」
「勿論です。わたくし共は、貴方を待ち望んでおりました」
進み出た巫女は、彼女に丁重に頭を下げた。
「お名前があるかとは思いますが、銀の姫とお呼び致します。わたくしは巫女長のさゆらと申す者」
「さゆら様、と仰るんですね」
巫女さん達の中でも偉い人のようなので敬称を付けたのだが、「いえ」と慌てられてしまった。
「わたくし共に『様』は付けなくてもよろしいのですよ」
「うーん。でも何も付けないのもどうかと思いますので、さゆらさんと呼びます。他の皆さんも」
彼女は他の巫女達を見渡し会釈をした。巫女達も戸惑い気味に礼を返す。完全に彼女のペースだが、さゆらは気を取り直すように咳払いをした。
「銀の姫が現れた事は、お上に報告しなければなりません。どうぞこちらへ。帝への目通りの為に、身支度を致しましょう」
「姫という柄ではないんですけど、わかりました。よろしくお願いします。お世話になります」
どうやら自分はかなり重要な立場らしい。この世界の現在の社会情勢、例えば公家が機能しているのかだとか、幕府が存在するのかだとか、はたまた自分が学んできた日本史とは全く別の社会形態なのかだとか、わからない事ばかりだが、いきなり帝に対面とは大変な事態なのだと思う。
正直、緊張はする。しかしまあ、歓迎されていない訳ではないみたいだし、こうして案内してくれる人達もいるから大丈夫かもしれない。
何より、『あえて一旦姿を消してから巫女達の前にわざわざ顕現してみせる』『彼女が鞘である即ち銀刀を扱える人間であるという事実を実証してみせる』というやり方で、銀大神は事情を知らぬ人間達に彼女がいち早く受け入れられるようにしてくれたのだろうなと、彼女は解釈していた。
さゆらを始めとする巫女達に導かれ、彼女は石室を後にした。