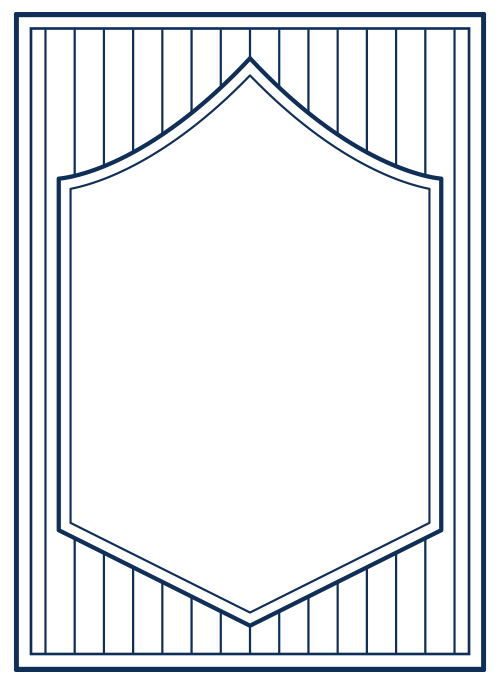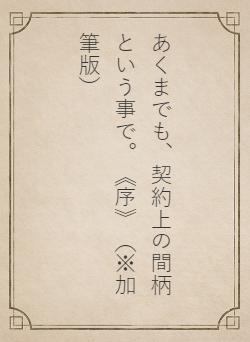「こんなに綺麗なのに、何で泥沼になんて捨てるかなあ」
失敗作と投げ捨てられた自分を磨き上げた彼女は呟いた。
「神職の人達なら大事にしてくれそう。いい守り神になってくれそうだし」
彼女は彼を神官達に託し、何の事も無さそうに去っていった。
彼が彼という意識も曖昧な頃の、遠い遠い記憶である。
失敗作と投げ捨てられた自分を磨き上げた彼女は呟いた。
「神職の人達なら大事にしてくれそう。いい守り神になってくれそうだし」
彼女は彼を神官達に託し、何の事も無さそうに去っていった。
彼が彼という意識も曖昧な頃の、遠い遠い記憶である。