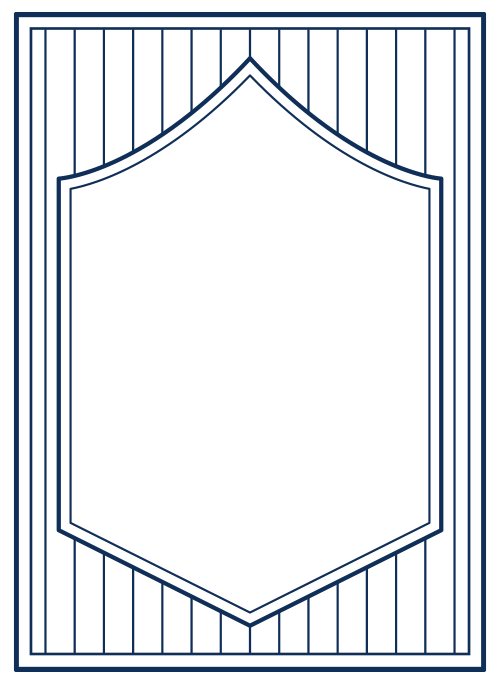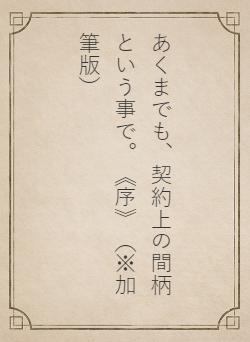「結界が破られました!」
「何だと!?」
異変は既に彼等にも伝わっていた。忙しない足音が近付いてきて、断りの言葉と共に襖が開けられる。使用人の報告に一同は腰を浮かせかけた。
「一体何者です!?」
「それがその、」
使用人は困ったように廊下に視線を向けた。複数の足音と「お待ち下さい!」「落ち着いて下さい!」と宥める声が響いてくる。ぱあんと大きな音と共に、襖が完全に開けられた。屋内であるにも関わらず土足の人物は、じろりと1名を睨み付けた。
「おいこらくそおやじ。うちに勝手に入った挙句、私の作品を持ち出すとか、よくもまあやってくれたな」
「えっ?」
「え?」
「これは、お前さんが作った物だったのですか?」
星のような光が輝く宝石が飾られた指輪を指して問いかけられた彼女は、姿勢を正して頭を下げた。
「ご当主様。結界を破壊した上に土足で申し訳ありません。このろくでなしが母と妹から暴力で私の作品を盗っていったと聞きましたもので、取り返しに参りました。警察には一応言ったのですが、身内の間の事だから身内で解決するようにと言われてしまいましたもので、このような強硬手段に出た次第です」
なお件の警官の名誉の為に書いておくが、
「あの、すみません。父親に自分の物を勝手に持ち出されてしまったのですが、被害届はどのように出せばよろしいでしょうか」
「え?お、お父さん?うーん、そういうのはまずご家族で話し合った方がいいと思うよ?」
とまあこのように、困惑しつつも対応はしてくれた。力になれない事には申し訳ないと謝られた。
「お、お前、一体どなたの御前だと思っているんだ!『御剣様』の御前だぞ!」
「御剣様?ああ。そちらの方が、あの」
辛うじて威厳を保つ為か、咎めだてする口調で父親は彼女を𠮟り付けてくるが、それで臆する彼女ではない。上座に視線を向け、座する美丈夫に頭を下げはしたが。
「『護りの神剣』様がいらしていると知らなかったものの、いきなり申し訳ありません。先程も申しました通り、この馬鹿…いいえ。この人が私の作品を勝手に持ち出したので、取り返しに参りました」
「親に対して馬鹿とは何だ!馬鹿とは!」
「父親だと思った事なんてありません」
彼女は恐ろしく冷たい、凄みのある視線を父親に向けた。
「つーか、論点をすり替えるんじゃないよ。ひとが作った物を盗った上に自分が作ったような顔をして渡そうとするとか、1人の人間として色々と終わっているし、何より神様に対して失礼だと思わないの?」
『護りの神剣』。文字通り、遥か神話の時代から、この日本を災いや穢れから護ってきた神剣である。いつからであったかは記録が曖昧だが、神剣に宿る神性・霊性が人の姿で顕現した。要するに付喪神である。付喪神といえば妖にカテゴライズされるが、一介の妖とは言えない程に神格は高い。
顕現して以来、本体たる剣及び意志と人格を持つ顕現体を『御剣様』と呼んで人々は祀り崇めている。
ただし、それでも侵入してくるあるいは侵入を試みる魔性はいる。魔性を駆逐する筆頭が、この神栖家だ。彼女と彼女の双子の妹は、神栖家の分家筋から本家の婿養子に入った父親が一般人の母親との間に成した、いわば外腹の子である。父親は、所帯持ちである事を隠していたばかりか、神栖の人間である事が露見しないように偽名まで使って彼女の母親と付き合っていたという、何処から何を言えばいいのかわからない程のどうしようも無さだ。なので彼女の態度はこの通りである。
「でも、どうして結界を破れたの?」
「それはあたしも気になってた。術は使えないはずでしょ?」
首を傾げて問うてきたのは、神栖家本家令嬢が2人。通称『壱の姫』と『弐の姫』だ。つまり彼女と彼女の妹たる美織とは、母親違いの姉妹になる。かと言って、彼女達は仲が悪い訳ではない。そもそも姉妹揃って気立てがいいので、彼女にも妹にも友好的に接してくれる。
彼女はひらひらと、アームカバーをはめた手を振ってみせた。
「これです。銀の腕って名前を付けたんですけど。結界だとかの術式を内部崩壊させる力を持たせました。私がそういう道具を作る事はできるのは知っているでしょ?」
「凄いわね!」
「そんなの作ってたの!?」
姉妹揃って素っ頓狂な声を上げた。
彼女は神栖家の人間達のように、魔性と戦う力は使えない。その代わりというべきか、彼女が特化しているのは『器物に力を込める事』『力ある物を作る事』だ。つまる所は、RPGだとかファンタジーだとかの用語で言うマジックアイテムの生成が可能なのだ。その腕は、本家でも高く評価されている。
「で、私が作った大事な作品の一つである『銀の星』を勝手に持ち出したのがこの人と」
因みに、彼女は自分が作る道具には、古今東西の神話や伝説にまつわる名を付けている。逆に、そのように名付けをした方が、道具に込める力のイメージを構築しやすいのだ。
「お父様…」
「パパ…」
「お前様。今の話は本当ですか?」
娘2人とその母親、神栖家現当主たる伴侶の視線を集めた父親は、だらだらと汗を流していた。
「…御剣様が花嫁を探されているから…お前達の婚約指輪になると思って…」
「そのようなやり方で得た指輪なんて、嬉しくありません!」
「そーよ!しかも暴力とか何考えてんのよ!美織ちゃんは身体が弱いのよ!ねえ美織ちゃんは大丈夫!?」
「大丈夫です。母も妹も怪我はありません」
彼女の妹を案じる弐の姫の問いに、彼女は答えた。神栖家当主は頭痛を堪えるような顔をしていたが、上座に向かって深々と頭を下げる。壱の姫と弐の姫及び父親、そして使用人達も、慌てて当主に倣った。
「この度は、身内の恥をお見せしてしまい、誠に申し訳ありません。神を謀った上に盗品を差し出すなど万死に値する所業と存じますが、責は全て当主たるわたくしが負います。娘達、そして一族の者には、何卒ご寛恕を頂きますよう」
「いいよ。やっと見付けたからね」
えっ、と当主一家及びお付きの者達は御剣様に視線を向けた。彼女も驚いて御剣様を見やる。
御剣様は、彼女を見ていた。視線が合うと、笑いかけてきた。無上の僥倖に巡り会えたかのような笑顔で、にっこりと。
「何だと!?」
異変は既に彼等にも伝わっていた。忙しない足音が近付いてきて、断りの言葉と共に襖が開けられる。使用人の報告に一同は腰を浮かせかけた。
「一体何者です!?」
「それがその、」
使用人は困ったように廊下に視線を向けた。複数の足音と「お待ち下さい!」「落ち着いて下さい!」と宥める声が響いてくる。ぱあんと大きな音と共に、襖が完全に開けられた。屋内であるにも関わらず土足の人物は、じろりと1名を睨み付けた。
「おいこらくそおやじ。うちに勝手に入った挙句、私の作品を持ち出すとか、よくもまあやってくれたな」
「えっ?」
「え?」
「これは、お前さんが作った物だったのですか?」
星のような光が輝く宝石が飾られた指輪を指して問いかけられた彼女は、姿勢を正して頭を下げた。
「ご当主様。結界を破壊した上に土足で申し訳ありません。このろくでなしが母と妹から暴力で私の作品を盗っていったと聞きましたもので、取り返しに参りました。警察には一応言ったのですが、身内の間の事だから身内で解決するようにと言われてしまいましたもので、このような強硬手段に出た次第です」
なお件の警官の名誉の為に書いておくが、
「あの、すみません。父親に自分の物を勝手に持ち出されてしまったのですが、被害届はどのように出せばよろしいでしょうか」
「え?お、お父さん?うーん、そういうのはまずご家族で話し合った方がいいと思うよ?」
とまあこのように、困惑しつつも対応はしてくれた。力になれない事には申し訳ないと謝られた。
「お、お前、一体どなたの御前だと思っているんだ!『御剣様』の御前だぞ!」
「御剣様?ああ。そちらの方が、あの」
辛うじて威厳を保つ為か、咎めだてする口調で父親は彼女を𠮟り付けてくるが、それで臆する彼女ではない。上座に視線を向け、座する美丈夫に頭を下げはしたが。
「『護りの神剣』様がいらしていると知らなかったものの、いきなり申し訳ありません。先程も申しました通り、この馬鹿…いいえ。この人が私の作品を勝手に持ち出したので、取り返しに参りました」
「親に対して馬鹿とは何だ!馬鹿とは!」
「父親だと思った事なんてありません」
彼女は恐ろしく冷たい、凄みのある視線を父親に向けた。
「つーか、論点をすり替えるんじゃないよ。ひとが作った物を盗った上に自分が作ったような顔をして渡そうとするとか、1人の人間として色々と終わっているし、何より神様に対して失礼だと思わないの?」
『護りの神剣』。文字通り、遥か神話の時代から、この日本を災いや穢れから護ってきた神剣である。いつからであったかは記録が曖昧だが、神剣に宿る神性・霊性が人の姿で顕現した。要するに付喪神である。付喪神といえば妖にカテゴライズされるが、一介の妖とは言えない程に神格は高い。
顕現して以来、本体たる剣及び意志と人格を持つ顕現体を『御剣様』と呼んで人々は祀り崇めている。
ただし、それでも侵入してくるあるいは侵入を試みる魔性はいる。魔性を駆逐する筆頭が、この神栖家だ。彼女と彼女の双子の妹は、神栖家の分家筋から本家の婿養子に入った父親が一般人の母親との間に成した、いわば外腹の子である。父親は、所帯持ちである事を隠していたばかりか、神栖の人間である事が露見しないように偽名まで使って彼女の母親と付き合っていたという、何処から何を言えばいいのかわからない程のどうしようも無さだ。なので彼女の態度はこの通りである。
「でも、どうして結界を破れたの?」
「それはあたしも気になってた。術は使えないはずでしょ?」
首を傾げて問うてきたのは、神栖家本家令嬢が2人。通称『壱の姫』と『弐の姫』だ。つまり彼女と彼女の妹たる美織とは、母親違いの姉妹になる。かと言って、彼女達は仲が悪い訳ではない。そもそも姉妹揃って気立てがいいので、彼女にも妹にも友好的に接してくれる。
彼女はひらひらと、アームカバーをはめた手を振ってみせた。
「これです。銀の腕って名前を付けたんですけど。結界だとかの術式を内部崩壊させる力を持たせました。私がそういう道具を作る事はできるのは知っているでしょ?」
「凄いわね!」
「そんなの作ってたの!?」
姉妹揃って素っ頓狂な声を上げた。
彼女は神栖家の人間達のように、魔性と戦う力は使えない。その代わりというべきか、彼女が特化しているのは『器物に力を込める事』『力ある物を作る事』だ。つまる所は、RPGだとかファンタジーだとかの用語で言うマジックアイテムの生成が可能なのだ。その腕は、本家でも高く評価されている。
「で、私が作った大事な作品の一つである『銀の星』を勝手に持ち出したのがこの人と」
因みに、彼女は自分が作る道具には、古今東西の神話や伝説にまつわる名を付けている。逆に、そのように名付けをした方が、道具に込める力のイメージを構築しやすいのだ。
「お父様…」
「パパ…」
「お前様。今の話は本当ですか?」
娘2人とその母親、神栖家現当主たる伴侶の視線を集めた父親は、だらだらと汗を流していた。
「…御剣様が花嫁を探されているから…お前達の婚約指輪になると思って…」
「そのようなやり方で得た指輪なんて、嬉しくありません!」
「そーよ!しかも暴力とか何考えてんのよ!美織ちゃんは身体が弱いのよ!ねえ美織ちゃんは大丈夫!?」
「大丈夫です。母も妹も怪我はありません」
彼女の妹を案じる弐の姫の問いに、彼女は答えた。神栖家当主は頭痛を堪えるような顔をしていたが、上座に向かって深々と頭を下げる。壱の姫と弐の姫及び父親、そして使用人達も、慌てて当主に倣った。
「この度は、身内の恥をお見せしてしまい、誠に申し訳ありません。神を謀った上に盗品を差し出すなど万死に値する所業と存じますが、責は全て当主たるわたくしが負います。娘達、そして一族の者には、何卒ご寛恕を頂きますよう」
「いいよ。やっと見付けたからね」
えっ、と当主一家及びお付きの者達は御剣様に視線を向けた。彼女も驚いて御剣様を見やる。
御剣様は、彼女を見ていた。視線が合うと、笑いかけてきた。無上の僥倖に巡り会えたかのような笑顔で、にっこりと。