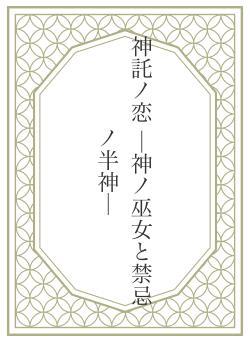住宅街を抜けると、小さな公園を見つけた。
こんなところに、公園なんてあったんだ。
なんとなく足を踏み入れてみた。
その公園は、滑り台とブランコが二つ、それに小さなベンチが一つあるだけの簡素な造りだった。
彼女はブランコに腰かけた。
誰もいない公園は、彼女に息を吹き返すような安堵感をもたらした。
しばらくの間、彼女は一人でブランコをゆらゆらと揺らしていた。
だけど夜の公園は、昼間のようなおひさまの香りはしなくて、代わりに深い闇の味がした。
さっきまで心地良かったはずの夜風が冷たくて、ひとり、世界から取り残されてしまったような気さえした。