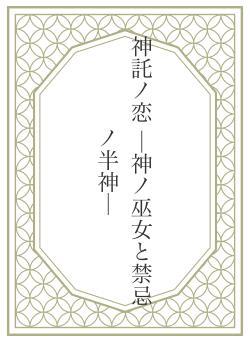夜の空気はひんやりとしていた。
熱にうなされていた頭が次第にすっきりとして元通りになるような感覚がした。
住宅街はしんと静まり返っていて、まるでこの世界には自分しかいないような、そんな錯覚さえ覚えた。
空には点々と星が輝いていた。
細い月明かりが、住宅街に影を落とす。
彼女が住むのは郊外から離れた場所で、こんな真夜中に出歩くような人は殆どいない。
家の明かりはおおよそ消えているため、ところどころにある街灯と、月明かりだけが頼りだった。
どこかに行きたいのに、どこにも行けないような、そんな気がする夜だった。
行くあてもなく、それがまた居場所のない寂しさのようで、胸にぽっかりと穴が空いているみたいだった。