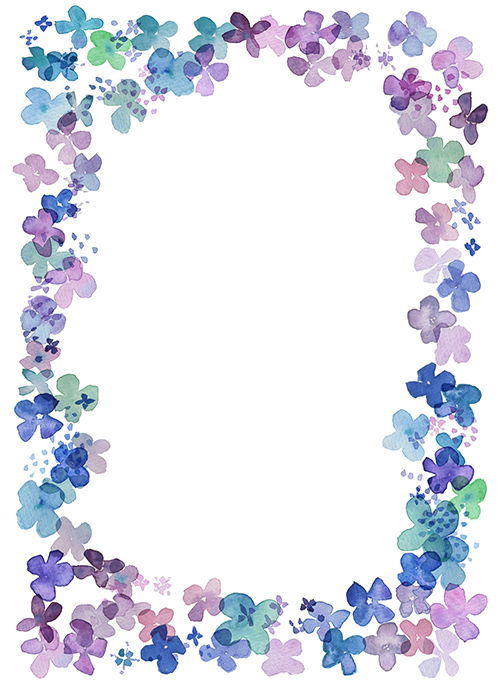貴族であるカーネリアン家とは雲泥の差だが、レオナルドは使用人として雇われているわけではない。世界でも一、二を争うトップクラスの大学院の博士課程をスキップ制度で史上最年少の、しかも首席卒業という頭脳明晰さをかわれ、大学で講師をしていたところをカーネリアン家から是非に、と依頼を受けてシオンの家庭教師をしているのだ。
だが、シオンの傍について二年になる今も尊敬されるどころか敬語もなく、軽口をたたかれる二十四歳。
しぶしぶミシンを進める手を止め、シオンはようやくレオナルドに向き合った。その表情からは、不機嫌さしか感じられないくらい無愛想そのもの。
レオナルドが握り締めていた新聞の号外をひったくると、これまた面倒くさそうに開いた。
「国王様の次女、マーシャ王女様が誘拐? マジで? それは大変だね」
大きく書かれた記事のタイトルををそのまま棒読みし、まるでたいした事でないかのように感想を吐き捨て、号外をレオナルドに突き返した。
「大変だねって、それだけですか」
「だって、それ以外どう言えってよ? 俺(おれ)にになにができるってわけじゃないんだし」
シオンは、ランドルフ王国の随一貴族であるカーネリアン家の人間として、権力も財力もある。
だが、それは先祖代々受け継いできた事業や、新たに興したいくつかの会社を経営しているのであって誘拐事件を解決するノウハウなど持っていない。それも一国の王女様の誘拐事件とあってはなおさらだ。
それは警察か、国王様直属の近衛兵の仕事なのだ。
「もういいだろ? 俺は今、追い込みで忙しいんだ」
再びミシンに向かおうとするシオンに、まだ話の途中です、とばかりにレオナルドは作業台にバンッと両手をついた。
「勇者の家系でもあるカーネリアン家に、国王様から直々に王女様救出の命令が下ったんです!」
「勇者だ? たしか祖先にそう呼ばれた人がいたとは聞いているが、大昔の話だぞ? ここ何代かは実業家として財を成しているし、現に父さんだっていくつか会社経営の傍ら、メガバンクの頭取だ。融資はしても、勇者になって人助けなんかできるかよ?」
「ですから、シオン様にと、ご命令が!」
だが、シオンの傍について二年になる今も尊敬されるどころか敬語もなく、軽口をたたかれる二十四歳。
しぶしぶミシンを進める手を止め、シオンはようやくレオナルドに向き合った。その表情からは、不機嫌さしか感じられないくらい無愛想そのもの。
レオナルドが握り締めていた新聞の号外をひったくると、これまた面倒くさそうに開いた。
「国王様の次女、マーシャ王女様が誘拐? マジで? それは大変だね」
大きく書かれた記事のタイトルををそのまま棒読みし、まるでたいした事でないかのように感想を吐き捨て、号外をレオナルドに突き返した。
「大変だねって、それだけですか」
「だって、それ以外どう言えってよ? 俺(おれ)にになにができるってわけじゃないんだし」
シオンは、ランドルフ王国の随一貴族であるカーネリアン家の人間として、権力も財力もある。
だが、それは先祖代々受け継いできた事業や、新たに興したいくつかの会社を経営しているのであって誘拐事件を解決するノウハウなど持っていない。それも一国の王女様の誘拐事件とあってはなおさらだ。
それは警察か、国王様直属の近衛兵の仕事なのだ。
「もういいだろ? 俺は今、追い込みで忙しいんだ」
再びミシンに向かおうとするシオンに、まだ話の途中です、とばかりにレオナルドは作業台にバンッと両手をついた。
「勇者の家系でもあるカーネリアン家に、国王様から直々に王女様救出の命令が下ったんです!」
「勇者だ? たしか祖先にそう呼ばれた人がいたとは聞いているが、大昔の話だぞ? ここ何代かは実業家として財を成しているし、現に父さんだっていくつか会社経営の傍ら、メガバンクの頭取だ。融資はしても、勇者になって人助けなんかできるかよ?」
「ですから、シオン様にと、ご命令が!」