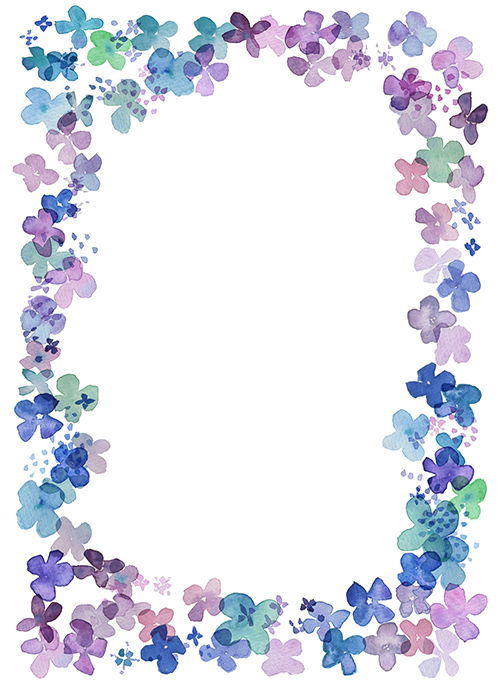「趣味じゃないって! これらはお客さんからのオーダー。どれも納品日が決まってるから、本来なら、勇者なんて面倒くさい事やってる暇ないの!」
「面倒くさいって……」
ソフィアが反論しようとしたところでレオナルドが口をはさんだ。
「ソフィアさん、シオン様は口は悪いですがセンスはありますし、シオン様へのご依頼は許容オーバーなくらいで、何日も徹夜で制作している事もあるのです。納期をきっちり守るのもシオン様のポリシーなので、移動中くらいは大目にみていただけませんか?」
デザイン画には、ウエディングドレスもあった事を思い出した。シオンのセンスならいくらでも素敵な作品を思い描く事はできるのだろうが、いざ制作となるとものすごく時間もかかるだろうから少しの隙間時間でももったいないし、大変な事というのはソフィアでもわかる。
しかし、自分にも他人にも厳しい性格のソフィアには、レオナルドのように「どうぞご自由に」なんて事は言えなかった。
「そうそう、最後のページのはキャロラインちゃんの新作だからね! 期待しててね」
シオンは、再び思いついたデザインを描きながらソフィアに呼びかけた。
最後のページの洋服は、スカートの裾が右は膝丈、左はくるぶしまであるアンシンメトリーになっていて、今、ソフィアが着ている洋服よりも胸元も肩も腕も足も露出の多いキャミワンピースだった。
「わたくしは着ませんので、そのデザインの洋服は他の女性にあげてください!」
「えー。この洋服も絶対似合うから着てみてよ! 一応ミシンや洋裁セットは持ってきてるんだけど、マーシャ王女様を救出する事が優先だってレオがうるさいから、作る時間なさそう。カーネリアン家のパーティまでには完成させるから、着て来てね!」
洋裁セットを持って来てるとか、パーティの洋服のデザインをしているとか、もうなにを考えているのだろうか。マーシャ王女様救出の任務を真面目に取り組んでいるとは思えない。
ソフィアはつい、
「あなたは、選ばれて勇者としてここに来ている事をお忘れにならないでください」
と、本来なら話しかけるのもタブーである貴族のシオンに意見してしまった。一歩間違えて怒らせてしまえば、ランドルフ王国から追放されるかもしれない事だ。
洋服の事だったり、シオンのワガママ三昧に蓄積されていたストレスが一気に爆発してしまった。
「面倒くさいって……」
ソフィアが反論しようとしたところでレオナルドが口をはさんだ。
「ソフィアさん、シオン様は口は悪いですがセンスはありますし、シオン様へのご依頼は許容オーバーなくらいで、何日も徹夜で制作している事もあるのです。納期をきっちり守るのもシオン様のポリシーなので、移動中くらいは大目にみていただけませんか?」
デザイン画には、ウエディングドレスもあった事を思い出した。シオンのセンスならいくらでも素敵な作品を思い描く事はできるのだろうが、いざ制作となるとものすごく時間もかかるだろうから少しの隙間時間でももったいないし、大変な事というのはソフィアでもわかる。
しかし、自分にも他人にも厳しい性格のソフィアには、レオナルドのように「どうぞご自由に」なんて事は言えなかった。
「そうそう、最後のページのはキャロラインちゃんの新作だからね! 期待しててね」
シオンは、再び思いついたデザインを描きながらソフィアに呼びかけた。
最後のページの洋服は、スカートの裾が右は膝丈、左はくるぶしまであるアンシンメトリーになっていて、今、ソフィアが着ている洋服よりも胸元も肩も腕も足も露出の多いキャミワンピースだった。
「わたくしは着ませんので、そのデザインの洋服は他の女性にあげてください!」
「えー。この洋服も絶対似合うから着てみてよ! 一応ミシンや洋裁セットは持ってきてるんだけど、マーシャ王女様を救出する事が優先だってレオがうるさいから、作る時間なさそう。カーネリアン家のパーティまでには完成させるから、着て来てね!」
洋裁セットを持って来てるとか、パーティの洋服のデザインをしているとか、もうなにを考えているのだろうか。マーシャ王女様救出の任務を真面目に取り組んでいるとは思えない。
ソフィアはつい、
「あなたは、選ばれて勇者としてここに来ている事をお忘れにならないでください」
と、本来なら話しかけるのもタブーである貴族のシオンに意見してしまった。一歩間違えて怒らせてしまえば、ランドルフ王国から追放されるかもしれない事だ。
洋服の事だったり、シオンのワガママ三昧に蓄積されていたストレスが一気に爆発してしまった。