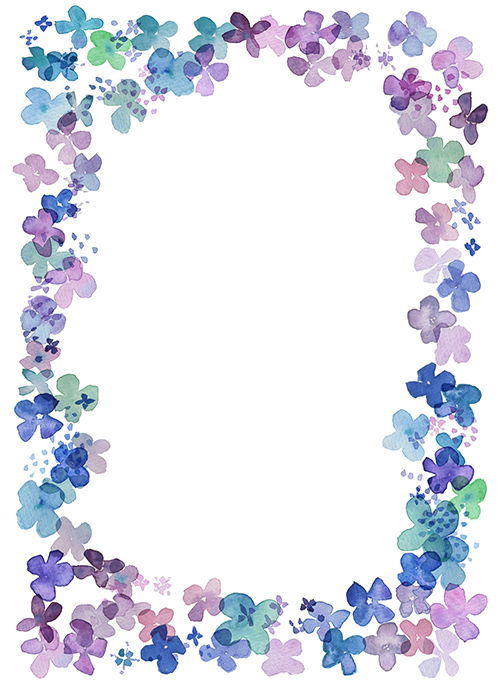ソフィアの身に纏っている服は、まるで修道女のようなローブ。ローブは、まさに伝統通りの魔術師の正装だった。
恐る恐るその条件はのめないと告げるソフィアに、シオンは組んでいた長い足を組み替えして言った。
「俺の腕とセンスを信じろって」
「センスという問題ではなく、規則が……」
あくまで『規則』が大事である事を強調したいソフィア。
しかし、その『規則』でつっぱねてまたシオンが作戦に協力しないと言いだしては、ハミルトンの立場もない。
それに、今回の作戦への参加はソフィアにとっても、人生のうちに一度あるかないかの光栄な事であるのは確かなので、このチャンスは逃したくない。というのも本音だった。
不安なのか、それともまだ怒りがおさまっていないのか、とにかく一気に表情をなくしてしまったソフィアに、レオナルドはなんとか機嫌をとり、承諾を得ようと考えた。
「あの、すみません! そうです! シオン様はお仕事も始められているのですよ。先日執り行われた第一王女・メアリー様のご成婚の際に、メアリー様が纏われたウエディングドレスはシオン様がデザインされたものなのですよ」
「そうなのですか。王女様のドレスはわたくしも拝見しました。とても素敵でした」
王女様のウエディングドレスはコンテスト形式で、プロ・アマ関係なく一般公募の中からデザインが選ばれて採用された。
この時にシオンは、カーネリアン家の息子ではなく、ただのシオンという名前以外、一切明かさないで応募したため、デザインが採用された時のシオンの喜びようは今でも忘れられないほどだった。
主催者側も、シオンがカーネリアン家の息子であると後で知ったのだ。
そのウエディングドレスは聡明さを引き立て、メアリー王女様の美しさを十二分に魅せていた。
メアリー王女様のウエディングドレスを手がけた事をきっかけに、シオンの名は広く世に知れ渡った。
もしかしたら自分でクリエイターと言っているだけあって、今は洋服にかける情熱は他に引けをとらないのではないか。
「わかりました。シオン様のおっしゃるとおりにいたします。どうぞよろしくお願いいたします」
ソフィアは深々とシオンに頭を下げた。
「りょーかーい。俺を信じろ。絶対、良いもの作ってやるから期待しててよ。じゃあ、マーシャ王女様の救出は俺とレオとキャロラインちゃんの三人で決定って事で」
恐る恐るその条件はのめないと告げるソフィアに、シオンは組んでいた長い足を組み替えして言った。
「俺の腕とセンスを信じろって」
「センスという問題ではなく、規則が……」
あくまで『規則』が大事である事を強調したいソフィア。
しかし、その『規則』でつっぱねてまたシオンが作戦に協力しないと言いだしては、ハミルトンの立場もない。
それに、今回の作戦への参加はソフィアにとっても、人生のうちに一度あるかないかの光栄な事であるのは確かなので、このチャンスは逃したくない。というのも本音だった。
不安なのか、それともまだ怒りがおさまっていないのか、とにかく一気に表情をなくしてしまったソフィアに、レオナルドはなんとか機嫌をとり、承諾を得ようと考えた。
「あの、すみません! そうです! シオン様はお仕事も始められているのですよ。先日執り行われた第一王女・メアリー様のご成婚の際に、メアリー様が纏われたウエディングドレスはシオン様がデザインされたものなのですよ」
「そうなのですか。王女様のドレスはわたくしも拝見しました。とても素敵でした」
王女様のウエディングドレスはコンテスト形式で、プロ・アマ関係なく一般公募の中からデザインが選ばれて採用された。
この時にシオンは、カーネリアン家の息子ではなく、ただのシオンという名前以外、一切明かさないで応募したため、デザインが採用された時のシオンの喜びようは今でも忘れられないほどだった。
主催者側も、シオンがカーネリアン家の息子であると後で知ったのだ。
そのウエディングドレスは聡明さを引き立て、メアリー王女様の美しさを十二分に魅せていた。
メアリー王女様のウエディングドレスを手がけた事をきっかけに、シオンの名は広く世に知れ渡った。
もしかしたら自分でクリエイターと言っているだけあって、今は洋服にかける情熱は他に引けをとらないのではないか。
「わかりました。シオン様のおっしゃるとおりにいたします。どうぞよろしくお願いいたします」
ソフィアは深々とシオンに頭を下げた。
「りょーかーい。俺を信じろ。絶対、良いもの作ってやるから期待しててよ。じゃあ、マーシャ王女様の救出は俺とレオとキャロラインちゃんの三人で決定って事で」