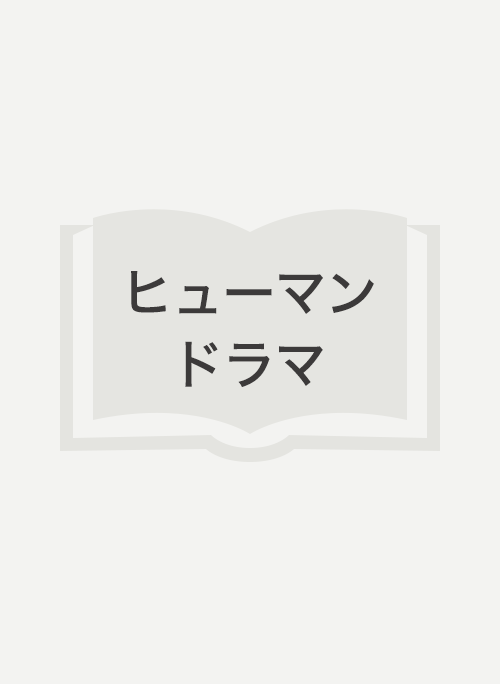「あら、おかえり」
私の帰りに気がついたお母さんが私を出迎えるようにスリッパをパタパタと鳴らして駆け寄る。ただいまと返して廊下を歩くと、「おかえり、お姉ちゃん」今度はリビングの方から声がする。足を止めて声のする方へ顔を向けると、妹の理緒が椅子に座っていた。
「…うん、ただいま」
妹の理緒は、私の一つ下。だから今年受験生になる。彼女から目を逸らして、お母さんとも目を合わさないように。
「今日は塾なかったんだ」
独り言のように言葉を漏らしていると。
「あ、う、うん。なんか急遽、なくなっちゃって。だから久しぶりに早く帰って来たの」
理緒もどこかぎこちなく返事をして、笑う。その表情さえも引き攣っているのは、私が一方的に妹に距離を取ってしまっているからだ。
「そー…なんだ」
よりによって塾がなくなってしまうなんて。今日はとことんついてないみたいだ。
「それでね今、理緒とクリスマスのことで話をしていたんだけどね」
〝クリスマス〟あと二週間もすれば、やってくる。世間ではそれを恋人や友人、家族と楽しく過ごすらしいけれど、私にとってそれは楽しみなイベントなんかではない。むしろその逆で。
「受験生だしあまり時間はないけど、家族みんなでご飯食べるくらいはしようかしらって考えているんだけれど」
そう告げられて、嫌な考えが頭の隅をよぎった。
「美月は、その日家にいれそう?」
そして、予想していた言葉が現れる。
苦い笑みを浮かべているお母さんの瞳の奥には、小さな期待が見え隠れしているようだった。
けれど、私にとってクリスマスなんてどうでもいい。
だから私は、
「……まだ分からないや」
曖昧な言葉で誤魔化した。
「そう、よね。バイトがあるかもしれないものね、まだ分からないわよね」
すると、私が返した言葉によってお母さんの表情が分かりやすく変化する。
バイトは二週間に一度、シフトを組む。だから今はまだクリスマスは埋まっていない。それでもその事実を言えないのは、どうしても家族と過ごすのが嫌だから。
「美月には美月の時間があるものね」
お母さんは、私の言葉を汲み取ってそれ以上〝クリスマス〟の話をするのはやめた。そのせいでリビングには変な空気が充満する。
「……ごめん」
私は、あの日からお母さんを困らせてる。
それは間違いなく、目に見えて感じる。
「う、ううん、いいの。気にしないで」
おまけに妹の理緒ともすれ違ってばかり。私は二人のことを避けている。距離をとっている。
掛け違えたボタンのように、私とお母さん、妹の距離はどんどん深くなる。一度ズレたらそのあとはずっとその距離を保っていくだけ。