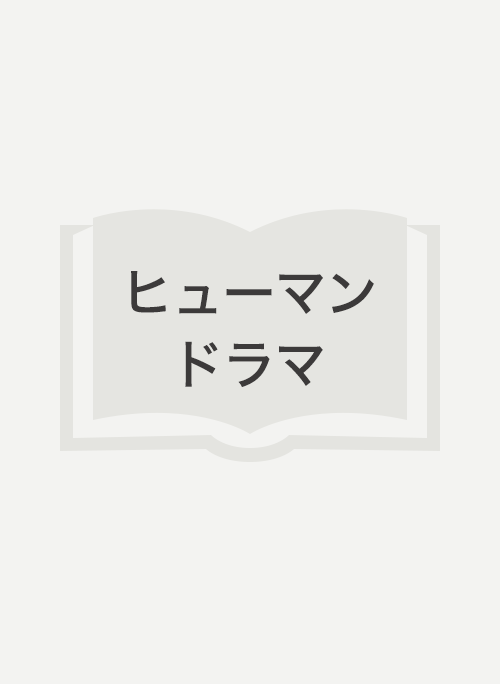理緒がそのことで悩んでいたなんて知らない。
私はずっと、自分ばかりを守っていたから。
けれど、それが私の過去のトラウマと何の関係があるっていうの。
「だけどね、どうしても諦められなくて……やっぱり志望校を変更したみたいなの。自分の未来のために」
私は受験に失敗したあの日から、自分の未来のビジョンが見えなくて、ずっと真っ暗闇の中だったのに。
──理緒には、未来が見えているの?
「あの子、学校の先生になりたいんですって」
悲しそうに、嬉しそうに、口元を緩ませながらつぶやいた。
「……学校の?」
理緒が、先生に。
「ええ、そうよ」
……なにそれ、聞いたことがない。
いや、それもそうか。だって私は、家族と距離をとって真剣に話を聞こうとしなかった。理緒に受験する学校を教えられたときだって、自分から何かを尋ねることはしなかった。
わざわざ自分の傷口を開こうと思う人間なんていないだろう。
「最初はあの子の実力では受からないだろうって言われたみたいなの。でもね、どうしても先生になるのを諦めたくないって塾に行かせてほしいってお願いしてきたのよ」
自ら進んで塾に行く、なんて意外だった。
べつに今まで疑問に思っても興味はなかったし、それ以上に深く関わろうとしてこなかった。家族なのに、姉妹なのに。
「……え、理緒が?」
すごく意外すぎて気の抜けた声を漏らしていると、「ええ、意外よね」とクスッと笑ったお母さんは。
「あの子、元々勉強は嫌いで机に向かっているより身体を動かすタイプだったのに」
私の表情を見て心を読み取ったのか、私の疑問を簡単に答える。
「じゃあ、なんで……」
小学生低学年の頃、宿題を教えてと泣きつかれたことがある。夏休みだってギリギリまで宿題を放置して私が手伝ったことだってある。理緒は、根っからの勉強嫌いだったはずなのに。
「──〝私は勉強が嫌いだったけど、いつもお姉ちゃんに勉強教えてって言ったら嫌な顔一つせず優しく丁寧に教えてくれた〟あの子、そう言っていたわ」
突然、告げられた言葉は、お母さんのものではないようで。
それに戸惑って、固まっていると。
「それにこうも言っていたの。〝お姉ちゃんに教えてもらっていたのがすごく分かりやすくて、こんな先生がいたら勉強を好きになれそう〟って」
と、もう一つ〝妹〟の言葉を追加した。