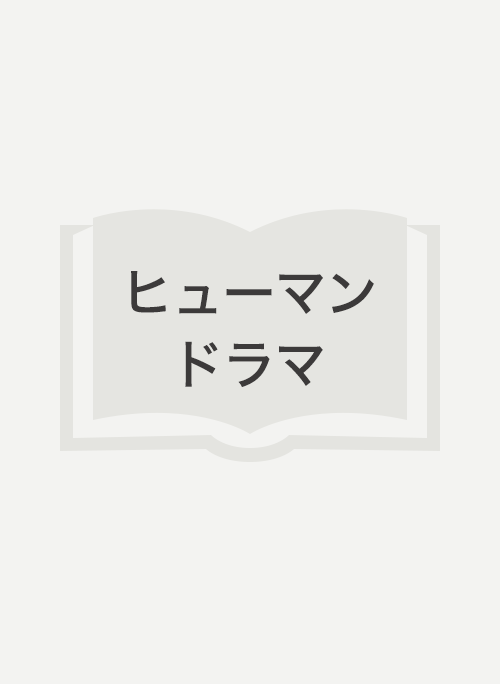「最初の美月、俺のことすごい拒絶してたじゃん。話しかけられるの迷惑そうにしてたし」
淡々と告げられる言葉で、私の記憶は急速に手繰り寄せられて、
「…あっ、そ、それは……」
少しだけ申し訳なく思い、目線を下げる。
「あのときは思い切り顔に出てたよね」
続けてはっきりとそう告げられるから、「うっ…」と言葉に詰まってしまう。
そんなに顔に嫌悪感が現れていたなんて。
「……ご、ごめん」
合わせる顔がなくて、顔があげられない。
「べつに美月を責めてるわけじゃないよ。だから、顔あげてよ」
「で、でも…」
「俺は、嬉しいんだよ」
そう聞こえたあと、え、と困惑して顔を上げると、
「それだけ俺のことを拒絶してた美月が、俺のことを頼ってくれて。嬉しいんだ、今」
千聖くんの顔は、とても優しそうに緩んでいた。
「美月が俺につらい過去を話してくれたってことは、俺のことを信用してくれたんだよね? 頼ってくれたんだよね? そう思ってもいいんだよね」
信用していたのは、間違いないし。
頼ったのも、間違いない。
「……うん」
私、千聖くんのこと信用してる。
いつのまにか。
気づかない間に心は無意識に求めていたのかもしれない。人の温かさを、優しさを。
「よかったぁ」
口元を弧に描いた千聖くん。
「美月さぁ、前に言ったことあったよね。〝私と千聖くんの住む世界は違うから〟って」
たしかに、そんなこと言ったことある。
千聖くんは〝陽〟で、私は〝陰〟だと。
「…あ、うん」
だから、どこまでいっても交わることはなくて。
それなのに千聖くんは──
「同じ空気吸って同じ場所にいて、同じ時間を過ごして、しゃべって名前だって知ってるし、住む世界が違うってなんだよ。俺たち一緒のこの世界にいるじゃん──って俺が言ったよね」
と、私が心の中で思い浮かべたそれと全く同じことを言った。
まるでそれが、以心伝心のようで。
「うん、覚えてる」
私が頷くと。
「俺と美月は、住む世界なんて違わない。別世界なんかじゃなくて、同じ場所同じ時間で過ごしてる」
私の手をとって、優しく包み込むと。