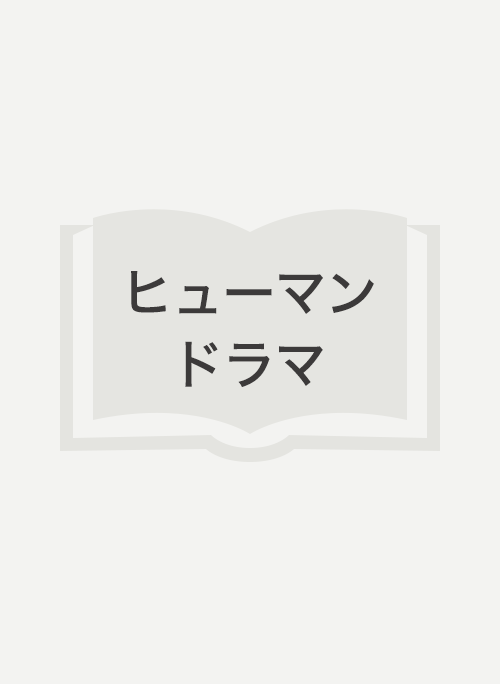「あー…そっか、あそこの高校だったっけ」
二人で顔を見合わせてうんうんと頷き合う。その二人が着ている制服は、私が行きたいと望んでいた高校の制服。私が着ることのできなかった制服。
それなのに二人は、それに身を纏っている。
「美月、卒業してから連絡ないから元気にしてるかなって梨生と言ってたんだけど。ここでバイトしてたんだね、知らなかった」
華菜がそう言うと、隣にいた梨生と顔を合わせて「ね」と困惑したように頷き合う。
連絡ないから、って言うけどそっちだって連絡しなかったじゃん。落ちた私が連絡しにくいなんて普通考えたらすぐに分かるはずなのに。
まるで私が悪いとでも言いたげな様子。
「いろいろと忙しくて、連絡できなかった。ごめん…ね」
どうして私が謝るんだろう、心の中で疑問が浮かぶ。
「う、ううん、大丈夫。こうやって元気な姿見れただけでも安心したし」
〝──元気な姿〟?
二人に私はそう見えているの?
私がどれだけ受験に失敗したことが悔しかったか、惨めだったか、二人は知っているはずなのに。どうしてそんなことか言えるの。
やり場のない苛立ちで、頭の芯がチリチリと音を立てる。
「そ、そうだ。美月がバイトない日、また中学の頃みたいに一緒に遊んだりしない?」
今度は華菜が提案する。ぱっと花が咲いたように梨生に笑いかける。当然、いいねいいね、と頷いて、答えを求めるように私へと顔を向けた。
「あ、えっと…」
これで一緒に遊べば中学の頃のように元通りになるのかもしれない。楽しいのかもしれない。
けれど、二人がその制服を着ている限り、きっと私だけが傷ついて、焼けるように胸が苦しくなる。
今まで通りなんて、不可能で。
「──ごめん。まだバイト慣れてなくて休みも疲れてたりするから、今はちょっと……」
だから私は、断った。
これ以上、自分が傷つかないために。苦しまないために。
きっとこれが最善の策なのだと、そう思った。
「そ、そっか、うん。じゃあ……また連絡するよ。美月が大丈夫なとき教えて。そのとき遊ぼうね」
せっかくの笑顔が曇る。まるで雲間に入ったような表情を浮かべて困惑した。私は、その言葉に小さく頷くことしかできなくて。