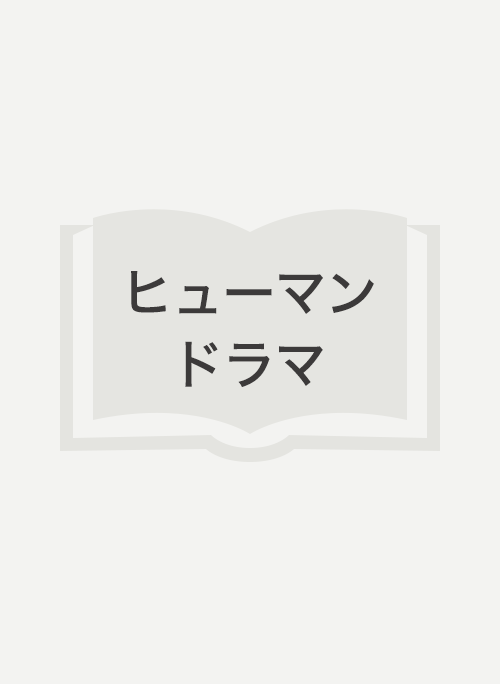「それにしてもさぁ、すっごい寒い!」
たった今穏やかだった表情がサイコロの反対の目を出したみたいに、顔をくしゃりとしわを寄せて自分の身体を抱きしめる。
全く私のことなど忘れたように「あー、寒い寒い」と続けて言う。そんなに寒いなら早く校内に戻ればいいのに、なぜか彼はフェンスに背を預けて長居するポーズをとりだした。
すんっと息を吸って、鼻先に触れたあと。
「まーでもそうだよね。だってもう十二月なわけだし、寒くて当然かあ」
一方的にしゃべり続ける。まるで栓が抜けた蛇口から水が一気に溢れ出すように、そこから次々と言葉が現れる。
「雪でも降ってきたらテンション上がるけど、当分雪は降らないみたいだし。ただ寒いだけとはわけ違うよな。そう思わない?」
不意に言葉を丸投げされるから、「はあ」と気の抜けた声しか返すことができなくて。彼の陽気な明るさについていけない私は、終始困った。
このままだと、いつ帰れるか分からないからだ。
だから、どうやって逃げよう。
そんなことを考えていると、
「──あっ、そうだ。名前教えてよ」
不意をついたように尋ねられて動揺した私は、え、と声を漏らす。が、そんなことなどつゆ知らず。
「俺、一年二組の伏見千聖。きみは?」
まるで川を流れる水のように、どんどん話が進んでゆく。あっという間に〝答える〟以外の選択肢がなくなって。
「……八組の、高野美月」
顔を逸らして、フェンスの向こう側へと目を向けていると、「美月かあ、うん、美月」私の名を確かめるように何度も呼んだ。
ガシャン。と、フェンスが揺れたあと、
「いい名前だね。これから俺、美月って呼ぶから」
すでに決定事項だとでも言いたげな明るさの言葉が落ちてきて、「え」弾けたように顔を上げた私は、彼の弧を描いた表情を見ることになる。
「俺のことも千聖って呼んで」
さらに伏見くんの言葉が続いて、戸惑った。
いくら同じ学校とはいえ、マンモス校であるこの高校は一クラス八組もある。その中で、二組と八組という端っこで、知り合いもいなければ友人もいない私にとって他のクラスの同級生を知るよしもない。出会ってまだ数分しか経っていないのに、互いのことを呼び捨てで呼び合うなんてそんなの不可能に近くて。
「いや、あの……」
断ろうと言葉を紡ごうと思うが。
「美月、八組なんだね。端っこ同士だからあんまり学校で会うことなかったのかぁ。でも、不思議だよね。同じ学校に通ってるはずなのに」
どんどん話が進んでゆくから断ることさえもできなくなって。
「それとも美月、あんまりこっちのクラス来ない?」
今日が初対面のはずなのに、彼は人懐っこささえ感じるから。
「ま、まぁ……」
気がつけば千聖くんのペースに巻き込まれて、名前のことに反論するどころか返事をしてしまう。