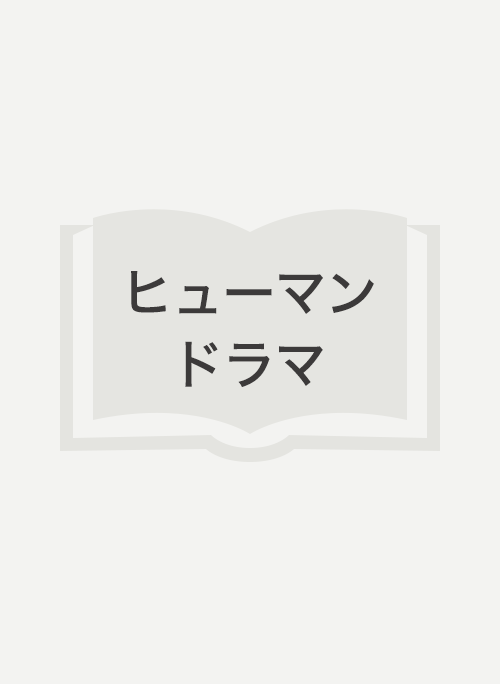そう思ってしまうのは、きっと私が人間だから。人間である限り、人を妬んだり羨ましがったり思うのは当然の真理だ。
「こんなに寒くても?」
斜め上にいる彼の顔を見つめるように尋ねると、「も!」と歯を見せてニイと笑った。
たった一文字で感情が伝わってくる。どうしようもないくらいに、ひしひしと。
「……こんなに寒いのが好きなんて、千聖くん、変わってるね」
〝伏見くん〟から〝千聖くん〟に変わった瞬間。私の中で何かが変化する。
それは、もちろん彼にも通用するわけで。
「美月がやっと俺の名前呼んでくれた!」
街灯の明かりに照らされて、目がしっかりと見開かれているのが分かる。それはもうレーザービームのように真っ直ぐ私を貫いていく。
「なにも名前呼んだだけでそんなにならなくても……」
「だってさ! お願いしても全然呼んでくれないし、ずっと伏見くんだったし、これはもうダメだなって諦めてたところだったから。まさかの想定外のパターンに」
ストップをかけなければこのまま一方的にしゃべりだすだろうと思って、焦って、
「わ、わかったから、少し静かに……! もうすぐ住宅街だから……」
そこでハッと気がついたのか、両手で口を覆った千聖くん。のどまで出かかった言葉をゴクリと飲み込んだあと「暴走しちゃってごめん」とへらりと笑った。
喜怒哀楽がオープンで、誰がどう見ても一発で分かるくらいに千聖くんの感性は豊かだ。見ている私でさえもおかしくなって、思わず口元が緩む。
「──あっ! 美月が笑った……!」
唐突に、声をあげる。それもかなりの声量で。
彼の言葉に驚いた私は、あたりをキョロキョロ見渡して人がいないか確認した。けれど、住宅街に入っていたため人通りはまばらだ。
シーッ、シーッと人差し指を立てて注意を促すと、もう一度口を覆ったあと、その興奮をゴクリと飲み呑んで、
「だってさぁ、美月が今まで笑ったことなかったから……!」
かなりボリュームを絞って、そのかわり身振り手振りは大袈裟っていうほどに。
あたりは街灯だけでお世辞にも明るいとは言えないけれど、それでもしっかりと彼の姿を確認できるのは、夜空に浮かぶ星のおかげかもしれない。
「そ、そりゃ、私だって人間だから笑うときだってあるし……」
なんて言ってはみたものの、ここ最近笑った記憶なんて一度もない。遡るように記憶をたどってみると、私が笑わなくなったのは、やっぱりあの日と関係していた。