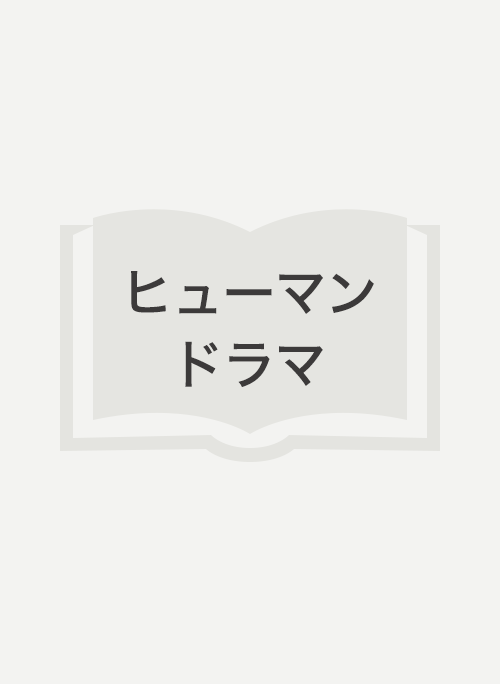「私はずっと……お姉ちゃんのこと、尊敬してた……お姉ちゃんの背中をずっと…追いかけてた……っ!」
途切れ途切れになる声は、かすれていて、けれど力強くて。
「お姉ちゃんのこと大好きなのに……嫌いになるはず、ないじゃん……っ!!」
理緒の切ない感情が、胸の奥に棘を刺すように次々と痛みが広がった。
「……理緒」
なんでもっと早くに気がつかなかったんだろう。妹が私のことをバカにするはずがないし、見下すわけでもないし、同情するわけでもない。妹が私のことをどう思っていたか、なんて知っていたはずなのに……
──バカは私だ。
「前から学校の先生になりたいって思ってた…嘘じゃないよ、ほんとに……そう思ったきっかけは、間違いなくお姉ちゃんなの……」
鼻をすん、とすすりながら涙を袖で拭いながら。
「お姉ちゃんみたいに勉強教えるのうまくなりたいって……そしたら嫌いな勉強だって覚えるの楽しくなるし、みんなの役に立てるし、だから……」
子どものように泣く理緒は、やっぱり私の妹で。ひとつしか違わないけど、私はお姉ちゃんで。
そのことに何も変わりはないのに、どこで私はそれを見失ってしまったんだろう。
「ごめん、理緒。間違ってたのは、私の方だったね」
私の言葉を聞いて、すん、と鼻をすすりながら顔をあげる理緒。
「どうしてこんなに私だけがうまくいかないのかなって、どうしてみんな幸せそうなんだろうって憎んで……自分だけが悲しい、苦しい、そんなふうに思ってた」
──それは、悲劇のヒロインだった。
「……お姉ちゃん」
けれど、実際はそんなことなくて。
「理緒も、お母さんもみんな……苦しんでいたのに、そのことに気づいてあげられなくて、ごめん」
静かに、深く、頭を下げた。
「理緒をたくさん傷つけて、ごめん」
一年先に生まれたら、お姉ちゃん。
一年後に生まれたら、妹。
世界でたった一人の大切な妹なのに。