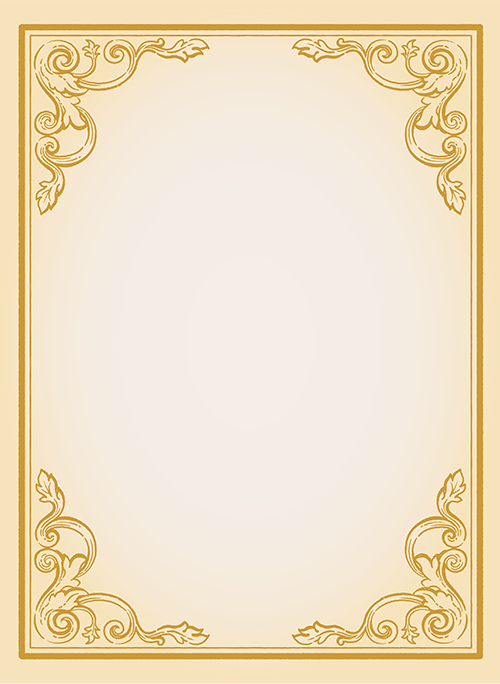「んまいっ」
正午を回ったところで、僕たちはお昼ごはんを食べることにした。遊園地内で食事をとるのは少々値が張る。お財布的にはあまり好ましくない。そして、遊園地内での食事とうのは、なぜか家の近くにある飲食店で食べるときよりも美味しく感じてしまう。実際に味は悪くないのかもしれない。けれど、それだけではなくて、この雰囲気みたいなのも一緒に味わっているような、そんな感じ。
栞が食べているのは玉子とかベーコンとかレタスが入っている、どこにでも売ってそうなサンドイッチだ。少しコンビニとかで売っているやつよりも、大きい以外に特徴はない。僕が頼んだのは、ハーフサイズのピザだ。ハーフサイズなのにかなり大きい。これの倍と思うと、一枚を一人で食べきるのは常人では厳しいだろう。基本的にシェアして食べるようなのかもしれない。
少し冷めてきたが、一応まだ伸びるチーズを堪能しながら、咀嚼する。
「私、花火観たいなー」
サンドイッチを呑み込んだ栞は、言った。マヨネーズが口元についている。
「人混みはあんまり得意じゃないから、気が進まないな」
口では言わず、あえてボディランゲージでマヨネーズがついていることを伝えた。
「え、なんかついてる?」
「うん」
お手拭きを彼女に渡した。
「ありがとー。で、さっきの話だけど、行こうよ!」
「考えとくよ」
「やったねっ」
残された期間は十日と少し、か。
栞と仲良くなればなるほど、別れるときにどういう思いをするのか、僕自身はわかっているようでわかっていないのかもしれない。僕が人並みの心を持ち合わせているのであれば、きっと辛いのだろう。けれど、まだ彼女が九月になれば、いなくなるという実感が湧かないのだ。そして、彼女がいなくなった後の、悲しむ自分の姿を想像できないのだ。
多分、想像できないのは、父さんがいなくなったときに何も感じなかったから。父さんとの関係は希薄だった。それでも、十年以上同じ家で暮らしてきた人だ。父さんがいなければ、僕はこうして彼女と出会うこともなかった。感謝している。
彼女と出会ってまだ数週間。そんな僕がちゃんと悲しめるのかわからない。悲しめなかったときの自分が怖い。
僕が一ヶ月後に消えるという彼女に付き合うことにしたのは、別れというものを知らないというのも一つの理由なのではないか、と思ってしまった。小学校や中学校で別れというのは経験してきたが、今回の状況と訳が違う。会いたくても会えないような別れ、たとえば両親の離婚や死別、そういった類の別れを経験していない。
まだ僕は別れに恐怖や不安といった感情を持っていないのだと思う。
「どうしたの?」
サンドイッチを平らげた彼女が訊いてきた。
「いや、何でもないよ」
「最近、ぼーっとしてること多くない? もしかして、私が色んなところに付きあわせちゃってるから、疲れちゃった?」
「まあ、それもあるね。毎日疲労感が拭いきれないよ」
僕はおどけて言った。
「もっとオブラートに包んでよ! 泣きそうです!」
「冗談だよ。ちゃんと楽しんでるし、疲れなんて全くない」
「イジワル」
ご飯を食べ終わった僕らはトレーを返却し、店を出た。彼女のことで考えることが最近多い。彼女の前ではあまり考えないようにしたいけれど、どうしても話していると、考え込んでしまうことが多かった。彼女に気を遣わせるわけにはいかないし、気をつけないといけない。
「次、どうする?」
「あれにしましょう!」
彼女は僕を置いて、コーヒーカップの方へかけて行った。少し風が強い。熱気を帯びた向かい風に立ち向かいながら、僕はついていった。
夕暮れ。昼間は汗が身体を流れ続けたが、この時間になると気温も落ち着いてきた。それでも、暑いけど。
そろそろ閉園の時間が迫っており、帰宅し始める人たちもいた。僕らは最後のアトラクションに乗るため、列に並んでいる。「観覧車に最後乗りたいです!」という彼女の希望だ。
今日一日歩きすぎて、足が痛い。明日は筋肉痛になりそうだ。普段から歩かされているが、今日はいつになく歩いた。楽しかったから、いいんだけれど。
チケットを渡し、乗り込んだ。渡したお姉さんには、一人で観覧車に乗る寂しい人、と思われてしまったかもしれない。
僕らを乗せたゴンドラはゆっくりと上昇していく。真っ赤な太陽は地平線に沈んでいく。こうしてちゃんと夕日を見たことがなかったので、神秘的だった。ゴンドラについている小さな窓から射し込んでくる夕日のせいか、栞の頬は少し赤らんでいるように見えた。横顔がとても綺麗だった。
「ん? またぼーっとしてた?」
栞にそう言われてしまったので、僕はまたぼんやりとした顔をしていたのか。彼女の姿が綺麗で、魅入っていたなんて言えないので、適当に誤魔化すことにした。
「綺麗だなって思って」
「そうだねぇ。私、いつも見てたはずなのに、こんなに綺麗なものなんだって初めて知ったよ」
「それは生前の話?」
「そう。生きてた頃の話」
僕は彼女の生前について質問してもいいのだろうか。出会った頃と比べると、自然に会話はできているし、関係も濃くなっている。知りたいけれど、あまり思い出したくないものだったらどうしよう、と思うと訊ねることを躊躇う。
「今日は楽しかったね」
ゴンドラが頂上に到達しそうなタイミングで彼女は突拍子もなく言った。
「うん。お化け屋敷を除いてね」
「私も絶叫系を除いてだけどねー」
後半は僕らが苦手なものは避けて、乗った。スリリングなものはなかったけれど、楽しむことができたのは彼女が楽しませてくれたからだと思う。会話は途切れることなく続いた。
「私だけが楽しんでるんじゃないかと思ってたから、安心したよ」
「どうして?」
「ぼーっとしてること多かったし」
「それは......」
僕は一呼吸置き、口を開く。
「君のことを考えてたから」
「え? これって告白?」
「違う」
栞は大げさに照れている。本気にしていないのは見たらわかる。
「それに、付き合ってる相手に告白っておかしいでしょ」
「確かにねー、じゃあどういうこと?」
やはり、彼女も僕らが付き合っているという感覚はあまりないのかもしれない。
「その......このまま栞が消えたら、僕はどうなるんだろう、って。辛いんだろうけど、意外と平気だったときの自分が怖いんだよ」
「そんなに私のこと想ってくれてたんだー。やっぱり、本気で好きになっちゃった?」
「好きか嫌いかの二択だったら好きになるけど、一度亡くなった人間に恋するはずないから安心して」
僕は彼女に聞こえないくらい小声で、「多分」と付け加えた。
「恋するはずない、まで言われるとちょっと傷つくなー。まあ、秋太くんは私が消えた後のことは心配しなくてもいいよ」
「なんで?」
心配しなくてもいい、とはどういうことだろう。文字通り、心配する必要はないということだろうけど、どうしてそう言えるのか。それと、少し寂しそうな顔をするのは、どうしてだ。
「なんでも! だよ。心配しなくていいって言ったら、心配しなくていいの。大丈夫だから」
彼女の言葉は優しかった。その言葉には安心感があり、不安だった気持ちは薄れた。
「わかったよ」
彼女は微笑んで、目線を窓の向こうに見える、夕日に向けた。その後も少し会話を交わしているうちに、ゴンドラは地上に戻ってきた。
出口を目指す群衆に紛れて、僕らも出口を目指した。
「夕飯はどうする?」
僕らが予約したホテルには夕食は付いていないので、これからお店を探さないといけない。
「ファミレス?」
「僕が質問したんだから、疑問で返されても困るんだけど」
「ファミレス!」
「別にファミレスを悪く言うつもりはないけど、そんなんでいいの? もっと高級なお店とかじゃなくて」
「全然いいよー。むしろ、普通の生活をしたいな、私」
僕はなんでも良かったので、ファミレスを探した。僕たちが住む地域にもある、チェーン店を見つけた。安くて、そこそこ美味しい、と評判のファミレスだ。入店すると、夏休みということもあり、数組待っていた。
「別の店にする?」
「ここでいいよ。話してれば、あっという間でしょ?」
栞と話していると、飛ぶように時間は過ぎていく。大井のような友達はいるけれど、交友関係は広い方ではないし、気兼ねなく話せる友達は少なかったので、彼女の存在は貴重だった。自分でもどうしてここまで打ち解けて話せているのかわからない。彼女の気さくさが要因なんだろうな、とぼんやり思う。
今日の遊園地の感想を言い合っていると、すぐに名前を呼ばれた。二人がけのテーブル席に案内された。隣には三人組の同い年くらいの男女がいた。
「ねえ、イヤフォンつけといた方がいいんじゃない?」
彼女なりの気遣いだろう。僕が怪しまれないように。
「いいよ、別に。食事中にイヤフォンするのは行儀悪いし、本当に気にしないから」
彼女は小さく、「ありがと」と言った。感謝されるほどのことはしていないんだけどな。
僕はオーソドックスなハンバーグを頼み、彼女はミートスパゲッティを注文した。あと、彼女が食べたいと言うので、ポテトも。
「私、旅行するのって初めてなんだよねー」
「そうなの?」
「うん」
「もしかして、僕より酷い家庭環境だったとか?」
「ううん。お父さんもお母さんも、私のこと真剣に考えてくれてたし、二人の仲は良好だったと思うよ」
「両親が旅行嫌いだったとか?」
「うーん。どうだろ。わかんないなぁ。今となっちゃ確かめることもできないしね」
せめて両親くらいは、彼女の姿が見えてもいいのに、と思った。僕より断然適しているだろう。きっと彼女も両親と一緒に一ヶ月を過ごした方が嬉しかったはずだ。どうして、僕なんだ。
「両親に会いに行ったりしたの?」
「イヤフォン取りに行くときとか、出会ったねー。認識しているのは私だけなのに、目が合うたびにドキッとしちゃう」
寂しげな表情をする彼女を見ると、どうして僕なんだ、という気持ちが一層強くなる。どうして彼女と一切無関係な、僕なんだよ......。
「今、秋太くんが考えてること当ててあげよっか?」
いきなり超能力者のような発言をし始めた。
「なんで自分だけが私のこと見えるんだー、ってそんなこと考えてたんじゃない?」
「やっぱり君は僕の頭の中を覗けるの?」
「違います! 表情見れば、大体わかるよ」
彼女は人をよく見ている。他人をあまり気にしない僕とは真反対な気がした。
「そんな自分を責めたりはしないでね? 私は君とこうして話したり、遊んだり、関わっていることが、すごい好きなんだから」
「そう言ってもらえると、少しは救われるよ」
「何回でも言ってあげるよー」
子どもがいたずらを仕掛けたときのような、無邪気な笑みを浮かべた。きっと彼女が思っている以上に、その言葉に僕の心は軽くなった。
「ねえねえ、隣の女の子、めちゃくちゃ引いてるよ?」
スパゲッティをすすった彼女は言った。
「僕も気づいてるよ」
男子二人は特に気にしていないようだけど、一人の女子は引き気味にこちらを見ている。当然だろう。男子高校生が独り言を垂れ流しているのだから。しかも、そこそこの声量で。
「さすがにそんな目で秋太くんが見られてると、私も気が引けちゃうなぁ」
「あと数十分だから。気にしないよ」
と言いつつも、ここまで視線を浴び続けたら、僕も少しは気にしてしまう。
「今から喋った方が負けゲームしない?」
「なにその明らかに僕に気を遣ったゲームは」
「いいじゃんいいじゃん。たまには無言の時間も大事だと思うんだよ。今日は、私たちの発声器官を酷使しすぎたし」
彼女の言う通り、今日はいつも以上に喋った。少し喉もかれている気がする。
「負けたら何かあるの?」
「うーん。あとでジュース奢り?」
「君が負けたとしても、払うの僕だよね」
「まあまあ! 細かいことは気にしないで。よーい、スタート!」
僕がゲームをすることに賛成しないまま、開始された。彼女なりの優しさと受け取っておこう。
何分経っただろう。もう十分は話していない感覚だけど、まだ一分しか経っていないような気もする。ずっと話していたせいか、落差がすごい。何とも言えない空気感だ。
僕らは目の前のご飯を口に運ぶ以外の動作を行っていない。口を開くのも、食べ物を入れるため。
少し、視線を向けられる頻度が下がった気がする。
僕がコーンを食べていると、彼女が机をトントンと叩いた。何かあったのか、と目を向ける。
そこには変顔をした彼女がいた。多分、一般的に面白い部類に入らないような、変顔だったけれど、突然のことで僕は笑みをこぼしてしまった。ぷっ、と声も出た。
「君の負けだね」
「それはちょっとずるくないか?」
「女の子はずるいくらいの方が可愛くないですか?」
「そうなのかな」
そんなことしなくても、充分可愛いと思ったけれど、口にできるはずがなかった。
結局僕は先ほどよりも痛い視線を浴びながら、ハンバーグを食べることとなった。
夕飯を食べ終わり、ファミレスを出た僕たちは今日泊まるホテルに向かった。その途中、自販機で栞にりんごジュースを買った。僕も喉が渇いていたので、麦茶を購入。
日はすっかり沈んでおり、じめじめとした空気に包まれている。昼間のカラッとした暑さの方がマシに思えてくる。
ファミレスから数分歩いたところで、ビジネスホテルが見えてきた。アプリを見ながら進んだので、迷わずにたどり着くことができた。
チェックインを済ませ、今回泊まる部屋に向かう。どうやら八階にあるらしく、エレベーターで上がることにした。エレベーターを降りると、真紅に染まった綺麗な絨毯と白を基調とした壁が目に入り、清潔感が滲み出ていた。少し歩くと、僕らの部屋があった。
扉を開け、中に入る。想像していたよりもかなり広かった。ちゃんとベッドも二つ用意されていた。オートロック式であるので、鍵の扱いには気をつけないと閉め出される可能性がある。
「うわーっ」
栞は子どもみたいにベッドにダイブした。少し前までの大人っぽい印象は徐々に上書きされていっている。こっちが本当の彼女の姿なのかもしれない。
「秋太くんもおいでよ」
栞は手を上下させ、招いた。
「子どもみたいなことしないよ」
「高校生なのに大人ぶっちゃってー」
少し腹立たしい言い方をしてくる彼女の発言をスルーする。
「お風呂先に入っちゃってもいい?」
「ん? 別にいいよー」
許可を貰えたので、ユニットバスへ向かった。
「次どうぞー」
「はーい」
栞はテレビを点けて、ゲラゲラ笑っていた。どうやらお笑い番組がやっていたようで、それを見ているらしかった。
「入らないの?」
「もうちょっと、あとちょっとで入るから」
中々動こうとしなかった。
「一日動き回った服で寝ると、ベッド汚れるよ」
「なっ。私は汚くないから大丈夫です! 今のちょっと失礼だからね!」
怒らせるつもりはなかったけれど、怒らせてしまったようだ。彼女はスッと立ち上がり、ユニットバスへ向かった。
そのまま入るのかと思いきや、こちらを振り返った。
「覗いちゃダメだからねー」
「バカ。早く入って」
クスクス笑いながら、栞は扉をすり抜けていった。僕には彼女のような能力は備わっていないので、絶対覗けるわけないんだけどな。
「気持ちよかったー」
シャンプーのいい香りと共に、栞は出てきた。パジャマを着ている。見たことがなかったので、新鮮だった。視線は自然と彼女の方へ向いてしまう。
彼女は僕が座っていたベッドの隣に座った。
「もう一つベッドは空いてるけど」
「いーじゃん。こっちでも」
さっきより香りが強くなる。少しドキッとしてしまったことに気づかれてないかな。彼女は何の気なしにテレビを見ているので、おそらく大丈夫。
やっぱり同じ部屋はやめた方が良かったかもしれない。意識するな、というのは無理がある。女の子と同じ部屋で寝たことなんてあるわけない。今度は緊張が伝わらないか、心配になる。心臓の音は聞こえてないだろうか? クーラーが効いており、涼しいはずの部屋の中で変な汗が吹き出てくる。
「ねえ」
いきなり話しかけられたせいで、自然と背筋が伸びてしまった。
「なに?」
僕の質問には答えず、彼女は自分の持ってきたカバンの方へ歩いて行った。何かを探しているようだ。見つかったのか、「おっ」と一声発した。
「じゃじゃーん。これしようよ!」
彼女が手に持っていたのは、『罰ゲーム』と書かれた四角い箱だった。カードゲームっぽい。
「罰ゲーム? とは」
「罰ゲームは罰ゲームだよ」
まだやると言っていないのに、彼女は箱を開け始めた。
「こういうのって大人数でやるものじゃないの? 絶対二人でやるものじゃないと思うんだけど」
「まあ普通はね。でも誘える人なんていないし、私たち二人でやるしかないでしょ?」
「別のゲームにするっていう考えはないの?」
「ない! 憧れだったの!」
見るからに過酷そうなゲームに憧れる彼女は、どうかしている。断りたいけれど、キラキラした彼女の目を見ると、やらない、とは言えなかった。
「わかった。ルール説明よろしく」
「任せて! えっと、このサイコロで大きい目を出した人が勝ちっぽい。負けた人がこのカードの束から一枚引いて、そのお題をクリアする。っていうゲームらしいよ」
サイコロで大きい目を出し続ければ、回避できるのか。運だからそう上手くいかないだろうけど。やると決めたからには、罰ゲームをできる限り受けないようにしたい。
ベッドに座っていた僕は、小さなテーブルに移動した。ベッドの上ではさすがにやりにくい。
「よし、じゃあやるよっ」
「ちょっと待って。罰ゲームは絶対?」
「絶対。と言いたいところだけど、さすがに無理ってのがあったら、逃げてもいいよ。そのときは私の言うこと聞いてもらうけどねー」
「それは僕も同じ条件だよね? 栞が拒否したら、僕の言うことを聞いてくれるってこと?」
「まあ、そういうことだね。私が拒否することはないけどね」
自信満々の彼女はサイコロを振った。
「げっ。2だ」
これならさすがに勝てる。余裕綽々の表情を浮かべながら、僕はサイコロを振った。
「......嘘だ」
「ふふっ。最高だね。ほらほら、引いて引いて」
1を出してしまった僕は、絶望しつつカードをめくった。
「自分の一番恥ずかしかった思い出を話す。だってさ」
「おぉ、気になる!」
恥ずかしかった思い出かぁ。記憶をたどるけれど、そんなに恥ずかしいと感じた思い出が出てこなかった。小さな羞恥は味わっているだろうけど、どれも大したことないので、一番を決めるのも難しい。
「小学生の頃、調子に乗って木から飛び降りて足を骨折したときは恥ずかしかったと思う」
「えー、意外! やんちゃだったんだ」
「あの頃は社交性が今よりも優れていた気がするね」
「過去の自分を見習わないとね。よし、次!」
彼女が振り、次に僕が振る。
「うわっ、私が引く番か」
彼女が恐る恐るカードを一枚引く。
「隣の人と手を繋ぐ。だって」
「隣に誰もいないし、もう一度引いてもいいよ」
「いやいや、目の前にいるじゃん!」
「僕は前にいるのであって、隣じゃないから......」
自分でも屁理屈を言っているのはわかっているけれど、回避できるものならしたかった。
「また私手をつなぐの断られるのかぁ」
そういや改札出るとき、そんなやりとりをした気がする。遊園地でつないだのは、ノーカウントなのかな。
「わかったよ。ん」
いたって冷静を装い、手を差し出した。心の中はぐちゃぐちゃになっているのに。
「失礼しまーす」
陽気な彼女は、僕の手を躊躇なく握った。
とてつもなく、恥ずかしい。一番恥ずかしかった出来事は今なのかもしれない。それぐらい顔が熱くなっているし、他に何も考えられなくなっている。中学の頃に付きあっていた子がいたけど、その子と手をつないだときはこんなにも緊張しなかったと思う。栞と手をつなぐのがどうしてこんなにもかき乱されるのかわからない。
僕らは愛しあって、付き合い始めたわけではない。だからこそ、付き合っているという感覚は薄く、友達として接する部分がある。友達と気楽に手をつなぐという、アメリカ人ばりのフレンドリーさが僕にはないので、こんなに動揺しているのかもしれない。
彼女の方はどう感じているのかと思い、顔を見ると、タコのように真っ赤になっていた。
「恥ずかしいの?」
僕が訊くと、すごい勢いで頷いた。僕らは手を離した。
「実際つないでみると、とっても恥ずかしいですね!」
「まあ、うん」
これでよく駅内で手をつなぐことを提案したな、と思う。なんだか僕よりも恥ずかしがる彼女が目の前にいると、羞恥心は消えていった。
「初めて男の子と手をつないだので、心臓バクバクしてます......」
やはり遊園地で手を握ったのは、カウントされていないらしい。ジェットコースターでつないだときは、恐怖でそれどころじゃなかったんだろうな。恐怖で心臓がバクバクしていたのだろう。
「前から思ってたけど、君の今まで誰とも付き合っていないというのは、設定じゃないの?」
「違いますー。だから本当は男の子と喋るのもあんまり慣れてないんですよ」
小さく、「女の子もだけど」と彼女は付け加えた。
「出会ったときから、普通に会話してた気がするけど」
「自分でも不思議なんですよね。秋太くんはなんかいけちゃった」
「僕は褒められてると思っていいのかな」
「うん。褒めてるよ」
笑顔で彼女はまたサイコロを振る。
「ふふっ。勝ちました!」
これで九戦目だ。二戦目に出た手をつなぐやつ以外は、スキンシップをとるような罰ゲームはなかった。あれって勝った人も罰を受けることになるんだよな。出ないことを祈る。
ここまでで出たやつは、『秘密を一つ教える』とか『腕立て伏せを十回する』とか、その程度のものだった。『デコピンをされる』というのもあったけれど、デコピンはスキンシップとは言いがたい。
「言われなくても、わかってるよ」
僕はカードを一枚めくる。
「初恋の話。だって」
「恋バナってやつですか! これが!」
「僕の初恋の話なんて面白くないと思うけどね」
「秋太くんの初恋を聞いて、面白くないはずないんで、大丈夫です!」
無駄にハードルを上げられたな。
僕は記憶を遡る。初恋はきっと小学生の頃だ。
「僕がさっきした骨折の話覚えてる?」
「当然」
「そのとき、一ヶ月くらいかな。入院することになったんだよね」
「かなり酷かったんですか?」
「手術もしたし、僕の人生で一番の怪我だったね」
今考えると、どうしてあんなバカなことをしたのだろう、と思う。小学生の頃の身長を考えれば、かなり高さだったように思える。確か友達がいる前だった。自分をすごい奴に見せたいがために、飛び降りた。ああいうのを見栄っ張りというのだろう。
「入院してると、とにかく暇なんだよ。ベッドの上で何もすることなくてさ。やることがなさすぎて、多分漫画にもハマることになったんだと思う」
栞は興味深そうに、頷く。こんなに興味を持ってくれると、こちらとしても話しやすい。
「足にギプスしてたんだけど、昔はやんちゃだったこともあって、ベッドから降りて抜け出すことがあったんだよね」
「それは本当にやんちゃですね」
「今ではお医者さんにも迷惑かけたなって思ってるよ。一応松葉杖があったから、それでウロウロしてたんだけど、あるきっかけで出会った子がいたんだよね。その子が僕の初恋だったと思う」
「一目惚れ?」
あの頃の僕の心情を覚えていないけれど、多分違う。今と性格は違うかもしれないけれど、本質みたいなものは変わっていないはずなので、その子の振る舞いとかそういう部分に惹かれたんだと思う。
「違うと思う。話していくうちに徐々に好きになっていったんだと思う」
「普通の恋愛をしていることに、私はびっくりしてます」
「僕を何だと思ってるの? まあ、いいや。その子が今どうなってるかはわからないし、プライバシーを考えると、あんまり言うべきではないのかもしれないけど......」
「他言無用って言葉があるよね。私以上に信用できる人いないと思うんで、安心してください」
僕は少し笑って、続きを言う。
「その子は確か何かの病気で、身体を自由に動かせなかったんだ。いつも母親に車椅子で押してもらって移動してた。基本的にベッドの上にいたから、僕が抜け出して、会いに行ってた」
彼女は今、何をしているのだろう。まだ病魔と闘っているのだろうか。連絡先を知らないので、知りようがないのだけど。あの頃に携帯を持っていれば、何とかなったかもしれないと後悔する。
「そ、そうなんだ! その子の名前とか覚えてないの?」
「十年も前の話だから覚えてないんだよね」
「初恋の相手が泣いちゃうよ」
「うーん。やっぱり、思い出せない」
「そうなんだ......」
彼女は少し元気がなくなったような、そんな様子。そんなに知りたかったのだろうか。
「どうしたの?」
「え、いや何でもないよ! その子とはどうやって出会ったの?」
「なんか病院内に子どもたちが遊べるスペースみたいなのがあって、そこで出会ったと思う。どういう風に話しかけたとかはさすがに覚えてないけどね」
「秋太くんの意外な一面がいっぱいだね」
「過去の話だけどね。こんなものでいい? 初恋の話」
「うん!」
彼女は笑顔に戻り、サイコロを振った。6が出た。負けが決定した。
「引いて!」
「隣の人とハグする。ってのが出た」
十戦目にして一番ハードなやつが出てしまった。栞とハグ......?
「どうぞ」
彼女は両手を広げ、全てを受け止めてくれそうな優しい笑みを浮かべた。さっきの手をつないだときのことを思い出したのか、彼女の頬が紅潮している。
さすがにこれは......ダメだよな。
「回避するよ」
「私は全然構わないのに」
「僕が構うよ......」
彼女の発言は強がりであることがすぐにわかった。手を繋いだだけであれだけ顔が赤くなっていたのだ。ハグなんてしたら沸騰してぶっ倒れるんじゃないだろうか。
十戦終えると、疲れがドッと襲ってきた。
「そろそろ寝ない?」
「いい時間ですしねー。寝ますか」
僕らは別々のベッドに飛び込んだ。ふかふかですぐに眠りに落ちそう。
「あ、私のお願い聞いてもらうね」
覚えていたのか......。忘れてくれて良かったのに。
「なに?」
「帰ったら、卒業アルバム見せて欲しいです」
「そんなのでいいの?」
「はい! 小学生の頃の秋太くんを見てみたいです」
助かった。無理難題を命令されるのかと思って、ビクビクしていたが、それくらいならいくらでも見せてあげよう。
「また見せるよ」
「ありがとう。おやすみ」
「おやすみ」
消灯し、僕らは眠った。
正午を回ったところで、僕たちはお昼ごはんを食べることにした。遊園地内で食事をとるのは少々値が張る。お財布的にはあまり好ましくない。そして、遊園地内での食事とうのは、なぜか家の近くにある飲食店で食べるときよりも美味しく感じてしまう。実際に味は悪くないのかもしれない。けれど、それだけではなくて、この雰囲気みたいなのも一緒に味わっているような、そんな感じ。
栞が食べているのは玉子とかベーコンとかレタスが入っている、どこにでも売ってそうなサンドイッチだ。少しコンビニとかで売っているやつよりも、大きい以外に特徴はない。僕が頼んだのは、ハーフサイズのピザだ。ハーフサイズなのにかなり大きい。これの倍と思うと、一枚を一人で食べきるのは常人では厳しいだろう。基本的にシェアして食べるようなのかもしれない。
少し冷めてきたが、一応まだ伸びるチーズを堪能しながら、咀嚼する。
「私、花火観たいなー」
サンドイッチを呑み込んだ栞は、言った。マヨネーズが口元についている。
「人混みはあんまり得意じゃないから、気が進まないな」
口では言わず、あえてボディランゲージでマヨネーズがついていることを伝えた。
「え、なんかついてる?」
「うん」
お手拭きを彼女に渡した。
「ありがとー。で、さっきの話だけど、行こうよ!」
「考えとくよ」
「やったねっ」
残された期間は十日と少し、か。
栞と仲良くなればなるほど、別れるときにどういう思いをするのか、僕自身はわかっているようでわかっていないのかもしれない。僕が人並みの心を持ち合わせているのであれば、きっと辛いのだろう。けれど、まだ彼女が九月になれば、いなくなるという実感が湧かないのだ。そして、彼女がいなくなった後の、悲しむ自分の姿を想像できないのだ。
多分、想像できないのは、父さんがいなくなったときに何も感じなかったから。父さんとの関係は希薄だった。それでも、十年以上同じ家で暮らしてきた人だ。父さんがいなければ、僕はこうして彼女と出会うこともなかった。感謝している。
彼女と出会ってまだ数週間。そんな僕がちゃんと悲しめるのかわからない。悲しめなかったときの自分が怖い。
僕が一ヶ月後に消えるという彼女に付き合うことにしたのは、別れというものを知らないというのも一つの理由なのではないか、と思ってしまった。小学校や中学校で別れというのは経験してきたが、今回の状況と訳が違う。会いたくても会えないような別れ、たとえば両親の離婚や死別、そういった類の別れを経験していない。
まだ僕は別れに恐怖や不安といった感情を持っていないのだと思う。
「どうしたの?」
サンドイッチを平らげた彼女が訊いてきた。
「いや、何でもないよ」
「最近、ぼーっとしてること多くない? もしかして、私が色んなところに付きあわせちゃってるから、疲れちゃった?」
「まあ、それもあるね。毎日疲労感が拭いきれないよ」
僕はおどけて言った。
「もっとオブラートに包んでよ! 泣きそうです!」
「冗談だよ。ちゃんと楽しんでるし、疲れなんて全くない」
「イジワル」
ご飯を食べ終わった僕らはトレーを返却し、店を出た。彼女のことで考えることが最近多い。彼女の前ではあまり考えないようにしたいけれど、どうしても話していると、考え込んでしまうことが多かった。彼女に気を遣わせるわけにはいかないし、気をつけないといけない。
「次、どうする?」
「あれにしましょう!」
彼女は僕を置いて、コーヒーカップの方へかけて行った。少し風が強い。熱気を帯びた向かい風に立ち向かいながら、僕はついていった。
夕暮れ。昼間は汗が身体を流れ続けたが、この時間になると気温も落ち着いてきた。それでも、暑いけど。
そろそろ閉園の時間が迫っており、帰宅し始める人たちもいた。僕らは最後のアトラクションに乗るため、列に並んでいる。「観覧車に最後乗りたいです!」という彼女の希望だ。
今日一日歩きすぎて、足が痛い。明日は筋肉痛になりそうだ。普段から歩かされているが、今日はいつになく歩いた。楽しかったから、いいんだけれど。
チケットを渡し、乗り込んだ。渡したお姉さんには、一人で観覧車に乗る寂しい人、と思われてしまったかもしれない。
僕らを乗せたゴンドラはゆっくりと上昇していく。真っ赤な太陽は地平線に沈んでいく。こうしてちゃんと夕日を見たことがなかったので、神秘的だった。ゴンドラについている小さな窓から射し込んでくる夕日のせいか、栞の頬は少し赤らんでいるように見えた。横顔がとても綺麗だった。
「ん? またぼーっとしてた?」
栞にそう言われてしまったので、僕はまたぼんやりとした顔をしていたのか。彼女の姿が綺麗で、魅入っていたなんて言えないので、適当に誤魔化すことにした。
「綺麗だなって思って」
「そうだねぇ。私、いつも見てたはずなのに、こんなに綺麗なものなんだって初めて知ったよ」
「それは生前の話?」
「そう。生きてた頃の話」
僕は彼女の生前について質問してもいいのだろうか。出会った頃と比べると、自然に会話はできているし、関係も濃くなっている。知りたいけれど、あまり思い出したくないものだったらどうしよう、と思うと訊ねることを躊躇う。
「今日は楽しかったね」
ゴンドラが頂上に到達しそうなタイミングで彼女は突拍子もなく言った。
「うん。お化け屋敷を除いてね」
「私も絶叫系を除いてだけどねー」
後半は僕らが苦手なものは避けて、乗った。スリリングなものはなかったけれど、楽しむことができたのは彼女が楽しませてくれたからだと思う。会話は途切れることなく続いた。
「私だけが楽しんでるんじゃないかと思ってたから、安心したよ」
「どうして?」
「ぼーっとしてること多かったし」
「それは......」
僕は一呼吸置き、口を開く。
「君のことを考えてたから」
「え? これって告白?」
「違う」
栞は大げさに照れている。本気にしていないのは見たらわかる。
「それに、付き合ってる相手に告白っておかしいでしょ」
「確かにねー、じゃあどういうこと?」
やはり、彼女も僕らが付き合っているという感覚はあまりないのかもしれない。
「その......このまま栞が消えたら、僕はどうなるんだろう、って。辛いんだろうけど、意外と平気だったときの自分が怖いんだよ」
「そんなに私のこと想ってくれてたんだー。やっぱり、本気で好きになっちゃった?」
「好きか嫌いかの二択だったら好きになるけど、一度亡くなった人間に恋するはずないから安心して」
僕は彼女に聞こえないくらい小声で、「多分」と付け加えた。
「恋するはずない、まで言われるとちょっと傷つくなー。まあ、秋太くんは私が消えた後のことは心配しなくてもいいよ」
「なんで?」
心配しなくてもいい、とはどういうことだろう。文字通り、心配する必要はないということだろうけど、どうしてそう言えるのか。それと、少し寂しそうな顔をするのは、どうしてだ。
「なんでも! だよ。心配しなくていいって言ったら、心配しなくていいの。大丈夫だから」
彼女の言葉は優しかった。その言葉には安心感があり、不安だった気持ちは薄れた。
「わかったよ」
彼女は微笑んで、目線を窓の向こうに見える、夕日に向けた。その後も少し会話を交わしているうちに、ゴンドラは地上に戻ってきた。
出口を目指す群衆に紛れて、僕らも出口を目指した。
「夕飯はどうする?」
僕らが予約したホテルには夕食は付いていないので、これからお店を探さないといけない。
「ファミレス?」
「僕が質問したんだから、疑問で返されても困るんだけど」
「ファミレス!」
「別にファミレスを悪く言うつもりはないけど、そんなんでいいの? もっと高級なお店とかじゃなくて」
「全然いいよー。むしろ、普通の生活をしたいな、私」
僕はなんでも良かったので、ファミレスを探した。僕たちが住む地域にもある、チェーン店を見つけた。安くて、そこそこ美味しい、と評判のファミレスだ。入店すると、夏休みということもあり、数組待っていた。
「別の店にする?」
「ここでいいよ。話してれば、あっという間でしょ?」
栞と話していると、飛ぶように時間は過ぎていく。大井のような友達はいるけれど、交友関係は広い方ではないし、気兼ねなく話せる友達は少なかったので、彼女の存在は貴重だった。自分でもどうしてここまで打ち解けて話せているのかわからない。彼女の気さくさが要因なんだろうな、とぼんやり思う。
今日の遊園地の感想を言い合っていると、すぐに名前を呼ばれた。二人がけのテーブル席に案内された。隣には三人組の同い年くらいの男女がいた。
「ねえ、イヤフォンつけといた方がいいんじゃない?」
彼女なりの気遣いだろう。僕が怪しまれないように。
「いいよ、別に。食事中にイヤフォンするのは行儀悪いし、本当に気にしないから」
彼女は小さく、「ありがと」と言った。感謝されるほどのことはしていないんだけどな。
僕はオーソドックスなハンバーグを頼み、彼女はミートスパゲッティを注文した。あと、彼女が食べたいと言うので、ポテトも。
「私、旅行するのって初めてなんだよねー」
「そうなの?」
「うん」
「もしかして、僕より酷い家庭環境だったとか?」
「ううん。お父さんもお母さんも、私のこと真剣に考えてくれてたし、二人の仲は良好だったと思うよ」
「両親が旅行嫌いだったとか?」
「うーん。どうだろ。わかんないなぁ。今となっちゃ確かめることもできないしね」
せめて両親くらいは、彼女の姿が見えてもいいのに、と思った。僕より断然適しているだろう。きっと彼女も両親と一緒に一ヶ月を過ごした方が嬉しかったはずだ。どうして、僕なんだ。
「両親に会いに行ったりしたの?」
「イヤフォン取りに行くときとか、出会ったねー。認識しているのは私だけなのに、目が合うたびにドキッとしちゃう」
寂しげな表情をする彼女を見ると、どうして僕なんだ、という気持ちが一層強くなる。どうして彼女と一切無関係な、僕なんだよ......。
「今、秋太くんが考えてること当ててあげよっか?」
いきなり超能力者のような発言をし始めた。
「なんで自分だけが私のこと見えるんだー、ってそんなこと考えてたんじゃない?」
「やっぱり君は僕の頭の中を覗けるの?」
「違います! 表情見れば、大体わかるよ」
彼女は人をよく見ている。他人をあまり気にしない僕とは真反対な気がした。
「そんな自分を責めたりはしないでね? 私は君とこうして話したり、遊んだり、関わっていることが、すごい好きなんだから」
「そう言ってもらえると、少しは救われるよ」
「何回でも言ってあげるよー」
子どもがいたずらを仕掛けたときのような、無邪気な笑みを浮かべた。きっと彼女が思っている以上に、その言葉に僕の心は軽くなった。
「ねえねえ、隣の女の子、めちゃくちゃ引いてるよ?」
スパゲッティをすすった彼女は言った。
「僕も気づいてるよ」
男子二人は特に気にしていないようだけど、一人の女子は引き気味にこちらを見ている。当然だろう。男子高校生が独り言を垂れ流しているのだから。しかも、そこそこの声量で。
「さすがにそんな目で秋太くんが見られてると、私も気が引けちゃうなぁ」
「あと数十分だから。気にしないよ」
と言いつつも、ここまで視線を浴び続けたら、僕も少しは気にしてしまう。
「今から喋った方が負けゲームしない?」
「なにその明らかに僕に気を遣ったゲームは」
「いいじゃんいいじゃん。たまには無言の時間も大事だと思うんだよ。今日は、私たちの発声器官を酷使しすぎたし」
彼女の言う通り、今日はいつも以上に喋った。少し喉もかれている気がする。
「負けたら何かあるの?」
「うーん。あとでジュース奢り?」
「君が負けたとしても、払うの僕だよね」
「まあまあ! 細かいことは気にしないで。よーい、スタート!」
僕がゲームをすることに賛成しないまま、開始された。彼女なりの優しさと受け取っておこう。
何分経っただろう。もう十分は話していない感覚だけど、まだ一分しか経っていないような気もする。ずっと話していたせいか、落差がすごい。何とも言えない空気感だ。
僕らは目の前のご飯を口に運ぶ以外の動作を行っていない。口を開くのも、食べ物を入れるため。
少し、視線を向けられる頻度が下がった気がする。
僕がコーンを食べていると、彼女が机をトントンと叩いた。何かあったのか、と目を向ける。
そこには変顔をした彼女がいた。多分、一般的に面白い部類に入らないような、変顔だったけれど、突然のことで僕は笑みをこぼしてしまった。ぷっ、と声も出た。
「君の負けだね」
「それはちょっとずるくないか?」
「女の子はずるいくらいの方が可愛くないですか?」
「そうなのかな」
そんなことしなくても、充分可愛いと思ったけれど、口にできるはずがなかった。
結局僕は先ほどよりも痛い視線を浴びながら、ハンバーグを食べることとなった。
夕飯を食べ終わり、ファミレスを出た僕たちは今日泊まるホテルに向かった。その途中、自販機で栞にりんごジュースを買った。僕も喉が渇いていたので、麦茶を購入。
日はすっかり沈んでおり、じめじめとした空気に包まれている。昼間のカラッとした暑さの方がマシに思えてくる。
ファミレスから数分歩いたところで、ビジネスホテルが見えてきた。アプリを見ながら進んだので、迷わずにたどり着くことができた。
チェックインを済ませ、今回泊まる部屋に向かう。どうやら八階にあるらしく、エレベーターで上がることにした。エレベーターを降りると、真紅に染まった綺麗な絨毯と白を基調とした壁が目に入り、清潔感が滲み出ていた。少し歩くと、僕らの部屋があった。
扉を開け、中に入る。想像していたよりもかなり広かった。ちゃんとベッドも二つ用意されていた。オートロック式であるので、鍵の扱いには気をつけないと閉め出される可能性がある。
「うわーっ」
栞は子どもみたいにベッドにダイブした。少し前までの大人っぽい印象は徐々に上書きされていっている。こっちが本当の彼女の姿なのかもしれない。
「秋太くんもおいでよ」
栞は手を上下させ、招いた。
「子どもみたいなことしないよ」
「高校生なのに大人ぶっちゃってー」
少し腹立たしい言い方をしてくる彼女の発言をスルーする。
「お風呂先に入っちゃってもいい?」
「ん? 別にいいよー」
許可を貰えたので、ユニットバスへ向かった。
「次どうぞー」
「はーい」
栞はテレビを点けて、ゲラゲラ笑っていた。どうやらお笑い番組がやっていたようで、それを見ているらしかった。
「入らないの?」
「もうちょっと、あとちょっとで入るから」
中々動こうとしなかった。
「一日動き回った服で寝ると、ベッド汚れるよ」
「なっ。私は汚くないから大丈夫です! 今のちょっと失礼だからね!」
怒らせるつもりはなかったけれど、怒らせてしまったようだ。彼女はスッと立ち上がり、ユニットバスへ向かった。
そのまま入るのかと思いきや、こちらを振り返った。
「覗いちゃダメだからねー」
「バカ。早く入って」
クスクス笑いながら、栞は扉をすり抜けていった。僕には彼女のような能力は備わっていないので、絶対覗けるわけないんだけどな。
「気持ちよかったー」
シャンプーのいい香りと共に、栞は出てきた。パジャマを着ている。見たことがなかったので、新鮮だった。視線は自然と彼女の方へ向いてしまう。
彼女は僕が座っていたベッドの隣に座った。
「もう一つベッドは空いてるけど」
「いーじゃん。こっちでも」
さっきより香りが強くなる。少しドキッとしてしまったことに気づかれてないかな。彼女は何の気なしにテレビを見ているので、おそらく大丈夫。
やっぱり同じ部屋はやめた方が良かったかもしれない。意識するな、というのは無理がある。女の子と同じ部屋で寝たことなんてあるわけない。今度は緊張が伝わらないか、心配になる。心臓の音は聞こえてないだろうか? クーラーが効いており、涼しいはずの部屋の中で変な汗が吹き出てくる。
「ねえ」
いきなり話しかけられたせいで、自然と背筋が伸びてしまった。
「なに?」
僕の質問には答えず、彼女は自分の持ってきたカバンの方へ歩いて行った。何かを探しているようだ。見つかったのか、「おっ」と一声発した。
「じゃじゃーん。これしようよ!」
彼女が手に持っていたのは、『罰ゲーム』と書かれた四角い箱だった。カードゲームっぽい。
「罰ゲーム? とは」
「罰ゲームは罰ゲームだよ」
まだやると言っていないのに、彼女は箱を開け始めた。
「こういうのって大人数でやるものじゃないの? 絶対二人でやるものじゃないと思うんだけど」
「まあ普通はね。でも誘える人なんていないし、私たち二人でやるしかないでしょ?」
「別のゲームにするっていう考えはないの?」
「ない! 憧れだったの!」
見るからに過酷そうなゲームに憧れる彼女は、どうかしている。断りたいけれど、キラキラした彼女の目を見ると、やらない、とは言えなかった。
「わかった。ルール説明よろしく」
「任せて! えっと、このサイコロで大きい目を出した人が勝ちっぽい。負けた人がこのカードの束から一枚引いて、そのお題をクリアする。っていうゲームらしいよ」
サイコロで大きい目を出し続ければ、回避できるのか。運だからそう上手くいかないだろうけど。やると決めたからには、罰ゲームをできる限り受けないようにしたい。
ベッドに座っていた僕は、小さなテーブルに移動した。ベッドの上ではさすがにやりにくい。
「よし、じゃあやるよっ」
「ちょっと待って。罰ゲームは絶対?」
「絶対。と言いたいところだけど、さすがに無理ってのがあったら、逃げてもいいよ。そのときは私の言うこと聞いてもらうけどねー」
「それは僕も同じ条件だよね? 栞が拒否したら、僕の言うことを聞いてくれるってこと?」
「まあ、そういうことだね。私が拒否することはないけどね」
自信満々の彼女はサイコロを振った。
「げっ。2だ」
これならさすがに勝てる。余裕綽々の表情を浮かべながら、僕はサイコロを振った。
「......嘘だ」
「ふふっ。最高だね。ほらほら、引いて引いて」
1を出してしまった僕は、絶望しつつカードをめくった。
「自分の一番恥ずかしかった思い出を話す。だってさ」
「おぉ、気になる!」
恥ずかしかった思い出かぁ。記憶をたどるけれど、そんなに恥ずかしいと感じた思い出が出てこなかった。小さな羞恥は味わっているだろうけど、どれも大したことないので、一番を決めるのも難しい。
「小学生の頃、調子に乗って木から飛び降りて足を骨折したときは恥ずかしかったと思う」
「えー、意外! やんちゃだったんだ」
「あの頃は社交性が今よりも優れていた気がするね」
「過去の自分を見習わないとね。よし、次!」
彼女が振り、次に僕が振る。
「うわっ、私が引く番か」
彼女が恐る恐るカードを一枚引く。
「隣の人と手を繋ぐ。だって」
「隣に誰もいないし、もう一度引いてもいいよ」
「いやいや、目の前にいるじゃん!」
「僕は前にいるのであって、隣じゃないから......」
自分でも屁理屈を言っているのはわかっているけれど、回避できるものならしたかった。
「また私手をつなぐの断られるのかぁ」
そういや改札出るとき、そんなやりとりをした気がする。遊園地でつないだのは、ノーカウントなのかな。
「わかったよ。ん」
いたって冷静を装い、手を差し出した。心の中はぐちゃぐちゃになっているのに。
「失礼しまーす」
陽気な彼女は、僕の手を躊躇なく握った。
とてつもなく、恥ずかしい。一番恥ずかしかった出来事は今なのかもしれない。それぐらい顔が熱くなっているし、他に何も考えられなくなっている。中学の頃に付きあっていた子がいたけど、その子と手をつないだときはこんなにも緊張しなかったと思う。栞と手をつなぐのがどうしてこんなにもかき乱されるのかわからない。
僕らは愛しあって、付き合い始めたわけではない。だからこそ、付き合っているという感覚は薄く、友達として接する部分がある。友達と気楽に手をつなぐという、アメリカ人ばりのフレンドリーさが僕にはないので、こんなに動揺しているのかもしれない。
彼女の方はどう感じているのかと思い、顔を見ると、タコのように真っ赤になっていた。
「恥ずかしいの?」
僕が訊くと、すごい勢いで頷いた。僕らは手を離した。
「実際つないでみると、とっても恥ずかしいですね!」
「まあ、うん」
これでよく駅内で手をつなぐことを提案したな、と思う。なんだか僕よりも恥ずかしがる彼女が目の前にいると、羞恥心は消えていった。
「初めて男の子と手をつないだので、心臓バクバクしてます......」
やはり遊園地で手を握ったのは、カウントされていないらしい。ジェットコースターでつないだときは、恐怖でそれどころじゃなかったんだろうな。恐怖で心臓がバクバクしていたのだろう。
「前から思ってたけど、君の今まで誰とも付き合っていないというのは、設定じゃないの?」
「違いますー。だから本当は男の子と喋るのもあんまり慣れてないんですよ」
小さく、「女の子もだけど」と彼女は付け加えた。
「出会ったときから、普通に会話してた気がするけど」
「自分でも不思議なんですよね。秋太くんはなんかいけちゃった」
「僕は褒められてると思っていいのかな」
「うん。褒めてるよ」
笑顔で彼女はまたサイコロを振る。
「ふふっ。勝ちました!」
これで九戦目だ。二戦目に出た手をつなぐやつ以外は、スキンシップをとるような罰ゲームはなかった。あれって勝った人も罰を受けることになるんだよな。出ないことを祈る。
ここまでで出たやつは、『秘密を一つ教える』とか『腕立て伏せを十回する』とか、その程度のものだった。『デコピンをされる』というのもあったけれど、デコピンはスキンシップとは言いがたい。
「言われなくても、わかってるよ」
僕はカードを一枚めくる。
「初恋の話。だって」
「恋バナってやつですか! これが!」
「僕の初恋の話なんて面白くないと思うけどね」
「秋太くんの初恋を聞いて、面白くないはずないんで、大丈夫です!」
無駄にハードルを上げられたな。
僕は記憶を遡る。初恋はきっと小学生の頃だ。
「僕がさっきした骨折の話覚えてる?」
「当然」
「そのとき、一ヶ月くらいかな。入院することになったんだよね」
「かなり酷かったんですか?」
「手術もしたし、僕の人生で一番の怪我だったね」
今考えると、どうしてあんなバカなことをしたのだろう、と思う。小学生の頃の身長を考えれば、かなり高さだったように思える。確か友達がいる前だった。自分をすごい奴に見せたいがために、飛び降りた。ああいうのを見栄っ張りというのだろう。
「入院してると、とにかく暇なんだよ。ベッドの上で何もすることなくてさ。やることがなさすぎて、多分漫画にもハマることになったんだと思う」
栞は興味深そうに、頷く。こんなに興味を持ってくれると、こちらとしても話しやすい。
「足にギプスしてたんだけど、昔はやんちゃだったこともあって、ベッドから降りて抜け出すことがあったんだよね」
「それは本当にやんちゃですね」
「今ではお医者さんにも迷惑かけたなって思ってるよ。一応松葉杖があったから、それでウロウロしてたんだけど、あるきっかけで出会った子がいたんだよね。その子が僕の初恋だったと思う」
「一目惚れ?」
あの頃の僕の心情を覚えていないけれど、多分違う。今と性格は違うかもしれないけれど、本質みたいなものは変わっていないはずなので、その子の振る舞いとかそういう部分に惹かれたんだと思う。
「違うと思う。話していくうちに徐々に好きになっていったんだと思う」
「普通の恋愛をしていることに、私はびっくりしてます」
「僕を何だと思ってるの? まあ、いいや。その子が今どうなってるかはわからないし、プライバシーを考えると、あんまり言うべきではないのかもしれないけど......」
「他言無用って言葉があるよね。私以上に信用できる人いないと思うんで、安心してください」
僕は少し笑って、続きを言う。
「その子は確か何かの病気で、身体を自由に動かせなかったんだ。いつも母親に車椅子で押してもらって移動してた。基本的にベッドの上にいたから、僕が抜け出して、会いに行ってた」
彼女は今、何をしているのだろう。まだ病魔と闘っているのだろうか。連絡先を知らないので、知りようがないのだけど。あの頃に携帯を持っていれば、何とかなったかもしれないと後悔する。
「そ、そうなんだ! その子の名前とか覚えてないの?」
「十年も前の話だから覚えてないんだよね」
「初恋の相手が泣いちゃうよ」
「うーん。やっぱり、思い出せない」
「そうなんだ......」
彼女は少し元気がなくなったような、そんな様子。そんなに知りたかったのだろうか。
「どうしたの?」
「え、いや何でもないよ! その子とはどうやって出会ったの?」
「なんか病院内に子どもたちが遊べるスペースみたいなのがあって、そこで出会ったと思う。どういう風に話しかけたとかはさすがに覚えてないけどね」
「秋太くんの意外な一面がいっぱいだね」
「過去の話だけどね。こんなものでいい? 初恋の話」
「うん!」
彼女は笑顔に戻り、サイコロを振った。6が出た。負けが決定した。
「引いて!」
「隣の人とハグする。ってのが出た」
十戦目にして一番ハードなやつが出てしまった。栞とハグ......?
「どうぞ」
彼女は両手を広げ、全てを受け止めてくれそうな優しい笑みを浮かべた。さっきの手をつないだときのことを思い出したのか、彼女の頬が紅潮している。
さすがにこれは......ダメだよな。
「回避するよ」
「私は全然構わないのに」
「僕が構うよ......」
彼女の発言は強がりであることがすぐにわかった。手を繋いだだけであれだけ顔が赤くなっていたのだ。ハグなんてしたら沸騰してぶっ倒れるんじゃないだろうか。
十戦終えると、疲れがドッと襲ってきた。
「そろそろ寝ない?」
「いい時間ですしねー。寝ますか」
僕らは別々のベッドに飛び込んだ。ふかふかですぐに眠りに落ちそう。
「あ、私のお願い聞いてもらうね」
覚えていたのか......。忘れてくれて良かったのに。
「なに?」
「帰ったら、卒業アルバム見せて欲しいです」
「そんなのでいいの?」
「はい! 小学生の頃の秋太くんを見てみたいです」
助かった。無理難題を命令されるのかと思って、ビクビクしていたが、それくらいならいくらでも見せてあげよう。
「また見せるよ」
「ありがとう。おやすみ」
「おやすみ」
消灯し、僕らは眠った。