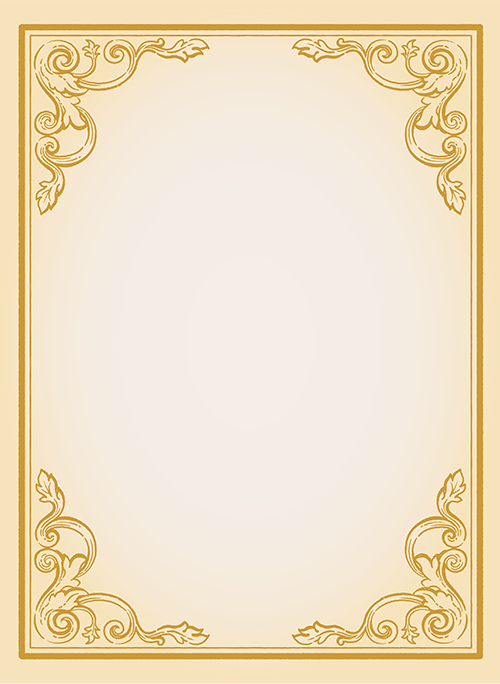ショッピングモール内の再奥に本屋はある。フードコートからは少し遠かったが、栞と話しながら歩いていると、あっという間に着いた。
僕が見たかったのは、漫画コーナーなので一旦栞と別れることにした。栞は雑誌なんかも見たいらしい。連絡を取り合えないので、出会えなかった場合、三十分後に本屋の入口集合にした。
最後に本屋に来たのは、八月に入ったばかりのときだった。栞と出会ったあの日だ。
あの日、僕が本屋に行ってなかったら、彼女はどうしていたのだろう。自分のことが見える人物を探していたのだろうか。そう考えると、あの日本屋に行く選択をとった自分に感謝する。あの時間に行ったから、彼女と出会うことができた。
もしかしたら、神様がそう仕向けたのかもしれない。神様なんて信じていなかったけれど、一度死んだ彼女が僕の前に現れた時点で、神様のような存在がいても、不思議ではないようなそんな気がした。
最寄りの本屋と違って、かなり規模の大きい本屋なので、漫画コーナーも充実している。初めて見る漫画も何冊もあって、心踊る。表紙を見たり、裏のあらすじなんかを見たりするだけで、楽しくなる。新刊も発売されているようで、数冊買って帰りたいな。僕は時間を忘れて夢中になった。
バトル漫画をいくつか見ていると、肩を優しく叩かれた。振り向くと、目を細め、明らかに怒った様子の栞がいた。スマホで時間を確認すると、三十分を過ぎていた。
しまった......。
「や、やあ」
「遅い!」
僕にしか非がない。完全に僕が悪い。どんな叱咤でも、僕はちゃんと受け止めよう。
「ど、どうしたの?」
罵倒する言葉を連発されるのかと思っていたが、彼女の口は閉ざされたままだった。気のせいかもしれないが、少し目が赤い気がした。
「見捨てられたのかと思ったんだよ......」
彼女の声は先ほどと違い、小さかった。
「そんなことするはずない」
「でも、時間通りに来なかったから、帰っちゃったのかと思った」
「それは......ごめん。漫画に夢中になりすぎた」
言い訳をつらつらと並べて、これ以上自分の過ちを大きくしたくなかった。
「いや......ごめんね。私はわがままに付き合ってもらってる立場なのに......邪魔だよね。秋太くんの枷にはなりたくないから、私──」
「邪魔なわけない! さっきのは僕が悪かった。君に付き合う選択をしたのは僕だ。僕の意思で栞と会ってる。誰かに命令されたわけじゃない。最後まで君に付き合う。だから、自分のことを枷だなんて言わないで欲しい」
彼女の言葉を遮り、僕は言った。そういえば、僕もさっき自分のことを足枷とか言ってしまったな。彼女が怒った理由も、今になってよくわかる。どうしてあんな風に言ってしまったんだろう。
僕は勘違いしていたかもしれない。彼女は決して一人でも平気な、強い女の子じゃない。きっと毎日、怖いんだと思う。彼女はあと数週間後には消えることが確定している。一日たりとも狂わない余命を宣告されているようなものだ。
それなのに全く怖がるそぶりを見せなかった彼女は、そういう意味では強いのかもしれない。でも、それは見せかけの、上っ面の、ただの強がりで、彼女の本質ではない。
もし僕が彼女の恐怖を和らげる存在となっているのなら、その僕が消えたら彼女はどう感じるのだろう。自分に置き換えればいい。もし僕が信頼している人全員がいなくなったら、僕はどう感じるのだろう。
そんなこと考えなくてもわかることだ。辛い、とかそんな言葉では、表せないくらいの悲壮感を覚えるはずだ。僕はそのことを自覚していなかった。
栞は、僕を彼氏としたけれど、本当に好きなわけではないと思う。それでも、彼女とこうして話せるのは僕しかいないのだから、僕を頼る以外の選択肢がないのだ。
「うん......ごめん」
「謝らないでくれ。悪いのは僕だから」
「ううん。私も悪いから」
「そんなはずないだろ。百、僕が悪い」
「違う! 私も悪いから!」
意地になって、ラリーを続ける。僕は周りから視線を集めていることに気づいていたけれど、全く気にならなかった。頭のおかしいやつって絶対思われているだろうな。もしかしたら、店員さんを呼ばれるかもしれない。それはちょっとまずい。
「ここは僕が悪いということで、手を打って......」
「どうしてそうなるんですか!」
怒り心頭と言った顔が、崩れた。彼女は笑い出した。
僕がキョトンとしていると、「ごめんなさい。周りのお客さんの目つきを見てると、面白くって」と言った。
「僕がヤバいやつだと思われるのが、そんなに面白いか?」
「そういうわけじゃないんですけど。とりあえず、出ましょう。通報されてもおかしくないよ?」
僕たちは本屋を出た。近くにあったベンチに腰かけた。
「さっき笑ったのは、あれです。あの状況で話し続ける秋太くん、面白かったんです」
「前にも言ったけど、僕とこれから一生関わることのないであろう人からどんな目を向けられても、気にならないから。まあ、大井とか、クラスメイトに見られたらちょっと気まずいけど」
「ふふっ。でも、私が笑ったのはただ面白かっただけじゃない......よ?」
「何?」
「嬉しかったんです。別に私をいないように扱えば、あんな目を向けられることがないのに、いっつも私をそこに存在するものとして扱ってくれるのが」
「彼女を無視する彼氏っている?」
「いないですね。何だか彼氏っぽくなってきましたね。心置きなく、成仏できそうです」
行き道と全く同じルートで、帰る。一度通った道なので、迷うことなく、駅に着き、電車に乗り込む。来たときと変わらぬ時間電車に揺られた後、降車した。
僕たちと同じ駅で降りる人はそう多くなかった。目で数えられるくらいの人数しかいなかった。改札を出て、駅前で別れることになった。彼女は数時間前の悲嘆に満ちた表情とは打って変わって、昨日と同じ優しい笑みを浮かべ、別れを告げた。僕も昨日までと同じように、手を振り、「また明日」と言った。
夕日に染まった茜色の空をぼんやりと見ながら、僕は一人で家を目指した。
僕はどうして彼女のために、ここまでするのだろう。考えてみたことはあったが、ピンと来る答えは出なかった。まだ出会って一ヶ月も経たない彼女に、どうして真剣になれるのだろう。僕は薄情なやつではないと自覚しているが、慈愛に満ちた、聖人というわけでもない。人並みの親切心を持った、人間だと思っている。
一般的に、僕のような立場に置かれたら、どういう行動を起こすものなのだろう。僕のように彼女に付き合ってあげる人もいれば、冷たく突き放す人もいるだろう。別に後者をとる人間がいても、薄情だとは思うが、そういう人間が一定数いても不思議ではない。
だって、全く関わりのない女の子から彼氏になって欲しい、と言われて付き合うようなお人好しの方が少ないんじゃないかな。相手がいくら美少女であったとしても、一ヶ月の間、ほぼ毎日会って、彼女と行動して、生前の願いを叶えてあげる。そこまでしてあげる人はきっと少数派なんだと思う。別に自分のことを素晴らしい人間だと思いたいのではなくて、どうして僕はその少数派になってしまったのか、ということを知りたい。
彼女に一目惚れ? 何度も頭に浮かんだことだけど、それはない、と断言できる。確かに容姿は抜群に良いけれど、一目惚れするほど僕も軽い男ではない。でも、彼女のことが嫌いというわけではなくて、二択であれば、好きと答える。きっとそれは友達に対して言うような好きと同じ性質のものだと思う。多分。
じゃあ、僕が彼女を助けようとするのは、同情から? これも何度も考えてはしっくり来ないと、捨てた考えだ。同情する気持ちはあるけれど、それだけではない、という気がしてならないのだ。
結局いつも答えは出せないままだ。無意味に頭を使ったような気がして、どっと疲労感に襲われる。この変な、釈然としない感覚をいつか拭たらいいな、と思いながら、自宅の扉を開けた。
今日も暑さに辟易しながら、真昼間の外を歩く。平気そうな顔をする隣の彼女は平常運転だ。何だか僕の方がスタミナがないことに少し悔しくなる。僕が鍛えたとしても、そこそこのスタミナを手に入れたときには、月をまたいでしまっているだろうな。
僕たちは無意味に、当てもなく歩いているわけではない。この暑さだ。さすがに僕もただの散歩なら、却下したくなる。
目指す場所は、小さなかき氷屋さんだ。町のはずれにあって、地元の人しか知らないような場所に店を構えている。小さい頃、今は亡き祖母に連れて行ってもらったことが何度かあったので、道順は覚えている。
栞が昨日、かき氷が食べたい、と言ったので、連れて行ってあげることにした。暑い中数十分歩くのは躊躇われたが、僕の記憶が正しければあのお店のかき氷はとても美味しかった。その美味しかったという記憶を信じて、僕は外へ出る決心をした。
「楽しみだねー。かき氷」
言った後に、ふふっ、と笑う栞は、心の底から楽しみにしていることがわかった。喜んでくれると嬉しいな。
「暑い日にはやっぱりかき氷は最高だよね」
「秋太くんはかき氷好きなんだ」
「嫌いな人はほとんどいないでしょ。栞は?」
「どうだろ。好きだといいんですけどね」
栞の言い方に、違和感を覚える。彼女との会話の中でたまに感じるやつだ。
「もしかして、かき氷、食べたことないの......?」
「ないよ」
何だと......。雷に打たれたような衝撃とはこのことか。ラーメンのときと言い、彼女は生前どういった生活を送っていたんだ? もしかして、親がとても厳しい人で、好きな物をあまり食べさせてもらえなかったとか?
「僕はびっくりしてる」
「真顔で言われると、本当にびっくりしてることが伝わるね」
「君の生前の食生活を見てみたいよ......」
「ふふっ。またいつか、教えてあげます!」
なんとか『氷』と書かれた看板が目立つ、かき氷屋さんにたどり着いた。お店の中に入ると、記憶が蘇ってきた。そうだそうだ。こんな感じだった。
扉を開けると、まずは四人掛けの赤いテーブルとイスが目に入る。その奥に座敷があって、そのエリアにもテーブルが一つ置かれている。僕ら以外にお客さんはいないようだった。
「お一人? そっちどうぞ」
店員の人が座敷の方を指した。僕らは靴を脱ぎ、座敷に座った。店員さんは奥の方へ消えていった。この空間には僕らしかいないので、話しやすい。
「どれにする?」
僕が訊くと、彼女は眉間にしわを寄せ、悩んでいる様子だった。味の種類はシンプルで、いちご、メロン、レモン、ブルーハワイ、練乳、みぞれの六種類あった。
「秋太くんはどれにするの?」
「いちごかな。どの味で迷ってるの?」
「いちごとレモン!」
「じゃあレモン頼めば? いちごは僕が頼むし、味見できるよ」
「おお。ナイスアイディア!」
彼女は、『ディ』にアクセントを置き、英語ができる感を醸し出して言った。
「すみません。注文いいですか」
僕が言うと、さっきの店員さんが奥から出てきた。
「はい。どうぞ」
「いちごとレモンを一杯ずつお願いします」
「いちごとレモンですね。一人で二杯も食べるのかい?」
「ま、まあ。外暑かったんで」
「お腹は壊さないようにするんだよ」
二杯頼めば、当然僕が二杯食べると思われる。いくらかき氷が好きでも、一度に二杯はきつい。
栞は物珍しそうに店内を見回している。確かに今時珍しい内装をしている。ここだけ何十年も時代が変わっていないような、そんな風に思わせられる。
開いた窓から入り込んでくる風とセミの鳴き声が夏らしいBGMとなっている。エアコンはついておらず、扇風機が回っているだけ。それでも外と比べると、大分涼しかった。
すぐに店員さんがかき氷二杯分を持って帰ってきた。
「おまちどーさま」
僕の前に置かれたかき氷の一杯を栞の方へ移動させた。彼女は少し口を開き、目をキラキラさせている。楽しみにしていたことが伝わってくる。
「溶けないうちに、食べようか」
「うん! いただきます!」
「いただきます」
銀色のスプーンで少し掬い、口に運ぶ。僕の記憶は正しかったようで、美味しかった。ふわふわの氷が口の中の温度を一気に下げる。上から順に、体温が徐々に下がっていくような気がした。来て良かったな。
「......最高です!」
彼女にもご満足いただけたようだ。彼女はかなりハイペースでかき氷をかけこむ。そんなに急いだら......。
「頭が痛いです......」
予想通りの反応に思わず、笑ってしまう。
「そんなに急がなくてもいいのに」
「溶けると思って......」
確かに溶けるけれど、最後にお皿に残った液体を飲み干すのも、またかき氷の楽しみ方の一つなのではないかと思う。
「秋太くんって何人家族?」
栞は頭を押さえながら、言った。
「二人だけど。どうしたの、急に」
「いや、秋太くんのお母さんの姿はよく見るんですけど、お父さんは一度も見たことないな、と思いまして......」
二人、と言った僕の言葉に、彼女は少し気まずそうに言った。
「僕は母さんと二人暮らしだね。父さんは僕が中学の頃に出て行ったから。僕らの生活費は今でも送ってくれてるらしいけど」
「なんか、ごめんなさい」
「謝らなくてもいいよ。別に父さんのことは何とも思ってないし。会いたいとも、会いたくないとも思ってない。どうでもいいんだよ。母さんは昔よりも活き活きしてる気がするし、僕は良かったと思ってる」
毎日夫婦喧嘩をしていたわけではない。傍から見れば、円満に見えていたかもしれない。けれど、実際は全く違い、一番近くで見ていた僕には二人がそう長くは続かないことを感じ取っていた。二人ともどこか遠慮しているというか、自然体ではなかった。常に気が張っているような状態だった。
夕食を食べるときも、会話は弾まなかった。僕がテストで良い点数をとったときは、大抵母さんだけが褒めてくれた。父さんは、そうか、の一言で済ますことが多かった。徐々に僕も父さんからは愛されていないのかな、と思い始めた。
三人で楽しくどこかへ出かけた記憶はほとんどない。だから、僕にとっても父さんはどうでもいい人なんだ。
「そうなんですね......秋太くんってあんまり自分のこと話さないし、知れて嬉しかったなぁ」
「自分の情報をオープンにするような趣味はないからね」
「なんか秋太くんは生きてるはずなのに、私より死人度高くないですかね?」
「死人度って言葉を初めて聞いた。僕には未練なんてないから、そう見えるんじゃないかな。この世に執着するものがないから、死んでるように見えるのかもしれない。かと言って、僕は別に死にたいわけじゃないけどね。まだまだ生きたいなって思うよ」
「なんか寂しいね」
言った彼女は、一口かき氷を食べた。目を細めて、顔のパーツが中心に寄ったような顔をした。
「そうかもね」
僕もそれだけ言って、かき氷を食べた。ちょっと話しすぎたかもしれない。かなり溶けていた。
「いちごもレモンも美味しかったなー。もっと早く教えてくれても良かったのにー」
「僕ももっと早くに提案すべきだったと後悔してる。また行きたいね」
僕は言ってから、『また』は来ないんじゃないかと思った。残り期間でもう一度あのお店を訪れることはない気がする。
彼女もそのことをわかっていたかもしれない。けれど、彼女は満面の笑みで、「そうだね」と言った。日に日に彼女といられる期間が短くなっていると思うと、形容しがたい気持ちになった。
今日は計画を立てましょう! 栞はそう言った。今日で彼女と出会って、十六日目。かなり濃い夏休みを僕は送っていた。十七年間の人生で確実にトップになるくらい濃い毎日を過ごしている。毎日何かしらの予定があって、忙しない。充実していると言っても、差し支えないだろう。
本日は僕の家で、ある計画を立てるために座り込んで、話している。そんなテロを起こすとか、犯罪の片棒を担ぐとか、そんな物騒なことではなくて、遊園地に行く計画を立てている。当たり前だけれど、僕から遊園地に行こう、と誘ったのではなく、彼女が行きたい、と言ったから行くことになった。僕も満更ではないけど。
家族仲があまり良くなかったため、小さい頃に遊園地に連れて行ってもらった記憶がない。もしかしたら、あったのかもしれないけれど、思い出せないということは、その程度の思い出だったのだろう。
どうやら、栞も遊園地に行ったことはないらしく、ウキウキしながら、僕のパソコンで検索をかけている。行ったことない同士、上手くいくのかな。
「ここがいいです!」
栞が振り返り、ディスプレイを指した。僕が覗き込むと、初めて見る遊園地のホームページが表示されていた。
「楽しそうだけど、ちょっと遠くない?」
遊園地の所在は、確実に数時間はかかる場所にあった。気軽に行ける距離ではなかった。多分、朝から向かっても、着くのはお昼前になりそうだ。
「じゃあ、一泊しない?」
「え」
僕の戸惑いはいたって正常なものだと思う。それなのに彼女は小首を傾げ、僕がおかしな態度をとったかのような目で見てくる。
「さすがに泊まるのは......」
「えー、いーじゃん。だって恋人と旅行って憧れなんだよ!」
普段は見せない、顔だ。甘えるようなその目は、餌をおねだりする子犬のようだ。
「君の言い分もわかるけど、怖くないの? 僕をそもそも異性として認識してないのかもしれないけど、一応男なんだよ。まだ出会って数週間の僕と二人で、旅行っていうのは......」
「私にとっては、『もう』、数週間経ったけどね。リミットまで半分切っちゃったんだから、もう、って言った方が正しいと思うなぁ」
そんな言い方をされるとまいる。栞の言う通り、残り期間は着々と少なくなっている。僕と彼女の八月が終わるまでの期間の感じ方は、絶対に違う。来年も訪れる八月を彼女は経験できない。
僕には二つの選択肢があるけれど、答えは決まった。
「......わかった。行くよ」
「ありがと! あと、さっきの怖くないの? って質問だけど、全然怖くないよ。優しい秋太くんだから、信頼できる」
「買いかぶりすぎだよ。僕は君が思っているほど、素晴らしい人間じゃない」
「人って、自分で評価するんじゃなくて、誰かに評価される生き物だと思うんだよね。だから、私が秋太くんに高い評価を下したんだから、それを受け入れてください!」
言いくるめられたような気がして、ちょっと悔しい。僕は小さく、「わかった」とだけ言った。
「ふふっ。じゃあ、色々決めていきましょう! ホテルは一部屋でいいよね?」
「いや、さすがにそれは......」
今日の栞はとんでもないことを言い出す率が高すぎる。一部屋でいいわけないだろ。
僕の方が彼女のことを変に意識してしまっているのか?
「二部屋もとったら、お金かかるよ?」
「返ってくるお金だろ......」
「そうだけど、夏休み最終日までお金もつ?」
痛いところを突かれた。最近金遣いが荒くなっていた。後で返ってくるし、いいか、と思い少々使い過ぎていた。
正直一部屋にしてもらった方がありがたい。まだ十日以上あるのだから、残金が多いに越したことはない。けれど、一番の問題は彼女と二人部屋ということだ。彼女が平然としているのが、不思議だ。僕を信頼してくれているようだけど、それでも同じ部屋で寝るというのは......。
「悩んでるようだねぇ」
彼女がニヤニヤしながら、言った。最近僕との距離感が違い気がする。これも信頼されていると捉えれば、プラスなのかもしれないけれど、僕はからかわれて高揚するような性癖はないので、もう少し距離感を考えて欲しいな、と思う。
「......わかった。一部屋でいい」
僕は折れた。栞と同じ部屋で寝ることになっても、確実に間違いは起こらない。僕も自信を持って言える。
「よし! じゃあ次は何時に出るかだねぇ。いっぱい遊びたいし、早朝だよね」
「全部任せるよ」
彼女はふふっ、と笑って、ダイヤを調べ始めた。駅名を入れるだけで、最短ルートや最安のルートが出てくるのだから、便利な時代になった、と痛感させられる。
すぐに検索は終わった。彼女が見せてくれたのは、最寄駅から数十分揺られ、新幹線に乗り換え、さらに一時間ほど乗るプランのようだ。僕の手持ちではおそらく足りないので、銀行に貯金してあったお年玉を引き出しておいた方が良さそうだ。
「あとなんか決めておくことありますかね?」
「どこに泊まるかじゃない?」
「そうでした! 泊まれればいいし、ビジネスホテルでいいよね?」
「別にお金は気にしなくていいから、そこそこ高いとこでもいいけど」
「贅沢しすぎるのも、あんまり良くないかなーって思うので、ビジネスホテルにしましょう!」
「栞がいいなら、僕は構わないけど」
遊園地近くのホテルを彼女は検索し始めた。いくつか候補の中から値段の割に部屋が綺麗で、良さげなビジネスホテルを見つけたので、そこに決めた。夏休みだというのに、一部屋空いていたのは奇跡とも言える。
明日は準備期間にして、明後日に出ることにした。一分一秒も惜しいので、可能な限り直近の方がいいだろう。
よくよく考えれば、可愛い彼女と旅行なんて、そうそう体験できるものではない。夢のようだ。僕は喜ぶべきだ。それなのに、心の底から喜べていないような、そんな感覚に陥るのはなぜだろう。
「他には何か決めることありますかね?」
きっと本当に夢のような、現実味のない体験をしているからではないだろうか。あと数週間もすれば、彼女が消えてしまうというありえないような出来事が実際に起こっているから。夢はいつかさめる。その事実がつきまとっているから、僕は素直に喜べないのだと思う。
「秋太くん?」
彼女が小首を傾げ、話しかけてきた。僕がぼーっとしていたからだろう。
「ごめんごめん。他にはないんじゃないかな。もし必要になったら、また考えればいいし」
「了解です! 明後日が楽しみですね」
彼女は嬉々とした気持ちを抑えられないようで、ふふっ、と笑っている。ただ遊園地に行くだけで、そんなに喜んでもらえるなら、付き添う僕もちょっぴり嬉しくなる。
僕も笑みを浮かべながら、「うん」と言っておいた。
「母さん、どっちがいいと思う?」
「そっち」
旅行前日、母さんに二種類の服で、どちらがいいかを訊いていた。母さんが指したのは、僕から見て右手に持っている、夏らしく爽やかそうに見える白いTシャツだった。
「ありがと」
「ねえ」
僕がリビングの扉を閉めようとしたとき、声をかけられた。
「どっか行くの?」
「言うの忘れてたけど、明日彼女と旅行に行ってくる」
「えらく急だね。どこまで?」
僕は母さんに場所と一泊することを伝えた。
「最近彼女ができたと思えば、もう二人で旅行か。あんた彼女のこと本当に好きなんだね。少し前と比べて、毎日が活き活きしてるよ」
自分では気づかなかったけれど、彼女のおかげで変わった部分があったのだろう。母さんの反応を見ると、変化は良い方向に向いていることがわかる。
「楽しんでくるんだよ」
「うん」
今度こそ僕が扉を閉めようとすると、最後に「ちょっと待って」と言われた。ソファに座っていた母さんが立ち上がり、カバンを探りだした。
「ほら。これで彼女に何か買ってあげな」
そう言った母さんは、僕にお小遣いを渡してくれた。
「ありがとう」
母さんは微笑んで、またソファに座った。見ていたテレビを再開した。
僕は扉を閉め、自分の部屋に向かった。母さんがくれたお小遣いも、彼女のために使えば母さんの元へ返ってくる。彼女のために何かしてあげても、形として残らないことに寂しさを覚えた。
僕が見たかったのは、漫画コーナーなので一旦栞と別れることにした。栞は雑誌なんかも見たいらしい。連絡を取り合えないので、出会えなかった場合、三十分後に本屋の入口集合にした。
最後に本屋に来たのは、八月に入ったばかりのときだった。栞と出会ったあの日だ。
あの日、僕が本屋に行ってなかったら、彼女はどうしていたのだろう。自分のことが見える人物を探していたのだろうか。そう考えると、あの日本屋に行く選択をとった自分に感謝する。あの時間に行ったから、彼女と出会うことができた。
もしかしたら、神様がそう仕向けたのかもしれない。神様なんて信じていなかったけれど、一度死んだ彼女が僕の前に現れた時点で、神様のような存在がいても、不思議ではないようなそんな気がした。
最寄りの本屋と違って、かなり規模の大きい本屋なので、漫画コーナーも充実している。初めて見る漫画も何冊もあって、心踊る。表紙を見たり、裏のあらすじなんかを見たりするだけで、楽しくなる。新刊も発売されているようで、数冊買って帰りたいな。僕は時間を忘れて夢中になった。
バトル漫画をいくつか見ていると、肩を優しく叩かれた。振り向くと、目を細め、明らかに怒った様子の栞がいた。スマホで時間を確認すると、三十分を過ぎていた。
しまった......。
「や、やあ」
「遅い!」
僕にしか非がない。完全に僕が悪い。どんな叱咤でも、僕はちゃんと受け止めよう。
「ど、どうしたの?」
罵倒する言葉を連発されるのかと思っていたが、彼女の口は閉ざされたままだった。気のせいかもしれないが、少し目が赤い気がした。
「見捨てられたのかと思ったんだよ......」
彼女の声は先ほどと違い、小さかった。
「そんなことするはずない」
「でも、時間通りに来なかったから、帰っちゃったのかと思った」
「それは......ごめん。漫画に夢中になりすぎた」
言い訳をつらつらと並べて、これ以上自分の過ちを大きくしたくなかった。
「いや......ごめんね。私はわがままに付き合ってもらってる立場なのに......邪魔だよね。秋太くんの枷にはなりたくないから、私──」
「邪魔なわけない! さっきのは僕が悪かった。君に付き合う選択をしたのは僕だ。僕の意思で栞と会ってる。誰かに命令されたわけじゃない。最後まで君に付き合う。だから、自分のことを枷だなんて言わないで欲しい」
彼女の言葉を遮り、僕は言った。そういえば、僕もさっき自分のことを足枷とか言ってしまったな。彼女が怒った理由も、今になってよくわかる。どうしてあんな風に言ってしまったんだろう。
僕は勘違いしていたかもしれない。彼女は決して一人でも平気な、強い女の子じゃない。きっと毎日、怖いんだと思う。彼女はあと数週間後には消えることが確定している。一日たりとも狂わない余命を宣告されているようなものだ。
それなのに全く怖がるそぶりを見せなかった彼女は、そういう意味では強いのかもしれない。でも、それは見せかけの、上っ面の、ただの強がりで、彼女の本質ではない。
もし僕が彼女の恐怖を和らげる存在となっているのなら、その僕が消えたら彼女はどう感じるのだろう。自分に置き換えればいい。もし僕が信頼している人全員がいなくなったら、僕はどう感じるのだろう。
そんなこと考えなくてもわかることだ。辛い、とかそんな言葉では、表せないくらいの悲壮感を覚えるはずだ。僕はそのことを自覚していなかった。
栞は、僕を彼氏としたけれど、本当に好きなわけではないと思う。それでも、彼女とこうして話せるのは僕しかいないのだから、僕を頼る以外の選択肢がないのだ。
「うん......ごめん」
「謝らないでくれ。悪いのは僕だから」
「ううん。私も悪いから」
「そんなはずないだろ。百、僕が悪い」
「違う! 私も悪いから!」
意地になって、ラリーを続ける。僕は周りから視線を集めていることに気づいていたけれど、全く気にならなかった。頭のおかしいやつって絶対思われているだろうな。もしかしたら、店員さんを呼ばれるかもしれない。それはちょっとまずい。
「ここは僕が悪いということで、手を打って......」
「どうしてそうなるんですか!」
怒り心頭と言った顔が、崩れた。彼女は笑い出した。
僕がキョトンとしていると、「ごめんなさい。周りのお客さんの目つきを見てると、面白くって」と言った。
「僕がヤバいやつだと思われるのが、そんなに面白いか?」
「そういうわけじゃないんですけど。とりあえず、出ましょう。通報されてもおかしくないよ?」
僕たちは本屋を出た。近くにあったベンチに腰かけた。
「さっき笑ったのは、あれです。あの状況で話し続ける秋太くん、面白かったんです」
「前にも言ったけど、僕とこれから一生関わることのないであろう人からどんな目を向けられても、気にならないから。まあ、大井とか、クラスメイトに見られたらちょっと気まずいけど」
「ふふっ。でも、私が笑ったのはただ面白かっただけじゃない......よ?」
「何?」
「嬉しかったんです。別に私をいないように扱えば、あんな目を向けられることがないのに、いっつも私をそこに存在するものとして扱ってくれるのが」
「彼女を無視する彼氏っている?」
「いないですね。何だか彼氏っぽくなってきましたね。心置きなく、成仏できそうです」
行き道と全く同じルートで、帰る。一度通った道なので、迷うことなく、駅に着き、電車に乗り込む。来たときと変わらぬ時間電車に揺られた後、降車した。
僕たちと同じ駅で降りる人はそう多くなかった。目で数えられるくらいの人数しかいなかった。改札を出て、駅前で別れることになった。彼女は数時間前の悲嘆に満ちた表情とは打って変わって、昨日と同じ優しい笑みを浮かべ、別れを告げた。僕も昨日までと同じように、手を振り、「また明日」と言った。
夕日に染まった茜色の空をぼんやりと見ながら、僕は一人で家を目指した。
僕はどうして彼女のために、ここまでするのだろう。考えてみたことはあったが、ピンと来る答えは出なかった。まだ出会って一ヶ月も経たない彼女に、どうして真剣になれるのだろう。僕は薄情なやつではないと自覚しているが、慈愛に満ちた、聖人というわけでもない。人並みの親切心を持った、人間だと思っている。
一般的に、僕のような立場に置かれたら、どういう行動を起こすものなのだろう。僕のように彼女に付き合ってあげる人もいれば、冷たく突き放す人もいるだろう。別に後者をとる人間がいても、薄情だとは思うが、そういう人間が一定数いても不思議ではない。
だって、全く関わりのない女の子から彼氏になって欲しい、と言われて付き合うようなお人好しの方が少ないんじゃないかな。相手がいくら美少女であったとしても、一ヶ月の間、ほぼ毎日会って、彼女と行動して、生前の願いを叶えてあげる。そこまでしてあげる人はきっと少数派なんだと思う。別に自分のことを素晴らしい人間だと思いたいのではなくて、どうして僕はその少数派になってしまったのか、ということを知りたい。
彼女に一目惚れ? 何度も頭に浮かんだことだけど、それはない、と断言できる。確かに容姿は抜群に良いけれど、一目惚れするほど僕も軽い男ではない。でも、彼女のことが嫌いというわけではなくて、二択であれば、好きと答える。きっとそれは友達に対して言うような好きと同じ性質のものだと思う。多分。
じゃあ、僕が彼女を助けようとするのは、同情から? これも何度も考えてはしっくり来ないと、捨てた考えだ。同情する気持ちはあるけれど、それだけではない、という気がしてならないのだ。
結局いつも答えは出せないままだ。無意味に頭を使ったような気がして、どっと疲労感に襲われる。この変な、釈然としない感覚をいつか拭たらいいな、と思いながら、自宅の扉を開けた。
今日も暑さに辟易しながら、真昼間の外を歩く。平気そうな顔をする隣の彼女は平常運転だ。何だか僕の方がスタミナがないことに少し悔しくなる。僕が鍛えたとしても、そこそこのスタミナを手に入れたときには、月をまたいでしまっているだろうな。
僕たちは無意味に、当てもなく歩いているわけではない。この暑さだ。さすがに僕もただの散歩なら、却下したくなる。
目指す場所は、小さなかき氷屋さんだ。町のはずれにあって、地元の人しか知らないような場所に店を構えている。小さい頃、今は亡き祖母に連れて行ってもらったことが何度かあったので、道順は覚えている。
栞が昨日、かき氷が食べたい、と言ったので、連れて行ってあげることにした。暑い中数十分歩くのは躊躇われたが、僕の記憶が正しければあのお店のかき氷はとても美味しかった。その美味しかったという記憶を信じて、僕は外へ出る決心をした。
「楽しみだねー。かき氷」
言った後に、ふふっ、と笑う栞は、心の底から楽しみにしていることがわかった。喜んでくれると嬉しいな。
「暑い日にはやっぱりかき氷は最高だよね」
「秋太くんはかき氷好きなんだ」
「嫌いな人はほとんどいないでしょ。栞は?」
「どうだろ。好きだといいんですけどね」
栞の言い方に、違和感を覚える。彼女との会話の中でたまに感じるやつだ。
「もしかして、かき氷、食べたことないの......?」
「ないよ」
何だと......。雷に打たれたような衝撃とはこのことか。ラーメンのときと言い、彼女は生前どういった生活を送っていたんだ? もしかして、親がとても厳しい人で、好きな物をあまり食べさせてもらえなかったとか?
「僕はびっくりしてる」
「真顔で言われると、本当にびっくりしてることが伝わるね」
「君の生前の食生活を見てみたいよ......」
「ふふっ。またいつか、教えてあげます!」
なんとか『氷』と書かれた看板が目立つ、かき氷屋さんにたどり着いた。お店の中に入ると、記憶が蘇ってきた。そうだそうだ。こんな感じだった。
扉を開けると、まずは四人掛けの赤いテーブルとイスが目に入る。その奥に座敷があって、そのエリアにもテーブルが一つ置かれている。僕ら以外にお客さんはいないようだった。
「お一人? そっちどうぞ」
店員の人が座敷の方を指した。僕らは靴を脱ぎ、座敷に座った。店員さんは奥の方へ消えていった。この空間には僕らしかいないので、話しやすい。
「どれにする?」
僕が訊くと、彼女は眉間にしわを寄せ、悩んでいる様子だった。味の種類はシンプルで、いちご、メロン、レモン、ブルーハワイ、練乳、みぞれの六種類あった。
「秋太くんはどれにするの?」
「いちごかな。どの味で迷ってるの?」
「いちごとレモン!」
「じゃあレモン頼めば? いちごは僕が頼むし、味見できるよ」
「おお。ナイスアイディア!」
彼女は、『ディ』にアクセントを置き、英語ができる感を醸し出して言った。
「すみません。注文いいですか」
僕が言うと、さっきの店員さんが奥から出てきた。
「はい。どうぞ」
「いちごとレモンを一杯ずつお願いします」
「いちごとレモンですね。一人で二杯も食べるのかい?」
「ま、まあ。外暑かったんで」
「お腹は壊さないようにするんだよ」
二杯頼めば、当然僕が二杯食べると思われる。いくらかき氷が好きでも、一度に二杯はきつい。
栞は物珍しそうに店内を見回している。確かに今時珍しい内装をしている。ここだけ何十年も時代が変わっていないような、そんな風に思わせられる。
開いた窓から入り込んでくる風とセミの鳴き声が夏らしいBGMとなっている。エアコンはついておらず、扇風機が回っているだけ。それでも外と比べると、大分涼しかった。
すぐに店員さんがかき氷二杯分を持って帰ってきた。
「おまちどーさま」
僕の前に置かれたかき氷の一杯を栞の方へ移動させた。彼女は少し口を開き、目をキラキラさせている。楽しみにしていたことが伝わってくる。
「溶けないうちに、食べようか」
「うん! いただきます!」
「いただきます」
銀色のスプーンで少し掬い、口に運ぶ。僕の記憶は正しかったようで、美味しかった。ふわふわの氷が口の中の温度を一気に下げる。上から順に、体温が徐々に下がっていくような気がした。来て良かったな。
「......最高です!」
彼女にもご満足いただけたようだ。彼女はかなりハイペースでかき氷をかけこむ。そんなに急いだら......。
「頭が痛いです......」
予想通りの反応に思わず、笑ってしまう。
「そんなに急がなくてもいいのに」
「溶けると思って......」
確かに溶けるけれど、最後にお皿に残った液体を飲み干すのも、またかき氷の楽しみ方の一つなのではないかと思う。
「秋太くんって何人家族?」
栞は頭を押さえながら、言った。
「二人だけど。どうしたの、急に」
「いや、秋太くんのお母さんの姿はよく見るんですけど、お父さんは一度も見たことないな、と思いまして......」
二人、と言った僕の言葉に、彼女は少し気まずそうに言った。
「僕は母さんと二人暮らしだね。父さんは僕が中学の頃に出て行ったから。僕らの生活費は今でも送ってくれてるらしいけど」
「なんか、ごめんなさい」
「謝らなくてもいいよ。別に父さんのことは何とも思ってないし。会いたいとも、会いたくないとも思ってない。どうでもいいんだよ。母さんは昔よりも活き活きしてる気がするし、僕は良かったと思ってる」
毎日夫婦喧嘩をしていたわけではない。傍から見れば、円満に見えていたかもしれない。けれど、実際は全く違い、一番近くで見ていた僕には二人がそう長くは続かないことを感じ取っていた。二人ともどこか遠慮しているというか、自然体ではなかった。常に気が張っているような状態だった。
夕食を食べるときも、会話は弾まなかった。僕がテストで良い点数をとったときは、大抵母さんだけが褒めてくれた。父さんは、そうか、の一言で済ますことが多かった。徐々に僕も父さんからは愛されていないのかな、と思い始めた。
三人で楽しくどこかへ出かけた記憶はほとんどない。だから、僕にとっても父さんはどうでもいい人なんだ。
「そうなんですね......秋太くんってあんまり自分のこと話さないし、知れて嬉しかったなぁ」
「自分の情報をオープンにするような趣味はないからね」
「なんか秋太くんは生きてるはずなのに、私より死人度高くないですかね?」
「死人度って言葉を初めて聞いた。僕には未練なんてないから、そう見えるんじゃないかな。この世に執着するものがないから、死んでるように見えるのかもしれない。かと言って、僕は別に死にたいわけじゃないけどね。まだまだ生きたいなって思うよ」
「なんか寂しいね」
言った彼女は、一口かき氷を食べた。目を細めて、顔のパーツが中心に寄ったような顔をした。
「そうかもね」
僕もそれだけ言って、かき氷を食べた。ちょっと話しすぎたかもしれない。かなり溶けていた。
「いちごもレモンも美味しかったなー。もっと早く教えてくれても良かったのにー」
「僕ももっと早くに提案すべきだったと後悔してる。また行きたいね」
僕は言ってから、『また』は来ないんじゃないかと思った。残り期間でもう一度あのお店を訪れることはない気がする。
彼女もそのことをわかっていたかもしれない。けれど、彼女は満面の笑みで、「そうだね」と言った。日に日に彼女といられる期間が短くなっていると思うと、形容しがたい気持ちになった。
今日は計画を立てましょう! 栞はそう言った。今日で彼女と出会って、十六日目。かなり濃い夏休みを僕は送っていた。十七年間の人生で確実にトップになるくらい濃い毎日を過ごしている。毎日何かしらの予定があって、忙しない。充実していると言っても、差し支えないだろう。
本日は僕の家で、ある計画を立てるために座り込んで、話している。そんなテロを起こすとか、犯罪の片棒を担ぐとか、そんな物騒なことではなくて、遊園地に行く計画を立てている。当たり前だけれど、僕から遊園地に行こう、と誘ったのではなく、彼女が行きたい、と言ったから行くことになった。僕も満更ではないけど。
家族仲があまり良くなかったため、小さい頃に遊園地に連れて行ってもらった記憶がない。もしかしたら、あったのかもしれないけれど、思い出せないということは、その程度の思い出だったのだろう。
どうやら、栞も遊園地に行ったことはないらしく、ウキウキしながら、僕のパソコンで検索をかけている。行ったことない同士、上手くいくのかな。
「ここがいいです!」
栞が振り返り、ディスプレイを指した。僕が覗き込むと、初めて見る遊園地のホームページが表示されていた。
「楽しそうだけど、ちょっと遠くない?」
遊園地の所在は、確実に数時間はかかる場所にあった。気軽に行ける距離ではなかった。多分、朝から向かっても、着くのはお昼前になりそうだ。
「じゃあ、一泊しない?」
「え」
僕の戸惑いはいたって正常なものだと思う。それなのに彼女は小首を傾げ、僕がおかしな態度をとったかのような目で見てくる。
「さすがに泊まるのは......」
「えー、いーじゃん。だって恋人と旅行って憧れなんだよ!」
普段は見せない、顔だ。甘えるようなその目は、餌をおねだりする子犬のようだ。
「君の言い分もわかるけど、怖くないの? 僕をそもそも異性として認識してないのかもしれないけど、一応男なんだよ。まだ出会って数週間の僕と二人で、旅行っていうのは......」
「私にとっては、『もう』、数週間経ったけどね。リミットまで半分切っちゃったんだから、もう、って言った方が正しいと思うなぁ」
そんな言い方をされるとまいる。栞の言う通り、残り期間は着々と少なくなっている。僕と彼女の八月が終わるまでの期間の感じ方は、絶対に違う。来年も訪れる八月を彼女は経験できない。
僕には二つの選択肢があるけれど、答えは決まった。
「......わかった。行くよ」
「ありがと! あと、さっきの怖くないの? って質問だけど、全然怖くないよ。優しい秋太くんだから、信頼できる」
「買いかぶりすぎだよ。僕は君が思っているほど、素晴らしい人間じゃない」
「人って、自分で評価するんじゃなくて、誰かに評価される生き物だと思うんだよね。だから、私が秋太くんに高い評価を下したんだから、それを受け入れてください!」
言いくるめられたような気がして、ちょっと悔しい。僕は小さく、「わかった」とだけ言った。
「ふふっ。じゃあ、色々決めていきましょう! ホテルは一部屋でいいよね?」
「いや、さすがにそれは......」
今日の栞はとんでもないことを言い出す率が高すぎる。一部屋でいいわけないだろ。
僕の方が彼女のことを変に意識してしまっているのか?
「二部屋もとったら、お金かかるよ?」
「返ってくるお金だろ......」
「そうだけど、夏休み最終日までお金もつ?」
痛いところを突かれた。最近金遣いが荒くなっていた。後で返ってくるし、いいか、と思い少々使い過ぎていた。
正直一部屋にしてもらった方がありがたい。まだ十日以上あるのだから、残金が多いに越したことはない。けれど、一番の問題は彼女と二人部屋ということだ。彼女が平然としているのが、不思議だ。僕を信頼してくれているようだけど、それでも同じ部屋で寝るというのは......。
「悩んでるようだねぇ」
彼女がニヤニヤしながら、言った。最近僕との距離感が違い気がする。これも信頼されていると捉えれば、プラスなのかもしれないけれど、僕はからかわれて高揚するような性癖はないので、もう少し距離感を考えて欲しいな、と思う。
「......わかった。一部屋でいい」
僕は折れた。栞と同じ部屋で寝ることになっても、確実に間違いは起こらない。僕も自信を持って言える。
「よし! じゃあ次は何時に出るかだねぇ。いっぱい遊びたいし、早朝だよね」
「全部任せるよ」
彼女はふふっ、と笑って、ダイヤを調べ始めた。駅名を入れるだけで、最短ルートや最安のルートが出てくるのだから、便利な時代になった、と痛感させられる。
すぐに検索は終わった。彼女が見せてくれたのは、最寄駅から数十分揺られ、新幹線に乗り換え、さらに一時間ほど乗るプランのようだ。僕の手持ちではおそらく足りないので、銀行に貯金してあったお年玉を引き出しておいた方が良さそうだ。
「あとなんか決めておくことありますかね?」
「どこに泊まるかじゃない?」
「そうでした! 泊まれればいいし、ビジネスホテルでいいよね?」
「別にお金は気にしなくていいから、そこそこ高いとこでもいいけど」
「贅沢しすぎるのも、あんまり良くないかなーって思うので、ビジネスホテルにしましょう!」
「栞がいいなら、僕は構わないけど」
遊園地近くのホテルを彼女は検索し始めた。いくつか候補の中から値段の割に部屋が綺麗で、良さげなビジネスホテルを見つけたので、そこに決めた。夏休みだというのに、一部屋空いていたのは奇跡とも言える。
明日は準備期間にして、明後日に出ることにした。一分一秒も惜しいので、可能な限り直近の方がいいだろう。
よくよく考えれば、可愛い彼女と旅行なんて、そうそう体験できるものではない。夢のようだ。僕は喜ぶべきだ。それなのに、心の底から喜べていないような、そんな感覚に陥るのはなぜだろう。
「他には何か決めることありますかね?」
きっと本当に夢のような、現実味のない体験をしているからではないだろうか。あと数週間もすれば、彼女が消えてしまうというありえないような出来事が実際に起こっているから。夢はいつかさめる。その事実がつきまとっているから、僕は素直に喜べないのだと思う。
「秋太くん?」
彼女が小首を傾げ、話しかけてきた。僕がぼーっとしていたからだろう。
「ごめんごめん。他にはないんじゃないかな。もし必要になったら、また考えればいいし」
「了解です! 明後日が楽しみですね」
彼女は嬉々とした気持ちを抑えられないようで、ふふっ、と笑っている。ただ遊園地に行くだけで、そんなに喜んでもらえるなら、付き添う僕もちょっぴり嬉しくなる。
僕も笑みを浮かべながら、「うん」と言っておいた。
「母さん、どっちがいいと思う?」
「そっち」
旅行前日、母さんに二種類の服で、どちらがいいかを訊いていた。母さんが指したのは、僕から見て右手に持っている、夏らしく爽やかそうに見える白いTシャツだった。
「ありがと」
「ねえ」
僕がリビングの扉を閉めようとしたとき、声をかけられた。
「どっか行くの?」
「言うの忘れてたけど、明日彼女と旅行に行ってくる」
「えらく急だね。どこまで?」
僕は母さんに場所と一泊することを伝えた。
「最近彼女ができたと思えば、もう二人で旅行か。あんた彼女のこと本当に好きなんだね。少し前と比べて、毎日が活き活きしてるよ」
自分では気づかなかったけれど、彼女のおかげで変わった部分があったのだろう。母さんの反応を見ると、変化は良い方向に向いていることがわかる。
「楽しんでくるんだよ」
「うん」
今度こそ僕が扉を閉めようとすると、最後に「ちょっと待って」と言われた。ソファに座っていた母さんが立ち上がり、カバンを探りだした。
「ほら。これで彼女に何か買ってあげな」
そう言った母さんは、僕にお小遣いを渡してくれた。
「ありがとう」
母さんは微笑んで、またソファに座った。見ていたテレビを再開した。
僕は扉を閉め、自分の部屋に向かった。母さんがくれたお小遣いも、彼女のために使えば母さんの元へ返ってくる。彼女のために何かしてあげても、形として残らないことに寂しさを覚えた。