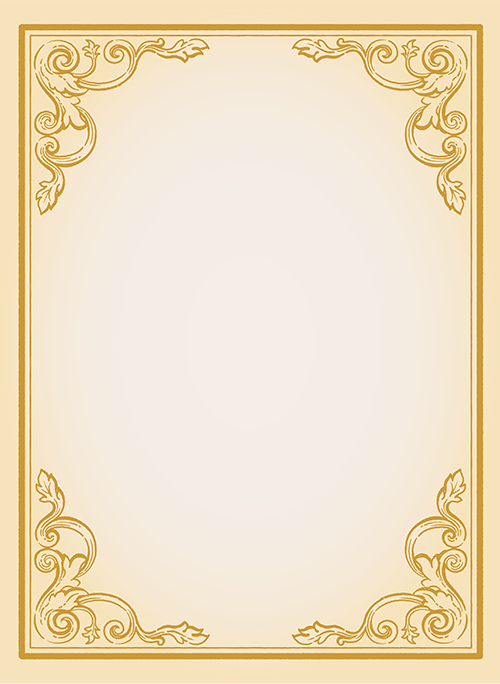「ラーメンって美味しいんですねえ」
「同い年の子からそんなセリフが聞けると思わなかった。満足してもらえたようなら、連れてきた甲斐があったよ」
「大満足ですっ。そういえば、同い年のお友達いないんですか? 私と毎日会っていて、友達と遊んでないようですし」
まずは友達の定義を......。いないわけではないけれど、少ない方ではあると思う。彼女の言う通り、夏休みの暑い中に遊びに行くような友達は全然いない。誘うこともなければ、誘われることもない。今のところだけど。でも、一人だけいるな、誘って来そうなやつが。
「友達はそこそこいるよ。そこそこ」
謎の見栄を張ってしまった。彼女の顔を直視できなかった。
「へー、そうなんですか。いいですねぇ」
どんな人ですか、とか訊いてこなかったあたり、柏木さんは僕を気遣ってくれたのだろう。きっと僕が本当のことを言っていないことくらい気づいてそうだから。
僕の家の前まで帰ってきた。今日もかなり歩いた。最近はウォーキングが趣味と言っても、差し支えないレベルだ。徐々に筋肉痛にもならなくなってきた。いつか隣町まで歩いて行ってしまうのではないだろうか。
「では、また明日もよろしくお願いします」
「うん。また」
彼女の後ろ姿は生き生きしていた。刻一刻と彼女が現世でいられる時間は減少しているのに。
僕も未練を残したら、彼女のようになってしまうのかな。そんなことを考えながら、玄関の扉を開けた。よく考えれば、僕には未練を残すほど執着しているものなんてなかった。
昨日は柏木さんと会うことができなかった。僕が友達と遊びに行ったからだ。友達は少ないけれど、一人もいないわけではない。一昨日に連絡が来たので、彼女に会えないことを伝えた。その時の寂しそうな顔を見ると、本当に付き合っているような気がしてきてしまった。
彼女は付き合っているというけれど、僕たちにはまだまだ距離感はあると思うし、僕の感覚では仲良くなり始めた友達ぐらいだ。彼女の敬語も一向になくなる気配はないし。たまに感極まった時に外れるくらいだ。
彼女の方も口では言うけれど、付き合っているという感覚はないんじゃないだろうか。自分にそう言い聞かせて、僕を彼氏と見立てる。彼女は僕にしか見えていないのだから、僕以外に候補がいないし仕方のないことなのかもしれない。
自分で言うの何だけど、僕を彼氏と考えるのはかなり無理がある気がする。彼女と僕とでは、全く釣り合っていない。主に容姿が。
神様は酷いと思う。彼女の人生を早々に終わらせた挙句、未練を消化する際ももっと相応しい人物を選んであげるべきだった。そういえば、彼女の死因を訊いたことがないな。本人に死因を訊くなんてこれから先、一生することのない経験だ。しかし、きっと思い出したくないことだろうし、訊ける環境にあるけれど、訊くことはないだろうな。
そんな彼女がもう少しで僕の家にやってくるはずだ。一日空いただけなのに、八月に入ってから毎日会っているせいで、久々に感じる。
部屋の扉が数回ノックされた。
「どうぞ」
「おじゃましまーす」
彼女は壁を通り抜ける能力を持っているが、僕のプライバシーを考え、一応ノックしてくれたようだ。玄関の扉は通り抜けてきたようだけど。
「今日は何するの?」
「そうですねー。この辺でおうちデートなんてどうです?」
「どうです? って言われても、するんでしょ。それ」
「その通りです。一応映画も借りてきました!」
借りてきた、ではなく、パクってきたのでは? 彼女がレンタルショップで、お金を出して、借りてる姿を想像することはできるけれど、実際にそうすることはできないのだから、勝手にディスクを引っこ抜いてきたのだろう。
僕の家に未清算のディスクがあるわけだけれど、捕まらないよね? 彼女の話では、夏休みが終わると、彼女がとってきた一枚のディスクもとられたという事実がなくなるので、捕まることはないのだろうけれど、犯罪に加担しているみたいで、罪悪感が芽生える。
「僕の家に、お菓子とかあんまりないから、今から買いに行く?」
「それもバッチリです。ポップコーン買ってきました」
そう言って、手に持っていた袋から、ポップコーンを取り出した。僕が想像していたのは、大袋の開ければ、食べれるやつだったのだけれど、彼女が買ってきたのは、ポップコーンの種だった。
「なあ、どうして種なんだ? 出来上がったやつはなかったのか?」
彼女は不思議そうに小首をかしげた。
僕は何か変なこと言ったかな?
「......ポップコーンってこうやって作るんじゃないんですか?」
「いや、まあ、間違ってないよ。間違ってないんだけど、火を使うし手間がかかるから、普通は完成したやつを買うもんだと思ってた」
僕は言って、スマホで画像検索し、それを彼女に見せた。
「お恥ずかしい......」
どうやら本当に知らなかったようだ。かなり珍しいけれど、そういう人がいてもおかしくはないだろう。僕にだって知らないお菓子はあるだろうし。
「せっかく買ってきてくれたんだし、一緒に作るか」
「はい!」
と思ったけれど、一つ問題がある。今日、僕の家にいるのは、僕と柏木さんだけではない。母さんがリビングのソファで鎮座している。
火を使うには、どうしてもそのリビングを通る必要がある。キッチンはリビングを抜けた先にあるから。リビングとキッチンの間には扉がないので、僕が喋った声が母さんに丸聞こえだ。
つまり、僕が今みたいに柏木さんと普通に会話してしまうと、母さんに訝しげな目で見られ、病院に連れて行かれる可能性があるということ。脳に異常がないか検査してもらうために。
それはまずい。本当のことを説明したいが、彼女の存在を母さんに知られるわけにいかない。
ポップコーンは諦めるしかないのか? 彼女がせっかく買って、いや持ってきてくれたポップコーンの種を無駄にしたくない。それに、やる気に満ち溢れた表情を見ると、とてもじゃないが、やっぱりやめとこう、なんて言えなかった。
彼女が、まだかまだか、と見つめてくる。これ以上、思案し続けるのは、無理か......。
「とりあえず、下行こっか」
彼女は大きく頷いた。どうしよう。
「母さんがリビングにいると思うけど、気にしないでね」
一応、言っておいた方がいいかと思い、階段を下りている最中に言った。
「そうなんですね。私は全然気にしないんですけど、秋太くんは大丈夫なんですか?」
彼女もこのまま二人でポップコーンを作り始めたら、どうなるのか気づいたようだ。
「まあ、何とかなるでしょ」
何とかなる算段が立たないまま、僕はリビングの扉の前まで来てしまった。テレビの音が聞こえるし、母さんが買い物に出かけている可能性も潰えた。
僕はゆっくり扉をスライドさせた。
いきなり扉が開いたのだから、当然母さんはこちらを向く。
「何それ、ポップコーン?」
母さんは僕の左手に持つ、ポップコーンの種を指して言った。
「そうだよ。ちょっと食べたくなってさ」
「それだったらわざわざ種から作らなくてもいいのに」
母さんの意見に同意だ。隣の彼女は少し頬を赤らめている。母さんには見えていないけれど、ダメージを与えてしまったようだ。
「出来たての方が美味しいでしょ。たまには、いいかと思って」
「全然いいけど、火使うんだから、気をつけんだよー」
「小学生じゃないんだから、大丈夫だよ」
リビングとキッチンは繋がっているが、申し訳程度に仕切るためのカーテンがあるので、僕の姿は母さんからほとんど見えないだろう。
「よし、作るか」
かなり小さめのボリュームで僕は、言った。
「はい」
なぜか声の大きさを気にする必要のない彼女まで、小声になっている。
「柏木さんはいつも通りの声の大きさでいいんだよ」
「あっ、そうでした。私の声は秋太くんにしか、聞こえてないですもんね」
彼女の声の大きさは、先ほど部屋にいたときと同じくらいに戻った。僕もつられて、声が大きくならないように気をつけないと。
僕はお鍋に種と油を入れ、火をつけた。作ると言っても、たったこれだけなので大した労力ではない。
隣の彼女は子どもみたいに、楽しそうにお鍋を見つめていた。
「弾けるまでもう少しかかると思うよ」
「そうなんですね。じゃあ一つお願い、いいですか?」
「どうぞ」
僕は何をお願いされるのだろう。無理のない範囲であれば、いいんだけど......。
「秋太くんも私のこと下の名前で呼んでください!」
「え、なんで」
「なんでって、彼女なのに柏木さんってずっと呼ぶの距離感ありません?」
その通りかもしれない。でも、僕はまだ、柏木さんイコール彼女という等式は成り立っていなかった。出会って一ヶ月も経っていないのだから、僕の感覚が普通であると信じたい。むしろ、いきなり初めて会った男の家に上がったり、その男に彼氏になるように頼んだり、彼女はフレンドリーすぎる気がする。
「まあ、そうだけど。栞って呼ばれたいの?」
「はい! 私の名前、覚えててくれたんですね」
「うん。努力はするけど、期待はしないでね。柏木さんで慣れちゃったんだから」
「努力してもらえるだけで、嬉しいですよ」
栞......か。僕は友達を苗字で呼ぶ習慣があるので、なかなか慣れそうにないな。というか、どうして僕は彼女のためにここまで真剣になっているのだろう。本当に好きになったから、とかそういうのではないだろうな。
「僕からも一つお願いがある」
「何ですか?」
言った彼女は、かなり顔を近づけてきた。覗き込むような感じで。甘い香りが僕の鼻腔を抜けた。
僕の声がかなり小さいのもあるけれど、近づきすぎだ。生前から彼女はこんな子だったのか? これで男の家上がったことないって、呪いでもかけられていたのか? 男の家に入ると、死ぬ、みたいな。
僕は耐えられなくなって、顔をそむけて、言う。
「敬語やめない? 同い年なんだし」
敬語は彼女の基本スタイルだ。以前にもどうして敬語なのか訊いたことがあった気がする。距離感で言えば、これもそれなりだと思うのだけれど、どうだろう。彼女は悩んでいるようだった。
「嫌ならいいんだけどさ。無理に変えてもらおうとは思わないし」
「えっと、秋太くんはタメの方がいいですか?」
「僕はそうだね。その方が話しやすい」
「わかりました。彼氏がそれを望むのなら、敬語やめます! 努力はしますが、期待はしないで......ね?」
敬語で慣れているせいか、違和感を覚える喋り方になってしまっている。八月が終わるまでに、慣れてくれればいいな、と思う。
そんな話をしているうちに、ポップコーンが出来始めた。お鍋の中からポコポコと弾ける音が聞こえる。
「こんな感じでポップコーンってできるんですねぇ」
「敬語」
「あっ、慣れない......よ」
僕も名前を呼ぶとき、柏木さんと呼んでしまいそうだ。慣れって怖いものだ。変えようと思っても、なかなか変えることはできない。
出来上がったポップコーンをお皿に移し、完成した。ポップコーンが出来上がったので、二階に戻ることにした。
キッチンを出た瞬間、母さんに声をかけられた。
「あんた、ぶつぶつ何言ってたの?」
小声とは言え、この距離だと聞こえてしまっていたようだ。どう誤魔化そう。
隣の彼女は両手を合わせて、謝罪のポーズをしている。別に彼女が悪いわけじゃないのに。僕がもう少し気をつけていれば、良かった話だ。
「彼女と通話中だった」
「いつの間に彼女できたの?」
「最近だね。またいつか紹介するよ」
「早く紹介するんだよ」
そう言った母さんは、テレビに向き直った。俺はリビングの扉を開け、出た。
「なんか、さっきの嬉しかった」
栞が言った。
少し嘘を言ったけど、完全な嘘ではない。彼女ができたというのは、本当だ。けれど、母さんに紹介するのは絶対に叶わないことなので、嘘になる。
僕は少し微笑んで、部屋に入った。
「よし、映画を観よー!」
栞はそう言って、カバンから一枚のディスクを取り出した。彼女が持ってきたのは、ホラー映画だった。なぜそのジャンルを選択したんだ......。
僕はホラー映画があまり得意でない。徐々に迫り来る恐怖感が苦手というわけではない。唐突に出てくる幽霊なんかに驚かされるのが嫌なんだ。びっくりするな、というのが無理な話だ。
だから僕は、正直ホラー映画を観たくない。しかし、彼女の前で苦手であることを伝えるのは憚れる。弱点を見せたくないのだ。無心になり、映画を観よう。
彼女はウキウキしているけれど、ホラー映画とか全然大丈夫なタイプなのだろうか? そうだとしたら、ちょっと意外だな。めちゃくちゃ怖がりそうなイメージがある。
「か──栞はホラー映画とか平気なの?」
「観たことないですね! だから楽しみ!」
それならもしかしたら僕より怖がってくれる可能性があるな。ビビってくれ!
「秋太くんはホラー映画好きですか?」
「まあまあかな」
素直になれない。見栄を張ってしまう。苦手であることを悟られないように、平然とした顔を貫き通せばいい話だ。それが難しいのだけど。
僕の部屋のテレビに繋がったDVDプレーヤーに彼女はセットした。
ああ、始まってしまう......。目瞑っていてもバレないかな。
「やっぱり、夏はホラー映画ですよねー」
そんなことをつぶやきながら、彼女はリモコンを操作する。僕は背筋が自然と伸びた。
「スタート!」
彼女の掛け声で、始まった。二時間後の僕は、生きているかな?
「秋太くんかわいい」
屈辱! 普通に悲鳴をあげてしまった。本当に早く終わって欲しかったけれど、そう願っているときに限って、時間というのは経つのが遅く感じる。
栞はケロっとしており、映画を楽しんでいた。
「......怖くなかったの?」
「確かに怖かったよ。でも、あの幽霊たちって作りものじゃないですか」
間違ってない。間違ってないけれど、怖いものは怖い。
「それに、ここに幽霊みたいな人が実際いるからね。映画で出てきた幽霊たちは友達みたいな感じ、かな?」
「笑えないんだけど」
「ふふっ。笑ってくれてもいいんだよ?」
栞はお茶目に笑う。
敬語は少しずつ消えかかっている。慣れたものが少しずつ崩れ始めている。僕の呼び方も同じだ。けれど、僕の隣にいる人がもう生きていないことに慣れることはないだろうなと思う。というか、慣れたくない。そう思う。
友達と話すような感覚で喋るけれど、彼女と僕とでは住む世界が違う。誇張なんかではなくて、本当に違うのだ。同じ世界に生きる人、と彼女を認識してしまうわけにはいかない。
ニコニコしながらあと少しとなったポップコーンを食べる彼女を見ていると、どうして死ぬのが彼女だったんだ。どうして僕だけにしか見えないんだ。そんな思いが募ってくる。神様がいれば、僕は恨む。あと数週間後に別れることが、確定しているのならこれ以上仲良くなりたくない。なりたくないのに、彼女に付き合ってしまう自分に辟易する。
「栞は携帯とか持ってないの?」
「逆に私が契約できると思う?」
「思わない」
僕たちが出会って十日目。大型のショッピングモールに向かっていた。歩いて行ける距離にはないので、電車を利用することにした。三十分ほど揺られると、そこにたどり着く。
僕は最寄駅までの切符を購入したが、栞は改札をスッと通り抜けた。無賃乗車でも誰も咎めたりしないだろう。
「やっぱり不便だよね。連絡取り合えないのは」
「そうだねー。もしかして、私が帰った後もお話したくなったんですか?」
彼女はニヤニヤしながら、上目遣いで覗き込んでくる。やはり出会った頃と比べると、大分砕けたと思う。嬉しい変化だ。
「僕が当日に何か予定入ったときに困るからだよ」
「なーんだ。まあ、そのときは秋太くんの部屋に置き手紙でも残してもらえると、助かるかな」
「いい案だね。採用」
「ふふっ」
最寄駅に着いたので、下車した。彼女の足取りは軽く、上機嫌であることが窺えた。
僕たちがショッピングモールに向かう理由は、彼女がご所望だったからだ。昨日、「私、ショッピングモールに行ってみたいです!」と彼女は言った。行ってみたい、という言い方に違和感を覚えたが、まさか一度も行ったことがないなんてことないよな? 僕たちが住む町にないとは言え、一度もないなんてことがあるとは思えなかった。
僕の偏見かもしれないが、女子高生と言えば、ショッピングモールのフードコートなんかで駄弁っているイメージがある。本当に僕の勝手な想像だけれど。
僕もあまり行ったことがないけれど、スマホの地図アプリで確認しながら進むと、なんとかたどり着いた。視界に全く収まりきらないくらい広い。
中に入ると、冷気を全身で感じ、とても気持ち良かった。外は熱された鉄板の上を歩いているような感覚になるくらい暑かった。今朝ニュースでやっていたけれど、どうやら今年一番の暑さらしい。これも温暖化の影響なのだろうか。冷房をガンガンに効かせると、温暖化を加速させてしまう。けれど、冷房がないと生きていける自信がないし、難しい話だ。
隣を歩いていた彼女もさすがに暑かったのか、「暑いねぇ」と何度も口にしていた。入った瞬間、「すっずしー」と言っていたので、ちゃんと温度感覚があるようで安心した。
「まずはどこに行くの?」
「迷います。うーん」
館内マップを見ながら、彼女は悩む。
「まずはここに行きましょう!」
言った彼女が指差したのは、洋服屋だった。女子高生らしいチョイスだと思った。
「了解」
エスカレーターで二階に上がった僕たちは、洋服屋を目指した。夏休みということもあり、かなり人が多かった。これだけ人が多いと、僕が独り言をつぶやいていてもあまり目立たないだろう。
「そういえば、いつも服が違うけど、盗んでるの?」
「ちょっと言い方ー。全部私の私物。生前に住んでいた家にまだ捨てられずにしまわれてるんだよねー。だから忍び込んで、貰ってきてます」
そういうことだったのか。てっきり僕は、毎日どこかの服屋からとってきているのかと思っていた。それでも誰も咎めはしないだろうし、いいと思うけれど。
「秋太くんはファッションに興味ないの?」
「ないかな。僕が着飾ったとしても、周りからの反応は大して変わらないだろうし、そこにお金を投資するなら別のことに使う」
「もう少しおしゃれしたら、もっとモテると思うのになー」
「彼女がいる僕がモテてもいいの?」
「九月からなら全然いいよ。彼女認定してくれるの、嬉しいなっ」
栞は試着室で着替えると、「どう?」と訊いてきて、僕は「似合ってる」と言う。そんなやり取りを三回ほど繰り返した。三着の中でどれが一番良かったか訊かれたので、二番目のやつ、と答えておいた。正直、どれもよく似合っていたし、甲乙つけがたかった。
「それ買うの?」
「買わないよー。お金ないし。でも、これ可愛いし欲しいなぁ」
甘い声で僕の方を見る彼女。盗めば? とは言えなかった。僕は栞が持っていた白いワンピースを受け取り、レジに向かった。
彼女は少し驚いた表情で、僕の後をついてきた。支払いを終え、店を出た。
「本当に買ってくれると思ってなかった......」
「これは買ってあげたって言っていいのかわからないけどね。九月になれば、僕の元にお金は返ってくるんだから」
栞に使ったお金は全て彼女が消えたら、戻ってくる。
「それでも私は嬉しいよ。お金が返ってくるとかそういう話って私が消えた後の話だから、今は秋太くんにプレゼントを貰えた。私にはその記憶だけが残って、消えるまで生きていくので」
「そういうものか」
「そういうものだよ」
僕たちは当てもなく歩いていた。涼しい館内を歩くのは、そんなに苦ではなかった。たまに面白そうな店があると、入る。そして数分後店を出て、またぶらつく。そんなことを繰り返していると、時刻は十一時半となっていた。
「そろそろご飯食べない? お腹すいた」
「あり! どこで食べる?」
大型のショッピングモールということもあり、色んな種類のお店が入っている。お寿司や中華、ファーストフードなんかも。僕は財布を開く。さっき服を買ったことで、かなり寂しい中身となっていた。
「悪いんだけど、お金あんまり持ってきてなかったから、そんなに高くないところで......単独行動なら君はお寿司とか食べてきてくれても全然いいんだけど」
言った僕を見て、栞は少し頰を膨らませた。怒らせるようなこと言ってしまったのかな。
「別々で食べる選択肢は絶対ないです!」
「でも、なんていうか、この世でいられる期間は残り少ないんだから、好きなもの食べた方がいいんじゃないかと思って。その足枷には、なりたくない」
僕と違って、栞には期限がある。もしかしたら、僕も明日死ぬのかもしれない。けれど、それは決定事項ではなくて、可能性の低い話だ。僕がこれから数十年生きる可能性の方が高い。彼女の場合は違う。何かを食べたり、飲んだり、どこかへ行ったり、遊んだり、そんなことができるのは、あと数週間しかないのだ。
彼女はもっと残りの人生を有意義に過ごすべきだと思う。僕が口出しするようなことでもないのかもしれないけれど。
「どうしてそうなるの」
どうやら本当に怒らせてしまったようだ。冷たい声が僕の耳に入ってくる。
「どうしてって......」
「私は秋太くんと一緒に食べられたら、それで満足です。カップルで来て、別々に食事を済ますことってありますか?」
「ない......です」
「だよね? そういうことだよ。私は同じ物を食べたい」
「悪かった。じゃあ、とりあえずフードコートでいいかな?」
彼女は数分前と同じ笑顔を浮かべ、大きく頷いた。
昼前だけれど、席はほとんど埋まっていた。なんとか二人がけのテーブル席を見つけたので、そこに座ることにした。
「荷物番お願いしていい? 僕が買ってくるから」
席がとられる可能性があるので、どちらかは残っておく必要があった。
「私、荷物番の役目果たせないと思います......」
どうして? と訊こうとしたが、栞が僕以外に見えていないことを思い出した。こうして普通に喋っていると、友達と話しているようで、彼女の置かれている状況を忘れそうになる。
確かに誰からも認知されないのなら、荷物番として不適だろう。けれど、買ってきてもらうにしても、注文することがそもそもできないので、そっちもダメだ。
「ごめん」
「こちらこそ、役立たずでごめんなさい」
彼女に変な気を遣わせてしまった。
「多分、これだけ人がいれば盗まれる心配はないだろうし、さっき買ったやつをテーブルに置いとこう。二人で買いに行こっか」
「はい!」
白昼堂々と盗んでいくやつはいないだろう。監視カメラもあるだろうし。僕は財布だけ持って行くことにした。
色んな店がある。牛丼屋だったり、ラーメン屋だったり、ハンバーガーショップなんかもある。これだけ多いと、何にするか迷うな。
「どれにするか決めた?」
「オムライス!」
彼女は無邪気な子どものように言った。
「じゃあ僕もそうするよ。そんなに並んでなさそうだね」
正直僕は何でも良かったので、彼女と同じ店にした。オムライスは嫌いではないし、それに手間が省ける。
一人しか待っていなかったので、すぐに僕たちの番が来た。同じオムライスを二つ注文し、呼び出しベルを受け取った。出来上がったらまた取りに行かなければならない。
「ごめんね。また払ってもらっちゃって」
「それは気にしなくていいから」
僕たちは一旦、テーブルに戻った。
「これで呼ばれるんですねー」
「そうだね。順番が来たら、音が鳴る感じ」
徐々にフードコート内の人が増えてきた。客層は多種多様で、子連れや学生グループ、お年寄りまでいた。僕も二人で来ているわけだけど、周りから見れば一人客だ。カウンター席ではなく、二人がけのテーブルに一人で座っている僕は、あまり良いようには見られていないのかもしれない。まだ満席ではないけれど、満席になれば露骨に嫌悪感を帯びた視線を浴びる可能性がある。あまり長居はできなそうだ。
「ねえねえ」
「ん?」
「秋太くんってマジックとかできないの?」
「えらく急だね。昔はちょこっとやってたんだけど、今は全然」
「今度見せてよ!」
「そんな人様に見せられるレベルじゃないよ。本当に簡単なやつしかできない」
僕がマジックにハマっていたのは、小学校低学年ぐらいまでだ。仲の良かった子に見せるために、練習していたけれど、会う機会が減ると、すっかりやらなくなってしまった。今は本当に簡単なやつしかできないと思う。
「それでもいいよー。私ね、マジック好きなの」
「初耳だ」
「そりゃあそうだよ。私言ってなかったから」
彼女が微笑んだのとほぼ同時に、呼び出しベルが鳴った。
「うわっ、びっくりした。心臓止まるかと思った」
たまに言う彼女の冗談はツッコミづらい。素なのか、冗談なのかもわからない。彼女の心臓って鼓動を刻んでるのかな。
「受け取るだけだし、行ってくるよ。待ってて」
「お言葉に甘えまーす」
先ほど注文した店は僕らが並んだときよりも、並ぶ人が多くなっていた。出来上がった二つのオムライスを受け取り、僕は彼女が待つテーブルに向かった。
片手で持つには、少々重たく一人で来たことを後悔した。
僕が戻ると、テーブルの上が少し違う。でも、その違和感がなんなのかわからなかった。さっきと同じ席に座る彼女はニコニコしている。
「お水入れてきたよっ」
水か。さっきまでなくて、今あるもの。違和感の正体がわかった僕は、すっきりした。
「ありがとう」
「こちらこそ、とってきてくれてありがとー」
二つのトレーをテーブルに慎重に置き、僕も座った。腕ちょっとプルプルしてるけど、彼女にバレてないかな? 非力だと思われたら、恥ずかしい。実際、非力だけれど。
「いただきまーす」
「いただきます」
一口食べる。
旨い。薄い膜のような玉子だけど、ちゃんと食感があり、ふわふわだった。包まれているチキンライスには刻まれた玉ねぎや人参が入っており、こっちの食感も良かった。ケチャップの酸味は強すぎず程よい。それぞれの部分の味を殺さず、いい塩梅だ。
「んー! 美味しい」
彼女も満足しているようで良かった。
「美味しいね」
「私、実は結構オムライス好きなんだよね」
「初耳」
「これも言ってなかったからね〜」
そう言いながら口に運ぶ彼女は、本当に至福の表情をしていた。こっちも自然と頰が緩む。
「さっきの続きなんですけど、簡単なやつでいいんでマジック見せてくださいねー」
「考えとくよ」
マジック好きの人に見せたら、笑われるレベルかもしれないが、彼女がそれを望むのならやろう。少しは練習期間が欲しいので、数日後になると思うけれど。
オムライスを完食した僕たちは、席を空けるため出ようとしていた。
「あれ? 佐竹か?」
栞の声ではないし、僕は声のした方向を向いた。そこには同じクラスの友達が立っていた。
「なんだ、大井か」
夏休み中に彼女以外と遊んだ唯一の人物だ。僕が一番仲の良いクラスメイトと言える。陽気なやつで、僕とは性格が真反対な気もするけれど、なぜか話が合うので一緒にいる。
「なんだ、ってひでーなー。お前こそ、何してんだよ。ん?」
大井は僕ではなく、僕の前に座る栞の方を見た。
「どうしたの?」
「いや、まさかお前も見えてるのかと思ってな......」
見えてる......? もしかして、栞のことだろうか? 大井も僕と同じで彼女のことが見えるのか?
彼女はとても驚いた表情をしている。どういうことだ。
「見えてる......とは?」
「見えてねえのか? 目の前にいる顔のでかい幽霊が」
「は?」
目の前にいるのはとてもスタイルの良い美少女だ。彼女の方を見ると、「私......顔でかいかな」と言いながら、顔面を手でペタペタ触っている。そんなことないよ、と言いたかったが、大井がいるので口にはできなかった。
「はははっ! 冗談だよ、冗談」
やっぱりそうだよな。彼女のことを認識できるのは、僕だけ。大井に見えるはずがない。彼女はホッと、胸をなで下ろしている。
じゃあ、どうして大井はあんなことを言ったのだろうか?
「なんでそんな冗談を」
「だってお前、誰かと喋ってるみたいだったから。もしかしたら、霊感が強いお前は幽霊と対話できる能力にでも目覚めたのかと思ってな」
見られてたのか......。フードコートは人が多いおかげで、声が届きづらく、一人で喋っているのがバレにくいと思ってたんだけどな。
無関係な人からどんな目で見られようが気にしないが、知り合いだと気まずいな。誤魔化すのも大変だ。
「そんなわけないでしょ」
「じゃあ誰と喋ってたんだよ」
彼女の名前を言うわけにはいかない。でも、いい誤魔化し方が思い浮かばない。
「......彼女」
僕は言った。当然、僕にしか見えない彼女は、驚いている。そして、友達の大井も驚いている。自分でもどうしてそんなことを言ったのかわからない。この状況を回避できる方法が思い浮かばなかったとは言え、最悪の選択をしてしまったのではないだろうか。
もっと考えて、発言するべきだった。後悔しても仕方ない。さっきよりも絶体絶命となった状況を回避する方法を考えなければならない。
「なるほどな......」
大井は言った。なぜ納得したんだ。
「お前、彼女が欲しすぎるあまり、彼女がいると見立てて、デートするとかヤバいな。ヤバすぎて、逆に尊敬するわ」
「いや、そういうわけじゃ......」
まずい。変な勘違いを起こされた。
「気にすんな。見たのが俺で良かったな。お前の名誉はちゃんと守ってやる。男二人の固い約束だ。あ、彼女も聞いてるから、三人の約束だな」
栞は、笑いをこらえるのに必死だった。別に僕にしか見えないから、笑ってもいいのに。大井は「がはははっ」と笑っていた。
「さ、さんきゅー」
「邪魔しちゃ悪いし、俺行くわ。じゃあな!」
そう言うと、大井は笑いながら、フードコートを去った。
まあ、見られたのが大井で良かったと思う。不幸中の幸いと言ったところ。他のそんなに仲がいいわけでもないクラスメイトに見られた場合、影で色々言われるに決まっている。佐竹ってめちゃくちゃ独り言多いらしいよ、とか。大井は悪いやつではない。本当に誰かに言いふらしたりすることはないだろう。
僕は安堵の息をついた。
「お友達?」
「ん、ああ。僕の一番の仲のいいやつかな」
「いいですねぇ。親友って感じがして」
「どうだろう。僕たちは親友って言っていいのかな。出会ったのは高校入ってからだし」
「期間なんて関係ないですよ。見てれば、仲がいいことが伝わってきました」
「なんか恥ずかしいな。ていうか、僕は栞って呼んでるのに、敬語抜けてないんじゃない?」
「誰に対しても敬語だったんで、抜けきらない、の!」
彼女はむぅ、と頰を膨らませた。なんか僕が悪いみたいだ。責められる筋合いはないんだけどな。
僕たちは今度こそトレーを持って立ち上がり、返却口に向かった。トレーを返却した後、フードコートを出た。彼女が見たいものは服ぐらいだったらしく、他に用があるお店はないようだ。適当にぶらつくだけでいい、と彼女は言ったので僕の意向で本屋に行くことにした。
「同い年の子からそんなセリフが聞けると思わなかった。満足してもらえたようなら、連れてきた甲斐があったよ」
「大満足ですっ。そういえば、同い年のお友達いないんですか? 私と毎日会っていて、友達と遊んでないようですし」
まずは友達の定義を......。いないわけではないけれど、少ない方ではあると思う。彼女の言う通り、夏休みの暑い中に遊びに行くような友達は全然いない。誘うこともなければ、誘われることもない。今のところだけど。でも、一人だけいるな、誘って来そうなやつが。
「友達はそこそこいるよ。そこそこ」
謎の見栄を張ってしまった。彼女の顔を直視できなかった。
「へー、そうなんですか。いいですねぇ」
どんな人ですか、とか訊いてこなかったあたり、柏木さんは僕を気遣ってくれたのだろう。きっと僕が本当のことを言っていないことくらい気づいてそうだから。
僕の家の前まで帰ってきた。今日もかなり歩いた。最近はウォーキングが趣味と言っても、差し支えないレベルだ。徐々に筋肉痛にもならなくなってきた。いつか隣町まで歩いて行ってしまうのではないだろうか。
「では、また明日もよろしくお願いします」
「うん。また」
彼女の後ろ姿は生き生きしていた。刻一刻と彼女が現世でいられる時間は減少しているのに。
僕も未練を残したら、彼女のようになってしまうのかな。そんなことを考えながら、玄関の扉を開けた。よく考えれば、僕には未練を残すほど執着しているものなんてなかった。
昨日は柏木さんと会うことができなかった。僕が友達と遊びに行ったからだ。友達は少ないけれど、一人もいないわけではない。一昨日に連絡が来たので、彼女に会えないことを伝えた。その時の寂しそうな顔を見ると、本当に付き合っているような気がしてきてしまった。
彼女は付き合っているというけれど、僕たちにはまだまだ距離感はあると思うし、僕の感覚では仲良くなり始めた友達ぐらいだ。彼女の敬語も一向になくなる気配はないし。たまに感極まった時に外れるくらいだ。
彼女の方も口では言うけれど、付き合っているという感覚はないんじゃないだろうか。自分にそう言い聞かせて、僕を彼氏と見立てる。彼女は僕にしか見えていないのだから、僕以外に候補がいないし仕方のないことなのかもしれない。
自分で言うの何だけど、僕を彼氏と考えるのはかなり無理がある気がする。彼女と僕とでは、全く釣り合っていない。主に容姿が。
神様は酷いと思う。彼女の人生を早々に終わらせた挙句、未練を消化する際ももっと相応しい人物を選んであげるべきだった。そういえば、彼女の死因を訊いたことがないな。本人に死因を訊くなんてこれから先、一生することのない経験だ。しかし、きっと思い出したくないことだろうし、訊ける環境にあるけれど、訊くことはないだろうな。
そんな彼女がもう少しで僕の家にやってくるはずだ。一日空いただけなのに、八月に入ってから毎日会っているせいで、久々に感じる。
部屋の扉が数回ノックされた。
「どうぞ」
「おじゃましまーす」
彼女は壁を通り抜ける能力を持っているが、僕のプライバシーを考え、一応ノックしてくれたようだ。玄関の扉は通り抜けてきたようだけど。
「今日は何するの?」
「そうですねー。この辺でおうちデートなんてどうです?」
「どうです? って言われても、するんでしょ。それ」
「その通りです。一応映画も借りてきました!」
借りてきた、ではなく、パクってきたのでは? 彼女がレンタルショップで、お金を出して、借りてる姿を想像することはできるけれど、実際にそうすることはできないのだから、勝手にディスクを引っこ抜いてきたのだろう。
僕の家に未清算のディスクがあるわけだけれど、捕まらないよね? 彼女の話では、夏休みが終わると、彼女がとってきた一枚のディスクもとられたという事実がなくなるので、捕まることはないのだろうけれど、犯罪に加担しているみたいで、罪悪感が芽生える。
「僕の家に、お菓子とかあんまりないから、今から買いに行く?」
「それもバッチリです。ポップコーン買ってきました」
そう言って、手に持っていた袋から、ポップコーンを取り出した。僕が想像していたのは、大袋の開ければ、食べれるやつだったのだけれど、彼女が買ってきたのは、ポップコーンの種だった。
「なあ、どうして種なんだ? 出来上がったやつはなかったのか?」
彼女は不思議そうに小首をかしげた。
僕は何か変なこと言ったかな?
「......ポップコーンってこうやって作るんじゃないんですか?」
「いや、まあ、間違ってないよ。間違ってないんだけど、火を使うし手間がかかるから、普通は完成したやつを買うもんだと思ってた」
僕は言って、スマホで画像検索し、それを彼女に見せた。
「お恥ずかしい......」
どうやら本当に知らなかったようだ。かなり珍しいけれど、そういう人がいてもおかしくはないだろう。僕にだって知らないお菓子はあるだろうし。
「せっかく買ってきてくれたんだし、一緒に作るか」
「はい!」
と思ったけれど、一つ問題がある。今日、僕の家にいるのは、僕と柏木さんだけではない。母さんがリビングのソファで鎮座している。
火を使うには、どうしてもそのリビングを通る必要がある。キッチンはリビングを抜けた先にあるから。リビングとキッチンの間には扉がないので、僕が喋った声が母さんに丸聞こえだ。
つまり、僕が今みたいに柏木さんと普通に会話してしまうと、母さんに訝しげな目で見られ、病院に連れて行かれる可能性があるということ。脳に異常がないか検査してもらうために。
それはまずい。本当のことを説明したいが、彼女の存在を母さんに知られるわけにいかない。
ポップコーンは諦めるしかないのか? 彼女がせっかく買って、いや持ってきてくれたポップコーンの種を無駄にしたくない。それに、やる気に満ち溢れた表情を見ると、とてもじゃないが、やっぱりやめとこう、なんて言えなかった。
彼女が、まだかまだか、と見つめてくる。これ以上、思案し続けるのは、無理か......。
「とりあえず、下行こっか」
彼女は大きく頷いた。どうしよう。
「母さんがリビングにいると思うけど、気にしないでね」
一応、言っておいた方がいいかと思い、階段を下りている最中に言った。
「そうなんですね。私は全然気にしないんですけど、秋太くんは大丈夫なんですか?」
彼女もこのまま二人でポップコーンを作り始めたら、どうなるのか気づいたようだ。
「まあ、何とかなるでしょ」
何とかなる算段が立たないまま、僕はリビングの扉の前まで来てしまった。テレビの音が聞こえるし、母さんが買い物に出かけている可能性も潰えた。
僕はゆっくり扉をスライドさせた。
いきなり扉が開いたのだから、当然母さんはこちらを向く。
「何それ、ポップコーン?」
母さんは僕の左手に持つ、ポップコーンの種を指して言った。
「そうだよ。ちょっと食べたくなってさ」
「それだったらわざわざ種から作らなくてもいいのに」
母さんの意見に同意だ。隣の彼女は少し頬を赤らめている。母さんには見えていないけれど、ダメージを与えてしまったようだ。
「出来たての方が美味しいでしょ。たまには、いいかと思って」
「全然いいけど、火使うんだから、気をつけんだよー」
「小学生じゃないんだから、大丈夫だよ」
リビングとキッチンは繋がっているが、申し訳程度に仕切るためのカーテンがあるので、僕の姿は母さんからほとんど見えないだろう。
「よし、作るか」
かなり小さめのボリュームで僕は、言った。
「はい」
なぜか声の大きさを気にする必要のない彼女まで、小声になっている。
「柏木さんはいつも通りの声の大きさでいいんだよ」
「あっ、そうでした。私の声は秋太くんにしか、聞こえてないですもんね」
彼女の声の大きさは、先ほど部屋にいたときと同じくらいに戻った。僕もつられて、声が大きくならないように気をつけないと。
僕はお鍋に種と油を入れ、火をつけた。作ると言っても、たったこれだけなので大した労力ではない。
隣の彼女は子どもみたいに、楽しそうにお鍋を見つめていた。
「弾けるまでもう少しかかると思うよ」
「そうなんですね。じゃあ一つお願い、いいですか?」
「どうぞ」
僕は何をお願いされるのだろう。無理のない範囲であれば、いいんだけど......。
「秋太くんも私のこと下の名前で呼んでください!」
「え、なんで」
「なんでって、彼女なのに柏木さんってずっと呼ぶの距離感ありません?」
その通りかもしれない。でも、僕はまだ、柏木さんイコール彼女という等式は成り立っていなかった。出会って一ヶ月も経っていないのだから、僕の感覚が普通であると信じたい。むしろ、いきなり初めて会った男の家に上がったり、その男に彼氏になるように頼んだり、彼女はフレンドリーすぎる気がする。
「まあ、そうだけど。栞って呼ばれたいの?」
「はい! 私の名前、覚えててくれたんですね」
「うん。努力はするけど、期待はしないでね。柏木さんで慣れちゃったんだから」
「努力してもらえるだけで、嬉しいですよ」
栞......か。僕は友達を苗字で呼ぶ習慣があるので、なかなか慣れそうにないな。というか、どうして僕は彼女のためにここまで真剣になっているのだろう。本当に好きになったから、とかそういうのではないだろうな。
「僕からも一つお願いがある」
「何ですか?」
言った彼女は、かなり顔を近づけてきた。覗き込むような感じで。甘い香りが僕の鼻腔を抜けた。
僕の声がかなり小さいのもあるけれど、近づきすぎだ。生前から彼女はこんな子だったのか? これで男の家上がったことないって、呪いでもかけられていたのか? 男の家に入ると、死ぬ、みたいな。
僕は耐えられなくなって、顔をそむけて、言う。
「敬語やめない? 同い年なんだし」
敬語は彼女の基本スタイルだ。以前にもどうして敬語なのか訊いたことがあった気がする。距離感で言えば、これもそれなりだと思うのだけれど、どうだろう。彼女は悩んでいるようだった。
「嫌ならいいんだけどさ。無理に変えてもらおうとは思わないし」
「えっと、秋太くんはタメの方がいいですか?」
「僕はそうだね。その方が話しやすい」
「わかりました。彼氏がそれを望むのなら、敬語やめます! 努力はしますが、期待はしないで......ね?」
敬語で慣れているせいか、違和感を覚える喋り方になってしまっている。八月が終わるまでに、慣れてくれればいいな、と思う。
そんな話をしているうちに、ポップコーンが出来始めた。お鍋の中からポコポコと弾ける音が聞こえる。
「こんな感じでポップコーンってできるんですねぇ」
「敬語」
「あっ、慣れない......よ」
僕も名前を呼ぶとき、柏木さんと呼んでしまいそうだ。慣れって怖いものだ。変えようと思っても、なかなか変えることはできない。
出来上がったポップコーンをお皿に移し、完成した。ポップコーンが出来上がったので、二階に戻ることにした。
キッチンを出た瞬間、母さんに声をかけられた。
「あんた、ぶつぶつ何言ってたの?」
小声とは言え、この距離だと聞こえてしまっていたようだ。どう誤魔化そう。
隣の彼女は両手を合わせて、謝罪のポーズをしている。別に彼女が悪いわけじゃないのに。僕がもう少し気をつけていれば、良かった話だ。
「彼女と通話中だった」
「いつの間に彼女できたの?」
「最近だね。またいつか紹介するよ」
「早く紹介するんだよ」
そう言った母さんは、テレビに向き直った。俺はリビングの扉を開け、出た。
「なんか、さっきの嬉しかった」
栞が言った。
少し嘘を言ったけど、完全な嘘ではない。彼女ができたというのは、本当だ。けれど、母さんに紹介するのは絶対に叶わないことなので、嘘になる。
僕は少し微笑んで、部屋に入った。
「よし、映画を観よー!」
栞はそう言って、カバンから一枚のディスクを取り出した。彼女が持ってきたのは、ホラー映画だった。なぜそのジャンルを選択したんだ......。
僕はホラー映画があまり得意でない。徐々に迫り来る恐怖感が苦手というわけではない。唐突に出てくる幽霊なんかに驚かされるのが嫌なんだ。びっくりするな、というのが無理な話だ。
だから僕は、正直ホラー映画を観たくない。しかし、彼女の前で苦手であることを伝えるのは憚れる。弱点を見せたくないのだ。無心になり、映画を観よう。
彼女はウキウキしているけれど、ホラー映画とか全然大丈夫なタイプなのだろうか? そうだとしたら、ちょっと意外だな。めちゃくちゃ怖がりそうなイメージがある。
「か──栞はホラー映画とか平気なの?」
「観たことないですね! だから楽しみ!」
それならもしかしたら僕より怖がってくれる可能性があるな。ビビってくれ!
「秋太くんはホラー映画好きですか?」
「まあまあかな」
素直になれない。見栄を張ってしまう。苦手であることを悟られないように、平然とした顔を貫き通せばいい話だ。それが難しいのだけど。
僕の部屋のテレビに繋がったDVDプレーヤーに彼女はセットした。
ああ、始まってしまう......。目瞑っていてもバレないかな。
「やっぱり、夏はホラー映画ですよねー」
そんなことをつぶやきながら、彼女はリモコンを操作する。僕は背筋が自然と伸びた。
「スタート!」
彼女の掛け声で、始まった。二時間後の僕は、生きているかな?
「秋太くんかわいい」
屈辱! 普通に悲鳴をあげてしまった。本当に早く終わって欲しかったけれど、そう願っているときに限って、時間というのは経つのが遅く感じる。
栞はケロっとしており、映画を楽しんでいた。
「......怖くなかったの?」
「確かに怖かったよ。でも、あの幽霊たちって作りものじゃないですか」
間違ってない。間違ってないけれど、怖いものは怖い。
「それに、ここに幽霊みたいな人が実際いるからね。映画で出てきた幽霊たちは友達みたいな感じ、かな?」
「笑えないんだけど」
「ふふっ。笑ってくれてもいいんだよ?」
栞はお茶目に笑う。
敬語は少しずつ消えかかっている。慣れたものが少しずつ崩れ始めている。僕の呼び方も同じだ。けれど、僕の隣にいる人がもう生きていないことに慣れることはないだろうなと思う。というか、慣れたくない。そう思う。
友達と話すような感覚で喋るけれど、彼女と僕とでは住む世界が違う。誇張なんかではなくて、本当に違うのだ。同じ世界に生きる人、と彼女を認識してしまうわけにはいかない。
ニコニコしながらあと少しとなったポップコーンを食べる彼女を見ていると、どうして死ぬのが彼女だったんだ。どうして僕だけにしか見えないんだ。そんな思いが募ってくる。神様がいれば、僕は恨む。あと数週間後に別れることが、確定しているのならこれ以上仲良くなりたくない。なりたくないのに、彼女に付き合ってしまう自分に辟易する。
「栞は携帯とか持ってないの?」
「逆に私が契約できると思う?」
「思わない」
僕たちが出会って十日目。大型のショッピングモールに向かっていた。歩いて行ける距離にはないので、電車を利用することにした。三十分ほど揺られると、そこにたどり着く。
僕は最寄駅までの切符を購入したが、栞は改札をスッと通り抜けた。無賃乗車でも誰も咎めたりしないだろう。
「やっぱり不便だよね。連絡取り合えないのは」
「そうだねー。もしかして、私が帰った後もお話したくなったんですか?」
彼女はニヤニヤしながら、上目遣いで覗き込んでくる。やはり出会った頃と比べると、大分砕けたと思う。嬉しい変化だ。
「僕が当日に何か予定入ったときに困るからだよ」
「なーんだ。まあ、そのときは秋太くんの部屋に置き手紙でも残してもらえると、助かるかな」
「いい案だね。採用」
「ふふっ」
最寄駅に着いたので、下車した。彼女の足取りは軽く、上機嫌であることが窺えた。
僕たちがショッピングモールに向かう理由は、彼女がご所望だったからだ。昨日、「私、ショッピングモールに行ってみたいです!」と彼女は言った。行ってみたい、という言い方に違和感を覚えたが、まさか一度も行ったことがないなんてことないよな? 僕たちが住む町にないとは言え、一度もないなんてことがあるとは思えなかった。
僕の偏見かもしれないが、女子高生と言えば、ショッピングモールのフードコートなんかで駄弁っているイメージがある。本当に僕の勝手な想像だけれど。
僕もあまり行ったことがないけれど、スマホの地図アプリで確認しながら進むと、なんとかたどり着いた。視界に全く収まりきらないくらい広い。
中に入ると、冷気を全身で感じ、とても気持ち良かった。外は熱された鉄板の上を歩いているような感覚になるくらい暑かった。今朝ニュースでやっていたけれど、どうやら今年一番の暑さらしい。これも温暖化の影響なのだろうか。冷房をガンガンに効かせると、温暖化を加速させてしまう。けれど、冷房がないと生きていける自信がないし、難しい話だ。
隣を歩いていた彼女もさすがに暑かったのか、「暑いねぇ」と何度も口にしていた。入った瞬間、「すっずしー」と言っていたので、ちゃんと温度感覚があるようで安心した。
「まずはどこに行くの?」
「迷います。うーん」
館内マップを見ながら、彼女は悩む。
「まずはここに行きましょう!」
言った彼女が指差したのは、洋服屋だった。女子高生らしいチョイスだと思った。
「了解」
エスカレーターで二階に上がった僕たちは、洋服屋を目指した。夏休みということもあり、かなり人が多かった。これだけ人が多いと、僕が独り言をつぶやいていてもあまり目立たないだろう。
「そういえば、いつも服が違うけど、盗んでるの?」
「ちょっと言い方ー。全部私の私物。生前に住んでいた家にまだ捨てられずにしまわれてるんだよねー。だから忍び込んで、貰ってきてます」
そういうことだったのか。てっきり僕は、毎日どこかの服屋からとってきているのかと思っていた。それでも誰も咎めはしないだろうし、いいと思うけれど。
「秋太くんはファッションに興味ないの?」
「ないかな。僕が着飾ったとしても、周りからの反応は大して変わらないだろうし、そこにお金を投資するなら別のことに使う」
「もう少しおしゃれしたら、もっとモテると思うのになー」
「彼女がいる僕がモテてもいいの?」
「九月からなら全然いいよ。彼女認定してくれるの、嬉しいなっ」
栞は試着室で着替えると、「どう?」と訊いてきて、僕は「似合ってる」と言う。そんなやり取りを三回ほど繰り返した。三着の中でどれが一番良かったか訊かれたので、二番目のやつ、と答えておいた。正直、どれもよく似合っていたし、甲乙つけがたかった。
「それ買うの?」
「買わないよー。お金ないし。でも、これ可愛いし欲しいなぁ」
甘い声で僕の方を見る彼女。盗めば? とは言えなかった。僕は栞が持っていた白いワンピースを受け取り、レジに向かった。
彼女は少し驚いた表情で、僕の後をついてきた。支払いを終え、店を出た。
「本当に買ってくれると思ってなかった......」
「これは買ってあげたって言っていいのかわからないけどね。九月になれば、僕の元にお金は返ってくるんだから」
栞に使ったお金は全て彼女が消えたら、戻ってくる。
「それでも私は嬉しいよ。お金が返ってくるとかそういう話って私が消えた後の話だから、今は秋太くんにプレゼントを貰えた。私にはその記憶だけが残って、消えるまで生きていくので」
「そういうものか」
「そういうものだよ」
僕たちは当てもなく歩いていた。涼しい館内を歩くのは、そんなに苦ではなかった。たまに面白そうな店があると、入る。そして数分後店を出て、またぶらつく。そんなことを繰り返していると、時刻は十一時半となっていた。
「そろそろご飯食べない? お腹すいた」
「あり! どこで食べる?」
大型のショッピングモールということもあり、色んな種類のお店が入っている。お寿司や中華、ファーストフードなんかも。僕は財布を開く。さっき服を買ったことで、かなり寂しい中身となっていた。
「悪いんだけど、お金あんまり持ってきてなかったから、そんなに高くないところで......単独行動なら君はお寿司とか食べてきてくれても全然いいんだけど」
言った僕を見て、栞は少し頰を膨らませた。怒らせるようなこと言ってしまったのかな。
「別々で食べる選択肢は絶対ないです!」
「でも、なんていうか、この世でいられる期間は残り少ないんだから、好きなもの食べた方がいいんじゃないかと思って。その足枷には、なりたくない」
僕と違って、栞には期限がある。もしかしたら、僕も明日死ぬのかもしれない。けれど、それは決定事項ではなくて、可能性の低い話だ。僕がこれから数十年生きる可能性の方が高い。彼女の場合は違う。何かを食べたり、飲んだり、どこかへ行ったり、遊んだり、そんなことができるのは、あと数週間しかないのだ。
彼女はもっと残りの人生を有意義に過ごすべきだと思う。僕が口出しするようなことでもないのかもしれないけれど。
「どうしてそうなるの」
どうやら本当に怒らせてしまったようだ。冷たい声が僕の耳に入ってくる。
「どうしてって......」
「私は秋太くんと一緒に食べられたら、それで満足です。カップルで来て、別々に食事を済ますことってありますか?」
「ない......です」
「だよね? そういうことだよ。私は同じ物を食べたい」
「悪かった。じゃあ、とりあえずフードコートでいいかな?」
彼女は数分前と同じ笑顔を浮かべ、大きく頷いた。
昼前だけれど、席はほとんど埋まっていた。なんとか二人がけのテーブル席を見つけたので、そこに座ることにした。
「荷物番お願いしていい? 僕が買ってくるから」
席がとられる可能性があるので、どちらかは残っておく必要があった。
「私、荷物番の役目果たせないと思います......」
どうして? と訊こうとしたが、栞が僕以外に見えていないことを思い出した。こうして普通に喋っていると、友達と話しているようで、彼女の置かれている状況を忘れそうになる。
確かに誰からも認知されないのなら、荷物番として不適だろう。けれど、買ってきてもらうにしても、注文することがそもそもできないので、そっちもダメだ。
「ごめん」
「こちらこそ、役立たずでごめんなさい」
彼女に変な気を遣わせてしまった。
「多分、これだけ人がいれば盗まれる心配はないだろうし、さっき買ったやつをテーブルに置いとこう。二人で買いに行こっか」
「はい!」
白昼堂々と盗んでいくやつはいないだろう。監視カメラもあるだろうし。僕は財布だけ持って行くことにした。
色んな店がある。牛丼屋だったり、ラーメン屋だったり、ハンバーガーショップなんかもある。これだけ多いと、何にするか迷うな。
「どれにするか決めた?」
「オムライス!」
彼女は無邪気な子どものように言った。
「じゃあ僕もそうするよ。そんなに並んでなさそうだね」
正直僕は何でも良かったので、彼女と同じ店にした。オムライスは嫌いではないし、それに手間が省ける。
一人しか待っていなかったので、すぐに僕たちの番が来た。同じオムライスを二つ注文し、呼び出しベルを受け取った。出来上がったらまた取りに行かなければならない。
「ごめんね。また払ってもらっちゃって」
「それは気にしなくていいから」
僕たちは一旦、テーブルに戻った。
「これで呼ばれるんですねー」
「そうだね。順番が来たら、音が鳴る感じ」
徐々にフードコート内の人が増えてきた。客層は多種多様で、子連れや学生グループ、お年寄りまでいた。僕も二人で来ているわけだけど、周りから見れば一人客だ。カウンター席ではなく、二人がけのテーブルに一人で座っている僕は、あまり良いようには見られていないのかもしれない。まだ満席ではないけれど、満席になれば露骨に嫌悪感を帯びた視線を浴びる可能性がある。あまり長居はできなそうだ。
「ねえねえ」
「ん?」
「秋太くんってマジックとかできないの?」
「えらく急だね。昔はちょこっとやってたんだけど、今は全然」
「今度見せてよ!」
「そんな人様に見せられるレベルじゃないよ。本当に簡単なやつしかできない」
僕がマジックにハマっていたのは、小学校低学年ぐらいまでだ。仲の良かった子に見せるために、練習していたけれど、会う機会が減ると、すっかりやらなくなってしまった。今は本当に簡単なやつしかできないと思う。
「それでもいいよー。私ね、マジック好きなの」
「初耳だ」
「そりゃあそうだよ。私言ってなかったから」
彼女が微笑んだのとほぼ同時に、呼び出しベルが鳴った。
「うわっ、びっくりした。心臓止まるかと思った」
たまに言う彼女の冗談はツッコミづらい。素なのか、冗談なのかもわからない。彼女の心臓って鼓動を刻んでるのかな。
「受け取るだけだし、行ってくるよ。待ってて」
「お言葉に甘えまーす」
先ほど注文した店は僕らが並んだときよりも、並ぶ人が多くなっていた。出来上がった二つのオムライスを受け取り、僕は彼女が待つテーブルに向かった。
片手で持つには、少々重たく一人で来たことを後悔した。
僕が戻ると、テーブルの上が少し違う。でも、その違和感がなんなのかわからなかった。さっきと同じ席に座る彼女はニコニコしている。
「お水入れてきたよっ」
水か。さっきまでなくて、今あるもの。違和感の正体がわかった僕は、すっきりした。
「ありがとう」
「こちらこそ、とってきてくれてありがとー」
二つのトレーをテーブルに慎重に置き、僕も座った。腕ちょっとプルプルしてるけど、彼女にバレてないかな? 非力だと思われたら、恥ずかしい。実際、非力だけれど。
「いただきまーす」
「いただきます」
一口食べる。
旨い。薄い膜のような玉子だけど、ちゃんと食感があり、ふわふわだった。包まれているチキンライスには刻まれた玉ねぎや人参が入っており、こっちの食感も良かった。ケチャップの酸味は強すぎず程よい。それぞれの部分の味を殺さず、いい塩梅だ。
「んー! 美味しい」
彼女も満足しているようで良かった。
「美味しいね」
「私、実は結構オムライス好きなんだよね」
「初耳」
「これも言ってなかったからね〜」
そう言いながら口に運ぶ彼女は、本当に至福の表情をしていた。こっちも自然と頰が緩む。
「さっきの続きなんですけど、簡単なやつでいいんでマジック見せてくださいねー」
「考えとくよ」
マジック好きの人に見せたら、笑われるレベルかもしれないが、彼女がそれを望むのならやろう。少しは練習期間が欲しいので、数日後になると思うけれど。
オムライスを完食した僕たちは、席を空けるため出ようとしていた。
「あれ? 佐竹か?」
栞の声ではないし、僕は声のした方向を向いた。そこには同じクラスの友達が立っていた。
「なんだ、大井か」
夏休み中に彼女以外と遊んだ唯一の人物だ。僕が一番仲の良いクラスメイトと言える。陽気なやつで、僕とは性格が真反対な気もするけれど、なぜか話が合うので一緒にいる。
「なんだ、ってひでーなー。お前こそ、何してんだよ。ん?」
大井は僕ではなく、僕の前に座る栞の方を見た。
「どうしたの?」
「いや、まさかお前も見えてるのかと思ってな......」
見えてる......? もしかして、栞のことだろうか? 大井も僕と同じで彼女のことが見えるのか?
彼女はとても驚いた表情をしている。どういうことだ。
「見えてる......とは?」
「見えてねえのか? 目の前にいる顔のでかい幽霊が」
「は?」
目の前にいるのはとてもスタイルの良い美少女だ。彼女の方を見ると、「私......顔でかいかな」と言いながら、顔面を手でペタペタ触っている。そんなことないよ、と言いたかったが、大井がいるので口にはできなかった。
「はははっ! 冗談だよ、冗談」
やっぱりそうだよな。彼女のことを認識できるのは、僕だけ。大井に見えるはずがない。彼女はホッと、胸をなで下ろしている。
じゃあ、どうして大井はあんなことを言ったのだろうか?
「なんでそんな冗談を」
「だってお前、誰かと喋ってるみたいだったから。もしかしたら、霊感が強いお前は幽霊と対話できる能力にでも目覚めたのかと思ってな」
見られてたのか......。フードコートは人が多いおかげで、声が届きづらく、一人で喋っているのがバレにくいと思ってたんだけどな。
無関係な人からどんな目で見られようが気にしないが、知り合いだと気まずいな。誤魔化すのも大変だ。
「そんなわけないでしょ」
「じゃあ誰と喋ってたんだよ」
彼女の名前を言うわけにはいかない。でも、いい誤魔化し方が思い浮かばない。
「......彼女」
僕は言った。当然、僕にしか見えない彼女は、驚いている。そして、友達の大井も驚いている。自分でもどうしてそんなことを言ったのかわからない。この状況を回避できる方法が思い浮かばなかったとは言え、最悪の選択をしてしまったのではないだろうか。
もっと考えて、発言するべきだった。後悔しても仕方ない。さっきよりも絶体絶命となった状況を回避する方法を考えなければならない。
「なるほどな......」
大井は言った。なぜ納得したんだ。
「お前、彼女が欲しすぎるあまり、彼女がいると見立てて、デートするとかヤバいな。ヤバすぎて、逆に尊敬するわ」
「いや、そういうわけじゃ......」
まずい。変な勘違いを起こされた。
「気にすんな。見たのが俺で良かったな。お前の名誉はちゃんと守ってやる。男二人の固い約束だ。あ、彼女も聞いてるから、三人の約束だな」
栞は、笑いをこらえるのに必死だった。別に僕にしか見えないから、笑ってもいいのに。大井は「がはははっ」と笑っていた。
「さ、さんきゅー」
「邪魔しちゃ悪いし、俺行くわ。じゃあな!」
そう言うと、大井は笑いながら、フードコートを去った。
まあ、見られたのが大井で良かったと思う。不幸中の幸いと言ったところ。他のそんなに仲がいいわけでもないクラスメイトに見られた場合、影で色々言われるに決まっている。佐竹ってめちゃくちゃ独り言多いらしいよ、とか。大井は悪いやつではない。本当に誰かに言いふらしたりすることはないだろう。
僕は安堵の息をついた。
「お友達?」
「ん、ああ。僕の一番の仲のいいやつかな」
「いいですねぇ。親友って感じがして」
「どうだろう。僕たちは親友って言っていいのかな。出会ったのは高校入ってからだし」
「期間なんて関係ないですよ。見てれば、仲がいいことが伝わってきました」
「なんか恥ずかしいな。ていうか、僕は栞って呼んでるのに、敬語抜けてないんじゃない?」
「誰に対しても敬語だったんで、抜けきらない、の!」
彼女はむぅ、と頰を膨らませた。なんか僕が悪いみたいだ。責められる筋合いはないんだけどな。
僕たちは今度こそトレーを持って立ち上がり、返却口に向かった。トレーを返却した後、フードコートを出た。彼女が見たいものは服ぐらいだったらしく、他に用があるお店はないようだ。適当にぶらつくだけでいい、と彼女は言ったので僕の意向で本屋に行くことにした。