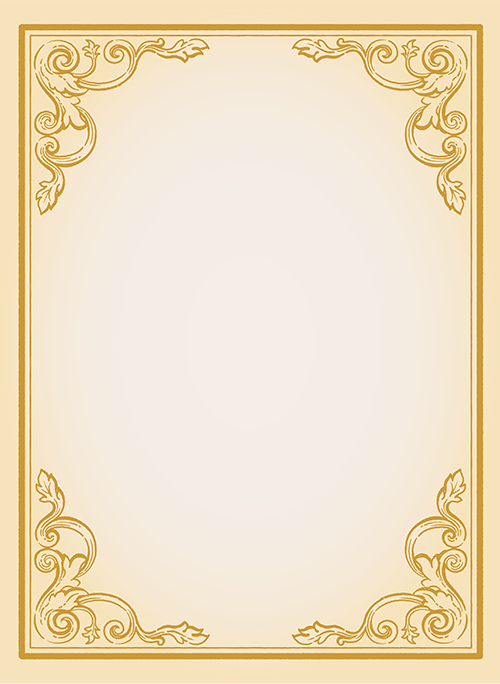僕、佐竹秋太は、夏休みを満喫していた。
長期休暇の素晴らしさを身にしみて感じる。これで宿題が出ていなかったら最高なんだけれど、学生という身分である以上、宿題が出ないはずもなく、その量にうんざりする。
それでもなんとか、今日の分の宿題を終わらせたので、近くの本屋に足を運ぶことにした。
外に出ると、暑さで身体が溶けそうだった。特に今日は快晴ということもあり、日差しも強い。どこまでも真っ青な空が広がっており、インドア派の僕にはしんどい天気だった。
本屋まで徒歩数分。くたくたになりながらも、たどり着くことができた。店の中は冷房がかなり効いていて、寒いくらいだった。きっと服がかなりの量の汗を吸収していることで冷えてしまったのもあるだろう。
僕が真っ先に向かうのは、漫画コーナー。小説は字ばっかりだし、全くと言っていいほど読まない。雑誌なんかも興味がない。
新刊と書かれたポップに目を通し、面白そうな漫画がないか物色する。
異世界に転生する漫画だったり、ラブコメだったり、歴史物だったり、多種多様な漫画たちが積まれている。
今日はなさそうだな。
心から読みたい、と思える漫画はなさそうだ。仕方なく、既刊の漫画で面白そうな物がないか、探していると、綺麗な人が目の前にいることに気がついた。
長い黒髪に、綺麗な目鼻立ちをしていた。肌はとても白く、透明感があった。横顔しか見えていないが、美人であることがよくわかった。年は同じくらいだろうか?
僕には縁のない女性だな。
容姿を自己評価すると、平均と言ったところだろう。中学時代に告白されて付き合ったことはあったので、多分平均くらいの容姿は持ち合わせていると思っている。
目の前にいる彼女は、誰が見ても、上の上。モデル活動をしていると言われても不思議ではない。
そんな人が漫画を読んでいるなんてちょっとした親近感を勝手に抱く。
僕には話しかける勇気なんてないので、彼女の後ろを触れないように、通る。故意ではなくとも、触れてしまい、警察沙汰になったらたまったもんじゃない。ここは紳士的行動をとるべし。
僕は軽く両手を挙げながら、背中合わせになるような状態で、狭い空間を通った。すれ違いにくいので、この本屋はもう少し道幅を広くして欲しい。
彼女の背後を通った直後、後ろを振り返ると、目が合った。目が合ってしまった、と被害的に表現した方がいいかもしれない。この場で目が合うなんて痴漢と思われたのではないか、と不安になる。
彼女は驚いているのか、口を半開きにし、見つめてくる。美人なので、普通ならバカっぽいしぐさでも美しいと感じてしまう。まあ、今はそれどころじゃないんだけど。
確実に僕の方を見ている。後ろの棚の漫画を見ているわけではないだろう。彼女の視線の先には僕がいる。
気をつけて通ったけれど、多少身体が接触した。そのことを咎められたら、僕は負ける。触れた事実は確かに存在するし、こういうのは大抵男が不利になってしまうのだ。冤罪だ、と訴えても、きっと聞き入れてもらえないだろう。
地元の新聞デビューを果たしてしまうのかな。こんな不名誉なことで新聞に載りたくはない。
落ち着いて話せば、きっとわかってくれると思い、僕は謝罪することにした。
「......あの、すみません。僕もわざとじゃないんです。不可抗力というか、なんというか」
触れたことを認めるような発言だが、触れてないことを主張するよりは、正直に言った方が印象は良くなるだろう。実際、背中にほんの少し触れてしまったわけだし。
「え、あ......いや、こちらこそ、なんかすみません」
あれ? どうして僕が謝罪される立場になっているんだ?
彼女が僕を見ていたのは、僕の勘違いだったのか?
沈黙が流れる。夏休みに入ってから、一番居心地の悪い時を過ごしている。数秒が体感では数分に感じられる。
「僕、何かしましたか......?」
僕の勘違いであれば、それでいい。勘違いでなければ、やはり全力で謝罪。土下座をする覚悟はできている。
「何もしてないです! 困らせちゃったみたいで、ごめんなさい!」
彼女は深々と頭を下げた。
そんな立派なお辞儀をされれば、どう対応すべきか困る。今、困らせられている。
本屋で綺麗な女性に謝罪されている状況を見れば、店員さんはどう思うだろうか? とりあえず、この場から離れるべきだと思った。
「一旦、外に出ませんか? 嫌なら、いいんですけど......」
僕に強制力はないので、あくまで提案だ。応じてくれれば、嬉しい。
「そうですね。ここじゃ、話しづらいですよね!」
僕たちは何も買わずに本屋を出た。駐車場の邪魔にならないところで、話を再開することにした。やっぱり暑いな。
「さっき目が合った気がするんだけど、僕の気のせい......かな?」
「いえ、しっかり合ってました!」
よし。ここまでは僕の思い違いではなかったようだ。
「じゃあ、君が僕を見ていたのは、僕が痴漢したから?」
「痴漢したんですか!?」
彼女は少し顔を引きつらせて、言った。
「ごめん。訊き方が悪かった。僕が痴漢したと思ったから、見てたの?」
「違いますよ」
「じゃあ、どうして?」
彼女は言うか言うまいか迷っているように見えた。
「多分、信じてもらえないと思います。私の話」
実は彼女はタレントさんで番組のドッキリ企画に、僕は参加させられているとか? それとも、友達との遊びで見知らぬ人と話をするのが罰ゲームだったり?
「私、死んでるんですよ。この世にいない存在なんです」
想像を遥かに超える話だ。僕が上げたハードルを余裕で飛び越えてきた。
彼女はイタイ子なのかな。
「......という設定なの?」
「違います! 本当です! だから信じてもらえないって前置きしたじゃないですか」
前置きをすれば、いいというものでもない。信じる人がいれば、そいつも頭がちょっとおかしい奴だ。言ってる本人が一番やばいんだけど。
僕の脳は正常に働いているので、そういう判断を下せる。信じたりはしない。
「何か証明できる方法はあるの?」
これがベストな返し方だろう。きっと何もできないはずだ。死んだ人間が見えるなんて、そんな能力僕に備わっていないのだから。僕が知らないうちにそういう能力に目覚めてしまったのかもしれないけれど、その可能性は限りなく低い。
「いいですよ」
予想に反した、返答だ。
彼女はもう一度本屋の方へ歩き始めた。自分で言っといて何だけど、どうやって証明するんだろう? 店員さんに、「私、死んでますよね?」みたいな会話をし始めたら、僕はこの人を関わっちゃいけない人認定をしてしまう。すっごい美人だけど、残念すぎる。
もし彼女がそういった行動をとったら、踵を返し、知らない人のふりをしよう。
冷房の効いた店内。
「生き返るなぁ」
「ブラックジョークはやめてくださいよ」
彼女はムスッとした。
僕の発言をジョークだと捉える人は、世界中探しても自称死人の彼女ぐらいだろう。
トコトコ僕の前を歩き、三十代ぐらいに見える男性の隣に立った。やはり話しかけるのだろうか?
「すみません。私のこと、見えますか?」
数秒が経っても、男性からの返答はなかった。
男性の視線は雑誌から離れることは一切なかった。むしろ、ジロジロ見てる僕の方を見て、嫌そうな顔をされてしまった。
いやいや、そんなはずないだろ。
彼女はドヤ顔で、僕の方を見ている。
また歩き始めて、次はこの近くの私立校の制服を着た女子高生の隣に彼女は立った。
「可愛いですねぇ。憧れちゃいます。良ければ、私と握手でもしてくれませんか?」
確かに可愛らしいとは思うけど、女優に匹敵するレベルの美貌を持つ彼女が言うと、嫌味にしか聞こえなかった。
参考書を見つめる女子高生の視線が、彼女の方へ向くことはなかった。その代わり、こちらへ視線は向けられた。
「何ですか?」
とても不愉快そうな声だ。それはそうだろう。見知らぬ男子高校生から、不思議そうな視線を向けられているのだから。
ここは穏便に、ことを荒げることなく、終えたい。
「僕もそこの参考書が見たくて。あっ、こんな近くで見てたら、集中できないですよね。すみません。離れてます」
そう言って、僕は本屋の出入口に直行した。彼女も後ろをついてきている。
外はカラッとした暑さだ。蒸し暑いよりはマシなのかもしれないけれど、不快指数を高めるのには充分な暑さだった。
「ね? 言った通りでしょ?」
「信じたくないけど、そうなのかもしれないって思えてきた」
まさかあの場にいた僕以外の全員が仕掛け人だったりする? やはり彼女は芸能人で、テレビのドッキリ企画のようなものなのか? 一般人をターゲットにしたやつ。
わかりやすい位置に配置してるとは思えないけれど、パッと見た感じ、カメラのようなものは発見できなかった。
彼女は、本当に死んでいる?
「でも、私もびっくりしたんですよ。私の存在に気づいたのは君だけだったから」
「まだ頭の中がこんがらがってるんだよね。もう少し詳しく話を訊きたいんだけど、ここだと暑さで集中できないし、移動しない?」
「いいですねー」
移動すると言ったって、どこへ向かうべきなんだ?
喫茶店やファミレスは話しやすいし、きっと涼しい。最高の環境であることには違いないんだけど、一つ問題があるとすれば、傍から見れば、僕は独り言を延々と喋り続けるイタイ子に見えてしまう。目の前に彼女がいたとしても、視認できるのはきっと僕だけであるはずだから。信じたくないけれど。
とすれば、他に候補はあるか? 一つ思いついた場所がある。快適に過ごせて、周りを気にする必要のない場所を。
「男の子の部屋って初めて」
僕の家に連れてきてしまった。誘った僕が言うのも何だけど、ホイホイついてきてしまうこの子は大丈夫だろうか?
誰もいない公園で話すのも一つの手ではあったが、暑さを全身で感じることになり、本屋の駐車場と何ら変わらないことに気づいた。なので僕の家にお招きした。
「何その女性アイドルが言いそうなセリフは」
「いや! 本当なんだって!」
彼女ほどの顔面偏差値があれば、世の男子たちが放っておくはずがないだろう。僕が知る男子の中に彼女に釣り合う人物は、誰一人思い当たらないけれど。
「それはどっちでもいいんだけど、会話に敬語が混ざるのはどうしてなの?」
僕も初めは彼女の美しさに目を奪われ、歳は近そうではあったけど自然と敬語になっていた。数分後には彼女はヤバい人であることに気づき、自然と敬語が消滅していた。
「だって、初めて会ったわけですし。年齢は同じくらいかもしれないですけど」
「歳は?」
「十七」
「僕もだ」
近いというか同じだったのか。彼女も僕と同じ高校生のようだ。
彼女の年齢は知ることができた。次は名前か。
「お名前は?」
「柏木栞、です。あなたは?」
「佐竹秋太」
お互いの情報を交換し終えた。ここから僕たちはどういう話を展開すればいいんだろう?
普通なら趣味は何だ? 部活は何をやっているの? そういったことを訊くのかもしれない。けれど、目の前にいるのはおそらく自称ではない僕以外には見えない人。特異すぎるのだ。
彼女は普通に当てはまらない。そういう人に対してはまず何から訊けばいいのだろう。
「えっと、こういう状況になった原因ってわかってるの?」
「まあ、よくある生前の未練を解消するやつですよ」
「よくあるってどこの世界線の話だよ......」
確かに漫画とか映画とか、そういった類の中では見たことはあるけれども、現実ではありえない話だ。
「フィクションの世界ですねー。実際に起こったので、ノンフィクションになっちゃいました」
彼女はおどけて言う。
彼女をどの角度から見ても、一度は死んだ人間だとは思えない。けれど、徐々にこの非現実的な状況を受け入れ始めてるのは、なぜだろう。彼女の陽気な性格がそうさせているのかもしれない。
僕の部屋のベッドの上に彼女は座っている。足をパタパタさせている。ちゃんと足もあるな......。
「柏木さんは生前の未練を解消したら、消えるわけ?」
「解消したら、というか、期限が来たら消えますね」
「そうなんだ。いつまで?」
「八月の終わりまでなんで、一ヶ月ですね」
今日は八月一日だ。九月になれば彼女の存在は消えてしまうのだろうか。
「たった一ヶ月?」
「ええ」
未練とやらの内容を知らないので一ヶ月という期間が充分なのかはわからなけど、決して長いことはないだろう。そんな簡単に未練を解消できるとは思えない。
でも僕が今死んで彼女のような状態になれば、何を未練とするのだろう。パッと思いつかないな。死にきれないほどの強いものでないと、彼女のようにはならないだろうし、僕が死んでも起こらない気がする。
「未練を訊いてもいいかな?」
「もちろん。秋太くんしか聞いてくれる人いないですしね」
いきなり名前で呼ばれ、ドキッとしてしまう。そこまで僕たちの仲は親密じゃないぞ。
「未練は何?」
「私の未練は、恋人を作る! です」
「つまり、彼氏が欲しいと?」
「そういうことです。ただ恋人を作るだけじゃなくて、ちゃんとデートとかしたいですね」
「今から失礼なこと言うね。生前の彼氏じゃ、遊び足りなかったということ?」
やはり彼女が男子の部屋に入ったことがないというのはにわかに信じがたい。
「今日はじめましての人に言うセリフじゃないよね?」
「だから前置きしたじゃないか。失礼なこと言うって」
「前置きしたら許されるわけじゃないからね?」
なんかさっきもこういう会話をした気がするな。その時は立場が逆だった気がするけど。
「でも恋人を作りたいってそういうことじゃないの?」
「違います! 一度もお付き合いした方がいなかったんです。だから最後の一ヶ月ぐらい彼氏が欲しいじゃないですか。やっぱり憧れるじゃないですか!」
一度も付き合ったことがない......だと? 彼女はまだその設定を通すつもりなのか? それとも本当に交際経験がゼロなのか?
容姿は抜群。性格も今のところ問題なさそうだ。初めはイタイ子なのかと思ったけど、どうやら本当に僕以外の人には見えていないらしいし。
あれ? 彼女の未練を解消してあげられるヒーローはどこにいるんだ?
「これからどうするの? 素敵な男性探しの旅にでも出るの?」
「ん? いるじゃないですか、ここに」
僕が見えていないだけで、もしかしてこの部屋に彼女に釣り合う男がいるのか?
僕がキョロキョロ部屋の隅々まで目線を飛ばしていると、彼女は口を開いた。
「ここですよ、ここ」
指差して、誰のことかわかりやすいように言った。
どうやら、僕のことらしい。
「僕?」
人差し指がこちらへ向いているので、わかってはいるけれど、一応訊いておいた。
「はい」
「どうして僕が?」
「だって他に私のこと見える人いないじゃないですか」
当然でしょ? というような口ぶりで彼女は言った。
確かに今のところ僕以外に彼女を認識できる人はいない。僕を選ぶ真っ当な理由だ。
「僕を選ぶ理由はわかった。わかったけど、僕が君を手助けする義理はないよね」
「まあ、そうですね。義理はないですけど、運命は感じてるんですよ」
「僕しか見えないからでしょ?」
「まあ、そうですね。でもでも、これを運命と呼ばずにはいられないでしょ?」
運命的なものを感じないと言えば、嘘になる。僕にしか見えてないなんて、何かあるんじゃないか、と考えるのが普通だ。残念ながら生前の彼女に見覚えはないし、関わった記憶もない。
絶対に見覚えがない、と自信を持っては言えない。もしかしたら、どこかで会ったことがあったのかもしれない。まさに本屋なんかで。けれど、彼女ほどの美貌を前に、僕の記憶から彼女の存在が完全に消滅しているのは、少し不思議だ。
おそらく出会っていなかったのだろう。会っていても、何年も前。彼女の美しさが未完成の状態。幼稚園とかそのくらいの年代。その頃なら覚えていないのは当然だし、それぐらいのことを接点とするなら、僕である必要は全くない。
僕はどういう基準で選ばれたのだろう。
「これが運命......なのかな」
「そうですよ! ぜひ! 私の彼氏に!」
ここまで彼氏になって欲しいとせがまれることは一生ないだろう。しかも、相手がとびきりの美人。来世にも訪れないような気がする。
「わかったよ。一ヶ月だよな」
「はい! よろしくお願いします。秋太くん」
「ああ。よろしく。柏木さん」
高校二年生の夏。僕に彼女ができた。彼女を見れば、誰もが羨むだろう。しかし、僕にしか見えていないのは残念だ。
どうして初めて会った彼女の願いを助けることになったのだろうか。拒否することもできたはずだ。そうしなかったのは、僕がお人好しだからだろうか? 自分ではわからない。
僕自身、夏休みを適当に過ごしているだけだったので、暇つぶしと思えば悪くない。それに、僕にしか見えていないけれど、かなり美人だ。こんなに綺麗な人と夏休みを過ごせると思えば、全く悪い気はしない。
昨日は、彼女となった柏木栞と僕の家で少し喋っただけだ。その後、彼女は帰ってしまった。訊いていなかったけれど、家はあるのだろうか? どこで生活するのだろう?
まだまだ彼女について知らないことが多すぎる。少しずつ、彼女のことを知っていく必要があるな。一応、僕の彼女となったわけだし。
「秋太くん、こんにちは」
「こんにちは。柏木さん」
彼女は昨日、「明日の一時頃にまた来ますね」と言って、帰った。時間通りに彼女は僕の家を訪れた。
「今日は秋太くんと色んなルールなどの諸々の話をしたいと思います」
「ルール?」
「はい。玄関で話すのも何ですし、お散歩しながら話しませんか?」
「構わないよ」
僕はすぐに外に出かけられる格好に着替えた。彼女は昨日と違う真っ白のブラウスを着ていた。
「お待たせ。じゃあ、行こうか」
「行きましょう。あっ、秋太くん、秋太くん」
「な、なに?」
そんな楽しそうな顔をしながら、いきなり名前を連呼されると、ドキッとする。柏木栞とはこういう人物なのだろう。慣れていかないと......。
「すっ」
彼女は小さな掛け声と共に、玄関の扉をすり抜けていった。
鏡を見ていないけれど、僕はひどく間抜け面をしていると思う。目の前で超常現象を見せられては、誰もが口を半開きにし、声を発することもできず、ただ呆然と眺めることしかできないと思う。
「どうでした?」
次はちゃんと扉を開き、彼女は戻ってきた。
「すごい」
「それだけですか?」
「人間って本当にすごいものを見ると、言葉が出ないんだよ」
僕がそう言うと、彼女は微笑んだ。
僕はそんな能力使えないので、普通に扉を開き、外へ出た。天気は今日も快晴。安定に暑い。どうして、こんなに夏は暑いんだ。夏だからか。
この暑さの中当てもなく歩くというのは、愚行に違いない。僕の部屋で話した方が良かったのではないだろうか。僕は選択を誤ってしまった。
隣の彼女を見ると、清々しい表情で歩を進めている。
「暑くないの?」
「暑いですよ?」
「じゃあ、どうしてそんなに元気そうなの?」
「どうして? そうですねー。生きてるーって感じがするからじゃないですかね。暑いとか寒いとか、そういう肌でしっかり感じられるのって生きてる証みたいな気がして、なんだか嬉しいんですよね」
僕には到底分かり得ない理由だった。死んだ彼女だからこその暑さに対する感じ方だ。普通の人ならば、この暑さをプラスに捉える人はまずいないだろう。喜ぶのは極寒の地に住んでいるような人たちだけじゃないのか。
不思議な気分だ。こうして普通に会話しているのに、彼女は生きていないだなんて。
「公園がありますねー」
彼女は僕の家から歩いて数分の公園を見つけて、はしゃいでいる。
「せっかくだし、入る?」
「はい!」
小学生だと思われる子どもたちが数人遊んでいた。広場でサッカーをする子やブランコに乗る子も。
僕の狙いとしては、屋根がついているベンチに座って日陰で休もうという作戦だ。僕は暑さを不快に感じるので、これ以上歩き続ければ、熱中症になってもおかしくない。飲み物持って来れば良かったかも。
「飲み物買ってくるけど、何か飲む?」
「優しいですね。お茶をお願いします」
「了解」
彼女にはベンチで座って待ってもらい、公園の外にある自販機まで歩いて行った。そこまで大きな公園ではないので、すぐそこだ。
彼女の分の麦茶と自分の分のスポーツドリンクを買い、彼女の元へ戻った。
ベンチで足をパタパタさせながら、空を見つめていた。風に吹かれるその様は、絵になった。彼女の存在を認識できれば、きっと注目を集めていたはずだ。小学生たちにも彼女の美しさくらい理解できるはずだ。
「どうぞ」
「ありがとうございます。いくらでした?」
「これぐらいいいよ。それにお金持ってるの?」
「持ってないですね」
彼女は申し訳なさそうに笑った。
水分、塩分がチャージされ、少し生き返った。
「さっき言ってたルールって?」
「まずはそれについて話さないといけませんね。私ってもう死んでるんですよ」
柏木さんの存在が誰からも認識されなかったり、金属の扉をすり抜けたりするのを見ると、彼女がこの世にいない人なんだと、少しずつ受け入れ始めた。
「死後、案内人さんみたいな人に連れて行かれて、色々説明を受けたんですよ。こうしてまたこの世界で未練を晴らす上での注意点みたいなものを」
「その話を信じてしまうようになってしまった僕の頭は正常だよね?」
「ふふっ。正常ですよ。三つ決まりごとみたいなのがありました。一つ目は期限です。これは最初に話したやつですね。八月三十一日を超えれば、私はいなくなります」
まだ三週間以上もあるけれど、あっという間に過ぎるんだろうな。九月になれば彼女がいなくなることに、まだまだ実感は湧かない。
一ヶ月後の僕は彼女がいなくなることに悲しがることはできるのだろうか。彼女の存在を認めることができる唯一の人間として、悲しがれたらいいな、と思う。
「二つ目は?」
「私の存在は、他の誰にも言ってはいけません。秋太くん以外に知られてはいけないっていうことです」
「僕が誰かに言ったら、柏木さんはどうなるの?」
「消えるらしいです。一ヶ月を待たずして、消えます」
彼女が誰かに伝えることはできないので、僕にかかっている。怪しまれないように、行動しないといけないな。
「まあ、このルールはあんまり気にしなくてもいいですよ」
「どうして?」
「だって私のことを見えない人が私がここにいると信じるはずないじゃないですか」
「おっしゃる通りで」
僕が必死に彼女の存在を誰かに認めさせようとした日には、精神科に連れて行かれることだろう。
「じゃあ、最後は?」
「最後は......言わないでおきます。言ったら、多分私のお手伝いをしたくなくなると思うので」
「わかった」
「気にならないんですか? 最後のルール」
彼女は小首を傾げて、言った。
「気にはなるけど、強制力はないからね。言いたくなったら、言えばいいよ」
「私のお願いを快く引き受けてくださるし、あなたが神様に見えてきました」
快く、というのが少々引っかかるが、結局引き受けてしまったあたり、お人好しなのかもしれない。
「僕が神様なら、恨んだ方がいいよ。君は若くして死ぬことになってしまったんだから」
「確かにそうですね。あなたを恨んでおきます」
そう言って、彼女は微笑んだ。
風が吹くと気持ちがいい。少々風が強いようで、公園の木々が唸っている。強い風に吹かれても、木は根強く生えているため、倒れることはない。見た目通りの強さだ。
隣の彼女は、発言などは平気そうに振舞っているが、実際のところ内心どう感じているのかわからない。死という経験をしたのは、彼女以外にいないので気持ちをわかってあげられない。彼女の苦しみを共感できるなんておこがましいこと言えない。彼女にしかわからない苦しみがもしあるのなら、少しでも緩和させてあげられればいいな、と思う。
僕たちが座るベンチの方に、サッカーボールが転がってきた。ボールは僕の足で止まったので、取ってあげた。
「はい」
「ありがとう、お兄ちゃん。さっきから誰と話してたの?」
小学校低学年ぐらいの男の子だ。サッカーに夢中で、こちらなど見ていないものだと思っていたが、見当違いだったようだ。隣に彼女はいるけれど、それを言うわけにいかない。僕も頭のおかしい奴だと思われるし、彼女も消えてしまう。本当のことは言えないのだ。
「考え事してただけだよ。独り言を言っちゃう癖があるんだ」
「へー。変なのー」
結局変な人扱いをされてしまった。これから関わることのないであろう子どもなので、別にこの子にどう思われようが構わない。
ボールを受け取った小学生は、友達のいるところへかけて行った。
「ふふっ。独り言を言う癖があるんですね」
「君を庇って言ったのに、酷くないか?」
「ごめんなさい。でも、もう少しマシな嘘があったんじゃないかなーって思いまして」
この暑さであまり考え事をしたくなかったので、パッと思いついた嘘を言ったが、否定されてしまった。次に備えて、家でいくつか返答のレパートリーを考えておこう。
「僕から一つ文句があるんだけど、言っていい?」
「何でしょう?」
「黙っておくなら、最初からルールは二つって言って欲しかった。三つあることを知ったら、気になる」
「その話はもう終わったものだと思ってました。それについては、本当にすみません」
彼女はペコリと頭を下げた。ちゃんと謝られると、調子が狂ってしまう。
「まあ、そんなに気にしないから、大丈夫。頭上げて」
「気になるのか、気にならないのか、どっちなんですか?」
彼女はまた笑いながら、言った。
「どちらかが本音で、どちらかが建前だね。別に当てなくていいからね」
「すぐにわかっちゃいますけど、優しさに甘えて、これ以上は言わないでおきます」
僕たちは公園を出ることにした。散歩を再開した。
「気になったんだけど、僕の家の扉をすり抜けることができたよね?」
「はい」
「じゃあ、さっきベンチに座ってたけど、あれって空気椅子だったの? すり抜けたりしてなかったけど」
座っているフリをしていたのなら、彼女の筋力はとてつもないことになる。僕なんて一瞬でノックアウトされてしまうのではないだろうか。
「ちゃんと座ってましたよ。私の意識次第何ですよね。ほら、触れます」
そう言って、彼女は僕の腕に触れた。ちょっとしたスキンシップなのに、また動揺してしまう。
「便利な能力だね」
「そうですね。結構便利です。ほいっ」
可愛らしい掛け声と共に、僕の左腕に触れていた彼女の右手は、僕の胴体、右腕を通過していった。
何かが通り抜けた感覚はないけれど、何か気持ち悪さが残った。
「変な気分だ」
「これからはちゃんと触れますね」
「歩きましたねー」
「元気すぎて、怖いんだけど......」
「だらしないですね。一時間ちょっと歩いただけじゃないですか」
真夏に一時間以上歩けば、疲れるに決まっている。柏木さんのスタミナは無限なのか? 平気な顔をしている。もしかして、疲れない身体になっているのか? そのことを安易に訊くのは躊躇われた。
やはり彼女と僕とでは住んでいる世界が違う。同じ地球上に立ち、同じ空気を吸っているけれど、決定的に違う部分がある。
僕が少し悩んでいると、彼女がこちらを凝視してきた。
「もしかして、疲れたりしないのか、とか思ってますか?」
「どうしてわかったの? それも能力?」
「違いますよ。そこまで便利な能力は持ってないです。何となく、そう感じただけです。ちょっと躊躇してるようだったので」
僕はそんなに顔に出やすいタイプだったのかな。自覚はなかったけれど、バレていたのでそういうことだろう。
「ちょっと言いづらかったからさ」
「気にしなくていいのに、です。私たちの今の関係は何ですか?」
「恋人」
「そうです。気軽に話して欲しいです。私をあそこで歩いている女の子と同じように、普通に接して欲しいです」
彼女は僕たちの正面の方から歩いてくる女子高生ぐらいの子を指差して、言った。
「悪かった。変な気を遣って」
「構いませんよ。さっきの質問ですけど、疲れますよ。疲れるのって生きてる証拠じゃないですか。だから嬉しいんですよ」
「そっか」
僕たちはその後も喋りながら歩いた。ペースは落として、ゆっくり。
日も暮れてきた。途中本屋で涼んだりしたが、合計するとかなり歩いた気がする。夏休みに入ってから昨日までの歩いた距離と今日一日の歩いた距離を比べれば、今日の方が多くなるのではないか、と思うくらい歩いた。おかげで足がパンパンだ。明日は筋肉痛だろうな。
彼女もさすがに疲れたのか、休憩を入れる頻度が後半多くなっていた。
「そろそろ帰ろうか」
「そうですね。楽しかったです」
「僕も楽しかったよ。ところで、柏木さんは帰る場所ってあるの?」
「私の能力があれば、人の家に勝手に入り込めちゃうんですよね。なので、使われてないベッドとかがあるお部屋を見つけて、そこで寝てます」
不法侵入だろ、とは言えなかった。死人に適応される刑罰はないだろうし。
「そうなんだ。なら、良かった。また明日」
「はい。私から言わなくても、明日も会ってくれるんですね。やっぱり、優しいです」
彼女は嬉しそうにした。僕も思いの外楽しかったし、一ヶ月間彼女に付き合うことにした。やるからにはしっかりやり遂げたいと思った。
「じゃあ」
「さようなら」
彼女は僕の家とは逆方向に歩いて行った。後ろ姿を眺めていたが、すぐに見えなくなった。
僕には明日も会ってあげる優しさはあっても、家に来てもいいと言ってあげられる優しさはまだなかった。
「今日はラーメンが食べたいです」
「そんなものでいいの?」
僕は決してラーメンをバカにしているわけではない。ラーメンは大好きだ。大好きだけれど、あと一ヶ月もないこの世での生活にラーメンを選択するのは意外だったのだ。それに彼女なら無銭飲食で捕まることはないし、誰かが頼んだラーメンを横取りしても咎められることはないだろう。
「私、ラーメン食べたことないんですよ。だから行ってみたいです!」
ラーメンを食べたことがないだと......? めったに食べないという人はいても、一度も食べたことがないという人に会ったのは初めてだった。もしかすると、生前の彼女の家族は、ラーメンを毛嫌いする一家だったのかもしれない。
彼女には驚かされてばっかりだ。
僕基準でこの辺りで一番美味しいと思える店に連れて行ってあげたい。
「わかった。ちょっと歩くけど、大丈夫?」
「余裕です!」
今日は僕と柏木栞が出会ってから、五日目だ。毎日一時から二時の間ぐらいに彼女は僕の家にやってきて、二人で何かしている。昨日は僕たちが出会った本屋でお互いの好きな漫画をプレゼンをしあったりした。おかげで僕は独り言を言い続ける、ヤバイ奴認定されたのかあまり人は近づいてこなかった。
初めて出会った彼女をどうして僕は、こんなに助けたいと思ったのだろう。物珍しさ、好奇心みたいなものも多少はあった。普通に生活していれば、絶対に体験することができない体験をさせてもらっている。壁をすり抜ける能力とか、フィクションの世界だけだと思っていた。
当然、同情心もある。彼女からしても、今まで関わりのなかった男から同情されても迷惑かもしれないが、僕と同い年ですでに生を断たれた彼女に同情する気持ちが芽生えないはずがなかった。
しかし、それだけではないような気がする。一目惚れとかそういうものじゃない。でもそれが何かはっきりしないままだ。
「ねえねえ、私、良いこと考えたんですよ」
「ろくなことじゃなさそうだけど、一応聞く」
「失礼ですね。秋太くんはこうして私とお話してくれてるじゃないですか」
「うん」
「でも、すっごい視線を集めてるじゃないですか」
「そうだね」
周りから見れば、そこそこ大きな声で独り言を喋ってる人なので、当然痛い視線を向けられる。
「スマホ持ってますか?」
「持ってるけど」
そう言って、僕はポケットに入っていたスマホを取り出した。
「常に誰かと電話してる風に見せかけるってのはどうでしょう」
確かに彼女の考えた作戦なら、一人で喋り続けても不審がられないだろう。
「いい作戦だと思う。でも、僕はこのままでいいよ。僕と無関係な人からどんな目を向けられても、どうってことないし」
出会った初日と違い、そんな風に考えるようになっていた。これから先、おそらく関わることのない人たちからどう思われようが、別に気にすることではない。同じ高校のやつに見られたら、ちょっと気まずいけれど。
「私はいい彼氏を持ったなー」
そう言って、彼女は歩くスピードを速めて、僕の前へ出た。
数十分歩いて、僕がよく行くラーメン屋に着いた。入る前からスープの香りが鼻腔をくすぐる。ピーク時は過ぎているので、並ぶことなく入店することができた。
僕たちはカウンター席に座った。再奥の壁に近いところ。
「どれにする?」
「色々種類あるんですね」
「そうだね。王道なのはしょうゆとかとんこつじゃないかな」
「秋太くんはどれに?」
「僕はしおラーメンかな。ここのしおラーメンの味は僕が保証する。あっさりしてて、食べやすいと思う」
彼女は今一度、メニューに目をさらっと通した後、閉じた。
「私も同じのにします」
僕はしおラーメンを二杯注文した。店員から少し不思議そうな顔をされた。僕みたいなひょろっとしたのが二杯食べると思われているのだから、当然だろう。
数分後に、ラーメンがやってきた。僕の前に二杯とも置かれた。
「ちょっと気になったんだけど、柏木さんの姿は誰にも見えない。じゃあ、柏木さんが食べたラーメンはどう見えるのかな? いきなり空の容器が現れたりするのかな」
「うーん。そこのところは私もあんまりわかんないですよね。周りの人から不思議な目をされたりはしないので、そういうわけではないんじゃないですかね? きっと全てが最後に上手く調整されるんでしょうね」
「調整?」
「はい。ちょっと難しいんですけど、このラーメンって本当は作られることがなかったラーメンじゃないですか。私が頼まなかったら、食べられることはなかったわけですから。私は死んだ人間なので、この世にいてはいけない存在なんです。きっと一ヶ月後に帳尻が合わせられるんじゃないかと。私がこの一ヶ月消費したものなんかが、消費されなかったものとして復活する、みたいなことを言ってました」
「柏木さんが本屋で一冊本を盗んだとする。在庫から一冊、本が消えるわけだから、普通本屋は損するはず。でも、一ヶ月後には盗まれたことなんてなかったことになると」
「そんな感じですね。いいたとえじゃなかったですけど」
深く考えずに言ったけれど、彼女を盗人としてたとえてしまった。これも罰せられることは絶対にないことだけど。
「気分を悪くしたようなら、ごめん」
「これくらいじゃ、何とも思いませんよ。秋太くんが私に使ったお金も一ヶ月後復活しますよ」
この一ヶ月で使用したお金が戻ってくるなんて、喜ばしいことのはずだ。今日払う予定のラーメン代、数日前に自販機で買った麦茶代なんかも一ヶ月後戻ってくる。そして、僕と彼女が一緒にいた記憶だけが残る。悪くない、悪くないはずなのに、少し寂しさを感じ、上手く笑うことができなかった。まだ出会って五日だというのに、毎日会っているせいもあり、ずっと前から知り合いだったような、そんな感じがした。
長期休暇の素晴らしさを身にしみて感じる。これで宿題が出ていなかったら最高なんだけれど、学生という身分である以上、宿題が出ないはずもなく、その量にうんざりする。
それでもなんとか、今日の分の宿題を終わらせたので、近くの本屋に足を運ぶことにした。
外に出ると、暑さで身体が溶けそうだった。特に今日は快晴ということもあり、日差しも強い。どこまでも真っ青な空が広がっており、インドア派の僕にはしんどい天気だった。
本屋まで徒歩数分。くたくたになりながらも、たどり着くことができた。店の中は冷房がかなり効いていて、寒いくらいだった。きっと服がかなりの量の汗を吸収していることで冷えてしまったのもあるだろう。
僕が真っ先に向かうのは、漫画コーナー。小説は字ばっかりだし、全くと言っていいほど読まない。雑誌なんかも興味がない。
新刊と書かれたポップに目を通し、面白そうな漫画がないか物色する。
異世界に転生する漫画だったり、ラブコメだったり、歴史物だったり、多種多様な漫画たちが積まれている。
今日はなさそうだな。
心から読みたい、と思える漫画はなさそうだ。仕方なく、既刊の漫画で面白そうな物がないか、探していると、綺麗な人が目の前にいることに気がついた。
長い黒髪に、綺麗な目鼻立ちをしていた。肌はとても白く、透明感があった。横顔しか見えていないが、美人であることがよくわかった。年は同じくらいだろうか?
僕には縁のない女性だな。
容姿を自己評価すると、平均と言ったところだろう。中学時代に告白されて付き合ったことはあったので、多分平均くらいの容姿は持ち合わせていると思っている。
目の前にいる彼女は、誰が見ても、上の上。モデル活動をしていると言われても不思議ではない。
そんな人が漫画を読んでいるなんてちょっとした親近感を勝手に抱く。
僕には話しかける勇気なんてないので、彼女の後ろを触れないように、通る。故意ではなくとも、触れてしまい、警察沙汰になったらたまったもんじゃない。ここは紳士的行動をとるべし。
僕は軽く両手を挙げながら、背中合わせになるような状態で、狭い空間を通った。すれ違いにくいので、この本屋はもう少し道幅を広くして欲しい。
彼女の背後を通った直後、後ろを振り返ると、目が合った。目が合ってしまった、と被害的に表現した方がいいかもしれない。この場で目が合うなんて痴漢と思われたのではないか、と不安になる。
彼女は驚いているのか、口を半開きにし、見つめてくる。美人なので、普通ならバカっぽいしぐさでも美しいと感じてしまう。まあ、今はそれどころじゃないんだけど。
確実に僕の方を見ている。後ろの棚の漫画を見ているわけではないだろう。彼女の視線の先には僕がいる。
気をつけて通ったけれど、多少身体が接触した。そのことを咎められたら、僕は負ける。触れた事実は確かに存在するし、こういうのは大抵男が不利になってしまうのだ。冤罪だ、と訴えても、きっと聞き入れてもらえないだろう。
地元の新聞デビューを果たしてしまうのかな。こんな不名誉なことで新聞に載りたくはない。
落ち着いて話せば、きっとわかってくれると思い、僕は謝罪することにした。
「......あの、すみません。僕もわざとじゃないんです。不可抗力というか、なんというか」
触れたことを認めるような発言だが、触れてないことを主張するよりは、正直に言った方が印象は良くなるだろう。実際、背中にほんの少し触れてしまったわけだし。
「え、あ......いや、こちらこそ、なんかすみません」
あれ? どうして僕が謝罪される立場になっているんだ?
彼女が僕を見ていたのは、僕の勘違いだったのか?
沈黙が流れる。夏休みに入ってから、一番居心地の悪い時を過ごしている。数秒が体感では数分に感じられる。
「僕、何かしましたか......?」
僕の勘違いであれば、それでいい。勘違いでなければ、やはり全力で謝罪。土下座をする覚悟はできている。
「何もしてないです! 困らせちゃったみたいで、ごめんなさい!」
彼女は深々と頭を下げた。
そんな立派なお辞儀をされれば、どう対応すべきか困る。今、困らせられている。
本屋で綺麗な女性に謝罪されている状況を見れば、店員さんはどう思うだろうか? とりあえず、この場から離れるべきだと思った。
「一旦、外に出ませんか? 嫌なら、いいんですけど......」
僕に強制力はないので、あくまで提案だ。応じてくれれば、嬉しい。
「そうですね。ここじゃ、話しづらいですよね!」
僕たちは何も買わずに本屋を出た。駐車場の邪魔にならないところで、話を再開することにした。やっぱり暑いな。
「さっき目が合った気がするんだけど、僕の気のせい......かな?」
「いえ、しっかり合ってました!」
よし。ここまでは僕の思い違いではなかったようだ。
「じゃあ、君が僕を見ていたのは、僕が痴漢したから?」
「痴漢したんですか!?」
彼女は少し顔を引きつらせて、言った。
「ごめん。訊き方が悪かった。僕が痴漢したと思ったから、見てたの?」
「違いますよ」
「じゃあ、どうして?」
彼女は言うか言うまいか迷っているように見えた。
「多分、信じてもらえないと思います。私の話」
実は彼女はタレントさんで番組のドッキリ企画に、僕は参加させられているとか? それとも、友達との遊びで見知らぬ人と話をするのが罰ゲームだったり?
「私、死んでるんですよ。この世にいない存在なんです」
想像を遥かに超える話だ。僕が上げたハードルを余裕で飛び越えてきた。
彼女はイタイ子なのかな。
「......という設定なの?」
「違います! 本当です! だから信じてもらえないって前置きしたじゃないですか」
前置きをすれば、いいというものでもない。信じる人がいれば、そいつも頭がちょっとおかしい奴だ。言ってる本人が一番やばいんだけど。
僕の脳は正常に働いているので、そういう判断を下せる。信じたりはしない。
「何か証明できる方法はあるの?」
これがベストな返し方だろう。きっと何もできないはずだ。死んだ人間が見えるなんて、そんな能力僕に備わっていないのだから。僕が知らないうちにそういう能力に目覚めてしまったのかもしれないけれど、その可能性は限りなく低い。
「いいですよ」
予想に反した、返答だ。
彼女はもう一度本屋の方へ歩き始めた。自分で言っといて何だけど、どうやって証明するんだろう? 店員さんに、「私、死んでますよね?」みたいな会話をし始めたら、僕はこの人を関わっちゃいけない人認定をしてしまう。すっごい美人だけど、残念すぎる。
もし彼女がそういった行動をとったら、踵を返し、知らない人のふりをしよう。
冷房の効いた店内。
「生き返るなぁ」
「ブラックジョークはやめてくださいよ」
彼女はムスッとした。
僕の発言をジョークだと捉える人は、世界中探しても自称死人の彼女ぐらいだろう。
トコトコ僕の前を歩き、三十代ぐらいに見える男性の隣に立った。やはり話しかけるのだろうか?
「すみません。私のこと、見えますか?」
数秒が経っても、男性からの返答はなかった。
男性の視線は雑誌から離れることは一切なかった。むしろ、ジロジロ見てる僕の方を見て、嫌そうな顔をされてしまった。
いやいや、そんなはずないだろ。
彼女はドヤ顔で、僕の方を見ている。
また歩き始めて、次はこの近くの私立校の制服を着た女子高生の隣に彼女は立った。
「可愛いですねぇ。憧れちゃいます。良ければ、私と握手でもしてくれませんか?」
確かに可愛らしいとは思うけど、女優に匹敵するレベルの美貌を持つ彼女が言うと、嫌味にしか聞こえなかった。
参考書を見つめる女子高生の視線が、彼女の方へ向くことはなかった。その代わり、こちらへ視線は向けられた。
「何ですか?」
とても不愉快そうな声だ。それはそうだろう。見知らぬ男子高校生から、不思議そうな視線を向けられているのだから。
ここは穏便に、ことを荒げることなく、終えたい。
「僕もそこの参考書が見たくて。あっ、こんな近くで見てたら、集中できないですよね。すみません。離れてます」
そう言って、僕は本屋の出入口に直行した。彼女も後ろをついてきている。
外はカラッとした暑さだ。蒸し暑いよりはマシなのかもしれないけれど、不快指数を高めるのには充分な暑さだった。
「ね? 言った通りでしょ?」
「信じたくないけど、そうなのかもしれないって思えてきた」
まさかあの場にいた僕以外の全員が仕掛け人だったりする? やはり彼女は芸能人で、テレビのドッキリ企画のようなものなのか? 一般人をターゲットにしたやつ。
わかりやすい位置に配置してるとは思えないけれど、パッと見た感じ、カメラのようなものは発見できなかった。
彼女は、本当に死んでいる?
「でも、私もびっくりしたんですよ。私の存在に気づいたのは君だけだったから」
「まだ頭の中がこんがらがってるんだよね。もう少し詳しく話を訊きたいんだけど、ここだと暑さで集中できないし、移動しない?」
「いいですねー」
移動すると言ったって、どこへ向かうべきなんだ?
喫茶店やファミレスは話しやすいし、きっと涼しい。最高の環境であることには違いないんだけど、一つ問題があるとすれば、傍から見れば、僕は独り言を延々と喋り続けるイタイ子に見えてしまう。目の前に彼女がいたとしても、視認できるのはきっと僕だけであるはずだから。信じたくないけれど。
とすれば、他に候補はあるか? 一つ思いついた場所がある。快適に過ごせて、周りを気にする必要のない場所を。
「男の子の部屋って初めて」
僕の家に連れてきてしまった。誘った僕が言うのも何だけど、ホイホイついてきてしまうこの子は大丈夫だろうか?
誰もいない公園で話すのも一つの手ではあったが、暑さを全身で感じることになり、本屋の駐車場と何ら変わらないことに気づいた。なので僕の家にお招きした。
「何その女性アイドルが言いそうなセリフは」
「いや! 本当なんだって!」
彼女ほどの顔面偏差値があれば、世の男子たちが放っておくはずがないだろう。僕が知る男子の中に彼女に釣り合う人物は、誰一人思い当たらないけれど。
「それはどっちでもいいんだけど、会話に敬語が混ざるのはどうしてなの?」
僕も初めは彼女の美しさに目を奪われ、歳は近そうではあったけど自然と敬語になっていた。数分後には彼女はヤバい人であることに気づき、自然と敬語が消滅していた。
「だって、初めて会ったわけですし。年齢は同じくらいかもしれないですけど」
「歳は?」
「十七」
「僕もだ」
近いというか同じだったのか。彼女も僕と同じ高校生のようだ。
彼女の年齢は知ることができた。次は名前か。
「お名前は?」
「柏木栞、です。あなたは?」
「佐竹秋太」
お互いの情報を交換し終えた。ここから僕たちはどういう話を展開すればいいんだろう?
普通なら趣味は何だ? 部活は何をやっているの? そういったことを訊くのかもしれない。けれど、目の前にいるのはおそらく自称ではない僕以外には見えない人。特異すぎるのだ。
彼女は普通に当てはまらない。そういう人に対してはまず何から訊けばいいのだろう。
「えっと、こういう状況になった原因ってわかってるの?」
「まあ、よくある生前の未練を解消するやつですよ」
「よくあるってどこの世界線の話だよ......」
確かに漫画とか映画とか、そういった類の中では見たことはあるけれども、現実ではありえない話だ。
「フィクションの世界ですねー。実際に起こったので、ノンフィクションになっちゃいました」
彼女はおどけて言う。
彼女をどの角度から見ても、一度は死んだ人間だとは思えない。けれど、徐々にこの非現実的な状況を受け入れ始めてるのは、なぜだろう。彼女の陽気な性格がそうさせているのかもしれない。
僕の部屋のベッドの上に彼女は座っている。足をパタパタさせている。ちゃんと足もあるな......。
「柏木さんは生前の未練を解消したら、消えるわけ?」
「解消したら、というか、期限が来たら消えますね」
「そうなんだ。いつまで?」
「八月の終わりまでなんで、一ヶ月ですね」
今日は八月一日だ。九月になれば彼女の存在は消えてしまうのだろうか。
「たった一ヶ月?」
「ええ」
未練とやらの内容を知らないので一ヶ月という期間が充分なのかはわからなけど、決して長いことはないだろう。そんな簡単に未練を解消できるとは思えない。
でも僕が今死んで彼女のような状態になれば、何を未練とするのだろう。パッと思いつかないな。死にきれないほどの強いものでないと、彼女のようにはならないだろうし、僕が死んでも起こらない気がする。
「未練を訊いてもいいかな?」
「もちろん。秋太くんしか聞いてくれる人いないですしね」
いきなり名前で呼ばれ、ドキッとしてしまう。そこまで僕たちの仲は親密じゃないぞ。
「未練は何?」
「私の未練は、恋人を作る! です」
「つまり、彼氏が欲しいと?」
「そういうことです。ただ恋人を作るだけじゃなくて、ちゃんとデートとかしたいですね」
「今から失礼なこと言うね。生前の彼氏じゃ、遊び足りなかったということ?」
やはり彼女が男子の部屋に入ったことがないというのはにわかに信じがたい。
「今日はじめましての人に言うセリフじゃないよね?」
「だから前置きしたじゃないか。失礼なこと言うって」
「前置きしたら許されるわけじゃないからね?」
なんかさっきもこういう会話をした気がするな。その時は立場が逆だった気がするけど。
「でも恋人を作りたいってそういうことじゃないの?」
「違います! 一度もお付き合いした方がいなかったんです。だから最後の一ヶ月ぐらい彼氏が欲しいじゃないですか。やっぱり憧れるじゃないですか!」
一度も付き合ったことがない......だと? 彼女はまだその設定を通すつもりなのか? それとも本当に交際経験がゼロなのか?
容姿は抜群。性格も今のところ問題なさそうだ。初めはイタイ子なのかと思ったけど、どうやら本当に僕以外の人には見えていないらしいし。
あれ? 彼女の未練を解消してあげられるヒーローはどこにいるんだ?
「これからどうするの? 素敵な男性探しの旅にでも出るの?」
「ん? いるじゃないですか、ここに」
僕が見えていないだけで、もしかしてこの部屋に彼女に釣り合う男がいるのか?
僕がキョロキョロ部屋の隅々まで目線を飛ばしていると、彼女は口を開いた。
「ここですよ、ここ」
指差して、誰のことかわかりやすいように言った。
どうやら、僕のことらしい。
「僕?」
人差し指がこちらへ向いているので、わかってはいるけれど、一応訊いておいた。
「はい」
「どうして僕が?」
「だって他に私のこと見える人いないじゃないですか」
当然でしょ? というような口ぶりで彼女は言った。
確かに今のところ僕以外に彼女を認識できる人はいない。僕を選ぶ真っ当な理由だ。
「僕を選ぶ理由はわかった。わかったけど、僕が君を手助けする義理はないよね」
「まあ、そうですね。義理はないですけど、運命は感じてるんですよ」
「僕しか見えないからでしょ?」
「まあ、そうですね。でもでも、これを運命と呼ばずにはいられないでしょ?」
運命的なものを感じないと言えば、嘘になる。僕にしか見えてないなんて、何かあるんじゃないか、と考えるのが普通だ。残念ながら生前の彼女に見覚えはないし、関わった記憶もない。
絶対に見覚えがない、と自信を持っては言えない。もしかしたら、どこかで会ったことがあったのかもしれない。まさに本屋なんかで。けれど、彼女ほどの美貌を前に、僕の記憶から彼女の存在が完全に消滅しているのは、少し不思議だ。
おそらく出会っていなかったのだろう。会っていても、何年も前。彼女の美しさが未完成の状態。幼稚園とかそのくらいの年代。その頃なら覚えていないのは当然だし、それぐらいのことを接点とするなら、僕である必要は全くない。
僕はどういう基準で選ばれたのだろう。
「これが運命......なのかな」
「そうですよ! ぜひ! 私の彼氏に!」
ここまで彼氏になって欲しいとせがまれることは一生ないだろう。しかも、相手がとびきりの美人。来世にも訪れないような気がする。
「わかったよ。一ヶ月だよな」
「はい! よろしくお願いします。秋太くん」
「ああ。よろしく。柏木さん」
高校二年生の夏。僕に彼女ができた。彼女を見れば、誰もが羨むだろう。しかし、僕にしか見えていないのは残念だ。
どうして初めて会った彼女の願いを助けることになったのだろうか。拒否することもできたはずだ。そうしなかったのは、僕がお人好しだからだろうか? 自分ではわからない。
僕自身、夏休みを適当に過ごしているだけだったので、暇つぶしと思えば悪くない。それに、僕にしか見えていないけれど、かなり美人だ。こんなに綺麗な人と夏休みを過ごせると思えば、全く悪い気はしない。
昨日は、彼女となった柏木栞と僕の家で少し喋っただけだ。その後、彼女は帰ってしまった。訊いていなかったけれど、家はあるのだろうか? どこで生活するのだろう?
まだまだ彼女について知らないことが多すぎる。少しずつ、彼女のことを知っていく必要があるな。一応、僕の彼女となったわけだし。
「秋太くん、こんにちは」
「こんにちは。柏木さん」
彼女は昨日、「明日の一時頃にまた来ますね」と言って、帰った。時間通りに彼女は僕の家を訪れた。
「今日は秋太くんと色んなルールなどの諸々の話をしたいと思います」
「ルール?」
「はい。玄関で話すのも何ですし、お散歩しながら話しませんか?」
「構わないよ」
僕はすぐに外に出かけられる格好に着替えた。彼女は昨日と違う真っ白のブラウスを着ていた。
「お待たせ。じゃあ、行こうか」
「行きましょう。あっ、秋太くん、秋太くん」
「な、なに?」
そんな楽しそうな顔をしながら、いきなり名前を連呼されると、ドキッとする。柏木栞とはこういう人物なのだろう。慣れていかないと......。
「すっ」
彼女は小さな掛け声と共に、玄関の扉をすり抜けていった。
鏡を見ていないけれど、僕はひどく間抜け面をしていると思う。目の前で超常現象を見せられては、誰もが口を半開きにし、声を発することもできず、ただ呆然と眺めることしかできないと思う。
「どうでした?」
次はちゃんと扉を開き、彼女は戻ってきた。
「すごい」
「それだけですか?」
「人間って本当にすごいものを見ると、言葉が出ないんだよ」
僕がそう言うと、彼女は微笑んだ。
僕はそんな能力使えないので、普通に扉を開き、外へ出た。天気は今日も快晴。安定に暑い。どうして、こんなに夏は暑いんだ。夏だからか。
この暑さの中当てもなく歩くというのは、愚行に違いない。僕の部屋で話した方が良かったのではないだろうか。僕は選択を誤ってしまった。
隣の彼女を見ると、清々しい表情で歩を進めている。
「暑くないの?」
「暑いですよ?」
「じゃあ、どうしてそんなに元気そうなの?」
「どうして? そうですねー。生きてるーって感じがするからじゃないですかね。暑いとか寒いとか、そういう肌でしっかり感じられるのって生きてる証みたいな気がして、なんだか嬉しいんですよね」
僕には到底分かり得ない理由だった。死んだ彼女だからこその暑さに対する感じ方だ。普通の人ならば、この暑さをプラスに捉える人はまずいないだろう。喜ぶのは極寒の地に住んでいるような人たちだけじゃないのか。
不思議な気分だ。こうして普通に会話しているのに、彼女は生きていないだなんて。
「公園がありますねー」
彼女は僕の家から歩いて数分の公園を見つけて、はしゃいでいる。
「せっかくだし、入る?」
「はい!」
小学生だと思われる子どもたちが数人遊んでいた。広場でサッカーをする子やブランコに乗る子も。
僕の狙いとしては、屋根がついているベンチに座って日陰で休もうという作戦だ。僕は暑さを不快に感じるので、これ以上歩き続ければ、熱中症になってもおかしくない。飲み物持って来れば良かったかも。
「飲み物買ってくるけど、何か飲む?」
「優しいですね。お茶をお願いします」
「了解」
彼女にはベンチで座って待ってもらい、公園の外にある自販機まで歩いて行った。そこまで大きな公園ではないので、すぐそこだ。
彼女の分の麦茶と自分の分のスポーツドリンクを買い、彼女の元へ戻った。
ベンチで足をパタパタさせながら、空を見つめていた。風に吹かれるその様は、絵になった。彼女の存在を認識できれば、きっと注目を集めていたはずだ。小学生たちにも彼女の美しさくらい理解できるはずだ。
「どうぞ」
「ありがとうございます。いくらでした?」
「これぐらいいいよ。それにお金持ってるの?」
「持ってないですね」
彼女は申し訳なさそうに笑った。
水分、塩分がチャージされ、少し生き返った。
「さっき言ってたルールって?」
「まずはそれについて話さないといけませんね。私ってもう死んでるんですよ」
柏木さんの存在が誰からも認識されなかったり、金属の扉をすり抜けたりするのを見ると、彼女がこの世にいない人なんだと、少しずつ受け入れ始めた。
「死後、案内人さんみたいな人に連れて行かれて、色々説明を受けたんですよ。こうしてまたこの世界で未練を晴らす上での注意点みたいなものを」
「その話を信じてしまうようになってしまった僕の頭は正常だよね?」
「ふふっ。正常ですよ。三つ決まりごとみたいなのがありました。一つ目は期限です。これは最初に話したやつですね。八月三十一日を超えれば、私はいなくなります」
まだ三週間以上もあるけれど、あっという間に過ぎるんだろうな。九月になれば彼女がいなくなることに、まだまだ実感は湧かない。
一ヶ月後の僕は彼女がいなくなることに悲しがることはできるのだろうか。彼女の存在を認めることができる唯一の人間として、悲しがれたらいいな、と思う。
「二つ目は?」
「私の存在は、他の誰にも言ってはいけません。秋太くん以外に知られてはいけないっていうことです」
「僕が誰かに言ったら、柏木さんはどうなるの?」
「消えるらしいです。一ヶ月を待たずして、消えます」
彼女が誰かに伝えることはできないので、僕にかかっている。怪しまれないように、行動しないといけないな。
「まあ、このルールはあんまり気にしなくてもいいですよ」
「どうして?」
「だって私のことを見えない人が私がここにいると信じるはずないじゃないですか」
「おっしゃる通りで」
僕が必死に彼女の存在を誰かに認めさせようとした日には、精神科に連れて行かれることだろう。
「じゃあ、最後は?」
「最後は......言わないでおきます。言ったら、多分私のお手伝いをしたくなくなると思うので」
「わかった」
「気にならないんですか? 最後のルール」
彼女は小首を傾げて、言った。
「気にはなるけど、強制力はないからね。言いたくなったら、言えばいいよ」
「私のお願いを快く引き受けてくださるし、あなたが神様に見えてきました」
快く、というのが少々引っかかるが、結局引き受けてしまったあたり、お人好しなのかもしれない。
「僕が神様なら、恨んだ方がいいよ。君は若くして死ぬことになってしまったんだから」
「確かにそうですね。あなたを恨んでおきます」
そう言って、彼女は微笑んだ。
風が吹くと気持ちがいい。少々風が強いようで、公園の木々が唸っている。強い風に吹かれても、木は根強く生えているため、倒れることはない。見た目通りの強さだ。
隣の彼女は、発言などは平気そうに振舞っているが、実際のところ内心どう感じているのかわからない。死という経験をしたのは、彼女以外にいないので気持ちをわかってあげられない。彼女の苦しみを共感できるなんておこがましいこと言えない。彼女にしかわからない苦しみがもしあるのなら、少しでも緩和させてあげられればいいな、と思う。
僕たちが座るベンチの方に、サッカーボールが転がってきた。ボールは僕の足で止まったので、取ってあげた。
「はい」
「ありがとう、お兄ちゃん。さっきから誰と話してたの?」
小学校低学年ぐらいの男の子だ。サッカーに夢中で、こちらなど見ていないものだと思っていたが、見当違いだったようだ。隣に彼女はいるけれど、それを言うわけにいかない。僕も頭のおかしい奴だと思われるし、彼女も消えてしまう。本当のことは言えないのだ。
「考え事してただけだよ。独り言を言っちゃう癖があるんだ」
「へー。変なのー」
結局変な人扱いをされてしまった。これから関わることのないであろう子どもなので、別にこの子にどう思われようが構わない。
ボールを受け取った小学生は、友達のいるところへかけて行った。
「ふふっ。独り言を言う癖があるんですね」
「君を庇って言ったのに、酷くないか?」
「ごめんなさい。でも、もう少しマシな嘘があったんじゃないかなーって思いまして」
この暑さであまり考え事をしたくなかったので、パッと思いついた嘘を言ったが、否定されてしまった。次に備えて、家でいくつか返答のレパートリーを考えておこう。
「僕から一つ文句があるんだけど、言っていい?」
「何でしょう?」
「黙っておくなら、最初からルールは二つって言って欲しかった。三つあることを知ったら、気になる」
「その話はもう終わったものだと思ってました。それについては、本当にすみません」
彼女はペコリと頭を下げた。ちゃんと謝られると、調子が狂ってしまう。
「まあ、そんなに気にしないから、大丈夫。頭上げて」
「気になるのか、気にならないのか、どっちなんですか?」
彼女はまた笑いながら、言った。
「どちらかが本音で、どちらかが建前だね。別に当てなくていいからね」
「すぐにわかっちゃいますけど、優しさに甘えて、これ以上は言わないでおきます」
僕たちは公園を出ることにした。散歩を再開した。
「気になったんだけど、僕の家の扉をすり抜けることができたよね?」
「はい」
「じゃあ、さっきベンチに座ってたけど、あれって空気椅子だったの? すり抜けたりしてなかったけど」
座っているフリをしていたのなら、彼女の筋力はとてつもないことになる。僕なんて一瞬でノックアウトされてしまうのではないだろうか。
「ちゃんと座ってましたよ。私の意識次第何ですよね。ほら、触れます」
そう言って、彼女は僕の腕に触れた。ちょっとしたスキンシップなのに、また動揺してしまう。
「便利な能力だね」
「そうですね。結構便利です。ほいっ」
可愛らしい掛け声と共に、僕の左腕に触れていた彼女の右手は、僕の胴体、右腕を通過していった。
何かが通り抜けた感覚はないけれど、何か気持ち悪さが残った。
「変な気分だ」
「これからはちゃんと触れますね」
「歩きましたねー」
「元気すぎて、怖いんだけど......」
「だらしないですね。一時間ちょっと歩いただけじゃないですか」
真夏に一時間以上歩けば、疲れるに決まっている。柏木さんのスタミナは無限なのか? 平気な顔をしている。もしかして、疲れない身体になっているのか? そのことを安易に訊くのは躊躇われた。
やはり彼女と僕とでは住んでいる世界が違う。同じ地球上に立ち、同じ空気を吸っているけれど、決定的に違う部分がある。
僕が少し悩んでいると、彼女がこちらを凝視してきた。
「もしかして、疲れたりしないのか、とか思ってますか?」
「どうしてわかったの? それも能力?」
「違いますよ。そこまで便利な能力は持ってないです。何となく、そう感じただけです。ちょっと躊躇してるようだったので」
僕はそんなに顔に出やすいタイプだったのかな。自覚はなかったけれど、バレていたのでそういうことだろう。
「ちょっと言いづらかったからさ」
「気にしなくていいのに、です。私たちの今の関係は何ですか?」
「恋人」
「そうです。気軽に話して欲しいです。私をあそこで歩いている女の子と同じように、普通に接して欲しいです」
彼女は僕たちの正面の方から歩いてくる女子高生ぐらいの子を指差して、言った。
「悪かった。変な気を遣って」
「構いませんよ。さっきの質問ですけど、疲れますよ。疲れるのって生きてる証拠じゃないですか。だから嬉しいんですよ」
「そっか」
僕たちはその後も喋りながら歩いた。ペースは落として、ゆっくり。
日も暮れてきた。途中本屋で涼んだりしたが、合計するとかなり歩いた気がする。夏休みに入ってから昨日までの歩いた距離と今日一日の歩いた距離を比べれば、今日の方が多くなるのではないか、と思うくらい歩いた。おかげで足がパンパンだ。明日は筋肉痛だろうな。
彼女もさすがに疲れたのか、休憩を入れる頻度が後半多くなっていた。
「そろそろ帰ろうか」
「そうですね。楽しかったです」
「僕も楽しかったよ。ところで、柏木さんは帰る場所ってあるの?」
「私の能力があれば、人の家に勝手に入り込めちゃうんですよね。なので、使われてないベッドとかがあるお部屋を見つけて、そこで寝てます」
不法侵入だろ、とは言えなかった。死人に適応される刑罰はないだろうし。
「そうなんだ。なら、良かった。また明日」
「はい。私から言わなくても、明日も会ってくれるんですね。やっぱり、優しいです」
彼女は嬉しそうにした。僕も思いの外楽しかったし、一ヶ月間彼女に付き合うことにした。やるからにはしっかりやり遂げたいと思った。
「じゃあ」
「さようなら」
彼女は僕の家とは逆方向に歩いて行った。後ろ姿を眺めていたが、すぐに見えなくなった。
僕には明日も会ってあげる優しさはあっても、家に来てもいいと言ってあげられる優しさはまだなかった。
「今日はラーメンが食べたいです」
「そんなものでいいの?」
僕は決してラーメンをバカにしているわけではない。ラーメンは大好きだ。大好きだけれど、あと一ヶ月もないこの世での生活にラーメンを選択するのは意外だったのだ。それに彼女なら無銭飲食で捕まることはないし、誰かが頼んだラーメンを横取りしても咎められることはないだろう。
「私、ラーメン食べたことないんですよ。だから行ってみたいです!」
ラーメンを食べたことがないだと......? めったに食べないという人はいても、一度も食べたことがないという人に会ったのは初めてだった。もしかすると、生前の彼女の家族は、ラーメンを毛嫌いする一家だったのかもしれない。
彼女には驚かされてばっかりだ。
僕基準でこの辺りで一番美味しいと思える店に連れて行ってあげたい。
「わかった。ちょっと歩くけど、大丈夫?」
「余裕です!」
今日は僕と柏木栞が出会ってから、五日目だ。毎日一時から二時の間ぐらいに彼女は僕の家にやってきて、二人で何かしている。昨日は僕たちが出会った本屋でお互いの好きな漫画をプレゼンをしあったりした。おかげで僕は独り言を言い続ける、ヤバイ奴認定されたのかあまり人は近づいてこなかった。
初めて出会った彼女をどうして僕は、こんなに助けたいと思ったのだろう。物珍しさ、好奇心みたいなものも多少はあった。普通に生活していれば、絶対に体験することができない体験をさせてもらっている。壁をすり抜ける能力とか、フィクションの世界だけだと思っていた。
当然、同情心もある。彼女からしても、今まで関わりのなかった男から同情されても迷惑かもしれないが、僕と同い年ですでに生を断たれた彼女に同情する気持ちが芽生えないはずがなかった。
しかし、それだけではないような気がする。一目惚れとかそういうものじゃない。でもそれが何かはっきりしないままだ。
「ねえねえ、私、良いこと考えたんですよ」
「ろくなことじゃなさそうだけど、一応聞く」
「失礼ですね。秋太くんはこうして私とお話してくれてるじゃないですか」
「うん」
「でも、すっごい視線を集めてるじゃないですか」
「そうだね」
周りから見れば、そこそこ大きな声で独り言を喋ってる人なので、当然痛い視線を向けられる。
「スマホ持ってますか?」
「持ってるけど」
そう言って、僕はポケットに入っていたスマホを取り出した。
「常に誰かと電話してる風に見せかけるってのはどうでしょう」
確かに彼女の考えた作戦なら、一人で喋り続けても不審がられないだろう。
「いい作戦だと思う。でも、僕はこのままでいいよ。僕と無関係な人からどんな目を向けられても、どうってことないし」
出会った初日と違い、そんな風に考えるようになっていた。これから先、おそらく関わることのない人たちからどう思われようが、別に気にすることではない。同じ高校のやつに見られたら、ちょっと気まずいけれど。
「私はいい彼氏を持ったなー」
そう言って、彼女は歩くスピードを速めて、僕の前へ出た。
数十分歩いて、僕がよく行くラーメン屋に着いた。入る前からスープの香りが鼻腔をくすぐる。ピーク時は過ぎているので、並ぶことなく入店することができた。
僕たちはカウンター席に座った。再奥の壁に近いところ。
「どれにする?」
「色々種類あるんですね」
「そうだね。王道なのはしょうゆとかとんこつじゃないかな」
「秋太くんはどれに?」
「僕はしおラーメンかな。ここのしおラーメンの味は僕が保証する。あっさりしてて、食べやすいと思う」
彼女は今一度、メニューに目をさらっと通した後、閉じた。
「私も同じのにします」
僕はしおラーメンを二杯注文した。店員から少し不思議そうな顔をされた。僕みたいなひょろっとしたのが二杯食べると思われているのだから、当然だろう。
数分後に、ラーメンがやってきた。僕の前に二杯とも置かれた。
「ちょっと気になったんだけど、柏木さんの姿は誰にも見えない。じゃあ、柏木さんが食べたラーメンはどう見えるのかな? いきなり空の容器が現れたりするのかな」
「うーん。そこのところは私もあんまりわかんないですよね。周りの人から不思議な目をされたりはしないので、そういうわけではないんじゃないですかね? きっと全てが最後に上手く調整されるんでしょうね」
「調整?」
「はい。ちょっと難しいんですけど、このラーメンって本当は作られることがなかったラーメンじゃないですか。私が頼まなかったら、食べられることはなかったわけですから。私は死んだ人間なので、この世にいてはいけない存在なんです。きっと一ヶ月後に帳尻が合わせられるんじゃないかと。私がこの一ヶ月消費したものなんかが、消費されなかったものとして復活する、みたいなことを言ってました」
「柏木さんが本屋で一冊本を盗んだとする。在庫から一冊、本が消えるわけだから、普通本屋は損するはず。でも、一ヶ月後には盗まれたことなんてなかったことになると」
「そんな感じですね。いいたとえじゃなかったですけど」
深く考えずに言ったけれど、彼女を盗人としてたとえてしまった。これも罰せられることは絶対にないことだけど。
「気分を悪くしたようなら、ごめん」
「これくらいじゃ、何とも思いませんよ。秋太くんが私に使ったお金も一ヶ月後復活しますよ」
この一ヶ月で使用したお金が戻ってくるなんて、喜ばしいことのはずだ。今日払う予定のラーメン代、数日前に自販機で買った麦茶代なんかも一ヶ月後戻ってくる。そして、僕と彼女が一緒にいた記憶だけが残る。悪くない、悪くないはずなのに、少し寂しさを感じ、上手く笑うことができなかった。まだ出会って五日だというのに、毎日会っているせいもあり、ずっと前から知り合いだったような、そんな感じがした。