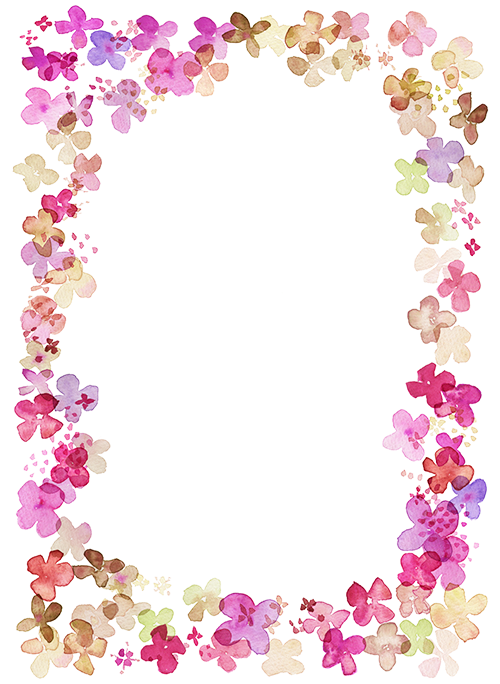やっと、終わった。
地獄のような日々が…、
愚かな戦争が……―――。
普通だった毎日が壊れてしまったのは、約六年前の夏のことだった。
あの日、あたしは彼と一緒にいた。
あたしたちは、二人のお気に入りの野原に向かって、駆けていった。
眩しい太陽の光が辺りを照らす中、
前を走る彼の白いシャツと黒っぽい髪が、風になびいていた。
「待ってよ、レメック!待ってってば!」
あたしが言うと、彼―レメックは、こちらを振り返った。
その顔は笑っていて、あたしの前に手が差し出された。
「しょうがないな。ほら、握って」
「ハア?嫌だ!」
「えっ、なんで?」
「なんでじゃない!アンタと手を繋いだりなんかしないんだから!」
あたしが叫ぶと、レメックは「やれやれ~」とため息を吐いた。
そして、あたしの隣に並んだ。
「分かったよ。じゃあ、ゆっくり行こう」
「最初からそうしてくれればいいじゃない!」
あたしは、イライラしていた。
いつも、レメックは、あたしの手が届かないところにいるような気がしていたのだ。
足は速いし、宿題を終わらせるのも早いし、何でもあたしより早い。
それに、あたしと違って、レメックにはたくさんの友達がいた。
あたしとは正反対に、たくさんの人に愛されていた。
それが、羨ましいという気持ちから、よく苛立ちに変わった。
「アンタって、いつもそうだよね。いつも自分ばっかり良くて、あたしのことなんか…」
つい言いかけると、レメックがあたしの目の前に立った。
「ちょっと待ってよ、アネタ。今日はやたらと機嫌が悪いね。
僕…何かした?」
レメックは、もう笑っていなかった。
なんだか、悲しそうな、不安そうな目。
それを見ると、なんとなく悪い気がしてきた。
「別に、何でもない!ほっといてよ!」
「でも、野原に行くんだろ?」
「…そうだけど」
言いながら、自分が嫌になってきた。
いつも一人でイライラして、
唯一そばにいてくれる友達に当たってばかりで、
そんな自分が情けなかった。
けれど、レメックは、
そんなダメなあたしのことを見捨てたことなんてなかった。
そう、小さい頃からずっと…。
「行くんだな?」
レメックは、笑いながら、あたしの顔をのぞき込むように見た。
あたしは、今さら後に引けず、顔を背けてうなずいた。
すると、レメックはゲラゲラと笑い出した。
「しょうがないな―!僕についておいでよ」
そう言って、レメックがあたしの手を握った。
次は、断ることも出来なかった。
恥ずかしさで、顔や身体が熱くなるのを感じた。
けれど、レメックはお構いなしに、あたしの手を握ったまま進んでいく。
その後ろ姿に向かって、あたしは心の中で言った。
…レメック、違うんだよ。
さっき、手を繋ぎたくなくて断ったわけじゃなかった。
ただ…恥ずかしかっただけなんだ。
いつも嫌な思いさせたり、傷つけてばかりで、ごめんね。
…こんなあたしといつも一緒にいてくれて、
見捨てないでそばにいてくれて、ありがとう。
あたしは、いつも意地を張ってばかりだったけど、
本当は、レメックのことが好きだった。
大好きだった。
だから、彼が他の誰かと楽しそうに話したりしているのを見ただけで、
腹が立った。
彼が、あたしではない誰かと一緒にいるだけで、
彼が離れていってしまいそうな気がして、
怖くなった。
あたしの世界には、いつも彼がいた。
けれど、分かっていた。好きなのは、あたしだけだと。