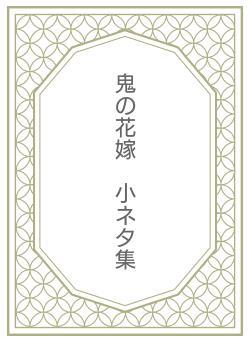出来上がったビーフシチューを皿に盛り、パンとサラダを添えてテーブルに並べる。
「どうぞ」
「ああ」
枢がスプーンですくって口に入れるのをじっと見る。
しかし、表情が変わらないので美味しいのか不味いのか分からない。
「どう?」
「ああ、美味しい」
「良かった」
それを聞いて瀬那もほっと顔を綻ばせた。
まあ、いつも瀬那の作るお弁当を食べているのだから、味覚が違うということはないだろう。
瀬那もいただきますと食事を始めると、枢が言葉をこぼした。
「こういう料理も作れるんだな」
「え?」
「いつもの弁当。あれも毎日自分で作ってるんだろう?」
「うん。お兄ちゃんと二人暮らしだから、他に作ってくれる人いないもの」
「みたいだな」
「みたいだなって、私が作ってるって知ってたの?」
そもそもだ。急に弁当を作ってこいだとか、もし母親が作っているものだったら、言い訳だとか大変だと思う。
けれど、枢は弁当を毎日瀬那が作っていることを知っていたということか。
「話しているのを聞いた」
「え、何を?」
「お前が弁当は自分で作ってきてるって話だ」
「いつのこと?」
「教室でたまに料理の本読んでる時あるだろう。その時に、いつもいる奴と弁当の献立を何しようかとか、次はこれを作ろうとか話してるのを聞いてた」
確かに、美玲とお弁当の話をしていたことはある。
けれど、そんなことを覚えていたのだろうか。
「そんなこと聞いてたの?」
「ああ、ずっと見てたからな、お前のこと」
「え……」
じっと瀬那を見つめる枢の瞳。
その真剣な瞳に吸い込まれてしまいそうだ。
「ずっと前から見てた。だから自然とお前の話してる声を拾ってた」
「っ……」
今まで視線が合っていると思っていたのは自分の勘違いではなかった。
あの目は確かに瀬那を見ていたのだ。