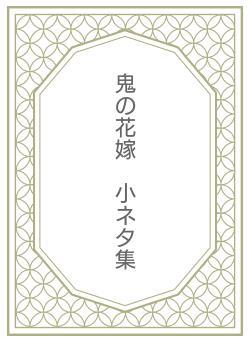「一条院以前に、一条院さんは素敵だから、女の子なら誰でも惹かれるのよ。
皆一条院さんの恋人になりたくて必死なのね」
一条院家というブランドがなくても、きっと彼の恋人になりたい子は沢山いるだろう。
モテる男は大変だなと思いながらハム卵のサンドイッチを取り、ぱくりと食べる。
すると、横から伸びてきた手のひらが瀬那の頬に添えられる。
驚きながら横を向くと、枢の全てをからめ取るような漆黒の眼差しと重なった。
「お前もか?」
「えっ……」
「お前も俺に惹かれるか?」
その問いにすぐには答えられず……いや、なんと答えたら良いのか分からず、瀬那は自分を見つめる枢の瞳を見つめ返す。
冗談で返せばいい。
けれど、その瞳があまりにも真剣で、笑って返すことができなかった。
沈黙がその場に落ちる。
その時、手に持っていたサンドイッチの具が、ポトリとスカートの上に落ち、瀬那は我に返る。
「わっ、きゃ」
大きく仰け反ったことで、頬に添えられていた手はするりと離れる。
そのことに少し寂しさと安堵がない交ぜになる。
「ティッシュ、ティッシュ」
バッグからティッシュを取り出し、汚れたスカートを拭く。
すぐに拭いたが、少し汚れが残ってしまった。
瀬那は拭いているふりをして、顔を俯かせていた。
きっと今瀬那の顔は赤いだろう。
それを悟られないように、髪で顔を隠しながら下を向いた。