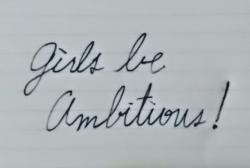頭巾をつけた姫が聚楽第の表書院の控の間に通されると、近習やら家中の小姓やら御伽衆やらが、熊野から呼ばれたという僧の指示で、護摩壇やら法具やらを慌ただしく運び入れている。
「かなり大がかりにございますな」
細川越中守忠興と並んで様子を見ていた、秀吉の実弟である豊臣大納言秀長が、露骨に嫌な顔をした。
「兄者どのも、何ゆえここまで近衛の姫さまに執心なさるのか」
と半ばこの兄の行動に嫌気が差していたようで、
「大納言さま、それは生まれ持った素性と申すものでございます」
と、脇にいた忠興は小声で答えた。
「素性、か」
確かにわれら兄弟は尾張中村の百姓の小せがれに過ぎん、と秀長はいう。
「だがな越中どの、われら素性も分からぬ者は、分からぬなりに世を渡らねばならぬ」
なれど兄者のやりようは異様としか言いようがない、と秀長はつぶやいた。
忠興は忠興で、
「よりによって近衛家の姫さまに目をおつけなさるとは」
それほど血筋が欲しいものか、というような目で護摩壇が組まれて行くのを眺めていた。