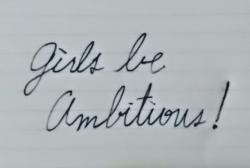斯くして。
選んで定められた、狐落としの祈祷の日が来た。
近衛家では姫のために輿を支度し、聚楽第に向けて進発させたのだが、
「御所さま、あれでよかったのでございますか?」
「いくら関白でも、よもやああなっておるとは思うまい」
信尹は目線を投げやった。
他方で。
聚楽第の周りの町衆は、左大臣家から姫が輿で来るというので、物見高きは世の常で辻という辻に人だかりが、十重二十重に出来ている。
金で近衛牡丹の紋が打たれた緋色の輿は、二条通を真っ直ぐ聚楽第へ目指して行く。
この様子を辻で眺めていた施薬院全宗も、さすがに計略を弄してまで女を漁る秀吉の態度にはいささか閉口気味であったのか、
「これが障りにならねば良いのだが」
と言ったきり、力のない目で輿の列をぼんやりと見ていた。