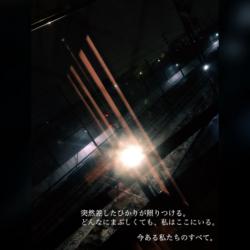真剣な表情で教授の話をノートにまとめる。親に払ってもらっている授業料を無駄にすることのないよう、宏紀は筆圧を強くしている。真也もその宏紀に刺激されて負けないようについていく。七海は長い髪の毛を束ねてやる気満々だ。
三時限目の眠気に襲われているはずの宏紀たちがこんなに生き生きとしている。どこか藁にも縋るように、必死さも感じられる。
背後からそれを見えていた私は、眠気対策で買ってきた目薬をさして、偽物の涙で自分を奮い立たせた。
沙織は眠っている。永遠に眺めていたいぐらい可愛いけどやむなく起こした。
「私もつられて寝そうだから起きて、沙織」
「はい……」
沙織は小さく体を伸ばした。
宏紀は三時限目を終えると、休憩時間の十五分を使ってトイレに向かう。高校生のように真也も宏紀についていった。それがなんか微笑ましくて、私は二人に見とれた。
宏紀は手を差し出して手洗い用の洗剤をすりこんでいく。
「ああ、なかなか聞けないな」
真也が宏紀の隣で嘆くように言った。
「聞いて……聞いてみればよくない? 案外、さっと教えてくれるかもよ……」
励ましのつもりで宏紀は言葉を並べるけど、真也に届いているかどうかは不明だ。宏紀の言葉にどこか張りがないし、よく聞こえない。
「そうだな……こんなところで悩んでいるより、聞いた方がいいな。気になって仕方ないし」
宏紀は黙って真也の言葉に耳を傾けている。もしも耳にミュート機能があれば、遠慮なく使いたいって思っているかもしれない。それ以上聞かれても、宏紀は答えられない。
「いないわけないよな、あれだけまっすぐで可愛いと」
真也の見えない何かが、彼の心に負荷かける。でもその状況をどこか楽しんでいるようにも見える。その負荷さえも真也に不思議な力を与えてくれるのか。
鏡越しで真也を視界に捉える宏紀。次の講義の時間が迫っていることをいいことに、
「さぁ、次の講義に行こう」と言った。
「未砂、私、マジで服がない」
講義室が並ぶ廊下を行く私と沙織。
「私もない。なんか最近同じ服ばっかり着てる」
別に大学にファッションショーをしに来ているわけじゃないからいいけど、同じ服ばかりだとつまらない。せっかく大学生になったのなら、服も楽しんでいきたい。
「今度、買い物行こうよ!」
「いいね! 沙織に服選んでもらおう!」
「いいよ! じゃあ未砂は私の服選んで! 高いものじゃなかったら買えるから」
「沙織は何でも似合いそうだから、とりあえず勧めるね」
私たちの目的地の講義室から七海と真也が出てきた。
「七海ちゃん!」
私は手を振って七海に挨拶をした。
七海も同じく手を振って私と沙織を迎える。
七海が宏紀といる時は不要に心を揺さぶられるけど、宏紀がその場にいなかったら七海のことは大好きだ。だからこうして笑顔でいられる。七海を嫌いになる人は、恐らくいないだろう。
「あれ、宏紀、一緒じゃなかったんだ」
「七海ちゃんたちと一緒じゃなかったんだ」
講義室を覗いてみるも宏紀の姿はなかった。講義と講義の時間の間の十五分で行く場所としたらトイレか自販機かコンビニだ。教育学部付近にコンビニがあり生活環境学部からは五分程度で行ける。
そんな宏紀の消息を話していると、宏紀が飲み物を手にして階段からふらりと現れた。視線は足元にあって私たちは視界には入っていない。
「あ」
宏紀は視線を上げると、目の前にある大きなブロックにぶつかったかのように歩く両足に急ブレーキをかけた。
「宏紀、どこ行ってたんだよ?」
真也がそう言って宏紀を遠くから声をかけた。
その声に私は振り返った。
宏紀は缶コーヒーを持っている。私はそれをじっと見つめていると何か不思議に思えてくる。缶コーヒーは新商品ではない。大きさも普通の缶コーヒーと違いはないはずなのに。この違和感は何だろう。
「ああ、ちょっと……」
詳しくは言わずに言葉を丸め込む。
「宏紀、コーヒー飲めるの?」
違和感の正体を七海が教えてくれた。
「ああ、うん……」
勢いに押されて言葉を外に押し出すような感じで宏紀は言った。
「マジで? 飲めないんじゃないの?」
真也はことの真相を探るために加えて質問をした。
「最近、飲めるようになってきてさ……」
宏紀は顔を上げて頬を無理やり吊り上げたが、どこか決まりが悪い。
七海が喫茶店で働き始めたから意識的に飲むようになったのかと、私は思った。よく見てみると、無糖の缶コーヒー。甘さがなくても飲めるようになってきたってことか。そう考え始めた瞬間、私は胸を鷲掴みにされたような痛みをギスギスと感じ始めた。湿り気を帯びてきた瞳で缶コーヒーを見つめる。これには罪はないのは分かっているけど、私の目の前から消えてほしかった。
「そうなんだ。大人に一歩近づいたね」
七海が宏紀をからかった。
そんなことで大人にならなくたっていい。宏紀は精神的に落ち着いているからそんなことしなくていい。
「本当だな」
真也は同調した。
その言葉も余計で私は耳を塞ぎたくなった。
講義室に入っていつもの席にそれぞれ着くと、宏紀は教科書のそばに缶コーヒーを置いた。まだ開封されていない。早く飲んで、早くゴミ箱に捨ててきてほしい。
階段を上り切ると、私は大船行きの電車に乗った。
別に気分が悪いわけじゃないけど、私はいつもの穏やかさを見失っている。缶コーヒーの心をかき乱されたのに始まって、宏紀の行動にも矛盾があってどこか気持ち悪い。
本当はこんなこと言いたくない。誰も悪くない。缶コーヒーはただ宏紀を少しだけ大人に成長させただけ。宏紀の行動の矛盾があったとしても、私に責められることじゃない。
こうして誰かを、何かを一時の感情で攻撃するのは、人として良くない。私に宿る良心が影を落とす私を窘めている。
ため息をついて壁にもたれた。
ふと横を見ると奥に宏紀がいる。ついさっきまでは感じなかった空気だから、今乗り込んできたのだろう。それが分かってしまう自分が怖くなった。
霧のかかった心を手で払う。せっかく見かけたから言葉を交わしたい。近づいていくと、宏紀の視線はしっかりしていても、そよ風が吹いたらどこかに飛ばされてしまいそうな浮遊感があった。
「宏紀」
手を振って伸びる視線を遮った。朦朧とする意識をひとつに重ね合わせて、宏紀は私を視界に迎え入れた。
「未砂……今帰り?」
ポツリとそう呟くと、私は「うん」と答えた。
念のためにまたさりげなく周囲を確認して大学の子たちがいないことを確認する。今日みたいな揺さぶりはもう嫌だ。そんなに我慢強いタイプではない。いつも笑っているから悩みがないとか、少しのことでは落ち込んだりしないって思われがちだけど、大きな間違いだ。
「どうかしたの? ボーっとしてたけど」
「ちょっと疲れただけ。毎日早起きしてると、この時間帯眠くならない?」
「分かる。講義中に寝るのは良くないしね」
宏紀が頑張って眠気を振り払って講義を聞いていた時のことを思い出す。
「うん。今日は黒なんだね」
宏紀はそう言って私の髪の毛に乗っかっているカチューシャを見つめた。
「うん。なんか気分で変わるんだ」
カチューシャのことを気にかけてくれる宏紀。前のことを気にしているのかと思ったけどもう大丈夫だ。むしろカチューシャは缶コーヒーと違って私を幸せレベルを上げてくれる。宏紀の優しさを思い出させてくれるからだ。
「育ちのいい女の子って感じだよね」
「そう? 育ちは良くないけど、そう言ってもらえると嬉しいな」
頬を緩ませて宏紀の手の甲を見た。
「宏紀、手……すごく乾燥してるね……」
手をすぐ見える場所に持ち上げて宏紀は、「乾燥しやすくて。それでバイトでアルコール消毒とかすると、カサカサになるんだ」
よく見ると、雨が降らない場所で土壌がひび割れているみたいな手だった。
「痛くない?」
顔を顰めながら宏紀に尋ねた。拳を握りしめたら、皮膚が引き裂かれて血が噴き出そうだ。
「大丈夫だよ。もう慣れてるから」
「ちょっと待って」
私はバックパックを下ろして、カバンの中を探る。いつも持っているハンドクリームを手にした。
「手出して」
宏紀は言われたままに手を差し出した。少し手を動かせば触れられる場所に宏紀の手がある。水に飢えている砂漠に水を与えよう。砂漠ほど大きな場所ではないから、私一人でも宏紀の手に潤いを与えることができる。
意を決してクリームをすりこんでいく。胸中で跳ねる鼓動を隠しながら。じっと見つめる宏紀の手が水を得た魚のように生き返りつつある。
「ありがとう……もう大丈夫だよ」
宏紀も人前で恥ずかしいんだろう。笑顔を見せつつも周囲のことも気にしている。
「まだもう片手が残ってるから待ってて」
目を手の甲に固定して動かさない。手も心配だけど、宏紀の手に触れていたいのもある。クリームを塗るふりをして安心感を得ている。今日の出来事をかき消してくれるぐらい宏紀の手は温かい。次にもう片方を手に取った。
「このハンドクリームあげるから、ちゃんと毎日塗ってね」
「いいよ。自分で買うから」
「じゃあ、買うまでこれ持ってて。もう一つあるから」
私は宏紀を見つめた。こんな手をしていたら、普通に見ていて心配になる。
「ありがとう。すぐ買ってくるね」
「うん……」
手を放した瞬間、急に恥ずかしくなってきて俯いてしまった。むしろ塗っている時の方が、作業に集中することができたからよかった。
出発時刻になり電車が動く。揺らされて変な気まずさを振り払えた。でも赤面した表情は変わらない。
「大学、どう?」
俯いたまま聞く。
「うん……楽しいかな……未砂はどう?」
『楽しい』の箇所に気持ちは感じられなかった。宏紀の本心は違うところにあるような気がする。でも宏紀に問いかけられてそれは覆い隠された。
「楽しいよ。宏紀たちにも出会えたし、行ってよかったよ」
自分自身でいることが難しい時もあるけど、宏紀や七海と出会えたことは、私の人生の宝物だ。それははっきりと声を大にして言える。
「そっか。良かった……長い時間かけて通う意味があるなら……」
「宏紀は……そうじゃないの?」
聞いていいかどうか分からなかったけど、声に力がない宏紀を気遣ったつもりだ。
「そんなことない。まだ慣れないから、必死って言うか、何ていうか……」
言い訳のように聞こえるけど、宏紀の言葉を額面通り受けておく。
「そっか。じゃあ、気分転換しようよ。帰る時に、色々寄り道したりして」
「そうだね……」
頷きながら笑ってくれたけど、何かに力を吸い取られている宏紀の今がある。
「映画とか観るの?」
「観るよ。最近はあまり行ってないけど、見たい映画があるときは映画館で」
「そうなんだ。じゃあ、今度一緒に行こうよ! もちろん、観たい映画があったら……だけど」
「うん。行きたい」
ささやくような声量だけど、宏紀は懸命に返事をしてくれいる感じだった。
「やった!」
響き渡る場所を制限して、私は小さくそう言った。本当は飛び上がって喜びたいところだけど、テンションを宏紀の目線にまで持っていった。
「何か観たい映画があるの?」
「うん。いくつかあるんだけど……宏紀が好きかどうか分からないから、一緒に選んで」
流れで映画の話を持ち出したから特に観たい映画はない。
「未砂が観たい映画でいいよ。だいたいどのジャンルでも観れるから」
「じゃあ」
多分、今なら気分が高揚するような楽しい映画がいいかもしれない。恋愛映画は恥ずかしくて見られないだろうし、宏紀がさらにしんみりして孤独な世界に入り込んでしまいそうだから。ホラーは私が苦手だから選択肢には入れない。
「未砂、誘ってくれてありがとう」
「えっ?」
「いや、何でもない。映画楽しみだね」
ちゃんと聞こえていた。普通のお礼だけど、でもなぜが気になる。裏返したら何か重要なことが隠されているような気がした。でも今は裏返す勇気はない。
私の勘違いかもしれないけど、宏紀の目元に薄っすら光るものがあった。
三時限目の眠気に襲われているはずの宏紀たちがこんなに生き生きとしている。どこか藁にも縋るように、必死さも感じられる。
背後からそれを見えていた私は、眠気対策で買ってきた目薬をさして、偽物の涙で自分を奮い立たせた。
沙織は眠っている。永遠に眺めていたいぐらい可愛いけどやむなく起こした。
「私もつられて寝そうだから起きて、沙織」
「はい……」
沙織は小さく体を伸ばした。
宏紀は三時限目を終えると、休憩時間の十五分を使ってトイレに向かう。高校生のように真也も宏紀についていった。それがなんか微笑ましくて、私は二人に見とれた。
宏紀は手を差し出して手洗い用の洗剤をすりこんでいく。
「ああ、なかなか聞けないな」
真也が宏紀の隣で嘆くように言った。
「聞いて……聞いてみればよくない? 案外、さっと教えてくれるかもよ……」
励ましのつもりで宏紀は言葉を並べるけど、真也に届いているかどうかは不明だ。宏紀の言葉にどこか張りがないし、よく聞こえない。
「そうだな……こんなところで悩んでいるより、聞いた方がいいな。気になって仕方ないし」
宏紀は黙って真也の言葉に耳を傾けている。もしも耳にミュート機能があれば、遠慮なく使いたいって思っているかもしれない。それ以上聞かれても、宏紀は答えられない。
「いないわけないよな、あれだけまっすぐで可愛いと」
真也の見えない何かが、彼の心に負荷かける。でもその状況をどこか楽しんでいるようにも見える。その負荷さえも真也に不思議な力を与えてくれるのか。
鏡越しで真也を視界に捉える宏紀。次の講義の時間が迫っていることをいいことに、
「さぁ、次の講義に行こう」と言った。
「未砂、私、マジで服がない」
講義室が並ぶ廊下を行く私と沙織。
「私もない。なんか最近同じ服ばっかり着てる」
別に大学にファッションショーをしに来ているわけじゃないからいいけど、同じ服ばかりだとつまらない。せっかく大学生になったのなら、服も楽しんでいきたい。
「今度、買い物行こうよ!」
「いいね! 沙織に服選んでもらおう!」
「いいよ! じゃあ未砂は私の服選んで! 高いものじゃなかったら買えるから」
「沙織は何でも似合いそうだから、とりあえず勧めるね」
私たちの目的地の講義室から七海と真也が出てきた。
「七海ちゃん!」
私は手を振って七海に挨拶をした。
七海も同じく手を振って私と沙織を迎える。
七海が宏紀といる時は不要に心を揺さぶられるけど、宏紀がその場にいなかったら七海のことは大好きだ。だからこうして笑顔でいられる。七海を嫌いになる人は、恐らくいないだろう。
「あれ、宏紀、一緒じゃなかったんだ」
「七海ちゃんたちと一緒じゃなかったんだ」
講義室を覗いてみるも宏紀の姿はなかった。講義と講義の時間の間の十五分で行く場所としたらトイレか自販機かコンビニだ。教育学部付近にコンビニがあり生活環境学部からは五分程度で行ける。
そんな宏紀の消息を話していると、宏紀が飲み物を手にして階段からふらりと現れた。視線は足元にあって私たちは視界には入っていない。
「あ」
宏紀は視線を上げると、目の前にある大きなブロックにぶつかったかのように歩く両足に急ブレーキをかけた。
「宏紀、どこ行ってたんだよ?」
真也がそう言って宏紀を遠くから声をかけた。
その声に私は振り返った。
宏紀は缶コーヒーを持っている。私はそれをじっと見つめていると何か不思議に思えてくる。缶コーヒーは新商品ではない。大きさも普通の缶コーヒーと違いはないはずなのに。この違和感は何だろう。
「ああ、ちょっと……」
詳しくは言わずに言葉を丸め込む。
「宏紀、コーヒー飲めるの?」
違和感の正体を七海が教えてくれた。
「ああ、うん……」
勢いに押されて言葉を外に押し出すような感じで宏紀は言った。
「マジで? 飲めないんじゃないの?」
真也はことの真相を探るために加えて質問をした。
「最近、飲めるようになってきてさ……」
宏紀は顔を上げて頬を無理やり吊り上げたが、どこか決まりが悪い。
七海が喫茶店で働き始めたから意識的に飲むようになったのかと、私は思った。よく見てみると、無糖の缶コーヒー。甘さがなくても飲めるようになってきたってことか。そう考え始めた瞬間、私は胸を鷲掴みにされたような痛みをギスギスと感じ始めた。湿り気を帯びてきた瞳で缶コーヒーを見つめる。これには罪はないのは分かっているけど、私の目の前から消えてほしかった。
「そうなんだ。大人に一歩近づいたね」
七海が宏紀をからかった。
そんなことで大人にならなくたっていい。宏紀は精神的に落ち着いているからそんなことしなくていい。
「本当だな」
真也は同調した。
その言葉も余計で私は耳を塞ぎたくなった。
講義室に入っていつもの席にそれぞれ着くと、宏紀は教科書のそばに缶コーヒーを置いた。まだ開封されていない。早く飲んで、早くゴミ箱に捨ててきてほしい。
階段を上り切ると、私は大船行きの電車に乗った。
別に気分が悪いわけじゃないけど、私はいつもの穏やかさを見失っている。缶コーヒーの心をかき乱されたのに始まって、宏紀の行動にも矛盾があってどこか気持ち悪い。
本当はこんなこと言いたくない。誰も悪くない。缶コーヒーはただ宏紀を少しだけ大人に成長させただけ。宏紀の行動の矛盾があったとしても、私に責められることじゃない。
こうして誰かを、何かを一時の感情で攻撃するのは、人として良くない。私に宿る良心が影を落とす私を窘めている。
ため息をついて壁にもたれた。
ふと横を見ると奥に宏紀がいる。ついさっきまでは感じなかった空気だから、今乗り込んできたのだろう。それが分かってしまう自分が怖くなった。
霧のかかった心を手で払う。せっかく見かけたから言葉を交わしたい。近づいていくと、宏紀の視線はしっかりしていても、そよ風が吹いたらどこかに飛ばされてしまいそうな浮遊感があった。
「宏紀」
手を振って伸びる視線を遮った。朦朧とする意識をひとつに重ね合わせて、宏紀は私を視界に迎え入れた。
「未砂……今帰り?」
ポツリとそう呟くと、私は「うん」と答えた。
念のためにまたさりげなく周囲を確認して大学の子たちがいないことを確認する。今日みたいな揺さぶりはもう嫌だ。そんなに我慢強いタイプではない。いつも笑っているから悩みがないとか、少しのことでは落ち込んだりしないって思われがちだけど、大きな間違いだ。
「どうかしたの? ボーっとしてたけど」
「ちょっと疲れただけ。毎日早起きしてると、この時間帯眠くならない?」
「分かる。講義中に寝るのは良くないしね」
宏紀が頑張って眠気を振り払って講義を聞いていた時のことを思い出す。
「うん。今日は黒なんだね」
宏紀はそう言って私の髪の毛に乗っかっているカチューシャを見つめた。
「うん。なんか気分で変わるんだ」
カチューシャのことを気にかけてくれる宏紀。前のことを気にしているのかと思ったけどもう大丈夫だ。むしろカチューシャは缶コーヒーと違って私を幸せレベルを上げてくれる。宏紀の優しさを思い出させてくれるからだ。
「育ちのいい女の子って感じだよね」
「そう? 育ちは良くないけど、そう言ってもらえると嬉しいな」
頬を緩ませて宏紀の手の甲を見た。
「宏紀、手……すごく乾燥してるね……」
手をすぐ見える場所に持ち上げて宏紀は、「乾燥しやすくて。それでバイトでアルコール消毒とかすると、カサカサになるんだ」
よく見ると、雨が降らない場所で土壌がひび割れているみたいな手だった。
「痛くない?」
顔を顰めながら宏紀に尋ねた。拳を握りしめたら、皮膚が引き裂かれて血が噴き出そうだ。
「大丈夫だよ。もう慣れてるから」
「ちょっと待って」
私はバックパックを下ろして、カバンの中を探る。いつも持っているハンドクリームを手にした。
「手出して」
宏紀は言われたままに手を差し出した。少し手を動かせば触れられる場所に宏紀の手がある。水に飢えている砂漠に水を与えよう。砂漠ほど大きな場所ではないから、私一人でも宏紀の手に潤いを与えることができる。
意を決してクリームをすりこんでいく。胸中で跳ねる鼓動を隠しながら。じっと見つめる宏紀の手が水を得た魚のように生き返りつつある。
「ありがとう……もう大丈夫だよ」
宏紀も人前で恥ずかしいんだろう。笑顔を見せつつも周囲のことも気にしている。
「まだもう片手が残ってるから待ってて」
目を手の甲に固定して動かさない。手も心配だけど、宏紀の手に触れていたいのもある。クリームを塗るふりをして安心感を得ている。今日の出来事をかき消してくれるぐらい宏紀の手は温かい。次にもう片方を手に取った。
「このハンドクリームあげるから、ちゃんと毎日塗ってね」
「いいよ。自分で買うから」
「じゃあ、買うまでこれ持ってて。もう一つあるから」
私は宏紀を見つめた。こんな手をしていたら、普通に見ていて心配になる。
「ありがとう。すぐ買ってくるね」
「うん……」
手を放した瞬間、急に恥ずかしくなってきて俯いてしまった。むしろ塗っている時の方が、作業に集中することができたからよかった。
出発時刻になり電車が動く。揺らされて変な気まずさを振り払えた。でも赤面した表情は変わらない。
「大学、どう?」
俯いたまま聞く。
「うん……楽しいかな……未砂はどう?」
『楽しい』の箇所に気持ちは感じられなかった。宏紀の本心は違うところにあるような気がする。でも宏紀に問いかけられてそれは覆い隠された。
「楽しいよ。宏紀たちにも出会えたし、行ってよかったよ」
自分自身でいることが難しい時もあるけど、宏紀や七海と出会えたことは、私の人生の宝物だ。それははっきりと声を大にして言える。
「そっか。良かった……長い時間かけて通う意味があるなら……」
「宏紀は……そうじゃないの?」
聞いていいかどうか分からなかったけど、声に力がない宏紀を気遣ったつもりだ。
「そんなことない。まだ慣れないから、必死って言うか、何ていうか……」
言い訳のように聞こえるけど、宏紀の言葉を額面通り受けておく。
「そっか。じゃあ、気分転換しようよ。帰る時に、色々寄り道したりして」
「そうだね……」
頷きながら笑ってくれたけど、何かに力を吸い取られている宏紀の今がある。
「映画とか観るの?」
「観るよ。最近はあまり行ってないけど、見たい映画があるときは映画館で」
「そうなんだ。じゃあ、今度一緒に行こうよ! もちろん、観たい映画があったら……だけど」
「うん。行きたい」
ささやくような声量だけど、宏紀は懸命に返事をしてくれいる感じだった。
「やった!」
響き渡る場所を制限して、私は小さくそう言った。本当は飛び上がって喜びたいところだけど、テンションを宏紀の目線にまで持っていった。
「何か観たい映画があるの?」
「うん。いくつかあるんだけど……宏紀が好きかどうか分からないから、一緒に選んで」
流れで映画の話を持ち出したから特に観たい映画はない。
「未砂が観たい映画でいいよ。だいたいどのジャンルでも観れるから」
「じゃあ」
多分、今なら気分が高揚するような楽しい映画がいいかもしれない。恋愛映画は恥ずかしくて見られないだろうし、宏紀がさらにしんみりして孤独な世界に入り込んでしまいそうだから。ホラーは私が苦手だから選択肢には入れない。
「未砂、誘ってくれてありがとう」
「えっ?」
「いや、何でもない。映画楽しみだね」
ちゃんと聞こえていた。普通のお礼だけど、でもなぜが気になる。裏返したら何か重要なことが隠されているような気がした。でも今は裏返す勇気はない。
私の勘違いかもしれないけど、宏紀の目元に薄っすら光るものがあった。