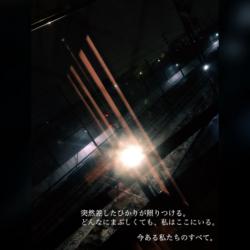私、宏紀、沙織の三人は何でもない話で盛り上がっていた。
宏紀は次に講義があるから席を立った。私と沙織は次の講義はないからゆっくりできる。沙織は私とほぼ私と同じスケジュールを組んだのでだいたい私の隣には沙織がいるだろう。そんな友達が早々できたことが私は嬉しい。
「じゃあ、講義行ってくるね」
「お昼ごはんの後って眠くない?」
宏紀は朝早く起きて通学しているからお昼の後は辛いだろう。私なら講義開始三分で眠りの世界に引き込まれそうだ。いや、三分ももたないかもしれない。
「眠いよ。でもなんとか起きてるよ。授業料も無駄になってしまうから」
目を見開いて宏紀はその場を後にした。
宏紀の姿が学食から消えるまで、後ろ姿を追う沙織。宏紀がいなくなったのをいいことに、少しだけ力を抜いて背もたれに身を任せた私。
「未砂、宏紀君のこと……気になる感じ?」
沙織が少しだけ回りくどく言った。間違っていたらどうしようという気持ちが先行したんだろう、そういう聞き方になったみたいだ。
「……どうして?」
「いや、なんとなく……間違ってたらごめんね」
私の真面目な反応から不穏な空気を感じ取ったのか、沙織はそう言った。今はいいタイミングではないっていう判断だったんだろう。
このままにしてたら、沙織に窮屈な気持ちにさせて終わりのような気がした。
「好きだよ……宏紀のこと」
沙織と目を合わさずに言った。意味もなくトレイを見つめながら。恥ずかしそうに語る自分の顔を見られるのがただ気まずかった。
「やっぱり」
「はずかしくて、言うのを迷ってた」
「そうなの? 未砂にも恥ずかしいとかあるんだね」
半笑いでからかうように沙織は言った。そこにさらに、「オリエンテーションの時に、気軽に話してくれた未砂だから、そう言うのはないかなって思ってた」
「あれは大丈夫。沙織も気軽に私と話してくれたから。嬉しかったよ」
宏紀も大事にした方が良いって言ってくれた私の話しやすさと親しみやすさ。今はそれを大事にしているから沙織にも感謝ができる。
「私も嬉しかったよ」
この言葉であの時の行動は、すべて救われるんだ。
「本当?」
少し泣きそうな目で私は沙織を見つめた。今度は沙織に泣かされる番だ。
「うん。まぁでも、好きって言うのは恥ずかしいよね。分かるよ、未砂の気持ち」
「ありがとう……なんか七海ちゃんと、自ずと比べてしまう自分がいて」
「宏紀君、七海ちゃんと仲いいよね。中学の同級生なんでしょ?」
私はただ首を縦に動かした。私にとってはどう頑張っても埋められない七海との差だ。それが先行して私を揺さぶってくる。
「それは仕方ないよ。前からお互いのこと知ってるから。それは気にしなくていいよ。未砂はこれから宏紀君と仲を作っていけば」
「そうだね……」
これがコンプレックスっていうものなんだろう。
「私は応援してるから。陰ながら」
もたれていた背中を起こして私は沙織の肩に触れて、「表立って応援してくれないの?」
「陰ながら」
首を振って沙織は否定した。
「全然表立っていいよ」
「それはいい」
私たちはおどけていった。宏紀への思い、七海への劣等感を知る人がこんなにも近くにいることに私は安心感を覚える。表立たなくてもいい。気持ちを共有してくれるだけで。
土曜日の横浜駅付近。
宏紀と真也は家電量販店にいた。真也が実家から持ってきていた掃除機が壊れてしまって代わりの新品を買いに来た。ついでに空気清浄機やスタンドライトも見たいらしい。一人で行くのは気が引けた真也は宏紀を誘った。わざわざ横浜まで出てきたのは、真也が一度行ってみたかったらしい。私と宏紀はここに住んでるからただの人の多い場所だけど、真也にとっては新鮮な場所みたいだ。
「ありがとう、一緒に来てくれて」
掃除機のラインナップを眺めながら真也が言った。
「いいよ。横浜だったら近いし、今日はバイトもないから家で少し勉強しようとかなって思ってたから」
横浜なら港南台から二十分ぐらい。磯子なら十五分ぐらい。
「大学の勉強? すごいな、週末に勉強するなんて」
「うん。せっかく大学に入ったし、せっかく授業料払ってもらっているから頑張ろうと思って」
「すごいな。みんなすごい」
「みんな?」
宏紀のことだけでなくほかに含まれている人が気になった。
「七海ちゃんとか」
宏紀は『七海』という言葉に敏感に反応した。確かに七海はすごい。でもその理由が気になるだろう。
「一人暮らし頑張るって。僕もこっちでの生活は大丈夫かなって思っていたけど、僕も何とか頑張ろうかと思って」
目の前にあるお値打ちの掃除機に触れた真也。
「ああ……そういうことか」
「まさか僕が、掃除機を買うなんて思ってもみなかった」
思い入れのある掃除機を見るように真也がノズル辺りに視線を集めた。
宏紀には七海の言葉の意味が透けて見えているだろう。高校時代に別れた彼氏に自分は大人になっている姿を見せたい。だから一人暮らしぐらいできる、一人でも難なく生活ができるって。どこかで会った時に、変わった姿を見せたいのかもしれない。一時期の恋だったかもしれないけど、七海にとっては相当なインパクトを残した恋だったみたいだ。
意味もなく宏紀は掃除機の値段を見つめる。不意に七海のことを考えると、ブラインドガラスのように宏紀を映し出す。今はぼやけて見える。
「宏紀!」
「ん?」
七海のことを考えるとどこまでも奥へ入り込むみたいだ。そんな奥まで入って身を隠すことはない。
「どうした? ボーっとしてたけど」
「何でもない……これ結構高いなって思って」
「ああ、これは買えないな」
プライスタグを自分に引き寄せて真也が言った。
「あと、ホットサンドメーカーも見たいな」
値段に圧倒されたのか真也は踵を返して、次にキッチン用品のコーナーへと足を運ぶ。
「いいよ。自炊もしないとね」
「うん。七海ちゃんもやっているみたいだし、頑張らないと」
また七海の名前が出てきた。七海には不思議な影響力があるのか。
「七海と争ってるんじゃないから真也のペースでいいんじゃない?」
宏紀は先輩のように真也を後輩のようにたしなめた。
「まぁ、そうなんだけど……親に電話して泣いてる自分が情けなくなってさ」
苦笑しながら言う真也を見た宏紀。自分で自分を少しだけ嘲笑っている真也が宏紀は心配にした。確かに何も分からない場所で暮らすって、学生とはいえども辛いことかもしれない。よほど家が嫌いだったり、何の思い入れもないなら別だけど。
「もし辛くなったら、話そうよ、真也。僕はだいたい暇だから」
宏紀と真也の状況を比べればまだ余裕がある。宏紀は本当に優しい。
「マジで? 頼りにしているよ、宏紀」
お互いに目を合わせて微笑み合った。真也の胸中に宿る不安は完ぺきではないかもしれないけど、軽くなっただろう。宏紀の優しさに、私も心を温められる。
「宏紀……」
真也はホットサンドメーカーを眺める。色は白と黒と赤。自然と赤が真也の目を赤に染める。言葉を決して失っているわけではないと思うけど、真也は赤を携えて神妙な顔でホットサンドメーカーを見つめている。そこまで見られると、人だったらはずかしいだろうけど、モノなら燃え上がってしまいそうだ。
横目で宏紀は真也を一瞥する。まさかそんなに強い目力だとは、宏紀は思っていないだろう。
「どうした?」
宏紀はミキサーを視界に捉えていた。ジュースやスムージーでも作ろうと計画しているのかもしれない。真也がハム、レタス、チーズが挟まったトーストサンドを、宏紀は果物の用いたスムージー。七海や真也のアパートで作れたらいいって思っているのかしれない。
もしそうなら、その時には私も仲間に入れてほしい。沙織も誘いたい。
「……」
口を紡いだ真也がいた。
「何だよ?」
宏紀は何も答えない真也に先回りした。名前を呼ばれて何もないことはない。
「やっぱりいいや」
この場の雰囲気を取り繕うように真也は笑った。ここで新しい何かを切り裂いても意味がないって思ったのだろうか。
「何だよ? 言いかけてやめるなよ」
真也に軽く抗議をする宏紀。確かにこの収め方は気になる。
「悪い、また言うわ。今はいいタイミングじゃないかなって……」
いいタイミングって何だろうって、宏紀は思っていると思う。タイミングを計るような出来事はなかったはずだ。
「そうか。また教えて」
「うん」
ひとまずそう言ってくれた宏紀に真也は安堵した。感謝にも似た安堵って感じ。
宏紀に打ち明けたい何かがある。内容はどうであれ、宏紀は真也を助けたいって、思っているだろう。
宏紀は次に講義があるから席を立った。私と沙織は次の講義はないからゆっくりできる。沙織は私とほぼ私と同じスケジュールを組んだのでだいたい私の隣には沙織がいるだろう。そんな友達が早々できたことが私は嬉しい。
「じゃあ、講義行ってくるね」
「お昼ごはんの後って眠くない?」
宏紀は朝早く起きて通学しているからお昼の後は辛いだろう。私なら講義開始三分で眠りの世界に引き込まれそうだ。いや、三分ももたないかもしれない。
「眠いよ。でもなんとか起きてるよ。授業料も無駄になってしまうから」
目を見開いて宏紀はその場を後にした。
宏紀の姿が学食から消えるまで、後ろ姿を追う沙織。宏紀がいなくなったのをいいことに、少しだけ力を抜いて背もたれに身を任せた私。
「未砂、宏紀君のこと……気になる感じ?」
沙織が少しだけ回りくどく言った。間違っていたらどうしようという気持ちが先行したんだろう、そういう聞き方になったみたいだ。
「……どうして?」
「いや、なんとなく……間違ってたらごめんね」
私の真面目な反応から不穏な空気を感じ取ったのか、沙織はそう言った。今はいいタイミングではないっていう判断だったんだろう。
このままにしてたら、沙織に窮屈な気持ちにさせて終わりのような気がした。
「好きだよ……宏紀のこと」
沙織と目を合わさずに言った。意味もなくトレイを見つめながら。恥ずかしそうに語る自分の顔を見られるのがただ気まずかった。
「やっぱり」
「はずかしくて、言うのを迷ってた」
「そうなの? 未砂にも恥ずかしいとかあるんだね」
半笑いでからかうように沙織は言った。そこにさらに、「オリエンテーションの時に、気軽に話してくれた未砂だから、そう言うのはないかなって思ってた」
「あれは大丈夫。沙織も気軽に私と話してくれたから。嬉しかったよ」
宏紀も大事にした方が良いって言ってくれた私の話しやすさと親しみやすさ。今はそれを大事にしているから沙織にも感謝ができる。
「私も嬉しかったよ」
この言葉であの時の行動は、すべて救われるんだ。
「本当?」
少し泣きそうな目で私は沙織を見つめた。今度は沙織に泣かされる番だ。
「うん。まぁでも、好きって言うのは恥ずかしいよね。分かるよ、未砂の気持ち」
「ありがとう……なんか七海ちゃんと、自ずと比べてしまう自分がいて」
「宏紀君、七海ちゃんと仲いいよね。中学の同級生なんでしょ?」
私はただ首を縦に動かした。私にとってはどう頑張っても埋められない七海との差だ。それが先行して私を揺さぶってくる。
「それは仕方ないよ。前からお互いのこと知ってるから。それは気にしなくていいよ。未砂はこれから宏紀君と仲を作っていけば」
「そうだね……」
これがコンプレックスっていうものなんだろう。
「私は応援してるから。陰ながら」
もたれていた背中を起こして私は沙織の肩に触れて、「表立って応援してくれないの?」
「陰ながら」
首を振って沙織は否定した。
「全然表立っていいよ」
「それはいい」
私たちはおどけていった。宏紀への思い、七海への劣等感を知る人がこんなにも近くにいることに私は安心感を覚える。表立たなくてもいい。気持ちを共有してくれるだけで。
土曜日の横浜駅付近。
宏紀と真也は家電量販店にいた。真也が実家から持ってきていた掃除機が壊れてしまって代わりの新品を買いに来た。ついでに空気清浄機やスタンドライトも見たいらしい。一人で行くのは気が引けた真也は宏紀を誘った。わざわざ横浜まで出てきたのは、真也が一度行ってみたかったらしい。私と宏紀はここに住んでるからただの人の多い場所だけど、真也にとっては新鮮な場所みたいだ。
「ありがとう、一緒に来てくれて」
掃除機のラインナップを眺めながら真也が言った。
「いいよ。横浜だったら近いし、今日はバイトもないから家で少し勉強しようとかなって思ってたから」
横浜なら港南台から二十分ぐらい。磯子なら十五分ぐらい。
「大学の勉強? すごいな、週末に勉強するなんて」
「うん。せっかく大学に入ったし、せっかく授業料払ってもらっているから頑張ろうと思って」
「すごいな。みんなすごい」
「みんな?」
宏紀のことだけでなくほかに含まれている人が気になった。
「七海ちゃんとか」
宏紀は『七海』という言葉に敏感に反応した。確かに七海はすごい。でもその理由が気になるだろう。
「一人暮らし頑張るって。僕もこっちでの生活は大丈夫かなって思っていたけど、僕も何とか頑張ろうかと思って」
目の前にあるお値打ちの掃除機に触れた真也。
「ああ……そういうことか」
「まさか僕が、掃除機を買うなんて思ってもみなかった」
思い入れのある掃除機を見るように真也がノズル辺りに視線を集めた。
宏紀には七海の言葉の意味が透けて見えているだろう。高校時代に別れた彼氏に自分は大人になっている姿を見せたい。だから一人暮らしぐらいできる、一人でも難なく生活ができるって。どこかで会った時に、変わった姿を見せたいのかもしれない。一時期の恋だったかもしれないけど、七海にとっては相当なインパクトを残した恋だったみたいだ。
意味もなく宏紀は掃除機の値段を見つめる。不意に七海のことを考えると、ブラインドガラスのように宏紀を映し出す。今はぼやけて見える。
「宏紀!」
「ん?」
七海のことを考えるとどこまでも奥へ入り込むみたいだ。そんな奥まで入って身を隠すことはない。
「どうした? ボーっとしてたけど」
「何でもない……これ結構高いなって思って」
「ああ、これは買えないな」
プライスタグを自分に引き寄せて真也が言った。
「あと、ホットサンドメーカーも見たいな」
値段に圧倒されたのか真也は踵を返して、次にキッチン用品のコーナーへと足を運ぶ。
「いいよ。自炊もしないとね」
「うん。七海ちゃんもやっているみたいだし、頑張らないと」
また七海の名前が出てきた。七海には不思議な影響力があるのか。
「七海と争ってるんじゃないから真也のペースでいいんじゃない?」
宏紀は先輩のように真也を後輩のようにたしなめた。
「まぁ、そうなんだけど……親に電話して泣いてる自分が情けなくなってさ」
苦笑しながら言う真也を見た宏紀。自分で自分を少しだけ嘲笑っている真也が宏紀は心配にした。確かに何も分からない場所で暮らすって、学生とはいえども辛いことかもしれない。よほど家が嫌いだったり、何の思い入れもないなら別だけど。
「もし辛くなったら、話そうよ、真也。僕はだいたい暇だから」
宏紀と真也の状況を比べればまだ余裕がある。宏紀は本当に優しい。
「マジで? 頼りにしているよ、宏紀」
お互いに目を合わせて微笑み合った。真也の胸中に宿る不安は完ぺきではないかもしれないけど、軽くなっただろう。宏紀の優しさに、私も心を温められる。
「宏紀……」
真也はホットサンドメーカーを眺める。色は白と黒と赤。自然と赤が真也の目を赤に染める。言葉を決して失っているわけではないと思うけど、真也は赤を携えて神妙な顔でホットサンドメーカーを見つめている。そこまで見られると、人だったらはずかしいだろうけど、モノなら燃え上がってしまいそうだ。
横目で宏紀は真也を一瞥する。まさかそんなに強い目力だとは、宏紀は思っていないだろう。
「どうした?」
宏紀はミキサーを視界に捉えていた。ジュースやスムージーでも作ろうと計画しているのかもしれない。真也がハム、レタス、チーズが挟まったトーストサンドを、宏紀は果物の用いたスムージー。七海や真也のアパートで作れたらいいって思っているのかしれない。
もしそうなら、その時には私も仲間に入れてほしい。沙織も誘いたい。
「……」
口を紡いだ真也がいた。
「何だよ?」
宏紀は何も答えない真也に先回りした。名前を呼ばれて何もないことはない。
「やっぱりいいや」
この場の雰囲気を取り繕うように真也は笑った。ここで新しい何かを切り裂いても意味がないって思ったのだろうか。
「何だよ? 言いかけてやめるなよ」
真也に軽く抗議をする宏紀。確かにこの収め方は気になる。
「悪い、また言うわ。今はいいタイミングじゃないかなって……」
いいタイミングって何だろうって、宏紀は思っていると思う。タイミングを計るような出来事はなかったはずだ。
「そうか。また教えて」
「うん」
ひとまずそう言ってくれた宏紀に真也は安堵した。感謝にも似た安堵って感じ。
宏紀に打ち明けたい何かがある。内容はどうであれ、宏紀は真也を助けたいって、思っているだろう。