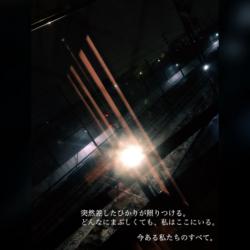第二限目の講義前に、私は宏紀、真也、沙織の三人と生活環境学部の一階のロビーで談笑していた。沙織と真也は以前まではただの顔見知りだったが、私と宏紀がお互いの友人を紹 介しあった事で、晴れて全員が友達になった。
何気に宏紀のことを呼び捨てするのが恥ずかしくて、名前を言うのは避けていたけど、流れで口にしてしまった。自分から言い出しておいて、恥ずかしいって。
それを聞いた沙織と真也は目を見合わせて、私たちの仲の進展具合に目を見張る。真也は半笑いで宏紀を見つめて、沙織は一歩だけさりげなく後退して私たちを眺めた。私と宏紀の関係をよりクリアに見れるのか。
入り口のドアが開く。私は少しだけ体を逸らして視線を送る。
背の高いパンツの似合いそうな女の子が入ってきた。七海の姿だった。立っている姿を見たことがなかった私は七海に釘付けになった。
「おはよう」
宏紀はそう挨拶して、視線が私を通り越して七海に向かう。
私も宏紀と同じように伸びた視線を辿る。
「おはよう」
七海は手を振る。少しだけ疲労感が見えるけど、七海は笑顔を絶やさない。
「バイトどうだった?」
宏紀が誰よりも早く先手を取った。
「疲れた。慣れていないから疲れちゃった。でも楽しかったけど」
瞬きをせずに七海と宏紀を見つめる。
何とか乗り遅れないように私は、「どこでバイトしているの? 七海ちゃん?」
「新浦安駅の中にある喫茶店、分かる?」
「分かる!」
「改札の近くにあるとこ。通学で通るよね」
宏紀が説明をフォローしてくれた。でもこれは私のためというよりは、七海へのフォローだろう。
「うん……」
「そこでやってるよ」
七海は宏紀の言葉に頷きながらそう言った。
「そうなんだ? 今度行ってみたいな。七海ちゃんがいる時に」
真也も会話の隙間に足を踏み入れてきた。
「今は仕事できないから、慣れたら来ていいよ」
苦笑いしながら七海は手を横に振った。七海の気持ちはよく分かる。でも私だったら、慣れてなくても来てって言っていたと思う。
「すぐ覚えられるでしょ? 七海、飲み込み早そうだよね」
中学時代の真面目さや、人当たりの良さで乗り切れると思ったのだろう、宏紀は自信をのぞかせて言った。
「なんとかするよ。生活もかかってるから」
下宿組の七海、真也と沙織は容易に親には頼れないから切実だ。私たち実家組は親と生活しているから楽なのに、七海が羨ましい。大変なことをしているのに。大学、バイトや人間関係を平行線で取り組んでいくのに。はるかに私の方が楽なはずなのに。
「でも無理しないでよ。体調崩したら元も子もないから」
七海を思いやる宏紀。真剣でも優しい真差しがあった。
私の表情が徐々に曇ってくる。でもそれを出さないように見えないワイパーで曇りを消していく。
沙織が私と距離を縮めて手に触れてきた。
突然のことで沙織を見つめると、何も言わずに沙織は笑顔で私を迎えてくれた。
「そうだな。少しずつやって、慣れたら良いんじゃない」
真也が宏紀に同意した。いずれ自分の身にふりかかることだから、真也も声をかけたのだろう。
「七海ちゃん、喫茶店の制服、似合いそうだね」
私はどこまでも自分で自分に罠をかけてしまう。七海のアパートに行った帰りに、自ら墓穴を掘るような質問をしてしまった時と同じように。
「ありがとう。時給がいいのもあるんだけど、あの制服着たいのもあったんだ」
「どんなのだっけ?」
宏紀も興味津々だ。七海が着ているとなればなおさらだろう。
「普通に白いシャツで黒のスカートって感じなんだけど……まぁ、今度見に来てよ」
宏紀は首を縦に振った。普通に嬉しいだろう、七海の言葉からそんなことを言われたら。
「コーヒー飲めないんだけど、コーラとかあるよね?」
恥ずかしそうに宏紀はそう言った。
「全然あるよ。あるに決まってるじゃん!」
七海は極めて冷静に宏紀に言った。
「何言ってるんだよ、宏紀!」
真也も七海に便乗して、宏紀の肩をポンと触れた。
「そうだよね」
もうすぐ講義が始まる。私たちは三階の講義室へと準備する。
私は少しだけかき乱された心を整えようと努める。
この胸の苦しみは、宏紀には分からないだろう。気にしなければいいんだけど、それができないんだ。胸に手を当てる。今なら沙織が手に触れてくれているから容易に自分を取り戻せそうだ。
助けてくれた沙織を私は笑顔で見つめる。沙織も何も言わずに笑ってくれた。いつもの自分を取り戻せそうだ。
第二限目の講義が十分ほど早く終わった。
私たち五人はお腹の虫を響かせながら一階の学生食堂に向かった。言うまでもなく満席で学食の隅の方で待機させられる。二限目の担当の非常勤講師の先生が、「みんな、ゆっくりご飯食べたいですよね? もう今日はここで終わりにしようか」と言ってくれたのに効果はなかった。でも配慮には感謝している。
「はぁ、お腹空いた」
私は人であふれるテーブルを見つめながら言った。
「未砂、お腹鳴ってたよね?」と沙織。
「バレた? 気付かれないようにしてたのに」
私は顔を少し赤くして下を向いた。
「シーンとしていると抑えても聞こえちゃうよね」
宏紀が共感を示してくれた。
私は「うんうん」と頷いて、「宏紀、もしかして、聞こえた?」
「それはない。席離れてたから」
席を一途に探していると、宏紀、沙織と私のグループと、七海と真也のペアとはぐれてしまっていた。
「未砂ちゃん、かわいいよね」
七海がそう呟いた。ドキッとしたけど、そんなことはない。でもせっかくほめてくれているから素直に受け取っておく。
「うん。なんかあの明るい感じが良いよね」
真也も七海に同調した。
「宏紀のこと、気になってるみたいだよ」
七海は宏紀を少しからかうように言った。私は分かりやすいみたいで、七海には私の心の中は透けて見えるようだ。
「マジで? 未砂ちゃんって、みんなに対等に接している感じあるから気がつかなかった」
同性にしか分からない気持ちがあるのかもしれない。確かに私は素直に自分の気持ちをぶつけるタイプだ。
「分からないけど、なんかそんな感じがあるかなって。多分、宏紀は鈍感だから気づいているかどうか分からないけど」
「そんな感じなんだ、宏紀って」
宏紀の目の前で席が空いた。私と沙織の圧力を感じたのかきれいに三席空いた。
私たち三人は七海と真也を申し訳なさそうに見た。
七海と真也は手を使って「遠慮なくどうぞ」と表現した。
私たちはそれを七海たちの気遣いと捉えて席を確保した。
宏紀は、七海と共に昼食の時間を過ごしたかったかもしれない。でもここまで来たら、わざわざここを離れることはできないだろう。私の見えない手が、宏紀を掴んでいるようだ。
七海は体をそらすと、カウンター席が二席空いた。
真也と七海は目を見合わせた。何も言わなくても今二人がしなければならないことは明確だ。二人は駆け足でカウンターへ突進していく。カウンター近くにあるエサを生きるために奪いに行く動物のように。
カウンター前でスピードを緩めて、少し乱暴に七海は自分の荷物を置いた。七海でもこんなスピード感に溢れることもあるんだ。穏やかな雰囲気からは想像もつかない。
「よし!」
七海が小さくガッツポーズを決めた。それにつられて真也も拳を握った。
「ご飯食べる準備だけでひと苦労だね」
「本当だね」
七海と真也は食券を買って、七海はきつねうどん、真也はカレーライスを手にして席に着いた。
「真也君、小食なの? それで足りる?」
トレイの中央に寂しそうに位置するカレーライスを見ていった。がっしりとした体格じゃない上に小食だと誰でも心配になりそうだ。
「大丈夫だよ。本当はもっと食べたいけど、今はお金ないから」
真也も一人暮らしをしているからお金の面に厳しいようだ。
「そうだよね。真也君もアルバイトするの?」
「いずれは。でも今はしないと思う。そこまで余裕ないから」
「そうだよね」
七海は真也に共感しながら、始めてしまったカフェでのアルバイトは早すぎたかなって思っているかもしれない。
「でもそう考えると、七海ちゃんはすごいね。もうバイトし始めてるし、自炊もしているもんね」
スーパーに行く途中で七海と遭遇した時のことを思い出す真也。そして今日耳にしたカフェのバイト。真也には七海がアクティブな感じに写っているだろう。
「うん……最初が肝心だからね」
顔を縦に振って頷く七海は、穏やかなきれいな顔に力強さを添えて言った。一点を集中的に見ている七海。
「すごいな」
「いや、そんなことないよ。私、大学の四年間はここでなんとか頑張ろうと思ってて」
一時的に添えた力強さを脇に置いて七海は、うどんをひとすじ食べた。
「そうなんだ」
真也も七海に合わせるようにカレーを口に運んだ。
「うん……自分で決めて一人暮らしし始めたから。今まではお母さんとか色々な人に影響を受けて何かを決めてきたけど、自分で決めたことだしここで頑張りたい。だから、バイトとかも早いって思ったけど、早々始めたんだ」
真也はただ頷いて七海の言葉に耳を傾けた。
「進路の話とかも出てきて、色々決めなきゃいけないことがあるのに一人で何もできなくて、時間だけが過ぎていくだけみたいな。そういう自分が嫌だなって思って」
「なるほどね」
「だからこれからは自分でちゃんと決められるようになりたい」
「すごいね。まさか、そんなに奥深い話だとは思わなかった」
「そんな深くもないよ……でも自分の道は自分で作りたいなって」
どこか恥ずかしそうに七海は言った。突然溢れ出す思いに歯止めが利かなくなって語ってしまった自分に顔を赤くしているんだろう。七海は、本当は気持ちの熱い人なのかもしれない。決めたことはとことんやり抜く人なんだろう。
「なんか、七海ちゃんのプライドって感じだね」
「どういうこと?」
口を紡いで真也は頭で言葉をとりつくろう。真也も自分で言ったけど、考えはまとまっていないようだ。
「なんていうか、強い気持ちというか、モットーって言うか……迷ったときに自分を見失わない強い気持ち……それが七海ちゃんのプライド……ごめん、分からなくなった」
真也はまとめようとしたけど、無理だったみたいだ。自分の言った言葉を煙に巻いて、目の前にいる七海を視界に入れた。
「ふふん、でもなんとなく分かるよ、真也君の言いたいこと」
七海は真也の言葉の要点を拾って七海なりに繋ぎ合わせた。
「すごいね。そこまで考えてここに来たんだね。僕は、ここでうまくやっていけるかどうかからのスタートだから。今も寂しいなって思うことが多くて、親に電話してるし」
「それは私も同じだよ。寂しいけど、頑張るよ」
不安を笑顔でかき消すように言った。
「何か困ったことがあったら、教えて。何かできるか分からないけど、近くに住んでるし協力できることはするから」
七海は少しだけ不安を押しのけてくれた真也の言葉に笑顔を見せて、「ありがとう」と言った。
「でも、しばらくは自分で頑張る!」
「プライドで頑張ろう!」
二人は拳を握って、うどんとカレーライスをそれぞれ食べた。
何気に宏紀のことを呼び捨てするのが恥ずかしくて、名前を言うのは避けていたけど、流れで口にしてしまった。自分から言い出しておいて、恥ずかしいって。
それを聞いた沙織と真也は目を見合わせて、私たちの仲の進展具合に目を見張る。真也は半笑いで宏紀を見つめて、沙織は一歩だけさりげなく後退して私たちを眺めた。私と宏紀の関係をよりクリアに見れるのか。
入り口のドアが開く。私は少しだけ体を逸らして視線を送る。
背の高いパンツの似合いそうな女の子が入ってきた。七海の姿だった。立っている姿を見たことがなかった私は七海に釘付けになった。
「おはよう」
宏紀はそう挨拶して、視線が私を通り越して七海に向かう。
私も宏紀と同じように伸びた視線を辿る。
「おはよう」
七海は手を振る。少しだけ疲労感が見えるけど、七海は笑顔を絶やさない。
「バイトどうだった?」
宏紀が誰よりも早く先手を取った。
「疲れた。慣れていないから疲れちゃった。でも楽しかったけど」
瞬きをせずに七海と宏紀を見つめる。
何とか乗り遅れないように私は、「どこでバイトしているの? 七海ちゃん?」
「新浦安駅の中にある喫茶店、分かる?」
「分かる!」
「改札の近くにあるとこ。通学で通るよね」
宏紀が説明をフォローしてくれた。でもこれは私のためというよりは、七海へのフォローだろう。
「うん……」
「そこでやってるよ」
七海は宏紀の言葉に頷きながらそう言った。
「そうなんだ? 今度行ってみたいな。七海ちゃんがいる時に」
真也も会話の隙間に足を踏み入れてきた。
「今は仕事できないから、慣れたら来ていいよ」
苦笑いしながら七海は手を横に振った。七海の気持ちはよく分かる。でも私だったら、慣れてなくても来てって言っていたと思う。
「すぐ覚えられるでしょ? 七海、飲み込み早そうだよね」
中学時代の真面目さや、人当たりの良さで乗り切れると思ったのだろう、宏紀は自信をのぞかせて言った。
「なんとかするよ。生活もかかってるから」
下宿組の七海、真也と沙織は容易に親には頼れないから切実だ。私たち実家組は親と生活しているから楽なのに、七海が羨ましい。大変なことをしているのに。大学、バイトや人間関係を平行線で取り組んでいくのに。はるかに私の方が楽なはずなのに。
「でも無理しないでよ。体調崩したら元も子もないから」
七海を思いやる宏紀。真剣でも優しい真差しがあった。
私の表情が徐々に曇ってくる。でもそれを出さないように見えないワイパーで曇りを消していく。
沙織が私と距離を縮めて手に触れてきた。
突然のことで沙織を見つめると、何も言わずに沙織は笑顔で私を迎えてくれた。
「そうだな。少しずつやって、慣れたら良いんじゃない」
真也が宏紀に同意した。いずれ自分の身にふりかかることだから、真也も声をかけたのだろう。
「七海ちゃん、喫茶店の制服、似合いそうだね」
私はどこまでも自分で自分に罠をかけてしまう。七海のアパートに行った帰りに、自ら墓穴を掘るような質問をしてしまった時と同じように。
「ありがとう。時給がいいのもあるんだけど、あの制服着たいのもあったんだ」
「どんなのだっけ?」
宏紀も興味津々だ。七海が着ているとなればなおさらだろう。
「普通に白いシャツで黒のスカートって感じなんだけど……まぁ、今度見に来てよ」
宏紀は首を縦に振った。普通に嬉しいだろう、七海の言葉からそんなことを言われたら。
「コーヒー飲めないんだけど、コーラとかあるよね?」
恥ずかしそうに宏紀はそう言った。
「全然あるよ。あるに決まってるじゃん!」
七海は極めて冷静に宏紀に言った。
「何言ってるんだよ、宏紀!」
真也も七海に便乗して、宏紀の肩をポンと触れた。
「そうだよね」
もうすぐ講義が始まる。私たちは三階の講義室へと準備する。
私は少しだけかき乱された心を整えようと努める。
この胸の苦しみは、宏紀には分からないだろう。気にしなければいいんだけど、それができないんだ。胸に手を当てる。今なら沙織が手に触れてくれているから容易に自分を取り戻せそうだ。
助けてくれた沙織を私は笑顔で見つめる。沙織も何も言わずに笑ってくれた。いつもの自分を取り戻せそうだ。
第二限目の講義が十分ほど早く終わった。
私たち五人はお腹の虫を響かせながら一階の学生食堂に向かった。言うまでもなく満席で学食の隅の方で待機させられる。二限目の担当の非常勤講師の先生が、「みんな、ゆっくりご飯食べたいですよね? もう今日はここで終わりにしようか」と言ってくれたのに効果はなかった。でも配慮には感謝している。
「はぁ、お腹空いた」
私は人であふれるテーブルを見つめながら言った。
「未砂、お腹鳴ってたよね?」と沙織。
「バレた? 気付かれないようにしてたのに」
私は顔を少し赤くして下を向いた。
「シーンとしていると抑えても聞こえちゃうよね」
宏紀が共感を示してくれた。
私は「うんうん」と頷いて、「宏紀、もしかして、聞こえた?」
「それはない。席離れてたから」
席を一途に探していると、宏紀、沙織と私のグループと、七海と真也のペアとはぐれてしまっていた。
「未砂ちゃん、かわいいよね」
七海がそう呟いた。ドキッとしたけど、そんなことはない。でもせっかくほめてくれているから素直に受け取っておく。
「うん。なんかあの明るい感じが良いよね」
真也も七海に同調した。
「宏紀のこと、気になってるみたいだよ」
七海は宏紀を少しからかうように言った。私は分かりやすいみたいで、七海には私の心の中は透けて見えるようだ。
「マジで? 未砂ちゃんって、みんなに対等に接している感じあるから気がつかなかった」
同性にしか分からない気持ちがあるのかもしれない。確かに私は素直に自分の気持ちをぶつけるタイプだ。
「分からないけど、なんかそんな感じがあるかなって。多分、宏紀は鈍感だから気づいているかどうか分からないけど」
「そんな感じなんだ、宏紀って」
宏紀の目の前で席が空いた。私と沙織の圧力を感じたのかきれいに三席空いた。
私たち三人は七海と真也を申し訳なさそうに見た。
七海と真也は手を使って「遠慮なくどうぞ」と表現した。
私たちはそれを七海たちの気遣いと捉えて席を確保した。
宏紀は、七海と共に昼食の時間を過ごしたかったかもしれない。でもここまで来たら、わざわざここを離れることはできないだろう。私の見えない手が、宏紀を掴んでいるようだ。
七海は体をそらすと、カウンター席が二席空いた。
真也と七海は目を見合わせた。何も言わなくても今二人がしなければならないことは明確だ。二人は駆け足でカウンターへ突進していく。カウンター近くにあるエサを生きるために奪いに行く動物のように。
カウンター前でスピードを緩めて、少し乱暴に七海は自分の荷物を置いた。七海でもこんなスピード感に溢れることもあるんだ。穏やかな雰囲気からは想像もつかない。
「よし!」
七海が小さくガッツポーズを決めた。それにつられて真也も拳を握った。
「ご飯食べる準備だけでひと苦労だね」
「本当だね」
七海と真也は食券を買って、七海はきつねうどん、真也はカレーライスを手にして席に着いた。
「真也君、小食なの? それで足りる?」
トレイの中央に寂しそうに位置するカレーライスを見ていった。がっしりとした体格じゃない上に小食だと誰でも心配になりそうだ。
「大丈夫だよ。本当はもっと食べたいけど、今はお金ないから」
真也も一人暮らしをしているからお金の面に厳しいようだ。
「そうだよね。真也君もアルバイトするの?」
「いずれは。でも今はしないと思う。そこまで余裕ないから」
「そうだよね」
七海は真也に共感しながら、始めてしまったカフェでのアルバイトは早すぎたかなって思っているかもしれない。
「でもそう考えると、七海ちゃんはすごいね。もうバイトし始めてるし、自炊もしているもんね」
スーパーに行く途中で七海と遭遇した時のことを思い出す真也。そして今日耳にしたカフェのバイト。真也には七海がアクティブな感じに写っているだろう。
「うん……最初が肝心だからね」
顔を縦に振って頷く七海は、穏やかなきれいな顔に力強さを添えて言った。一点を集中的に見ている七海。
「すごいな」
「いや、そんなことないよ。私、大学の四年間はここでなんとか頑張ろうと思ってて」
一時的に添えた力強さを脇に置いて七海は、うどんをひとすじ食べた。
「そうなんだ」
真也も七海に合わせるようにカレーを口に運んだ。
「うん……自分で決めて一人暮らしし始めたから。今まではお母さんとか色々な人に影響を受けて何かを決めてきたけど、自分で決めたことだしここで頑張りたい。だから、バイトとかも早いって思ったけど、早々始めたんだ」
真也はただ頷いて七海の言葉に耳を傾けた。
「進路の話とかも出てきて、色々決めなきゃいけないことがあるのに一人で何もできなくて、時間だけが過ぎていくだけみたいな。そういう自分が嫌だなって思って」
「なるほどね」
「だからこれからは自分でちゃんと決められるようになりたい」
「すごいね。まさか、そんなに奥深い話だとは思わなかった」
「そんな深くもないよ……でも自分の道は自分で作りたいなって」
どこか恥ずかしそうに七海は言った。突然溢れ出す思いに歯止めが利かなくなって語ってしまった自分に顔を赤くしているんだろう。七海は、本当は気持ちの熱い人なのかもしれない。決めたことはとことんやり抜く人なんだろう。
「なんか、七海ちゃんのプライドって感じだね」
「どういうこと?」
口を紡いで真也は頭で言葉をとりつくろう。真也も自分で言ったけど、考えはまとまっていないようだ。
「なんていうか、強い気持ちというか、モットーって言うか……迷ったときに自分を見失わない強い気持ち……それが七海ちゃんのプライド……ごめん、分からなくなった」
真也はまとめようとしたけど、無理だったみたいだ。自分の言った言葉を煙に巻いて、目の前にいる七海を視界に入れた。
「ふふん、でもなんとなく分かるよ、真也君の言いたいこと」
七海は真也の言葉の要点を拾って七海なりに繋ぎ合わせた。
「すごいね。そこまで考えてここに来たんだね。僕は、ここでうまくやっていけるかどうかからのスタートだから。今も寂しいなって思うことが多くて、親に電話してるし」
「それは私も同じだよ。寂しいけど、頑張るよ」
不安を笑顔でかき消すように言った。
「何か困ったことがあったら、教えて。何かできるか分からないけど、近くに住んでるし協力できることはするから」
七海は少しだけ不安を押しのけてくれた真也の言葉に笑顔を見せて、「ありがとう」と言った。
「でも、しばらくは自分で頑張る!」
「プライドで頑張ろう!」
二人は拳を握って、うどんとカレーライスをそれぞれ食べた。