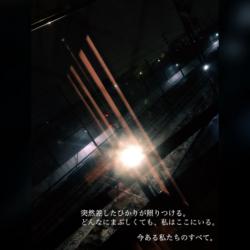宏紀がベッドの前に置かれた小さなテーブルの前で、居心地が悪そうにあぐらをかいている。七海がキッチンでフライパンの上で食べ物を遊ばせている姿を見ている。ご丁寧にエプロンもつけているから宏紀の想像は膨らんでいるだろう。
七海が自炊をしていることを聞いた宏紀が『食べてみたい』と軽いノリで言ったら、七海は宏紀を自分のアパートに招いてくれた。
「今日、泊っていってもいいよ」
ここから二時間かけて帰る宏紀への配慮だったんだろう、七海はそう言った。
願ってもない七海の提案に宏紀は、
「ああ、それはやめとくよ。明日朝からバイトがあるし」
宏紀はこれから間違っても朝からバイトを入れないでおこうと思っていると思う。高校生の時からボーリング場でアルバイトをしていて、大学に入学してからも続けていくつもりだ。
「そうなんだ。残念だな。宏紀なら気にしないのに」
プライパンを上手にかえして、七海は野菜と豚肉を空気に触れさせる。うまくできて笑顔を見せた。
「なんだよ、それ」
「ふふん、冗談だよ」
冗談でも何でもいいと思う。七海と共に時間を刻むことができるなら。
「七海って、得意な料理は何なの?」
「得意なんて言うほど料理してないよ。一人暮らしを始めたから頑張ってやろうと思っているだけだよ」
七海は二人分の野菜炒めをお皿に盛りつけていく。食欲をそそる香りがキッチンから漂い、宏紀の嗅覚を刺激している。
「すごくいい匂い」
「本当? ちょっと待っててね」
見栄えを確認して、七海はシェフとしての自信をのぞかせてから宏紀の前に持ってきた。それに少なめのご飯、みそ汁、塩漬けのキュウリも添えた。
「すごい!」
宏紀が思っていたよりもきちんとしていたからそう声をあげた。
「食べてみて! うまくできたと思う!」
宏紀はさっそく箸を手に取って野菜と豚肉をうまく絡めて口に運ぶと、七海は黙って宏紀の反応を待った。
「おいしいよ、七海、上手だね」
安堵して頬を緩ませて、七海も一口食べた。
「いいね」
親指を立てて、七海は野菜炒めを評価した。少し力強い仕草をしてもかわいい。宏紀もそう思っていると思う。
「今日、未砂ちゃんと話したよ」
七海が唐突に私の名前を出した。今日の実験科目の時のことだ。
「未砂ちゃん? 永井さんのこと?」
「そうそう。なんか、宏紀のこと優しいって言ってたよ」
急に頬を赤に染まらせて、目の前にあった水を飲んだ。喉のあたりで食べ物が詰まったかもしれない。私の推測だと、褒められるのが苦手なんだと思う。
「そんなこと言ってた?」
水の助けを借りて、正常に話せるまでになった宏紀はそう言った。
「うん。宏紀、何したの?」
七海がからかうように言った。一口みそ汁を飲んで宏紀の反応を待つ。
宏紀には心当たりがあるはずだけど、それは見せずに「特に何もしてないよ」と言った。
「嘘だ! じゃなかったら未砂ちゃんがあんなこと言わないよ。宏紀、照れないで言いなさい!」
年上の女性が後輩をいじるように七海は言った。それを甘んじて受ける宏紀。
「いや、別に……人を助けただけだよ、東京駅で」
「えー優しい」
「そんなことないよ。相手はおばあちゃんだから」
そう言ってご飯を乱暴に口に放り込んだ。チラッと七海を見ると、頷きながら宏紀を見ていた。すぐさま目を逸らしてみそ汁を持ち上げた。
「私にも優しくしてね」
「してなかったっけ?」
口に運ぶ豚肉を見つめて宏紀は言った。そんなぶっきらぼうな態度だったかと思って、宏紀は過去の記憶をたどった。中学の時のことなんて、そこまで細かく覚えてないだろう。
「してないじゃない」
七海はおどけていった。
「してるよ」
宏紀も嬉しそうに笑っている。こんな風に七海と会話できるのは、宏紀にとって嬉しいだろう。見ていて私まで嬉しくなってしまいそうだった。
でも何だろう。この光るものに霧のような濁ったものが覆い始めて来る感じは。
「未砂ちゃん、宏紀のこと好きなんじゃないかな? 今日話していてそんな感じだったけど」
さらに七海の口撃は続く。
こうやって話すことができるのは宏紀だからかもしれない。
「そういうことじゃないと思うよ。なんか、すごく親しみやすい感じの子だから、そう感じただけじゃない?」
「そうかな……私はいいなって思ってると思うけどな」
宏紀はしつこいなって思っているだろうけど、そんな言い方はしない。でも実際、好きな人を目の前にして、そんなこと言われたら嫌かもしれない。たとえ冗談だとしても。
「そんな話はいいよ。七海はどうなの? す、好きな人とか……いないの?」
宏紀は息を飲んでそう聞いた。
『彼氏がいる』なんて何でもない顔で言われたら、宏紀はどうするつもりだったのか。いるのかいないのか知らずにこれからを過ごす方が宏紀にとっては歯がゆいのか。
「いないよ。高校の時に……彼氏はいたけど、それ以来いないな」
どこか寂しそうにつぶやきながら七海は言った。
宏紀は緊張の一瞬をやり過ごした半面、踏み入れてはいけない領域だったかもしれないと思った。さっきまでの七海が宏紀をいじる表情から、真剣な表情にガラッと変わってしまったから、宏紀はまじまじと七海を見ている。『何かある』とかすかにでも思ってしまうと聞きたくなってしまう。
「何か……あった、感じ?」
「……大学生の人と付き合ってたんだけど、別れちゃって」
『年上だったんだ』って、宏紀はまだ見ぬ世界へ足を踏み入れるように七海の話に聞き入った。これ以上は聞くことはやめた方がいいかと思った宏紀だったけど、ここまで来たら後戻りはできない。宏紀も聞きたいだろうから。
「宏紀、覚えてるかな? 私、油絵やってたじゃない?」
「うん」
「そこの油絵教室で知り合って、何回かご飯食べに行って、向こうから付き合ってほしいって言われて……ぐいぐい引っ張ってくれる頼りがいのある人だったから、優柔不断な私にとっては すごく楽だった」
口から滑り落ちるように言葉がどんどん発していく七海。このことには、ただならない思いがあるみたいだ。
「そうなんだ……」
「それで数か月ぐらい付き合っていたんだけど、浮気されて。大学生だったから私よりはずっと大人で、だんだん私じゃ物足りないって思われたのかもね。今考えると」
次々と明かされる七海の人生の一部に、宏紀はついていけてない様子だった。今、懸命にひとつひとつの思いを宏紀の中で整理している感じだ。
「それで……」
七海の溢れる思いがきれいに並んだのか、宏紀はそう言った。
「それで、喧嘩して別れた。私が子供すぎてついていけなくなったのかな……」
七海は自分を嘲笑うように言った。高校生でもプライドがあった。
「喧嘩したあとに、何回か連絡したんだけど、そのままつながらなくなって……」
ただ聞いていた宏紀は、どんな言葉をかけたらいいか分からなくなったのだろう、七海をただ見つめている。七海が高校生ながらにそんな経験をしていたなんてショックだったのかもしれない。七海の胸に眠る癒し難い傷を見たんだ。
「だから、早く大人になりたいって思った」
七海は無理に頬を上げて宏紀を見つめた。宏紀が反応に困っているのは、七海も分かっているだろう。
「……」
遊ばれた感じが拭えない。でも宏紀はそんなこと口が裂けても言えないだろう。
「さっきは、子供だったって言っていたけど、僕らはこれからどんどん大人になっていくから仕方ないと思う。気にしなくていいと思う。その人とはうまくいかなかったかもしれないけど、もっといい人がいるから大丈夫だよ」
宏紀なりに精いっぱい言葉を振り絞った。七海に伝わっているかどうかは定かではないけど、励ましの言葉を伝えたつもりだ。
「宏紀、ありがとう」
宏紀を見つめて七海は言った。さっきまではなかった目に輝きが存在する。宏紀の言葉を、七海はちゃんと受け取っていたみたいだ。
「その時のショックが大きくて、そのあと人を好きになれなかった。もう会うこともないんだから、忘れて次に行けばよかったのにね。心に大きな穴があいたままでそのままみたいな」
宏紀に伝わるかどうかは別にして、七海は自分の心の一部を描写した。私は宏紀には七海の気持ちはちゃんと伝わっていると思う。
「さぁ、冷めるから食べようか!」
しんみりした空気を振り払って七海はご飯を食べた。
宏紀は七海のアパートを出た。
七海の表情を思い浮かべる。一人になってまた七海のことを整理する。
夜だと少し肌寒くて上に羽織っているジャケットのポケットに両手をしまい込んだ。七海の笑顔の裏にある影を見つめると、宏紀の胸も締め付けられるだろう。
好きな人が悩み苦しんでいる姿は見るに堪えない。これが宏紀の心情だろう。
宏紀は七海が、前向きに恋愛ができるように応援したくなった。それを担うのが、自分であればいいと宏紀は思っている。芽生えた決意を胸に、宏紀は目と鼻の先にある大学のバス停を目指して夜道を切り裂いて歩く。
ただ宏紀に何ができるかを考えて、居座った思いと向き合っている。
乗車中と灯した赤いランプを宏紀は顔に染めさせて、バスに乗り込んだ。
時刻は八時過ぎだから、乗車している学生はそんなに多くない。行き帰りの電車のように座席を争奪しなくても大丈夫だった。
後ろの方へ足を運ぶと、一番後ろの席でイヤホンを装着しようとしている私と目が合った。私は暗がりですぐには認知できなかったけど、宏紀はすぐに真剣な表情を少しだけ緩ました。
「永井さん」
「宏紀君」
「遅くまで残っていたんだね」
「うん。沙織たちと話していたら、こんな時間になって」
「いいね。話が盛り上がった感じだね」
私はそばに置いていたリュックサックを膝の上に乗せて、ポンポンと隣の席を触った。
「ここ、座る?」
「うん、ありがとう」
バスは乗車時間を迎えて、静かに動き出した。
「宏紀君は、大学にいたの?」
「いや、ちょっと、外に出てたんだ」
どこかごまかすように言った宏紀が気になって、私は「ちょっとって……」
「あの、七海の、アパートに行ってたんだ……」
私から視線を外して意味なく吊革を見つめて宏紀は言った。
言葉をそのまま飲み込んでいくと、私の胸で何かが逆流してくるような感覚を覚えた。少しだけ過呼吸になってしまいそうで、さりげなく胸を抑えた。抑えたとしてもそれは何の意味もない。
「そうなんだ……何か、用があったの?」
そう聞いた瞬間に、七海のアパートで何をしていたのか色々と考えてしまって落ち着きがどこか遠くに行ってしまった。
「七海が自炊してて、それで御馳走してくれるって言ってくれたから食べてきた」
宏紀は照れくさそうに語るも、嬉しさをも滲ませている。さぞや楽しいひと時だったんだろう。
「そうなんだ……」
中学時代からの仲だから、アパートぐらい行くだろうと、私は無理やりにでも落ち着かせようと自分自身に話しかけていた。この場面は動揺を押し殺して、気丈に振る舞う方がいい。せっかくまた一緒に帰れるんだ。今回は東京駅からではなく、大学から。そう思い直して私はこう聞いた。
「何を作ってもらったの?」
得意の笑顔もどこかやらされている感が出ていると思う。私は正直だから。
「野菜炒めとかみそ汁とか。美味しかったよ」
満足げに七海の料理を振り返る宏紀。私もおなかが空いているから聞いているだけでもお腹が悲鳴を上げそうだった。
「そっか……七海ちゃん、料理上手そうだもんね……」
宏紀は私をチラッと見て、「うん」と頷いた。
私は自分で自分の首を絞めてしまった。私の動揺を逆撫でするような質問だった。せっかく自分を落ち着かせて聞いたのに台無しになった。
「今日は、あまり元気ないみたいだね……」
言葉を失った私を見て宏紀はそう言った。私が黙っていると、怖いらしい。怖いって言うのは、いつもの明るさとギャップがありすぎて心配になるらしい、私にだって、こういう時もあるんだ。
「ううん、私はいつも元気だよ……」
宏紀の目には明らかに『元気』という言葉は、今の私に当てはまらないと思っていると思う。宏紀が嬉しそうに七海の手料理の話なんてするからだ。長々とささやいていた。
時間だけが過ぎていく。バスは新浦安駅に向かってただ車輪を回転させる。
眠れずに時計の針を一つ一つ数えていくように、この時間が刻々と削られていく。
タイミングが悪かった。会わない方が良いタイミングに会ってしまったから仕方ない。宏紀と過ごせる時間は長くあるわけじゃない。時間が流れていくのをただ眺めている自分がいて、顔に焦りが見えてきた。
宏紀はバスに少しだけ揺らされながら車内に入り込む光を見つめている。
「宏紀君は……」
私は耐えられず口を開いた。宏紀に『元気がない』って心配されるのも嫌だから話しかけてみる。気分が乗らない時に乗ったふりをするって、大変だ。でもまた宏紀の笑顔を見れば、それはすぐに解決されるはず。
「うん」
すぐに視線を私に向けて宏紀は反応した。
「宏紀君は、休みの日は何をしてるの?」
「だいたい、家でごろごろしてるか、バイトしてる」
「そうなんだ。どこでバイトしてるの?」
地元がお互いに近いから知っている場所かもしれない。
「石川町駅の近くにある、ボーリング場分かる?」
「ああ、分かる! あそこでやってるの?」
「うん。あの薄汚れたボーリング場で」
宏紀は店長に悪いと思ったのだろう、そこに付け足して「店長には申し訳ないけど、薄汚れたって」
私はただ笑って宏紀を見つめた。
「私、あそこよく高校生の時に行ってたよ。中学や高校の友達と」
わざわざ横浜やみなとみらいまで出ていくのが面倒な時は、私は石川町駅周辺で遊んでいた。友達もその辺に住んでいる子たちが多かった。
「そうなんだ。なら会ったことあったかもしれないね。高校一年生の時からやってるから」
「すごい! 長くやってるんだ。お店の人に頼られているんだね」
「そんなことないよ。ただ人が少ないだけだよ。永井さんは明るい感じだから、友達とかたくさんいそうだね」
「そうかな? でも人と仲良くなるのは早い方かもしれない。相手の人から壁が見えなければ……」
「相手の人は話しやすいと思うよ」
「本当? ありがとう。そう言ってくれる人はいいんだけど、みんながみんなそうじゃないから気をつけるようにしてるよ」
「どういうこと?」
「私、初対面の人とかでも全く壁がないって言うか、誰でも普通に話しかけちゃうから……仲良くなりたいだけなんだけど、人によってはただの馴れ馴れしい八方美人みたいに思われてさ」
過去の人間関係でできた傷が疼きだす。仲良くしたいけど、受け入れてもらえなかった。誰とでも隔てなく仲良くしたい私にとって辛い経験だった。
「そうなんだ。なんか嫌だね、悪気はないのに」
「うん。宏紀君みたいに受け入れてくれる人ならいいけど、なんか壁を感じる人は、なんだろう……人一倍、気を遣っちゃう。無理に笑ったり、口数が多くなったりとかして」
宏紀に愚痴を聞かせてしまった。その場を取り繕うために笑顔を作ってみせた。 あぁ。こうやっていつも無理に笑うんだ。
そんな私を見て、宏紀はこう言った。
「でも僕は嬉しかったよ」
私は少しだけ瞳を光らせて宏紀の言葉を拾った。
「僕は自分から話しかけられるタイプじゃないから、一人が好きなのに寂しがり屋だから……だから色々話しかけてくれるのは嬉しいよ。東京駅でも声かけてくれたもんね」
「ありがとう……」
私は唇を少し突き出して、目から光るものが落ちないようにこらえた。宏紀、これ以上、私の涙腺を刺激してはいけない。
「逆にそれがなくなったら、永井さんじゃないような気がするから、大事にした方がいいかもね」
瞳からの雫が滑り落ちて私のスカートに消えた。幸い、宏紀は気づいていないようだった。暗がりは私に意外な形で味方してくれたんだ。
「ありがとう……」
力強くも小さく私は言った。バスが走行する騒音ですべてかき消されているから気にしなくていい。
新浦安駅のロータリーが見えてきた。ゆっくりと停車すると、お疲れさまという言葉がこだまするようにドアが開いた。
宏紀が降りる態勢を整えていると、俯いたままかえってこない私を見た。スカートにいくつか湿り気を帯びたものが点在している。
「永井さん……」
素早く涙を拭き取って、私は何事もなかったかのように立ち上がった。
宏紀は私を見つめたままバスから降りた。
目の前にある新浦安駅の入り口の前。宏紀に背を向けたその場で立ち止まった。一度ちゃんと拭いたはずの涙が頬をまた熱くする。私の目の前に優しく添えてくれた言葉は、私に取り巻く影をほどいてくれた。
「泣いてるの?」
宏紀が私の顔を覗き込んで言った。そこまで化粧はしてないけど、変な顔をしているかもしれないから、それ以上は近づかないでほしい。普通の時だったら大歓迎だけど。
「ごめん……」
「大丈夫?」
宏紀は私の背中を撫で始めた。
「嬉しくて泣いてるの。宏紀君の言葉が嬉しくて……」
「ああ……そっか。僕が泣かしちゃった感じだね」
苦笑しながらそう言った。夜でも人はまだまだ街にいるから、宏紀は女の子を泣かしてしまって落ち着かない様子だった。宏紀が悪いんじゃないから気にしないでほしい。
「宏紀君、ありがとう。そんな風に言ってくれて。だから私、今いる周囲の人たちを私なりに大事にしようって思ったんだ。私のことを変だって思わずに普通に受け入れてくれた人を。前に人間関係で悩んでいた時にそう思った」
「いいと思う。僕もそうするよ。僕も……友達……」
その後が続かずに迷子になっている宏紀の言葉。
声の余韻が消えていくさまが気になって私は少しだけ顔を上げた。
「友達、いないからさ」
「そうなの?」
「本当にいない」
「でもこれから大学でできるよ」
「そうだといいね……もうすぐ電車来るね。急ごう!」
「うん」
一人で決心したことが私の胸の中にある。そこに宏紀が光を灯してくれた。それなら私も、もう少し自信を持って、誰かに怯むことなく一途に前を向いていい。誰か一人が同じ方向を向いてくれるだけで、人はこんなにも前向きになれるんだ。
宏紀がそう教えてくれた。
港南台駅に着いて改札を出る。
宏紀は信号で立ち止まって、また七海のことを考え始めた。
ここから五分ほど歩いた場所に宏紀のアパートがある。そこに行きつくまで、ただひたすら七海を考えて足を前に出すんだろう。
宏紀の目が赤から青に変わる。地に足をつけて歩む足跡が音を立てている。
スマホが小刻みに揺れ始めた。七海からだと思って一瞬期待した宏紀には悪いけど、私からだった。
「もしもし」
「もしもし。もう、家着いた?」
一足先に磯子で降りた私は、家の前で宏紀の言葉を心の中で繰り返していた。
「もうすぐ着くよ。永井さんはもう家?」
「うん。もう家のそばにいる……」
「どうしたの? 何かあった?」
七海のことを考える時間に充てたかったのだろうか、答えを急かすように宏紀が聞いた。私と磯子駅までは一緒にいたから、ゆっくり考える時間はなかっただろうから。
「あのさ……宏紀って、呼んでいい?」
照れくさくて、ゆっくり私は口を動かした。普段ならサラッと言えることでも、宏紀のことなら話は別だ。
「ビックリした……そんなことか。全然いいよ」
ふっと息をはいた宏紀。もしかしたら告白かと思ったのか。
「ごめん……ありがとう。宏紀も、永井さんじゃなくて、未砂でいいよ」
「うん。分かった。でもなんか恥ずかしいね」
噴き出して宏紀が笑った。
「恥ずかしいね。でもこれでいきたいな」
私も同じ思いだ。でも電話越しでも勇気を出して言ったから名前で呼び合いたい。
「いいよ。そうしようか……じゃあ、また明日ね」
「うん、おやすみなさい」
静かにスマホは通常画面に戻った。宏紀からダメって言われる想定も少なからずしていたから、承諾してくれた宏紀に感謝した。
もうバレてるかもしれない。それでもよかった。
自分の気持ちをはっきり持つことができるのは嬉しいことだな。
私は宏紀のことが好きになってしまったんだ。
七海が自炊をしていることを聞いた宏紀が『食べてみたい』と軽いノリで言ったら、七海は宏紀を自分のアパートに招いてくれた。
「今日、泊っていってもいいよ」
ここから二時間かけて帰る宏紀への配慮だったんだろう、七海はそう言った。
願ってもない七海の提案に宏紀は、
「ああ、それはやめとくよ。明日朝からバイトがあるし」
宏紀はこれから間違っても朝からバイトを入れないでおこうと思っていると思う。高校生の時からボーリング場でアルバイトをしていて、大学に入学してからも続けていくつもりだ。
「そうなんだ。残念だな。宏紀なら気にしないのに」
プライパンを上手にかえして、七海は野菜と豚肉を空気に触れさせる。うまくできて笑顔を見せた。
「なんだよ、それ」
「ふふん、冗談だよ」
冗談でも何でもいいと思う。七海と共に時間を刻むことができるなら。
「七海って、得意な料理は何なの?」
「得意なんて言うほど料理してないよ。一人暮らしを始めたから頑張ってやろうと思っているだけだよ」
七海は二人分の野菜炒めをお皿に盛りつけていく。食欲をそそる香りがキッチンから漂い、宏紀の嗅覚を刺激している。
「すごくいい匂い」
「本当? ちょっと待っててね」
見栄えを確認して、七海はシェフとしての自信をのぞかせてから宏紀の前に持ってきた。それに少なめのご飯、みそ汁、塩漬けのキュウリも添えた。
「すごい!」
宏紀が思っていたよりもきちんとしていたからそう声をあげた。
「食べてみて! うまくできたと思う!」
宏紀はさっそく箸を手に取って野菜と豚肉をうまく絡めて口に運ぶと、七海は黙って宏紀の反応を待った。
「おいしいよ、七海、上手だね」
安堵して頬を緩ませて、七海も一口食べた。
「いいね」
親指を立てて、七海は野菜炒めを評価した。少し力強い仕草をしてもかわいい。宏紀もそう思っていると思う。
「今日、未砂ちゃんと話したよ」
七海が唐突に私の名前を出した。今日の実験科目の時のことだ。
「未砂ちゃん? 永井さんのこと?」
「そうそう。なんか、宏紀のこと優しいって言ってたよ」
急に頬を赤に染まらせて、目の前にあった水を飲んだ。喉のあたりで食べ物が詰まったかもしれない。私の推測だと、褒められるのが苦手なんだと思う。
「そんなこと言ってた?」
水の助けを借りて、正常に話せるまでになった宏紀はそう言った。
「うん。宏紀、何したの?」
七海がからかうように言った。一口みそ汁を飲んで宏紀の反応を待つ。
宏紀には心当たりがあるはずだけど、それは見せずに「特に何もしてないよ」と言った。
「嘘だ! じゃなかったら未砂ちゃんがあんなこと言わないよ。宏紀、照れないで言いなさい!」
年上の女性が後輩をいじるように七海は言った。それを甘んじて受ける宏紀。
「いや、別に……人を助けただけだよ、東京駅で」
「えー優しい」
「そんなことないよ。相手はおばあちゃんだから」
そう言ってご飯を乱暴に口に放り込んだ。チラッと七海を見ると、頷きながら宏紀を見ていた。すぐさま目を逸らしてみそ汁を持ち上げた。
「私にも優しくしてね」
「してなかったっけ?」
口に運ぶ豚肉を見つめて宏紀は言った。そんなぶっきらぼうな態度だったかと思って、宏紀は過去の記憶をたどった。中学の時のことなんて、そこまで細かく覚えてないだろう。
「してないじゃない」
七海はおどけていった。
「してるよ」
宏紀も嬉しそうに笑っている。こんな風に七海と会話できるのは、宏紀にとって嬉しいだろう。見ていて私まで嬉しくなってしまいそうだった。
でも何だろう。この光るものに霧のような濁ったものが覆い始めて来る感じは。
「未砂ちゃん、宏紀のこと好きなんじゃないかな? 今日話していてそんな感じだったけど」
さらに七海の口撃は続く。
こうやって話すことができるのは宏紀だからかもしれない。
「そういうことじゃないと思うよ。なんか、すごく親しみやすい感じの子だから、そう感じただけじゃない?」
「そうかな……私はいいなって思ってると思うけどな」
宏紀はしつこいなって思っているだろうけど、そんな言い方はしない。でも実際、好きな人を目の前にして、そんなこと言われたら嫌かもしれない。たとえ冗談だとしても。
「そんな話はいいよ。七海はどうなの? す、好きな人とか……いないの?」
宏紀は息を飲んでそう聞いた。
『彼氏がいる』なんて何でもない顔で言われたら、宏紀はどうするつもりだったのか。いるのかいないのか知らずにこれからを過ごす方が宏紀にとっては歯がゆいのか。
「いないよ。高校の時に……彼氏はいたけど、それ以来いないな」
どこか寂しそうにつぶやきながら七海は言った。
宏紀は緊張の一瞬をやり過ごした半面、踏み入れてはいけない領域だったかもしれないと思った。さっきまでの七海が宏紀をいじる表情から、真剣な表情にガラッと変わってしまったから、宏紀はまじまじと七海を見ている。『何かある』とかすかにでも思ってしまうと聞きたくなってしまう。
「何か……あった、感じ?」
「……大学生の人と付き合ってたんだけど、別れちゃって」
『年上だったんだ』って、宏紀はまだ見ぬ世界へ足を踏み入れるように七海の話に聞き入った。これ以上は聞くことはやめた方がいいかと思った宏紀だったけど、ここまで来たら後戻りはできない。宏紀も聞きたいだろうから。
「宏紀、覚えてるかな? 私、油絵やってたじゃない?」
「うん」
「そこの油絵教室で知り合って、何回かご飯食べに行って、向こうから付き合ってほしいって言われて……ぐいぐい引っ張ってくれる頼りがいのある人だったから、優柔不断な私にとっては すごく楽だった」
口から滑り落ちるように言葉がどんどん発していく七海。このことには、ただならない思いがあるみたいだ。
「そうなんだ……」
「それで数か月ぐらい付き合っていたんだけど、浮気されて。大学生だったから私よりはずっと大人で、だんだん私じゃ物足りないって思われたのかもね。今考えると」
次々と明かされる七海の人生の一部に、宏紀はついていけてない様子だった。今、懸命にひとつひとつの思いを宏紀の中で整理している感じだ。
「それで……」
七海の溢れる思いがきれいに並んだのか、宏紀はそう言った。
「それで、喧嘩して別れた。私が子供すぎてついていけなくなったのかな……」
七海は自分を嘲笑うように言った。高校生でもプライドがあった。
「喧嘩したあとに、何回か連絡したんだけど、そのままつながらなくなって……」
ただ聞いていた宏紀は、どんな言葉をかけたらいいか分からなくなったのだろう、七海をただ見つめている。七海が高校生ながらにそんな経験をしていたなんてショックだったのかもしれない。七海の胸に眠る癒し難い傷を見たんだ。
「だから、早く大人になりたいって思った」
七海は無理に頬を上げて宏紀を見つめた。宏紀が反応に困っているのは、七海も分かっているだろう。
「……」
遊ばれた感じが拭えない。でも宏紀はそんなこと口が裂けても言えないだろう。
「さっきは、子供だったって言っていたけど、僕らはこれからどんどん大人になっていくから仕方ないと思う。気にしなくていいと思う。その人とはうまくいかなかったかもしれないけど、もっといい人がいるから大丈夫だよ」
宏紀なりに精いっぱい言葉を振り絞った。七海に伝わっているかどうかは定かではないけど、励ましの言葉を伝えたつもりだ。
「宏紀、ありがとう」
宏紀を見つめて七海は言った。さっきまではなかった目に輝きが存在する。宏紀の言葉を、七海はちゃんと受け取っていたみたいだ。
「その時のショックが大きくて、そのあと人を好きになれなかった。もう会うこともないんだから、忘れて次に行けばよかったのにね。心に大きな穴があいたままでそのままみたいな」
宏紀に伝わるかどうかは別にして、七海は自分の心の一部を描写した。私は宏紀には七海の気持ちはちゃんと伝わっていると思う。
「さぁ、冷めるから食べようか!」
しんみりした空気を振り払って七海はご飯を食べた。
宏紀は七海のアパートを出た。
七海の表情を思い浮かべる。一人になってまた七海のことを整理する。
夜だと少し肌寒くて上に羽織っているジャケットのポケットに両手をしまい込んだ。七海の笑顔の裏にある影を見つめると、宏紀の胸も締め付けられるだろう。
好きな人が悩み苦しんでいる姿は見るに堪えない。これが宏紀の心情だろう。
宏紀は七海が、前向きに恋愛ができるように応援したくなった。それを担うのが、自分であればいいと宏紀は思っている。芽生えた決意を胸に、宏紀は目と鼻の先にある大学のバス停を目指して夜道を切り裂いて歩く。
ただ宏紀に何ができるかを考えて、居座った思いと向き合っている。
乗車中と灯した赤いランプを宏紀は顔に染めさせて、バスに乗り込んだ。
時刻は八時過ぎだから、乗車している学生はそんなに多くない。行き帰りの電車のように座席を争奪しなくても大丈夫だった。
後ろの方へ足を運ぶと、一番後ろの席でイヤホンを装着しようとしている私と目が合った。私は暗がりですぐには認知できなかったけど、宏紀はすぐに真剣な表情を少しだけ緩ました。
「永井さん」
「宏紀君」
「遅くまで残っていたんだね」
「うん。沙織たちと話していたら、こんな時間になって」
「いいね。話が盛り上がった感じだね」
私はそばに置いていたリュックサックを膝の上に乗せて、ポンポンと隣の席を触った。
「ここ、座る?」
「うん、ありがとう」
バスは乗車時間を迎えて、静かに動き出した。
「宏紀君は、大学にいたの?」
「いや、ちょっと、外に出てたんだ」
どこかごまかすように言った宏紀が気になって、私は「ちょっとって……」
「あの、七海の、アパートに行ってたんだ……」
私から視線を外して意味なく吊革を見つめて宏紀は言った。
言葉をそのまま飲み込んでいくと、私の胸で何かが逆流してくるような感覚を覚えた。少しだけ過呼吸になってしまいそうで、さりげなく胸を抑えた。抑えたとしてもそれは何の意味もない。
「そうなんだ……何か、用があったの?」
そう聞いた瞬間に、七海のアパートで何をしていたのか色々と考えてしまって落ち着きがどこか遠くに行ってしまった。
「七海が自炊してて、それで御馳走してくれるって言ってくれたから食べてきた」
宏紀は照れくさそうに語るも、嬉しさをも滲ませている。さぞや楽しいひと時だったんだろう。
「そうなんだ……」
中学時代からの仲だから、アパートぐらい行くだろうと、私は無理やりにでも落ち着かせようと自分自身に話しかけていた。この場面は動揺を押し殺して、気丈に振る舞う方がいい。せっかくまた一緒に帰れるんだ。今回は東京駅からではなく、大学から。そう思い直して私はこう聞いた。
「何を作ってもらったの?」
得意の笑顔もどこかやらされている感が出ていると思う。私は正直だから。
「野菜炒めとかみそ汁とか。美味しかったよ」
満足げに七海の料理を振り返る宏紀。私もおなかが空いているから聞いているだけでもお腹が悲鳴を上げそうだった。
「そっか……七海ちゃん、料理上手そうだもんね……」
宏紀は私をチラッと見て、「うん」と頷いた。
私は自分で自分の首を絞めてしまった。私の動揺を逆撫でするような質問だった。せっかく自分を落ち着かせて聞いたのに台無しになった。
「今日は、あまり元気ないみたいだね……」
言葉を失った私を見て宏紀はそう言った。私が黙っていると、怖いらしい。怖いって言うのは、いつもの明るさとギャップがありすぎて心配になるらしい、私にだって、こういう時もあるんだ。
「ううん、私はいつも元気だよ……」
宏紀の目には明らかに『元気』という言葉は、今の私に当てはまらないと思っていると思う。宏紀が嬉しそうに七海の手料理の話なんてするからだ。長々とささやいていた。
時間だけが過ぎていく。バスは新浦安駅に向かってただ車輪を回転させる。
眠れずに時計の針を一つ一つ数えていくように、この時間が刻々と削られていく。
タイミングが悪かった。会わない方が良いタイミングに会ってしまったから仕方ない。宏紀と過ごせる時間は長くあるわけじゃない。時間が流れていくのをただ眺めている自分がいて、顔に焦りが見えてきた。
宏紀はバスに少しだけ揺らされながら車内に入り込む光を見つめている。
「宏紀君は……」
私は耐えられず口を開いた。宏紀に『元気がない』って心配されるのも嫌だから話しかけてみる。気分が乗らない時に乗ったふりをするって、大変だ。でもまた宏紀の笑顔を見れば、それはすぐに解決されるはず。
「うん」
すぐに視線を私に向けて宏紀は反応した。
「宏紀君は、休みの日は何をしてるの?」
「だいたい、家でごろごろしてるか、バイトしてる」
「そうなんだ。どこでバイトしてるの?」
地元がお互いに近いから知っている場所かもしれない。
「石川町駅の近くにある、ボーリング場分かる?」
「ああ、分かる! あそこでやってるの?」
「うん。あの薄汚れたボーリング場で」
宏紀は店長に悪いと思ったのだろう、そこに付け足して「店長には申し訳ないけど、薄汚れたって」
私はただ笑って宏紀を見つめた。
「私、あそこよく高校生の時に行ってたよ。中学や高校の友達と」
わざわざ横浜やみなとみらいまで出ていくのが面倒な時は、私は石川町駅周辺で遊んでいた。友達もその辺に住んでいる子たちが多かった。
「そうなんだ。なら会ったことあったかもしれないね。高校一年生の時からやってるから」
「すごい! 長くやってるんだ。お店の人に頼られているんだね」
「そんなことないよ。ただ人が少ないだけだよ。永井さんは明るい感じだから、友達とかたくさんいそうだね」
「そうかな? でも人と仲良くなるのは早い方かもしれない。相手の人から壁が見えなければ……」
「相手の人は話しやすいと思うよ」
「本当? ありがとう。そう言ってくれる人はいいんだけど、みんながみんなそうじゃないから気をつけるようにしてるよ」
「どういうこと?」
「私、初対面の人とかでも全く壁がないって言うか、誰でも普通に話しかけちゃうから……仲良くなりたいだけなんだけど、人によってはただの馴れ馴れしい八方美人みたいに思われてさ」
過去の人間関係でできた傷が疼きだす。仲良くしたいけど、受け入れてもらえなかった。誰とでも隔てなく仲良くしたい私にとって辛い経験だった。
「そうなんだ。なんか嫌だね、悪気はないのに」
「うん。宏紀君みたいに受け入れてくれる人ならいいけど、なんか壁を感じる人は、なんだろう……人一倍、気を遣っちゃう。無理に笑ったり、口数が多くなったりとかして」
宏紀に愚痴を聞かせてしまった。その場を取り繕うために笑顔を作ってみせた。 あぁ。こうやっていつも無理に笑うんだ。
そんな私を見て、宏紀はこう言った。
「でも僕は嬉しかったよ」
私は少しだけ瞳を光らせて宏紀の言葉を拾った。
「僕は自分から話しかけられるタイプじゃないから、一人が好きなのに寂しがり屋だから……だから色々話しかけてくれるのは嬉しいよ。東京駅でも声かけてくれたもんね」
「ありがとう……」
私は唇を少し突き出して、目から光るものが落ちないようにこらえた。宏紀、これ以上、私の涙腺を刺激してはいけない。
「逆にそれがなくなったら、永井さんじゃないような気がするから、大事にした方がいいかもね」
瞳からの雫が滑り落ちて私のスカートに消えた。幸い、宏紀は気づいていないようだった。暗がりは私に意外な形で味方してくれたんだ。
「ありがとう……」
力強くも小さく私は言った。バスが走行する騒音ですべてかき消されているから気にしなくていい。
新浦安駅のロータリーが見えてきた。ゆっくりと停車すると、お疲れさまという言葉がこだまするようにドアが開いた。
宏紀が降りる態勢を整えていると、俯いたままかえってこない私を見た。スカートにいくつか湿り気を帯びたものが点在している。
「永井さん……」
素早く涙を拭き取って、私は何事もなかったかのように立ち上がった。
宏紀は私を見つめたままバスから降りた。
目の前にある新浦安駅の入り口の前。宏紀に背を向けたその場で立ち止まった。一度ちゃんと拭いたはずの涙が頬をまた熱くする。私の目の前に優しく添えてくれた言葉は、私に取り巻く影をほどいてくれた。
「泣いてるの?」
宏紀が私の顔を覗き込んで言った。そこまで化粧はしてないけど、変な顔をしているかもしれないから、それ以上は近づかないでほしい。普通の時だったら大歓迎だけど。
「ごめん……」
「大丈夫?」
宏紀は私の背中を撫で始めた。
「嬉しくて泣いてるの。宏紀君の言葉が嬉しくて……」
「ああ……そっか。僕が泣かしちゃった感じだね」
苦笑しながらそう言った。夜でも人はまだまだ街にいるから、宏紀は女の子を泣かしてしまって落ち着かない様子だった。宏紀が悪いんじゃないから気にしないでほしい。
「宏紀君、ありがとう。そんな風に言ってくれて。だから私、今いる周囲の人たちを私なりに大事にしようって思ったんだ。私のことを変だって思わずに普通に受け入れてくれた人を。前に人間関係で悩んでいた時にそう思った」
「いいと思う。僕もそうするよ。僕も……友達……」
その後が続かずに迷子になっている宏紀の言葉。
声の余韻が消えていくさまが気になって私は少しだけ顔を上げた。
「友達、いないからさ」
「そうなの?」
「本当にいない」
「でもこれから大学でできるよ」
「そうだといいね……もうすぐ電車来るね。急ごう!」
「うん」
一人で決心したことが私の胸の中にある。そこに宏紀が光を灯してくれた。それなら私も、もう少し自信を持って、誰かに怯むことなく一途に前を向いていい。誰か一人が同じ方向を向いてくれるだけで、人はこんなにも前向きになれるんだ。
宏紀がそう教えてくれた。
港南台駅に着いて改札を出る。
宏紀は信号で立ち止まって、また七海のことを考え始めた。
ここから五分ほど歩いた場所に宏紀のアパートがある。そこに行きつくまで、ただひたすら七海を考えて足を前に出すんだろう。
宏紀の目が赤から青に変わる。地に足をつけて歩む足跡が音を立てている。
スマホが小刻みに揺れ始めた。七海からだと思って一瞬期待した宏紀には悪いけど、私からだった。
「もしもし」
「もしもし。もう、家着いた?」
一足先に磯子で降りた私は、家の前で宏紀の言葉を心の中で繰り返していた。
「もうすぐ着くよ。永井さんはもう家?」
「うん。もう家のそばにいる……」
「どうしたの? 何かあった?」
七海のことを考える時間に充てたかったのだろうか、答えを急かすように宏紀が聞いた。私と磯子駅までは一緒にいたから、ゆっくり考える時間はなかっただろうから。
「あのさ……宏紀って、呼んでいい?」
照れくさくて、ゆっくり私は口を動かした。普段ならサラッと言えることでも、宏紀のことなら話は別だ。
「ビックリした……そんなことか。全然いいよ」
ふっと息をはいた宏紀。もしかしたら告白かと思ったのか。
「ごめん……ありがとう。宏紀も、永井さんじゃなくて、未砂でいいよ」
「うん。分かった。でもなんか恥ずかしいね」
噴き出して宏紀が笑った。
「恥ずかしいね。でもこれでいきたいな」
私も同じ思いだ。でも電話越しでも勇気を出して言ったから名前で呼び合いたい。
「いいよ。そうしようか……じゃあ、また明日ね」
「うん、おやすみなさい」
静かにスマホは通常画面に戻った。宏紀からダメって言われる想定も少なからずしていたから、承諾してくれた宏紀に感謝した。
もうバレてるかもしれない。それでもよかった。
自分の気持ちをはっきり持つことができるのは嬉しいことだな。
私は宏紀のことが好きになってしまったんだ。