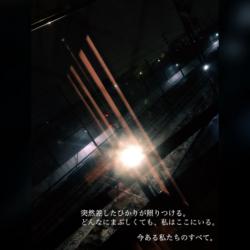磯子駅の東京方面行きのホームで宏紀を待つ私。
この過去二日間で劇的に私が見ている世界は変わった。お互いに本心をぶつけることの大切さを、身をもって体感した。だから前より私の視界はよりクリアに見える。まるで私に合った眼鏡がようやく買えたような気分だった。知ることが良いことなのか悪いことなのか分からない。でも私はここに辿り着けて良かったと思っている。
昨夜、三重県にあるホテルと、横浜駅の近くにあるレンタカーを予約した。宏紀は車を持っているみたいだけど、「両親と共同で使っているから自由には使えない」と言っていたのを思い出してレンタカーのお店を検索した。
我ながら大胆なプランだと思った。でも思いっきり楽しむには地元では物足りなさを感じた。宏紀は基本的に否定しないから、大丈夫って言ってくれるだろうっていう私の解釈だった。もしも難色を示したら、『仕方ない』という言葉で押し通すつもりだ。宏紀には一応、「泊りになるからお泊りセット持って来てね」とは伝えてある。文面を額面通り受け止めてくれたようで、宏紀から「はい!」という返事をもらったから変には思ってないだろう。
昨日の出来事を境に、私はより積極的になっている。なっているというより元の私に戻ったという感覚だ。でもあまり調子に乗らないようにしたい。相手は宏紀だから。
宏紀を乗せた電車がやってきた。目で追いながら宏紀の居場所を探る。私が立っていた場所とはかけ離れた車両にいて、宏紀の車両へ駆け寄っていく。
さぁ旅に出よう。そう、私たちが私たちでいられる場所に。
高速道路を車が行く。
横浜駅でレンタカーを借りて、少しだけ下道を走った後、高速道路に乗って三重県へ。「なんでわざわざ三重に?」って突っ込みを入れられてしまうかもしれないけど、ただの勢いだった。悪く言うなら、私の暴走だった。付き合ってもいないのにいきなり二泊三日の旅行はないだろう。でも宏紀が気にしていなかったら、私はそれでいい。
好きな人と仲良くなったり、グッと距離を近くするにはこういう大胆なことも必要だ。今はそうやって正当化する。
「なんで三重なの?」
予測していた質問が宏紀からとびだした。
「なんか三重に行ってみたいなって」
用意していた答えを悠長に答える私。
「何があるの?」
私はスマホで色々調べ上げた場所を読み上げていく。本当のことを言うと、楽しく過ごせて、宏紀が笑顔でいられるならどこでもよかった。でも行ったことがなくて、私でも運転できる距離だと思ったから三重県になった。宏紀一人に運転させるつもりは最初からなかったから。
「いいね。伊勢神宮とかナガシマとか有名だよね」
「うん。それと愛知県も何気に近いみたいだから」
「愛知県も行けそう? それなら味噌カツとか食べたいな」
前方に注意を向けながらも少しだけテンションを上げた宏紀。その目の輝きが嬉しくて横顔に見とれてしまった。
夕方ごろに宿泊先である三重県四日市市内にあるホテルに着いた。ここのホテルを予約したのはたまたま空いていたから。でも伊勢神宮にも名古屋にも行けるいい場所だったからよかった。ホテルは駅からも距離があったけど、車だから大丈夫かって思った。
ずっと宏紀が運転していたから、ホテルに着いてからは私がハンドルを握った。
せっかくなら三重県ならではのものを食べたいと私は思っていたけど宏紀が、
「未砂、このお店ってどう思う?」
夕食を食べるためにとりあえず外出をしてコンビニに寄った時に、宏紀がスマホのスクリーンを見せてきた。焼肉屋さんのホームページでイチボがお皿に乗っている写真が目に飛び込んできた。きれいな波を描くようにイチボが四切れ。よだれが出てきそうな勢いだった。
「美味しそうだね」
「松坂牛とまではいかないかもしれないけど、これぐらいだったら僕らでも食べられるかなって。サガリとか冷麺も美味しそうだし」
松坂牛のことが頭に残っていたみたいだ。
「ここに行こう!」
「うん! 行こう!」
宏紀からここに行きたいと言ってきてくれたのが嬉しくて喜んでアクセルを踏んだ。誰かを誘ってばかりいるもの辛いんだ。
お店の近くのコインパーキングに車を停めて、お店を覗いてみると結構な人が入っていた。「座れないかも」っていう言葉が脳裏をよぎったけど、たまたまカウンターが二席空いていたから待たずに入店することができた。
換気がよくできていて私も臆することなく席に着けた。メニューを見る宏紀が早く頼みたそうで、イチボ以外のお肉の選択は宏紀に任せた。サガリやホルモンが運びこまれてくるとトングを握ってずっと焼いてくれた。
私は店員さんとコミュニケーションを取って、美味しい食べ方やおすすめを聞いた。宏紀は恥ずかしそうにしていたけど、途中から慣れてきて宏紀も会話していた。
「お兄さん、イチボはどのたれをつければいいですか?」
「お好みですけど、この塩をかけてみてください」
アルバイトの男の子が塩を私に渡してきた。
「これですか? すごい」
「めちゃくちゃ美味しいですよ」
宏紀は笑って頷いた。
「焼くのも数秒でいいですよ。生でも食べられますから」
アルバイトのお兄さんは宏紀からトングを手からスルリと抜き取って、実演をし始めた。
「ありがとうございます。すごく美味しそう」
網の上であぶられたイチボを一切れ、私のお皿においた。
「僕もやってみていいですか?」
「もちろんです!」
「ここのキムチ美味しいですね? キムチ食べたことなかったですけど、これからは食べられると思います。」
「ありがとうございます!」
オーナーらしき人がお兄さんの後ろから元気に叫んだ。
「自家製ですか?」
宏紀も私と争うように質問をはさんだ。
「そうですよね。試行錯誤して作ったものなので自信作です」
胸を張りながらオーナーらしき人は喜びを顔に満ち溢れさせた。
「すごい! もう一つもらってもいいですか?」
「もちろんです!」
「宏紀ももう一つ頼む?」
「うん」
「お願いします」
「はい!」
オーナーらしき人は厨房に軽快な足取りで戻って行った。それを見届けた宏紀は、「未砂ってすごいね」
初めて食べたイチボを口の中で溶かしながら私は目を丸くした。
「すぐに人と仲良くなって……色々アドバイスもらってたもんね」
「本当? ありがとう……なんか恥ずかしいな」
「なんで? 褒めてるんだよ。それが聞けたから、僕も美味しく食べられるから」
「良かった……これが何も飾り気がない私なんだって思えばいいよね?」
「うん。その明るさは、いつになっても失ってほしくない。ありのままの自分を出して、周りの人を大切にするんだよね?」
宏紀の優しさを直に触れた時だった。
「うん」
宏紀は焼きあがったサガリを私のお皿に乗せて、宏紀も一切れ食べた。
「マジでうまいね」
「うん。宏紀、いい所見つけたね!」
最後に宏紀が目を光らせていた冷麺を食べた。
オーナーらしき人によれば、韓国から輸入しているそうで、口直しに食べる人が多いらしい。宏紀に褒められて気をよくした私が帰り際に聞いた話だった。
移動時間のせいで疲労も携えてホテルに行き着いた私たちは、明日に備えて九時すぎにはお風呂に入る準備に入った。ホテルはツインの部屋で、もちろんベッドが二つあり、その奥に円形のテーブルのそばに大きめのソファがあった。
宏紀が運転疲れしていると思ったから先に入らせてあげようと思ったけど宏紀は先にすすめてくれた。断る理由もなかったから宏紀の言葉に甘えさせてもらうことにした。
二十分ぐらいしてから私は浴室の扉をゆっくりと開けた。コンタクトをはめてないから眼鏡をかけて視界を良好にすると、宏紀がソファに座って四日市市内の夜景を見つめていた。
宏紀に背を向けて浴室を離れると、顔を両手で隠しながら、自分のベッドに座った。壁際のベッドを選んでおいたから宏紀にスッピン姿を見られることなくベッドに辿り着けた。
ドアが開いたとき、宏紀は私がお風呂から出たことは知っていたと思うけど、何も言わず目は何の変哲もない夜景に奪われたままだった。
「お先にお風呂頂きました。もしよかったら入って」
「うん。ありがとう」
鏡台の鏡越しに宏紀を見た。
昼間に見せた笑顔が嘘のように、今はしんみりしている。もしかしたら七海のことを思い出しているだろうか。手の届かない場所に知らぬ間に行ってしまった。何もできなかった自分を悔いているのか。前にも思ったけど、まだまだ宏紀に分があるんじゃないかと思う。今はまだ友達として七海は宏紀をとらえているかもしれないけど、これから時間をかけて七海をまた引き戻せばいいような気がする。その方が宏紀は幸せなんだ……。
再び見る宏紀の哀愁を漂わせる表情に、私はただ俯いて膝に置いた手を見つめた。
「未砂」
宏紀が不意に私の名前を呼んだ。私は振り向かずに体をピクリと跳ねさせて、背中を見せながら「何?」
「誘ってくれてありがとう」
「えっ?」
また鏡台の力を借りて宏紀を鏡越しに見た。
「ありがとう。ここに連れてきてくれて。未砂が言わなかったら、来ることはなかったかもしれない」
「全然いいよ。宏紀も、突然付き合ってくれてありがとう。焼肉、美味しかったね」
イチボのとろけるうまさを口の中で思い出す。またお腹が空いてきそうで困る。もう歯磨きをしてしまった。
「美味しかったね……ただ移動してきただけだけど、地元の人とも話せたし、すごく楽しかった」
焼肉屋さんの店員さんやオーナーらしき人もそうだけど、三重県に向かう途中のサービスエリアでも旅の途中の人や、お土産屋さんの店員さんとも少しだけ言葉を投げ合った。
「うん。楽しかったね……どうしたの?」
どこか不安に煽られたように言葉数が多くなる宏紀を心配した。
「いや何もないけど、なんかお礼が言いたくなって」
「そっか……」
その先に何かがありそうで不安の水かさが増す。
「僕は『一人でいるのが好き』って言ったの、覚えてる?」
宏紀が七海のアパートに行った後に、私に優しく言葉をかけてくれた時に、そう言っていたと思う。「一人が好きだけど、寂しがり屋だ」と。
「覚えてるよ。どうして?」
「一人でいるのもいいけど、やっぱり人が周りにいる方が楽しいね……友達が欲しいって……」
宏紀のセリフをうまく繋げられなくて困惑した。なぜ『友達』という言葉を発したのか。でもここの中に何か重要な何かが隠されている……『友達』という言葉。それをきれいに整理していると、私の脳裏に光が猛スピードで通り抜けて消えていった。
「友達……」
「友達、全然いないから」
その言葉が全てだったような気がした。
宏紀は目の前に立ちはだかった透明の壁にぶち当たってしまった。真也は数少ない友達だった。まだ会って間もないといえ、これから大学で生活を共にしていく相手だった。それが宏紀の全てにブレーキをかけてしまったんだ。
言葉にはできないほどやりきれない気持ちになった。
まさか、そんなことで宏紀は自分の気持ちに蓋をしてしまった。
優しいと言えばそうかもしれないけど、あまりにももったいなくて気が遠くなった。
実際に七海への未練は拭いされない。七海と真也との間で目をつむったまま耐えていた宏紀がいた。
友達なんてすぐにできたと思う。私がいくらでも紹介してあげた。『友達』という言葉におどらされた感が拭えない。
今からでも、宏紀に七海へ気持ちを伝えるように促してあげた方がいいか。
七海が交際を承諾するかは置いておいて、自分の気持ちを伝えないまま宏紀はこれから七海や真也と共に歩んでいかないといけない。想像するだけでも体にある力をすべて吸い取られてその場に倒れ込んでしまいそうだった。
スッピンのままの私を忘れて立ち上がった。
宏紀を七海にとられたくない。
不思議な力に導かれるように私は宏紀のそばに座って宏紀を抱きしめた。突然のことに驚きは隠せないかもしれないけど、何も言わずに私に包まれる宏紀がいた。七海のことを一緒に応援してあげられない頑なな私のせめてもの振る舞いだった。
「たくさん友達作ろう……きっとたくさんできるから」
「ありがとう……髪の毛乾かさないと風邪引くよ」
私は何も答えない。そんなことどうでもいい。今は宏紀の気持ちにただ寄り添わせてほしい。
この過去二日間で劇的に私が見ている世界は変わった。お互いに本心をぶつけることの大切さを、身をもって体感した。だから前より私の視界はよりクリアに見える。まるで私に合った眼鏡がようやく買えたような気分だった。知ることが良いことなのか悪いことなのか分からない。でも私はここに辿り着けて良かったと思っている。
昨夜、三重県にあるホテルと、横浜駅の近くにあるレンタカーを予約した。宏紀は車を持っているみたいだけど、「両親と共同で使っているから自由には使えない」と言っていたのを思い出してレンタカーのお店を検索した。
我ながら大胆なプランだと思った。でも思いっきり楽しむには地元では物足りなさを感じた。宏紀は基本的に否定しないから、大丈夫って言ってくれるだろうっていう私の解釈だった。もしも難色を示したら、『仕方ない』という言葉で押し通すつもりだ。宏紀には一応、「泊りになるからお泊りセット持って来てね」とは伝えてある。文面を額面通り受け止めてくれたようで、宏紀から「はい!」という返事をもらったから変には思ってないだろう。
昨日の出来事を境に、私はより積極的になっている。なっているというより元の私に戻ったという感覚だ。でもあまり調子に乗らないようにしたい。相手は宏紀だから。
宏紀を乗せた電車がやってきた。目で追いながら宏紀の居場所を探る。私が立っていた場所とはかけ離れた車両にいて、宏紀の車両へ駆け寄っていく。
さぁ旅に出よう。そう、私たちが私たちでいられる場所に。
高速道路を車が行く。
横浜駅でレンタカーを借りて、少しだけ下道を走った後、高速道路に乗って三重県へ。「なんでわざわざ三重に?」って突っ込みを入れられてしまうかもしれないけど、ただの勢いだった。悪く言うなら、私の暴走だった。付き合ってもいないのにいきなり二泊三日の旅行はないだろう。でも宏紀が気にしていなかったら、私はそれでいい。
好きな人と仲良くなったり、グッと距離を近くするにはこういう大胆なことも必要だ。今はそうやって正当化する。
「なんで三重なの?」
予測していた質問が宏紀からとびだした。
「なんか三重に行ってみたいなって」
用意していた答えを悠長に答える私。
「何があるの?」
私はスマホで色々調べ上げた場所を読み上げていく。本当のことを言うと、楽しく過ごせて、宏紀が笑顔でいられるならどこでもよかった。でも行ったことがなくて、私でも運転できる距離だと思ったから三重県になった。宏紀一人に運転させるつもりは最初からなかったから。
「いいね。伊勢神宮とかナガシマとか有名だよね」
「うん。それと愛知県も何気に近いみたいだから」
「愛知県も行けそう? それなら味噌カツとか食べたいな」
前方に注意を向けながらも少しだけテンションを上げた宏紀。その目の輝きが嬉しくて横顔に見とれてしまった。
夕方ごろに宿泊先である三重県四日市市内にあるホテルに着いた。ここのホテルを予約したのはたまたま空いていたから。でも伊勢神宮にも名古屋にも行けるいい場所だったからよかった。ホテルは駅からも距離があったけど、車だから大丈夫かって思った。
ずっと宏紀が運転していたから、ホテルに着いてからは私がハンドルを握った。
せっかくなら三重県ならではのものを食べたいと私は思っていたけど宏紀が、
「未砂、このお店ってどう思う?」
夕食を食べるためにとりあえず外出をしてコンビニに寄った時に、宏紀がスマホのスクリーンを見せてきた。焼肉屋さんのホームページでイチボがお皿に乗っている写真が目に飛び込んできた。きれいな波を描くようにイチボが四切れ。よだれが出てきそうな勢いだった。
「美味しそうだね」
「松坂牛とまではいかないかもしれないけど、これぐらいだったら僕らでも食べられるかなって。サガリとか冷麺も美味しそうだし」
松坂牛のことが頭に残っていたみたいだ。
「ここに行こう!」
「うん! 行こう!」
宏紀からここに行きたいと言ってきてくれたのが嬉しくて喜んでアクセルを踏んだ。誰かを誘ってばかりいるもの辛いんだ。
お店の近くのコインパーキングに車を停めて、お店を覗いてみると結構な人が入っていた。「座れないかも」っていう言葉が脳裏をよぎったけど、たまたまカウンターが二席空いていたから待たずに入店することができた。
換気がよくできていて私も臆することなく席に着けた。メニューを見る宏紀が早く頼みたそうで、イチボ以外のお肉の選択は宏紀に任せた。サガリやホルモンが運びこまれてくるとトングを握ってずっと焼いてくれた。
私は店員さんとコミュニケーションを取って、美味しい食べ方やおすすめを聞いた。宏紀は恥ずかしそうにしていたけど、途中から慣れてきて宏紀も会話していた。
「お兄さん、イチボはどのたれをつければいいですか?」
「お好みですけど、この塩をかけてみてください」
アルバイトの男の子が塩を私に渡してきた。
「これですか? すごい」
「めちゃくちゃ美味しいですよ」
宏紀は笑って頷いた。
「焼くのも数秒でいいですよ。生でも食べられますから」
アルバイトのお兄さんは宏紀からトングを手からスルリと抜き取って、実演をし始めた。
「ありがとうございます。すごく美味しそう」
網の上であぶられたイチボを一切れ、私のお皿においた。
「僕もやってみていいですか?」
「もちろんです!」
「ここのキムチ美味しいですね? キムチ食べたことなかったですけど、これからは食べられると思います。」
「ありがとうございます!」
オーナーらしき人がお兄さんの後ろから元気に叫んだ。
「自家製ですか?」
宏紀も私と争うように質問をはさんだ。
「そうですよね。試行錯誤して作ったものなので自信作です」
胸を張りながらオーナーらしき人は喜びを顔に満ち溢れさせた。
「すごい! もう一つもらってもいいですか?」
「もちろんです!」
「宏紀ももう一つ頼む?」
「うん」
「お願いします」
「はい!」
オーナーらしき人は厨房に軽快な足取りで戻って行った。それを見届けた宏紀は、「未砂ってすごいね」
初めて食べたイチボを口の中で溶かしながら私は目を丸くした。
「すぐに人と仲良くなって……色々アドバイスもらってたもんね」
「本当? ありがとう……なんか恥ずかしいな」
「なんで? 褒めてるんだよ。それが聞けたから、僕も美味しく食べられるから」
「良かった……これが何も飾り気がない私なんだって思えばいいよね?」
「うん。その明るさは、いつになっても失ってほしくない。ありのままの自分を出して、周りの人を大切にするんだよね?」
宏紀の優しさを直に触れた時だった。
「うん」
宏紀は焼きあがったサガリを私のお皿に乗せて、宏紀も一切れ食べた。
「マジでうまいね」
「うん。宏紀、いい所見つけたね!」
最後に宏紀が目を光らせていた冷麺を食べた。
オーナーらしき人によれば、韓国から輸入しているそうで、口直しに食べる人が多いらしい。宏紀に褒められて気をよくした私が帰り際に聞いた話だった。
移動時間のせいで疲労も携えてホテルに行き着いた私たちは、明日に備えて九時すぎにはお風呂に入る準備に入った。ホテルはツインの部屋で、もちろんベッドが二つあり、その奥に円形のテーブルのそばに大きめのソファがあった。
宏紀が運転疲れしていると思ったから先に入らせてあげようと思ったけど宏紀は先にすすめてくれた。断る理由もなかったから宏紀の言葉に甘えさせてもらうことにした。
二十分ぐらいしてから私は浴室の扉をゆっくりと開けた。コンタクトをはめてないから眼鏡をかけて視界を良好にすると、宏紀がソファに座って四日市市内の夜景を見つめていた。
宏紀に背を向けて浴室を離れると、顔を両手で隠しながら、自分のベッドに座った。壁際のベッドを選んでおいたから宏紀にスッピン姿を見られることなくベッドに辿り着けた。
ドアが開いたとき、宏紀は私がお風呂から出たことは知っていたと思うけど、何も言わず目は何の変哲もない夜景に奪われたままだった。
「お先にお風呂頂きました。もしよかったら入って」
「うん。ありがとう」
鏡台の鏡越しに宏紀を見た。
昼間に見せた笑顔が嘘のように、今はしんみりしている。もしかしたら七海のことを思い出しているだろうか。手の届かない場所に知らぬ間に行ってしまった。何もできなかった自分を悔いているのか。前にも思ったけど、まだまだ宏紀に分があるんじゃないかと思う。今はまだ友達として七海は宏紀をとらえているかもしれないけど、これから時間をかけて七海をまた引き戻せばいいような気がする。その方が宏紀は幸せなんだ……。
再び見る宏紀の哀愁を漂わせる表情に、私はただ俯いて膝に置いた手を見つめた。
「未砂」
宏紀が不意に私の名前を呼んだ。私は振り向かずに体をピクリと跳ねさせて、背中を見せながら「何?」
「誘ってくれてありがとう」
「えっ?」
また鏡台の力を借りて宏紀を鏡越しに見た。
「ありがとう。ここに連れてきてくれて。未砂が言わなかったら、来ることはなかったかもしれない」
「全然いいよ。宏紀も、突然付き合ってくれてありがとう。焼肉、美味しかったね」
イチボのとろけるうまさを口の中で思い出す。またお腹が空いてきそうで困る。もう歯磨きをしてしまった。
「美味しかったね……ただ移動してきただけだけど、地元の人とも話せたし、すごく楽しかった」
焼肉屋さんの店員さんやオーナーらしき人もそうだけど、三重県に向かう途中のサービスエリアでも旅の途中の人や、お土産屋さんの店員さんとも少しだけ言葉を投げ合った。
「うん。楽しかったね……どうしたの?」
どこか不安に煽られたように言葉数が多くなる宏紀を心配した。
「いや何もないけど、なんかお礼が言いたくなって」
「そっか……」
その先に何かがありそうで不安の水かさが増す。
「僕は『一人でいるのが好き』って言ったの、覚えてる?」
宏紀が七海のアパートに行った後に、私に優しく言葉をかけてくれた時に、そう言っていたと思う。「一人が好きだけど、寂しがり屋だ」と。
「覚えてるよ。どうして?」
「一人でいるのもいいけど、やっぱり人が周りにいる方が楽しいね……友達が欲しいって……」
宏紀のセリフをうまく繋げられなくて困惑した。なぜ『友達』という言葉を発したのか。でもここの中に何か重要な何かが隠されている……『友達』という言葉。それをきれいに整理していると、私の脳裏に光が猛スピードで通り抜けて消えていった。
「友達……」
「友達、全然いないから」
その言葉が全てだったような気がした。
宏紀は目の前に立ちはだかった透明の壁にぶち当たってしまった。真也は数少ない友達だった。まだ会って間もないといえ、これから大学で生活を共にしていく相手だった。それが宏紀の全てにブレーキをかけてしまったんだ。
言葉にはできないほどやりきれない気持ちになった。
まさか、そんなことで宏紀は自分の気持ちに蓋をしてしまった。
優しいと言えばそうかもしれないけど、あまりにももったいなくて気が遠くなった。
実際に七海への未練は拭いされない。七海と真也との間で目をつむったまま耐えていた宏紀がいた。
友達なんてすぐにできたと思う。私がいくらでも紹介してあげた。『友達』という言葉におどらされた感が拭えない。
今からでも、宏紀に七海へ気持ちを伝えるように促してあげた方がいいか。
七海が交際を承諾するかは置いておいて、自分の気持ちを伝えないまま宏紀はこれから七海や真也と共に歩んでいかないといけない。想像するだけでも体にある力をすべて吸い取られてその場に倒れ込んでしまいそうだった。
スッピンのままの私を忘れて立ち上がった。
宏紀を七海にとられたくない。
不思議な力に導かれるように私は宏紀のそばに座って宏紀を抱きしめた。突然のことに驚きは隠せないかもしれないけど、何も言わずに私に包まれる宏紀がいた。七海のことを一緒に応援してあげられない頑なな私のせめてもの振る舞いだった。
「たくさん友達作ろう……きっとたくさんできるから」
「ありがとう……髪の毛乾かさないと風邪引くよ」
私は何も答えない。そんなことどうでもいい。今は宏紀の気持ちにただ寄り添わせてほしい。