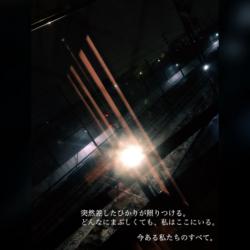「どうだった? 何か言ってた?」
沙織が学食のテーブルに手をついて言った。
「たぶん、私の思った通りだと思う」
沙織は口を抑えて私の言葉を耳に入れている。
「特に、何かを言っていたわけではないんだけど、間違いないと思う」
「そっか……じゃあ、辛いね。真也君の前でどうしたらいいか分からないよね」
私は俯いて膝の上に添えている手を見つめる。ハンドクリームを塗ってあげること以外に、この手で何かできることはあるだろうか。
「もう触れない方がいいのかな……周囲に気付かれ始めているって思ってるだろうし……」
「だね。でもとりあえず、宏紀君の今が分かったのは良かった。何かできること探してみたらいいんじゃない?」
「そうだね……」
沙織が視線を外した。テーブルを小刻みに叩いて私の視線を持ち上げた。
「あれ、宏紀君じゃない?」
ゆっくりとした足取りで、足跡を確認するように生活環境学部の建物を出ていく宏紀の姿だった。
スマホで時間を確認するとまだ講義中のはず。宏紀は一人で講義室を出てきたのか。
立ち上がって宏紀の後を追う私と沙織。夢中で宏紀の足跡をたどる私に対して、沙織は気を遣って尾行する刑事のように影に隠れた。
「宏紀!」
そのまま私の呼びかけに動じずに歩いていく。精一杯声を張ったつもりだった。
「宏紀!」
色彩のない宏紀がいた。
「未砂……」
小粒のような声だった。聞こえなかったけど、口の微かな動きで何を発したか理解した。
「今講義中じゃないの?」
講義中に出てきた自分が後ろめたいのか、宏紀は何も言わない。
「何か私にできること……」
何もないと思う。でも、今の宏紀をただ見ているのは酷だった。
「大丈夫……ちょっと体調が悪いだけ。すぐによくなるから」
何一つ信じることができない宏紀の言葉たち。本音をぶつけてきてほしいけどできないのが今の宏紀だ。
そのまま去っていく。
宏紀のあまりにも軟弱で頼りない背中を見つめる。堪らず沙織に別れを告げて追いかけた。リュックサックを背負わずに駆け足で。
誰かの気配を感じたのか、宏紀は再び振り返った。私に呼ばれてもないのに。
「未砂……帰るの?」
顔を上げて宏紀を見つめて、「一緒に帰ってもい?」と頬を上げた。
「……ごめん、今日は一人にしてくれない?」
そう言って宏紀はまた歩き始めた。
そこで立ち尽くすことができない私は、距離を保ったまま歩いていく。まるで、おつかいに出かけた子供を心配そうに後ろからついていくお母さんのように。
バスの中、新浦安駅、東京駅に着いても、私はずっと同じように距離を保った。
宏紀がチラッと背後を確認する。
「何?」
「えっ……」
「一人になりたいって言ったでしょ?」
「……」
宏紀が私に向かって歩いてくる。後退りしながら身が小さくなっていくのが分かった。宏紀は何も言わずにただの通行人のように通り過ぎて行った。
「どこ行くの?」
宏紀は何も答えない。さっきまでの軟弱で頼りない背中にピリピリした空気が漂っている。
「ねぇ宏紀!」
宏紀は私の問いかけを無視したままだ。今日は私の相手なんてしている暇はないんだろう。
「宏紀」
背中を追いかけながら問いかける私に反応するようにいきなり宏紀は立ち止まった。私は急ブレーキをかけたけど、間に合わずに宏紀にぶつかってしまった。私の後ろを歩いていた人も険しい表情で舌打ちをして宏紀と私に抗議した。
「あ、ごめん……痛かった?」
私が宏紀の背中に触れようとした瞬間、宏紀は振り返った。それはいつになく鋭い目つきだった。あまりの目力に少しだけ距離を置いた。
「……一人になりたいって言ったよね? 日本語通じないの?」
言葉が出ずに私はその場に立ち尽くすだけだった。
「無神経だよ! いやがらせでもしたいわけ?」
「いやがらせ? いやがらせじゃない」
「じゃあ何だよ?」
私は唇を噛んで言葉が外に出ないように必死で止めている。少しだけ潤んだ目に憤慨した宏紀がいる。優しい宏紀には似合わない姿だった。
「私はただ……」
その先が出てこない。こんなことになったのは誰のせい? 誰のせいでもない。
「ただ何だよ?」
低い声が迸る。そんな怖い声を出さないでほしい。
私は背を向けて宏紀の問いかけに答えることなくゆっくりと歩き出した。別に宏紀の真似をしているわけじゃない。
沙織が学食のテーブルに手をついて言った。
「たぶん、私の思った通りだと思う」
沙織は口を抑えて私の言葉を耳に入れている。
「特に、何かを言っていたわけではないんだけど、間違いないと思う」
「そっか……じゃあ、辛いね。真也君の前でどうしたらいいか分からないよね」
私は俯いて膝の上に添えている手を見つめる。ハンドクリームを塗ってあげること以外に、この手で何かできることはあるだろうか。
「もう触れない方がいいのかな……周囲に気付かれ始めているって思ってるだろうし……」
「だね。でもとりあえず、宏紀君の今が分かったのは良かった。何かできること探してみたらいいんじゃない?」
「そうだね……」
沙織が視線を外した。テーブルを小刻みに叩いて私の視線を持ち上げた。
「あれ、宏紀君じゃない?」
ゆっくりとした足取りで、足跡を確認するように生活環境学部の建物を出ていく宏紀の姿だった。
スマホで時間を確認するとまだ講義中のはず。宏紀は一人で講義室を出てきたのか。
立ち上がって宏紀の後を追う私と沙織。夢中で宏紀の足跡をたどる私に対して、沙織は気を遣って尾行する刑事のように影に隠れた。
「宏紀!」
そのまま私の呼びかけに動じずに歩いていく。精一杯声を張ったつもりだった。
「宏紀!」
色彩のない宏紀がいた。
「未砂……」
小粒のような声だった。聞こえなかったけど、口の微かな動きで何を発したか理解した。
「今講義中じゃないの?」
講義中に出てきた自分が後ろめたいのか、宏紀は何も言わない。
「何か私にできること……」
何もないと思う。でも、今の宏紀をただ見ているのは酷だった。
「大丈夫……ちょっと体調が悪いだけ。すぐによくなるから」
何一つ信じることができない宏紀の言葉たち。本音をぶつけてきてほしいけどできないのが今の宏紀だ。
そのまま去っていく。
宏紀のあまりにも軟弱で頼りない背中を見つめる。堪らず沙織に別れを告げて追いかけた。リュックサックを背負わずに駆け足で。
誰かの気配を感じたのか、宏紀は再び振り返った。私に呼ばれてもないのに。
「未砂……帰るの?」
顔を上げて宏紀を見つめて、「一緒に帰ってもい?」と頬を上げた。
「……ごめん、今日は一人にしてくれない?」
そう言って宏紀はまた歩き始めた。
そこで立ち尽くすことができない私は、距離を保ったまま歩いていく。まるで、おつかいに出かけた子供を心配そうに後ろからついていくお母さんのように。
バスの中、新浦安駅、東京駅に着いても、私はずっと同じように距離を保った。
宏紀がチラッと背後を確認する。
「何?」
「えっ……」
「一人になりたいって言ったでしょ?」
「……」
宏紀が私に向かって歩いてくる。後退りしながら身が小さくなっていくのが分かった。宏紀は何も言わずにただの通行人のように通り過ぎて行った。
「どこ行くの?」
宏紀は何も答えない。さっきまでの軟弱で頼りない背中にピリピリした空気が漂っている。
「ねぇ宏紀!」
宏紀は私の問いかけを無視したままだ。今日は私の相手なんてしている暇はないんだろう。
「宏紀」
背中を追いかけながら問いかける私に反応するようにいきなり宏紀は立ち止まった。私は急ブレーキをかけたけど、間に合わずに宏紀にぶつかってしまった。私の後ろを歩いていた人も険しい表情で舌打ちをして宏紀と私に抗議した。
「あ、ごめん……痛かった?」
私が宏紀の背中に触れようとした瞬間、宏紀は振り返った。それはいつになく鋭い目つきだった。あまりの目力に少しだけ距離を置いた。
「……一人になりたいって言ったよね? 日本語通じないの?」
言葉が出ずに私はその場に立ち尽くすだけだった。
「無神経だよ! いやがらせでもしたいわけ?」
「いやがらせ? いやがらせじゃない」
「じゃあ何だよ?」
私は唇を噛んで言葉が外に出ないように必死で止めている。少しだけ潤んだ目に憤慨した宏紀がいる。優しい宏紀には似合わない姿だった。
「私はただ……」
その先が出てこない。こんなことになったのは誰のせい? 誰のせいでもない。
「ただ何だよ?」
低い声が迸る。そんな怖い声を出さないでほしい。
私は背を向けて宏紀の問いかけに答えることなくゆっくりと歩き出した。別に宏紀の真似をしているわけじゃない。