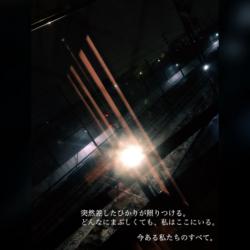またオレンジ色の太陽を直視する。
私と新浦安駅まで歩いたときに見た夕焼けとほとんど同じで、あのきれいな情景を思い出して、少しでも宏紀の心の中に居座る煙を消し去ってほしい。
部活動に精を出す子たちを、宏紀は緑色のグランドを囲む観覧席で意味もなく何かを眺めている。ざわついたメインストリート、溢れかえる学生の波に飲まれて帰るのが億劫になって知らぬ間にここに行き着いた。
緑を背景に笑い声がこだまする。高校時代に見た景色が宏紀の視界に映る。心の中で力なくつぶやく。あの時と変わっていない……。
「宏紀」
宏紀は反応せずにただグラウンドを見つめたままだ。
二度目の呼びかけにようやく体をひねる。呼びかけたのは七海だった。
「ああ、七海」
ただでさえ身長がある七海が大きく見える。
「何してるの? こんなところで?」
七海は宏紀の真横に座った。七海のアパートの匂いを思い出す。一人暮らしも板についてきたのかと宏紀は想像する。
「いや……別に」
理由を探しても、理由が見つからなくて宏紀はただそう言うしかなかった。
「そうなんだ。後ろ姿、なんか絵になる感じだったよ」
七海は微笑む。
「そんなにいい背中してないよ……これからバイト?」
バイトの制服らしきものが入っている七海のトートバッグを見つめた。
「うん。まだちゃんと仕事覚えてないから、なるべく入ろうと思って」
「じゃあ、あんまり時間ない感じか……」
寂しそうに宏紀の視線が落ちる。
「そんなことないよ。私も講義が終わった後は、少し休みたいから大丈夫だよ」
七海の笑顔に触れる宏紀。宏紀の気持ちは何もしなくても楽になっていくのが分かる。何か重いものが取り払われて、体が風船のように浮いた気がした。
「今日はどのくらい働くの?」
「今日はね、六時からラストまで」
「そっか。頑張ってるね」
優しく頬を緩ませて宏紀は言った。
「宏紀たちがいるからだよ。大学でうまくやっていけるか不安だったけど、宏紀がいたのは大きかった。一人でも知っている子がいるって、こんなに楽なんだね」
宏紀は七海の言葉をどう受け止めたのか。優しさに包まれた言葉でも宏紀の捉え方は分からない。七海への強くなるばかりか。それを振り払うのか。
「僕も同じだよ。七海が一緒で良かった」
「今度さ、バイト先も来てよ。ごちそうはできないけど、来てくれたら嬉しい」
宏紀の心を癒せるのは七海しかいない。
「行きたい。コーヒー……飲めるようになったから……」
「そうだったね! どうしてまた?」
「なんか……飲んでみようって……今より、大人になりたかったのかな……」
「なにそれ? コーヒーで大人になれるの? 私はもっと頑張らないと!」
「無理しないでよ……」
「うん、ありがとう。じゃあ、そろそろ行くね」
七海は立ち上がって夕焼けと緑色のグラウンドを後にしようとする。
「……七海」
「ん?」
呼び止められて七海は振り返った。
「もう……やめたい」
「なんて?」
聞こえるはずもない。ひどく力のない声だった。この言葉にすべてが詰まっているようだった。宏紀の迷いも何もかも。
「もうやめたい……」
繰り返し言うことで宏紀の声が乗った。
「大学を?」
宏紀は黙ったまま何も言わない。呼び止めておいて何も言わない。七海は困惑顔だ。
再び七海は宏紀のそばにつく。肩に下げていたバイトの制服が入ったトートバッグを外して宏紀の今に耳を傾けた。
「何かあったの? なんかよく見ると顔色も良くない感じだよね?」
宏紀の顔を覗き込む七海。子供を優しく看る看護師のようだった。
心中でうごめくものを吐露したけど、この先のことは七海に安易と話せるわけもない。口が裂けたとしても。
「ごめん、変なこと言って。もう大丈夫」
「本当? 絶対やめないでよ。まだ入ったばっかりじゃん」
そう。まだ入学して間もないのだ。こんな近くに闇が待ち構えていたなんて、宏紀は考えてもみなかっただろう。
「そう……だね」
「何かあったら教えて。話聞けるから」
再び七海は立ち上がって宏紀の肩をかすめるように触れた。
「ありがとう……バイト頑張って」
「うん」
七海は手を振って宏紀から離れていく。まともに七海と会話ができること。それは今はどこか恐怖なのだ。
日曜日の横浜駅。
スマホを片手に私は行き交う人々の群れから宏紀の姿を探し出す。LINEを介してメッセージを送ると、「もうすぐ着きます!」と宏紀から連絡があった。
すぐそばにあるベーカリーのガラスで今の私を確認する。いつもより入念に化粧をしてきた。宏紀の反応が若干怖いけど、気にせず向き合うつもりだ。今日は大きな仕事を背負っているような感じだ。
今日は以前に話していた映画を観に行く予定だ。その前にランチに行く。
観たい映画はピックアップしてきたけど、別にこだわりはないから宏紀と相談して決めればいい。
体がピクリと反応する。
「ごめん。少し遅れちゃった」
手を振って宏紀が近づいてきた。
「いいよ。私もさっき来たばかりだから」
宏紀に顔を見つめられる。化粧が濃いことはバレている。恥ずかしくて目を逸らしたけど、宏紀に見つめられるなら見返さないと思って宏紀を直視する。自分らしさは失いたくない。
「ランチなんだけど、カフェレストランとか、モールの中にあるすごくヘルシーなお店があるんだけど、どっちがいい?」
スマホに呼び出したレストランを宏紀に見せた。
「ああ……どっちもよさそうだね。未砂はどっちがいいの?」
「私は……モールのところがいいな」
映画館もモールの中にあるから効率がいい。
「じゃあ、そこにしよう」
モールに向かって歩き始めた。ヒールを履いてるから最初は歩く速さがうまく合わなくて気になったけど、時計の時間を合わせるように宏紀が合わせて歩いてくれたからモールに着くころには普通になった。
「七海とかは誘わなかったの?」
「うん……」
七海や真也は誘っていない。七海を誘ったら自動的に真也もっていうことになるだろう。今の宏紀にこの組み合わせは合わない。私にとってもその方がありがたい。
「映画なんだけど、これが観たいな」
誤魔化すようにスマホの画面を見せた。
「これか。すごく人気のやつだよね? 映画館に行くのは久しぶりだ」
「そうなの? いつも家で観るタイプ?」
「いや……そうでもないんだけど、行く機会がなかったっていうか……」
「そうなんだ。二ヵ月に一回行ってた、私」
「観たい映画がたくさんあるんだね、未砂は。たくさん友達もいるしね」
「強引に連れてっているだけだよ」
過去の行動を思い返して少し苦笑してしまう。宏紀を無理に歩かせて新浦安駅に行ったのもかなり強引だった。
「それでも付き合ってくれる人がいるんだからいいじゃん。相手は嬉しいと思うよ」
「そうだといいな」
嬉しさを十二分に噛みしめる。宏紀の言葉には魔法に似た不思議な力がある。
店の前には行列ができていた。宏紀と暇つぶしするなら時間はいくらあってもいい。それに今日は大仕事が待っている。
今の宏紀を知りたい。
でもこうやって宏紀と話していると、そんな話は蓋をして永遠に出てこられないようにしたい。考え過ぎだと思えるぐらい宏紀の表情は明るい。
「どうしたの? 未砂?」
「えっ?」
私の目が遠くに行ったままだった。
「大丈夫?」
「大丈夫、大丈夫」
今は考えない方がいいかもしれない。
「未砂、どれにするの?」
知らぬ間に宏紀は簡易メニューを渡されていたけど、気が付かなかった。
私は脳裏で飛び交っている思考を隠すように笑う。そして前をしっかり見据えて冷静さを取り戻す。
宏紀の今を知りたい。
助けてあげたい。私がそばにいる。それをしてどうなるか分からない。それに私の勘違いってこともある。それならすべての邪念を振り払う。
でも複雑なんだ。
宏紀と真也の間で何もないなら、宏紀はただ七海に向かってひた走るだろう。中学時代の思い出を駆け抜けるように。それなら私に勝ち目なんてない。宏紀に七海への気持ちを叶えてほしい気持ちもある。でも、それを私がただ眺めるだけの覚悟は据え置いてない。
もしも推測が正しいなら、炙り出さあれるように勝機は顔を出す。宏紀は足元に釘を打たれて動けないはず。その中で苦しんでいるはず。私のことを肯定してくれる宏紀を苦しめてまで手の中に収めたいのか。
メニューを眺める宏紀の表情を伺う。
『助けたい』と銘打った正当化は宏紀の視界にはどう映るんだろう。
「宏紀……」
「何?」
きょとんした宏紀の顔。私の真面目な顔は怖いらしいのか。
「最近、気になることが……あるんだけど……」
宏紀は少し後退りをしたような気がした。このひしめき合うような行列の後方に十分なスペースなんてないはずだ。
「……なに?」
後ろに一歩下がっても距離を詰めることで相殺する。
目を逸らして私は宏紀の胸板の辺りを見つめた。
「最近、なんか……元気、なくない?」
少しだけ硬直する宏紀の体。少しだけ触れて硬さを取り除きたくなった。顔は怖くて見られない。ただ音や私たちを包む雰囲気で判断することになる。
「真也……君と何か……」
きっと『真也』という名はダメ押しになるだろう。
「……」
口を紡ぐってことは、推測は間違いないのかもしれない。宏紀は何も言わずにただそこにいるだけだ。私に何事もないことを強調しようと言葉を選んでいるのか。
宏紀を責めているみたいだった。だんだんこの沈黙が苦しくなってくる。今日は日曜日。私たちの前後にはカップルや女友達でご飯に来ている。店内を見てみても活気があふれている。嫌な雰囲気が漂っていること、周囲にも伝わっているかもしれない。
聞かなければよかった。
わざわざ宏紀の根幹に触れなくてもよかった。
自己嫌悪になった。
「未砂」
宏紀の声で頭を秒速で上げた。
「特にないよ。最近、疲れてるのかな。ほら、大学まだまだ慣れてないし」
無理に頬を上げる宏紀がいた。それが痛くて目をどこかに投げたくなった。傷口を抉ったのはここにいる私だ。
「そっか……ごめん、変なこと聞いて」
宏紀はただ頷いて言葉を飲み込んだ。
今の反応でなんとなく答えは見つかった。私が思い描いた妄想にすっぽりとはまっている。そこから宏紀を助け出す。
「宏紀、私これも食べたい!」
私が指をさしたのは食後のデザートだった。落ち込んだ雰囲気は持ち前の明るさでなんとかしようと自分で背中を押した。
「うん」
宏紀は小さく笑った。
一度落とした気持ちをすぐに持ち直すのがどれだけ大変か知っている。宏紀は無理に笑ってくれているんだ。
その後、宏紀は何事もなかったかのように話してくれた。宏紀も周囲に少なからず自分の異変を感じ取られているって思っているのかもしれない。
宏紀の前でこんなに無理に笑おうとするのは違和感があるけど、今日は仕方ない。
私と新浦安駅まで歩いたときに見た夕焼けとほとんど同じで、あのきれいな情景を思い出して、少しでも宏紀の心の中に居座る煙を消し去ってほしい。
部活動に精を出す子たちを、宏紀は緑色のグランドを囲む観覧席で意味もなく何かを眺めている。ざわついたメインストリート、溢れかえる学生の波に飲まれて帰るのが億劫になって知らぬ間にここに行き着いた。
緑を背景に笑い声がこだまする。高校時代に見た景色が宏紀の視界に映る。心の中で力なくつぶやく。あの時と変わっていない……。
「宏紀」
宏紀は反応せずにただグラウンドを見つめたままだ。
二度目の呼びかけにようやく体をひねる。呼びかけたのは七海だった。
「ああ、七海」
ただでさえ身長がある七海が大きく見える。
「何してるの? こんなところで?」
七海は宏紀の真横に座った。七海のアパートの匂いを思い出す。一人暮らしも板についてきたのかと宏紀は想像する。
「いや……別に」
理由を探しても、理由が見つからなくて宏紀はただそう言うしかなかった。
「そうなんだ。後ろ姿、なんか絵になる感じだったよ」
七海は微笑む。
「そんなにいい背中してないよ……これからバイト?」
バイトの制服らしきものが入っている七海のトートバッグを見つめた。
「うん。まだちゃんと仕事覚えてないから、なるべく入ろうと思って」
「じゃあ、あんまり時間ない感じか……」
寂しそうに宏紀の視線が落ちる。
「そんなことないよ。私も講義が終わった後は、少し休みたいから大丈夫だよ」
七海の笑顔に触れる宏紀。宏紀の気持ちは何もしなくても楽になっていくのが分かる。何か重いものが取り払われて、体が風船のように浮いた気がした。
「今日はどのくらい働くの?」
「今日はね、六時からラストまで」
「そっか。頑張ってるね」
優しく頬を緩ませて宏紀は言った。
「宏紀たちがいるからだよ。大学でうまくやっていけるか不安だったけど、宏紀がいたのは大きかった。一人でも知っている子がいるって、こんなに楽なんだね」
宏紀は七海の言葉をどう受け止めたのか。優しさに包まれた言葉でも宏紀の捉え方は分からない。七海への強くなるばかりか。それを振り払うのか。
「僕も同じだよ。七海が一緒で良かった」
「今度さ、バイト先も来てよ。ごちそうはできないけど、来てくれたら嬉しい」
宏紀の心を癒せるのは七海しかいない。
「行きたい。コーヒー……飲めるようになったから……」
「そうだったね! どうしてまた?」
「なんか……飲んでみようって……今より、大人になりたかったのかな……」
「なにそれ? コーヒーで大人になれるの? 私はもっと頑張らないと!」
「無理しないでよ……」
「うん、ありがとう。じゃあ、そろそろ行くね」
七海は立ち上がって夕焼けと緑色のグラウンドを後にしようとする。
「……七海」
「ん?」
呼び止められて七海は振り返った。
「もう……やめたい」
「なんて?」
聞こえるはずもない。ひどく力のない声だった。この言葉にすべてが詰まっているようだった。宏紀の迷いも何もかも。
「もうやめたい……」
繰り返し言うことで宏紀の声が乗った。
「大学を?」
宏紀は黙ったまま何も言わない。呼び止めておいて何も言わない。七海は困惑顔だ。
再び七海は宏紀のそばにつく。肩に下げていたバイトの制服が入ったトートバッグを外して宏紀の今に耳を傾けた。
「何かあったの? なんかよく見ると顔色も良くない感じだよね?」
宏紀の顔を覗き込む七海。子供を優しく看る看護師のようだった。
心中でうごめくものを吐露したけど、この先のことは七海に安易と話せるわけもない。口が裂けたとしても。
「ごめん、変なこと言って。もう大丈夫」
「本当? 絶対やめないでよ。まだ入ったばっかりじゃん」
そう。まだ入学して間もないのだ。こんな近くに闇が待ち構えていたなんて、宏紀は考えてもみなかっただろう。
「そう……だね」
「何かあったら教えて。話聞けるから」
再び七海は立ち上がって宏紀の肩をかすめるように触れた。
「ありがとう……バイト頑張って」
「うん」
七海は手を振って宏紀から離れていく。まともに七海と会話ができること。それは今はどこか恐怖なのだ。
日曜日の横浜駅。
スマホを片手に私は行き交う人々の群れから宏紀の姿を探し出す。LINEを介してメッセージを送ると、「もうすぐ着きます!」と宏紀から連絡があった。
すぐそばにあるベーカリーのガラスで今の私を確認する。いつもより入念に化粧をしてきた。宏紀の反応が若干怖いけど、気にせず向き合うつもりだ。今日は大きな仕事を背負っているような感じだ。
今日は以前に話していた映画を観に行く予定だ。その前にランチに行く。
観たい映画はピックアップしてきたけど、別にこだわりはないから宏紀と相談して決めればいい。
体がピクリと反応する。
「ごめん。少し遅れちゃった」
手を振って宏紀が近づいてきた。
「いいよ。私もさっき来たばかりだから」
宏紀に顔を見つめられる。化粧が濃いことはバレている。恥ずかしくて目を逸らしたけど、宏紀に見つめられるなら見返さないと思って宏紀を直視する。自分らしさは失いたくない。
「ランチなんだけど、カフェレストランとか、モールの中にあるすごくヘルシーなお店があるんだけど、どっちがいい?」
スマホに呼び出したレストランを宏紀に見せた。
「ああ……どっちもよさそうだね。未砂はどっちがいいの?」
「私は……モールのところがいいな」
映画館もモールの中にあるから効率がいい。
「じゃあ、そこにしよう」
モールに向かって歩き始めた。ヒールを履いてるから最初は歩く速さがうまく合わなくて気になったけど、時計の時間を合わせるように宏紀が合わせて歩いてくれたからモールに着くころには普通になった。
「七海とかは誘わなかったの?」
「うん……」
七海や真也は誘っていない。七海を誘ったら自動的に真也もっていうことになるだろう。今の宏紀にこの組み合わせは合わない。私にとってもその方がありがたい。
「映画なんだけど、これが観たいな」
誤魔化すようにスマホの画面を見せた。
「これか。すごく人気のやつだよね? 映画館に行くのは久しぶりだ」
「そうなの? いつも家で観るタイプ?」
「いや……そうでもないんだけど、行く機会がなかったっていうか……」
「そうなんだ。二ヵ月に一回行ってた、私」
「観たい映画がたくさんあるんだね、未砂は。たくさん友達もいるしね」
「強引に連れてっているだけだよ」
過去の行動を思い返して少し苦笑してしまう。宏紀を無理に歩かせて新浦安駅に行ったのもかなり強引だった。
「それでも付き合ってくれる人がいるんだからいいじゃん。相手は嬉しいと思うよ」
「そうだといいな」
嬉しさを十二分に噛みしめる。宏紀の言葉には魔法に似た不思議な力がある。
店の前には行列ができていた。宏紀と暇つぶしするなら時間はいくらあってもいい。それに今日は大仕事が待っている。
今の宏紀を知りたい。
でもこうやって宏紀と話していると、そんな話は蓋をして永遠に出てこられないようにしたい。考え過ぎだと思えるぐらい宏紀の表情は明るい。
「どうしたの? 未砂?」
「えっ?」
私の目が遠くに行ったままだった。
「大丈夫?」
「大丈夫、大丈夫」
今は考えない方がいいかもしれない。
「未砂、どれにするの?」
知らぬ間に宏紀は簡易メニューを渡されていたけど、気が付かなかった。
私は脳裏で飛び交っている思考を隠すように笑う。そして前をしっかり見据えて冷静さを取り戻す。
宏紀の今を知りたい。
助けてあげたい。私がそばにいる。それをしてどうなるか分からない。それに私の勘違いってこともある。それならすべての邪念を振り払う。
でも複雑なんだ。
宏紀と真也の間で何もないなら、宏紀はただ七海に向かってひた走るだろう。中学時代の思い出を駆け抜けるように。それなら私に勝ち目なんてない。宏紀に七海への気持ちを叶えてほしい気持ちもある。でも、それを私がただ眺めるだけの覚悟は据え置いてない。
もしも推測が正しいなら、炙り出さあれるように勝機は顔を出す。宏紀は足元に釘を打たれて動けないはず。その中で苦しんでいるはず。私のことを肯定してくれる宏紀を苦しめてまで手の中に収めたいのか。
メニューを眺める宏紀の表情を伺う。
『助けたい』と銘打った正当化は宏紀の視界にはどう映るんだろう。
「宏紀……」
「何?」
きょとんした宏紀の顔。私の真面目な顔は怖いらしいのか。
「最近、気になることが……あるんだけど……」
宏紀は少し後退りをしたような気がした。このひしめき合うような行列の後方に十分なスペースなんてないはずだ。
「……なに?」
後ろに一歩下がっても距離を詰めることで相殺する。
目を逸らして私は宏紀の胸板の辺りを見つめた。
「最近、なんか……元気、なくない?」
少しだけ硬直する宏紀の体。少しだけ触れて硬さを取り除きたくなった。顔は怖くて見られない。ただ音や私たちを包む雰囲気で判断することになる。
「真也……君と何か……」
きっと『真也』という名はダメ押しになるだろう。
「……」
口を紡ぐってことは、推測は間違いないのかもしれない。宏紀は何も言わずにただそこにいるだけだ。私に何事もないことを強調しようと言葉を選んでいるのか。
宏紀を責めているみたいだった。だんだんこの沈黙が苦しくなってくる。今日は日曜日。私たちの前後にはカップルや女友達でご飯に来ている。店内を見てみても活気があふれている。嫌な雰囲気が漂っていること、周囲にも伝わっているかもしれない。
聞かなければよかった。
わざわざ宏紀の根幹に触れなくてもよかった。
自己嫌悪になった。
「未砂」
宏紀の声で頭を秒速で上げた。
「特にないよ。最近、疲れてるのかな。ほら、大学まだまだ慣れてないし」
無理に頬を上げる宏紀がいた。それが痛くて目をどこかに投げたくなった。傷口を抉ったのはここにいる私だ。
「そっか……ごめん、変なこと聞いて」
宏紀はただ頷いて言葉を飲み込んだ。
今の反応でなんとなく答えは見つかった。私が思い描いた妄想にすっぽりとはまっている。そこから宏紀を助け出す。
「宏紀、私これも食べたい!」
私が指をさしたのは食後のデザートだった。落ち込んだ雰囲気は持ち前の明るさでなんとかしようと自分で背中を押した。
「うん」
宏紀は小さく笑った。
一度落とした気持ちをすぐに持ち直すのがどれだけ大変か知っている。宏紀は無理に笑ってくれているんだ。
その後、宏紀は何事もなかったかのように話してくれた。宏紀も周囲に少なからず自分の異変を感じ取られているって思っているのかもしれない。
宏紀の前でこんなに無理に笑おうとするのは違和感があるけど、今日は仕方ない。