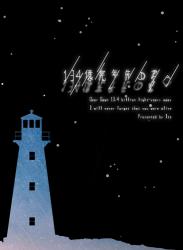…………
……
…
雨が降っていた。
パタ、パタ、パタ。大粒の雫が庇を叩く。
2年前、突然姿を消した秋里楓は再開した時、その体を花の敷きつめられた棺の中に横たえていた。
それを受け入れられるほど俺は大人ではなかったし、彼女との日々を思い出にできるほど単純な脳も持ち合わせていなかった。
葬式の後、楓に怒られるかもしれないと泣きながら俺にボイスメッセージを手渡した彼女の母親は、どんな気持ちで俺を見ていたんだろう。涙を流さない俺を軽蔑しただろうか。憎いと思っただろうか。
不思議なもので、感情はいつも遅れてやってくる。
「っ俺だって…愛してる……っ」
どんなにその名を呼んでも、届かない。もう誰も使わないマグカップ。お気に入りだと言っていた花の香りがするシャンプーに、窓の外を眺めたままのぬいぐるみ。彼女の欠片はまだここにあるのに。
なぁ、楓。掃除なんて出来なくていい。オムレツに殻が入ってたって構わない。帰ってきてくれなんて願いを、お前は聞いてはくれないのか。
「愛してる……っ」
パタ、パタ、パタ。雨はまだ、止まない。
……
…
雨が降っていた。
パタ、パタ、パタ。大粒の雫が庇を叩く。
2年前、突然姿を消した秋里楓は再開した時、その体を花の敷きつめられた棺の中に横たえていた。
それを受け入れられるほど俺は大人ではなかったし、彼女との日々を思い出にできるほど単純な脳も持ち合わせていなかった。
葬式の後、楓に怒られるかもしれないと泣きながら俺にボイスメッセージを手渡した彼女の母親は、どんな気持ちで俺を見ていたんだろう。涙を流さない俺を軽蔑しただろうか。憎いと思っただろうか。
不思議なもので、感情はいつも遅れてやってくる。
「っ俺だって…愛してる……っ」
どんなにその名を呼んでも、届かない。もう誰も使わないマグカップ。お気に入りだと言っていた花の香りがするシャンプーに、窓の外を眺めたままのぬいぐるみ。彼女の欠片はまだここにあるのに。
なぁ、楓。掃除なんて出来なくていい。オムレツに殻が入ってたって構わない。帰ってきてくれなんて願いを、お前は聞いてはくれないのか。
「愛してる……っ」
パタ、パタ、パタ。雨はまだ、止まない。