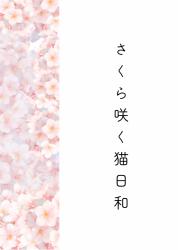パティシエの朝は早い。
六時に起床して、寝ぼけた頭を起こすために顔を洗い、衛生面を考慮して髪を結ぶ。もう何年もウルフカットにしているけれど、結んでいる時間の方が長いと思う。
コックコートに着替えて厨房に行ったら、まずはオーブンの電源を入れて、それから道具や材料を準備する。七時には作業を開始するため、テキパキと行動しなければならない。
準備が整ったら、早速その日の商品の仕込みを始める。生菓子は基本的に作り置きができず、当日に作る必要があるため、ここでも効率的な作業が求められる。
「苺! そろそろ自分の支度しなさい」
父さんにそう言われるまで、時間を忘れて手伝いをしてしまうことも多い。時計を確認すれば、確かに家を出る時刻が迫っている。
制服に着替え、急ぎながらも朝食を味わって食べて、歯磨きをして、リュックを背負って……今日もなんとか、いつものバスに間に合う時刻に家を出ることができた。
海沿いの国道を走るバスからの眺めは、毎日見ても飽きないほどに爽やかで心地良い。朝日を反射して優しく煌めく海は、どんな人間の心も平等に照らそうとしてくれている気がする。
俺の最寄りから二つ先の駅に着くと、見慣れた栗色の髪の持ち主が乗ってくる。今日も相変わらず、「眠くて機嫌が悪いです」という顔をしている。
「苺、おはよー。あー眠い眠い」
「歩、おはよう」
歩は隣に座ると、丸い手鏡と折りたたみ式のコームを取り出して髪の毛を梳かし始める。高校の最寄りに着くまで、こだわりの前髪のセットに集中して、降りる直前には器用な手つきで薄ピンクのリップを塗るのだ。
歩がバスを降りれば、そこには花が咲く。同級生も先輩も、隣を歩く俺ではなく、歩に見惚れているのだと分かる。
歩は入学初日からみんなの注目を集めていた。男子しかいないこの高校で、その可愛らしい顔立ちは特別目立っていたのだろう。
「はぁ〜……」
「歩? どうしたの?」
下駄箱に靴を入れながら、歩は大きなため息を吐いた。その様子は、たまに漫画で見るような、魂が口から抜けたイラストを想起させた。
歩は周りをキョロキョロと確認したあと、俺の耳に口を寄せる。
「苺も見たっしょ? あの三年の二人組!」
「ん? ああ、あそこにいる……」
「あいつら入学式のときからしつこい! 視線がキモい! てか、なんであの顔で俺を狙えると思ってんのかな〜」
歩はこう見えて、実はかなりの毒舌家だ。
もちろん、俺の前でしかその性質は見せないけれど。
「歩は水上先輩だけだもんね」
「そうっ! マジで全員さ、水上先輩よりかっこよくなってから出直してこいって感じー」
水上先輩は俺たちより一つ上の二年生で、歩の幼馴染かつ初恋の人だ。高身長イケメンで成績は常にトップ層、さらには運動神経も良いというのだから、歩がメロメロになるのも頷ける。
しかし、驚いたことに、この男子校には水上先輩のような人間があと三人もいる。彼らは校内に限らず、近隣の共学校からも注目されているイケメン集団だ。
「苺は好きな人いないの? あ、水上先輩はダメだよ」
「それは絶対ないから大丈夫。俺は……好きな人いないな」
「んー、じゃあ推しは?」
「推しも……いないかな」
俺はこのとき、歩に嘘をついたかもしれない。
かもしれない、という曖昧な表現を選ぶのは、その人に対して、俺の中で「推し」と呼べるほどの熱量はないと思うからだ。
二週間前の体育祭で、その人が徒競走をぶっちぎりの一位でゴールした姿が、ちょっとかっこよく見えただけ。
それ以降、イケメン集団が廊下を歩くとき、なんとなくその人のことを目が追いかけてしまうだけ。
その程度のことなのだ。
最近の推し活ブームは凄まじい。グッズをたくさん買って飾ったり、推しカラーの持ち物を揃えたりする人々の様子を見ていると、とてもじゃないけど自分が誰かを推しているなどと口にできない。
でも、俺にだって夢中になる「こと」ならある。
これだけは自信を持って好きだと言える、そんな、特別なこと……それは――。
◇
「では、今週の活動を始めます。よろしくお願いします!」
部長の如月先輩の号令で、今週も楽しい部活の時間が始まる。歩も「バレンタインまでにお菓子作りの腕を上げる!」と張り切った様子だ。
俺と歩の所属する調理部では、週に一度みんなでお菓子を作る。部員がリクエストしたお菓子の中から毎週どれか一つを選び、各学年が一人ずつ集まった三人班で調理をするのだ。
俺と同じ班なのは、部長の如月先輩と二年の高橋先輩。二人ともとても優しくて、入部したばかりの頃からたくさん話しかけてくれる。
それなのに俺は人見知りを発動して、最低限の言葉しか声にならないし、おそらく無表情で接してしまっているから、いつも申し訳なく思っている。
「苺は本当に手際がいいよね」
「ですね。家がケーキ屋って知ってても、やっぱりすごい」
「ありがとうございます……」
先輩たちは俺の人見知りを咎めるどころか、長所を見つけて褒めてくれる。俺はただ、小さい頃から大好きなお菓子作りを、楽しいという気持ちに突き動かされるままに続けてきただけなのだけど……「好き」を褒めてもらえると、自分の全てを肯定してもらえたような浮かれた気分になる。
「苺! 薄力粉多すぎない?」
「あ……」
今日の俺は、浮かれすぎていたのかもしれない。俺が分量を盛大に間違えた結果、一時間後には想定の約三倍のマフィンが完成してしまった。
「わ〜、苺、たくさん作ったね」
「歩……ちょっといる?」
「いや、俺も自分の班の分あるし。まあ二個くらいなら貰ってあげる」
歩は言葉通り、マフィンを二つ持っていってくれた。水上先輩には自分の班のやつをあげたいから間違えないようにって、ちゃんと違う袋に入れていた。
それにしても、まだまだマフィンは多い。これでも先輩たちと三等分したのだけれど。
俺の家族は自分の店の余ったケーキを食べるから、甘いものを持って帰っても食べてくれないだろう。つまり、俺が一人で食べるしかない。
もちろん味は美味しいから、飽きるまでは最高の食べ放題だと思えるけれど、やはり後半は飽きが来るだろうし、義務感で食べるのはこのマフィンに失礼な気がして……既に心が痛い。
「んー……」
「そのマフィン、俺にちょうだい」
「……え?」
心臓が止まるかと思った。いや、もしかしたら本当に一瞬だけ止まったかも。だって、俺しかいないはずの調理室で、他の人の声が聞こえたのだから。
まさか、まさかとは思うけど、この学校には実は調理室にまつわる七不思議があって、今まさにその怪奇現象が起こったという可能性が……?
「ねぇ、苺ちゃん。聞こえてる?」
「ひゃっ」
いつのまにか隣にいた人物から咄嗟に離れ、掃除用具入れの陰に隠れた。でも、そういえば、この声にはどこかで聞き覚えがある。それに先ほど淡く香った香りも……。
恐る恐るその人物を確認すると、青空の色をした瞳がこちらを見ていた。俺の予想は当たっていた。
「甘伊先輩……?」
「苺ちゃん、俺の名前知ってるの?」
「有名、なので……」
逆に、なぜ俺の名前を知っているのか聞きたいけれど、甘伊先輩と目が合うだけで今この瞬間も鼓動が速くなって、全く言葉が出てこない。
「俺はね〜、高橋からたまに苺ちゃんの話聞いててさ。ほら、同じ班なんでしょ?」
「ぁ、はい」
俺が聞きたいことを見透かしたみたいに甘伊先輩は話した。なるほど、高橋先輩が話していたというなら納得だ。裏でどんな話をされているのか分からないから少し怖いけれど、甘伊先輩の様子を見る限り嫌われているようには感じない。
「それで、そのマフィンってどうするの?」
「持って、帰ります」
「たくさんあるけど……俺が貰っちゃダメ、かな?」
甘伊先輩は上半身を屈めて俺の表情を伺おうとする。せっかく目線を合わせていただいたが、多分、俺は今も無表情だ。家族以外の前だと、顔の筋肉の動かし方が分からなくなるのだ。
親友の歩はそのことを理解してくれている。だから俺も安心して、無理に表情を作ろうとすることもなくなってしまった。俺は今の人間関係に甘えているのだ。
「……苺ちゃんって、案外分かりやすいよね」
「ぇ」
「視線の動きとか、瞬きの回数とか、顔の血色とか……じっと見てると、何考えてるのか分かってくる」
はらりと落ちてきた後れ毛を耳にかけられる。甘伊先輩の指が耳たぶに触れたせいで、心臓が勢いよく跳ねた。まだ先輩の誕生日も好きな食べ物も知らないのに、体温が意外と高いということだけは知ってしまった。
「顔赤くなった」
「っ……」
笑顔は作れないし、声も出せないのに、顔は赤くなるだなんて……恥ずかしいにもほどがある。甘伊先輩はふんわりした微笑みを向けてくれるけれど、今すぐにでもここから逃げ出したい気分だ。
「で、マフィンはやっぱりダメ?」
「だ、ダメじゃないです。どうぞ……」
使おうと思っていた紙袋に全てのマフィンを入れて渡すと、甘伊先輩は瞳を輝かせて受け取ってくれた。渡した直後に気づいたけれど、さすがに全部はいらなかったかもしれない。
「今、一つ食べてもいい?」
首を縦に振ると、先輩はまたまた瞳をきらきらさせて「いただきます」とマフィンを一口食べた。大きな一口だった。
「ん〜! すごく美味しい!」
「っ! ほ、ほんとに?」
「うん、ほんとに」
ぱくり、ぱくり、とあっという間にマフィンは先輩の口の中へ消えていく。その様子を見て「あげて良かった」と思った。家の店で売ってるケーキも調理部で作るお菓子も、食べ物は全て、心の底から「美味しい」と思ってもらうべき存在だと俺は考えているから。
「ねぇ、苺ちゃん」
先輩は、紙袋を持っていない方の手を差し出してくる。非日常的な出来事の連続で動けずにいると、その手は優しく俺の手を取ったのだった。
「バス停まで一緒に行かない?」
◇
海沿いの道を、甘伊先輩と並んで歩いている。海に沈もうとする夕日はきっと綺麗だろうが、横を見れば先輩と目が合ってしまうかもしれないから、安易に視線を動かせない。
でも、夕日を反射する海を背景に先輩が笑ったなら、おそらくものすごく美しい。想像したら「恥ずかしい」という気持ちより「見てみたい」という気持ちの方が、うんと大きくなってしまった。
「今日ね、教室に宿題のプリント忘れちゃって。部活終わりに取りに戻るの面倒だな〜って思ってたんだけど……結果的に、苺ちゃんに会えたからラッキーだった」
「……!」
思わず顔を上げてしまった。そして息を呑んだ。この目で見る先輩の笑顔は、想像していたよりずっと綺麗だったから。
「……あの、さ、苺ちゃんがよければ、なんだけど」
先輩は少し躊躇いがちに、けれども視線は逸らさずに何かを言おうとしている。なんだろう、と首を傾げると、先輩は紙袋から大切そうにマフィンを一つ取り出してみせた。
「苺ちゃんが部活で作ったお菓子、また、食べさせてもらえませんか?」
「えっ」
「あ、もちろん余ったらで大丈夫だから。それに、何かお礼もするから」
甘伊先輩が、俺の作ったものを、また食べたいと言ってくれた? あんなにも美味しそうに食べてくれる人が、また……。
想像しただけで胸が高鳴る。経験則上、この想像を遥かに超える現実が待っている。
「食べてほしい、です……」
「っ! ほんとに?」
必死で何度も頷いた。言葉にするのも表情を作るのも苦手だけど、先輩にこの気持ちが伝わってほしいから。
「嬉しい……ありがとう、苺ちゃん」
「い、いえ」
いつのまにか沈みきった太陽に感謝した。一日のうちに二度も顔の赤さを指摘されては敵わないから。もっとも、薄暗くてもバレてしまうものなのかもしれないが……。
「あれ、待って、苺ちゃんってバス通学だよね?」
「はい……」
「うわぁ〜ほんとにごめん! バス停ちょっと過ぎちゃったよね。俺、浮かれてて、普通に歩いてた……」
いつだか女子が話していたが、甘伊先輩は徒歩で通える範囲に住んでいる。だから、いつも通り歩いてしまったのだろう。
「ごめんね、言い出しにくかったよね……」
「……がいます」
「ん?」
「ち、違います」
気づけば口が勝手に動いていて、自分でも驚いた。でも、きっとそれほどに訂正したかったのだ。
「あ、そっか、俺がずっと話しかけてたから、苺ちゃんも通り過ぎたの気づかなかったか」
「違いますっ」
「違うの……?」
言い出しにくかったとか、気づかなかったとか、全然そんなのじゃない。俺はバス停を通り過ぎてしまったことに「気づいていた」し、その上で敢えて「何も言わなかった」んだ。
「……苺ちゃん、それって、」
「帰りますっ」
一礼して、先輩の顔は見ずに引き返した。ちょっと今日はもう限界だ、色々と。俺が対応できるコミュニケーションの域を飛び出てしまった。
「苺ちゃん!」
背中にぶつかった声がブレーキになる。早くこの場を去りたいのに、もう一度先輩の顔を見たくなってしまう。
「また明日ね!」
「っ……!」
「あと、お礼! 何がいいか考えておいて!」
ドキドキとうるさく鳴る心臓を抑えながら、先輩とは目を合わせないよう軽く後ろを向いてお辞儀をした。そして今度こそ駆け出した。
バス停に着いて息を整えていると、後ろから肩を叩かれる。振り向けば、やけにご機嫌な顔をした歩がいるではないか。
「苺〜っ、聞いて聞いて! 水上先輩にマフィン渡したらね、その場で食べて『美味しい』って言ってくれてぇ、しかも頭をなでなでしてくれて〜……って、苺?」
「っ、よ、良かったね」
「ん〜? んん〜?」
歩は俺の顔を穴が開くほどじっと見つめてくる。
まずい、これは、何か言われる。
歩のことを騙せるほど俺は器用じゃないというのに。
「……氷雨苺さん。あなた、恋をしていますね?」
「っ! してない……」
「いや、してるね〜。だって目にハートがあるもん」
そんなまさか、漫画じゃないんだから、目にハートなんてあるわけない……と言いたいところだが、もしかすると本当に? なんて思って鏡を見たくなる。
それは、やはり、自覚があるからだ。
この放課後のやりとりを通して、甘伊先輩への興味が確実に深くなったという自覚が。
「……推し、は、できたかも」
「ほほう。ズバリ、その推しの名前は?」
「……ぁ、甘伊先輩」
「そ、そうだったの!?」
徒競走をぶっちぎりの一位でゴールした姿が、ちょっとかっこよく見えただけ。
イケメン集団が廊下を歩くとき、なんとなく目が追いかけてしまうだけ。
その程度のことのはずだったのに……。
この日から、俺と甘伊先輩の、少し不思議な関係が始まってしまったんだ――。
六時に起床して、寝ぼけた頭を起こすために顔を洗い、衛生面を考慮して髪を結ぶ。もう何年もウルフカットにしているけれど、結んでいる時間の方が長いと思う。
コックコートに着替えて厨房に行ったら、まずはオーブンの電源を入れて、それから道具や材料を準備する。七時には作業を開始するため、テキパキと行動しなければならない。
準備が整ったら、早速その日の商品の仕込みを始める。生菓子は基本的に作り置きができず、当日に作る必要があるため、ここでも効率的な作業が求められる。
「苺! そろそろ自分の支度しなさい」
父さんにそう言われるまで、時間を忘れて手伝いをしてしまうことも多い。時計を確認すれば、確かに家を出る時刻が迫っている。
制服に着替え、急ぎながらも朝食を味わって食べて、歯磨きをして、リュックを背負って……今日もなんとか、いつものバスに間に合う時刻に家を出ることができた。
海沿いの国道を走るバスからの眺めは、毎日見ても飽きないほどに爽やかで心地良い。朝日を反射して優しく煌めく海は、どんな人間の心も平等に照らそうとしてくれている気がする。
俺の最寄りから二つ先の駅に着くと、見慣れた栗色の髪の持ち主が乗ってくる。今日も相変わらず、「眠くて機嫌が悪いです」という顔をしている。
「苺、おはよー。あー眠い眠い」
「歩、おはよう」
歩は隣に座ると、丸い手鏡と折りたたみ式のコームを取り出して髪の毛を梳かし始める。高校の最寄りに着くまで、こだわりの前髪のセットに集中して、降りる直前には器用な手つきで薄ピンクのリップを塗るのだ。
歩がバスを降りれば、そこには花が咲く。同級生も先輩も、隣を歩く俺ではなく、歩に見惚れているのだと分かる。
歩は入学初日からみんなの注目を集めていた。男子しかいないこの高校で、その可愛らしい顔立ちは特別目立っていたのだろう。
「はぁ〜……」
「歩? どうしたの?」
下駄箱に靴を入れながら、歩は大きなため息を吐いた。その様子は、たまに漫画で見るような、魂が口から抜けたイラストを想起させた。
歩は周りをキョロキョロと確認したあと、俺の耳に口を寄せる。
「苺も見たっしょ? あの三年の二人組!」
「ん? ああ、あそこにいる……」
「あいつら入学式のときからしつこい! 視線がキモい! てか、なんであの顔で俺を狙えると思ってんのかな〜」
歩はこう見えて、実はかなりの毒舌家だ。
もちろん、俺の前でしかその性質は見せないけれど。
「歩は水上先輩だけだもんね」
「そうっ! マジで全員さ、水上先輩よりかっこよくなってから出直してこいって感じー」
水上先輩は俺たちより一つ上の二年生で、歩の幼馴染かつ初恋の人だ。高身長イケメンで成績は常にトップ層、さらには運動神経も良いというのだから、歩がメロメロになるのも頷ける。
しかし、驚いたことに、この男子校には水上先輩のような人間があと三人もいる。彼らは校内に限らず、近隣の共学校からも注目されているイケメン集団だ。
「苺は好きな人いないの? あ、水上先輩はダメだよ」
「それは絶対ないから大丈夫。俺は……好きな人いないな」
「んー、じゃあ推しは?」
「推しも……いないかな」
俺はこのとき、歩に嘘をついたかもしれない。
かもしれない、という曖昧な表現を選ぶのは、その人に対して、俺の中で「推し」と呼べるほどの熱量はないと思うからだ。
二週間前の体育祭で、その人が徒競走をぶっちぎりの一位でゴールした姿が、ちょっとかっこよく見えただけ。
それ以降、イケメン集団が廊下を歩くとき、なんとなくその人のことを目が追いかけてしまうだけ。
その程度のことなのだ。
最近の推し活ブームは凄まじい。グッズをたくさん買って飾ったり、推しカラーの持ち物を揃えたりする人々の様子を見ていると、とてもじゃないけど自分が誰かを推しているなどと口にできない。
でも、俺にだって夢中になる「こと」ならある。
これだけは自信を持って好きだと言える、そんな、特別なこと……それは――。
◇
「では、今週の活動を始めます。よろしくお願いします!」
部長の如月先輩の号令で、今週も楽しい部活の時間が始まる。歩も「バレンタインまでにお菓子作りの腕を上げる!」と張り切った様子だ。
俺と歩の所属する調理部では、週に一度みんなでお菓子を作る。部員がリクエストしたお菓子の中から毎週どれか一つを選び、各学年が一人ずつ集まった三人班で調理をするのだ。
俺と同じ班なのは、部長の如月先輩と二年の高橋先輩。二人ともとても優しくて、入部したばかりの頃からたくさん話しかけてくれる。
それなのに俺は人見知りを発動して、最低限の言葉しか声にならないし、おそらく無表情で接してしまっているから、いつも申し訳なく思っている。
「苺は本当に手際がいいよね」
「ですね。家がケーキ屋って知ってても、やっぱりすごい」
「ありがとうございます……」
先輩たちは俺の人見知りを咎めるどころか、長所を見つけて褒めてくれる。俺はただ、小さい頃から大好きなお菓子作りを、楽しいという気持ちに突き動かされるままに続けてきただけなのだけど……「好き」を褒めてもらえると、自分の全てを肯定してもらえたような浮かれた気分になる。
「苺! 薄力粉多すぎない?」
「あ……」
今日の俺は、浮かれすぎていたのかもしれない。俺が分量を盛大に間違えた結果、一時間後には想定の約三倍のマフィンが完成してしまった。
「わ〜、苺、たくさん作ったね」
「歩……ちょっといる?」
「いや、俺も自分の班の分あるし。まあ二個くらいなら貰ってあげる」
歩は言葉通り、マフィンを二つ持っていってくれた。水上先輩には自分の班のやつをあげたいから間違えないようにって、ちゃんと違う袋に入れていた。
それにしても、まだまだマフィンは多い。これでも先輩たちと三等分したのだけれど。
俺の家族は自分の店の余ったケーキを食べるから、甘いものを持って帰っても食べてくれないだろう。つまり、俺が一人で食べるしかない。
もちろん味は美味しいから、飽きるまでは最高の食べ放題だと思えるけれど、やはり後半は飽きが来るだろうし、義務感で食べるのはこのマフィンに失礼な気がして……既に心が痛い。
「んー……」
「そのマフィン、俺にちょうだい」
「……え?」
心臓が止まるかと思った。いや、もしかしたら本当に一瞬だけ止まったかも。だって、俺しかいないはずの調理室で、他の人の声が聞こえたのだから。
まさか、まさかとは思うけど、この学校には実は調理室にまつわる七不思議があって、今まさにその怪奇現象が起こったという可能性が……?
「ねぇ、苺ちゃん。聞こえてる?」
「ひゃっ」
いつのまにか隣にいた人物から咄嗟に離れ、掃除用具入れの陰に隠れた。でも、そういえば、この声にはどこかで聞き覚えがある。それに先ほど淡く香った香りも……。
恐る恐るその人物を確認すると、青空の色をした瞳がこちらを見ていた。俺の予想は当たっていた。
「甘伊先輩……?」
「苺ちゃん、俺の名前知ってるの?」
「有名、なので……」
逆に、なぜ俺の名前を知っているのか聞きたいけれど、甘伊先輩と目が合うだけで今この瞬間も鼓動が速くなって、全く言葉が出てこない。
「俺はね〜、高橋からたまに苺ちゃんの話聞いててさ。ほら、同じ班なんでしょ?」
「ぁ、はい」
俺が聞きたいことを見透かしたみたいに甘伊先輩は話した。なるほど、高橋先輩が話していたというなら納得だ。裏でどんな話をされているのか分からないから少し怖いけれど、甘伊先輩の様子を見る限り嫌われているようには感じない。
「それで、そのマフィンってどうするの?」
「持って、帰ります」
「たくさんあるけど……俺が貰っちゃダメ、かな?」
甘伊先輩は上半身を屈めて俺の表情を伺おうとする。せっかく目線を合わせていただいたが、多分、俺は今も無表情だ。家族以外の前だと、顔の筋肉の動かし方が分からなくなるのだ。
親友の歩はそのことを理解してくれている。だから俺も安心して、無理に表情を作ろうとすることもなくなってしまった。俺は今の人間関係に甘えているのだ。
「……苺ちゃんって、案外分かりやすいよね」
「ぇ」
「視線の動きとか、瞬きの回数とか、顔の血色とか……じっと見てると、何考えてるのか分かってくる」
はらりと落ちてきた後れ毛を耳にかけられる。甘伊先輩の指が耳たぶに触れたせいで、心臓が勢いよく跳ねた。まだ先輩の誕生日も好きな食べ物も知らないのに、体温が意外と高いということだけは知ってしまった。
「顔赤くなった」
「っ……」
笑顔は作れないし、声も出せないのに、顔は赤くなるだなんて……恥ずかしいにもほどがある。甘伊先輩はふんわりした微笑みを向けてくれるけれど、今すぐにでもここから逃げ出したい気分だ。
「で、マフィンはやっぱりダメ?」
「だ、ダメじゃないです。どうぞ……」
使おうと思っていた紙袋に全てのマフィンを入れて渡すと、甘伊先輩は瞳を輝かせて受け取ってくれた。渡した直後に気づいたけれど、さすがに全部はいらなかったかもしれない。
「今、一つ食べてもいい?」
首を縦に振ると、先輩はまたまた瞳をきらきらさせて「いただきます」とマフィンを一口食べた。大きな一口だった。
「ん〜! すごく美味しい!」
「っ! ほ、ほんとに?」
「うん、ほんとに」
ぱくり、ぱくり、とあっという間にマフィンは先輩の口の中へ消えていく。その様子を見て「あげて良かった」と思った。家の店で売ってるケーキも調理部で作るお菓子も、食べ物は全て、心の底から「美味しい」と思ってもらうべき存在だと俺は考えているから。
「ねぇ、苺ちゃん」
先輩は、紙袋を持っていない方の手を差し出してくる。非日常的な出来事の連続で動けずにいると、その手は優しく俺の手を取ったのだった。
「バス停まで一緒に行かない?」
◇
海沿いの道を、甘伊先輩と並んで歩いている。海に沈もうとする夕日はきっと綺麗だろうが、横を見れば先輩と目が合ってしまうかもしれないから、安易に視線を動かせない。
でも、夕日を反射する海を背景に先輩が笑ったなら、おそらくものすごく美しい。想像したら「恥ずかしい」という気持ちより「見てみたい」という気持ちの方が、うんと大きくなってしまった。
「今日ね、教室に宿題のプリント忘れちゃって。部活終わりに取りに戻るの面倒だな〜って思ってたんだけど……結果的に、苺ちゃんに会えたからラッキーだった」
「……!」
思わず顔を上げてしまった。そして息を呑んだ。この目で見る先輩の笑顔は、想像していたよりずっと綺麗だったから。
「……あの、さ、苺ちゃんがよければ、なんだけど」
先輩は少し躊躇いがちに、けれども視線は逸らさずに何かを言おうとしている。なんだろう、と首を傾げると、先輩は紙袋から大切そうにマフィンを一つ取り出してみせた。
「苺ちゃんが部活で作ったお菓子、また、食べさせてもらえませんか?」
「えっ」
「あ、もちろん余ったらで大丈夫だから。それに、何かお礼もするから」
甘伊先輩が、俺の作ったものを、また食べたいと言ってくれた? あんなにも美味しそうに食べてくれる人が、また……。
想像しただけで胸が高鳴る。経験則上、この想像を遥かに超える現実が待っている。
「食べてほしい、です……」
「っ! ほんとに?」
必死で何度も頷いた。言葉にするのも表情を作るのも苦手だけど、先輩にこの気持ちが伝わってほしいから。
「嬉しい……ありがとう、苺ちゃん」
「い、いえ」
いつのまにか沈みきった太陽に感謝した。一日のうちに二度も顔の赤さを指摘されては敵わないから。もっとも、薄暗くてもバレてしまうものなのかもしれないが……。
「あれ、待って、苺ちゃんってバス通学だよね?」
「はい……」
「うわぁ〜ほんとにごめん! バス停ちょっと過ぎちゃったよね。俺、浮かれてて、普通に歩いてた……」
いつだか女子が話していたが、甘伊先輩は徒歩で通える範囲に住んでいる。だから、いつも通り歩いてしまったのだろう。
「ごめんね、言い出しにくかったよね……」
「……がいます」
「ん?」
「ち、違います」
気づけば口が勝手に動いていて、自分でも驚いた。でも、きっとそれほどに訂正したかったのだ。
「あ、そっか、俺がずっと話しかけてたから、苺ちゃんも通り過ぎたの気づかなかったか」
「違いますっ」
「違うの……?」
言い出しにくかったとか、気づかなかったとか、全然そんなのじゃない。俺はバス停を通り過ぎてしまったことに「気づいていた」し、その上で敢えて「何も言わなかった」んだ。
「……苺ちゃん、それって、」
「帰りますっ」
一礼して、先輩の顔は見ずに引き返した。ちょっと今日はもう限界だ、色々と。俺が対応できるコミュニケーションの域を飛び出てしまった。
「苺ちゃん!」
背中にぶつかった声がブレーキになる。早くこの場を去りたいのに、もう一度先輩の顔を見たくなってしまう。
「また明日ね!」
「っ……!」
「あと、お礼! 何がいいか考えておいて!」
ドキドキとうるさく鳴る心臓を抑えながら、先輩とは目を合わせないよう軽く後ろを向いてお辞儀をした。そして今度こそ駆け出した。
バス停に着いて息を整えていると、後ろから肩を叩かれる。振り向けば、やけにご機嫌な顔をした歩がいるではないか。
「苺〜っ、聞いて聞いて! 水上先輩にマフィン渡したらね、その場で食べて『美味しい』って言ってくれてぇ、しかも頭をなでなでしてくれて〜……って、苺?」
「っ、よ、良かったね」
「ん〜? んん〜?」
歩は俺の顔を穴が開くほどじっと見つめてくる。
まずい、これは、何か言われる。
歩のことを騙せるほど俺は器用じゃないというのに。
「……氷雨苺さん。あなた、恋をしていますね?」
「っ! してない……」
「いや、してるね〜。だって目にハートがあるもん」
そんなまさか、漫画じゃないんだから、目にハートなんてあるわけない……と言いたいところだが、もしかすると本当に? なんて思って鏡を見たくなる。
それは、やはり、自覚があるからだ。
この放課後のやりとりを通して、甘伊先輩への興味が確実に深くなったという自覚が。
「……推し、は、できたかも」
「ほほう。ズバリ、その推しの名前は?」
「……ぁ、甘伊先輩」
「そ、そうだったの!?」
徒競走をぶっちぎりの一位でゴールした姿が、ちょっとかっこよく見えただけ。
イケメン集団が廊下を歩くとき、なんとなく目が追いかけてしまうだけ。
その程度のことのはずだったのに……。
この日から、俺と甘伊先輩の、少し不思議な関係が始まってしまったんだ――。