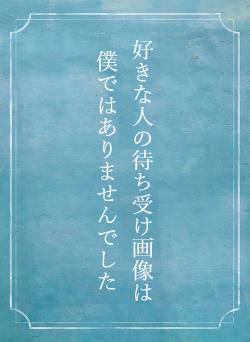この世界に転生してから二十年が経とうとしていた。
実は俺がこの体に転生してベッドで目覚めたときにはすでに一歳の誕生日を迎えた後だったらしく、グランが離乳食を温め直そうかとエヴィに提案をしていたときには気がつくべきだったのだろうが、あの時はそれどころではなかったため、もしも俺以外が転生していたとしても自身の年齢に気がつくことはなかっただろう。
そんなことはさておき、現在二十一歳である俺が初めて魔法を使ったのは一歳の頃、レヴィに訓練所に連れて行ってもらったとき、見様見真似で呪文を唱えたことがきっかけだ。
当時は魔力が体力であることを知らなかったため、魔法を発動した瞬間に俺は意識を失ってしまったが、今は様々な魔法を同時に行使しても倒れることはないほどの体力を手に入れていた。というのもあの時俺のもとにいち早く駆けつけた上官らしき人物は”らしき”ではなく本当に上官だったようで、俺の魔法を見た上官騎士は俺を騎士団にスカウトするために何度もオルシルク家へと足を運んだのだ。
オルシルクというのは俺の苗字でもあり、グランとレヴィの苗字でもある。この世界ではファーストネームというべきだろうか。
つまり俺はグランとレヴィとの間にできた子どもなのだが、転生して二十年経っても正直まだ二人に対して親という感情が芽生えたことはない。それもそうだろう。俺は元の世界で二十七年ほど生きていたわけで、当然その世界で両親はいたのだ。そう考えるとこのグランとレヴィを生みの親を認識するのは転生者である俺に取っては難しく、二人のこともお父さんやお母さんではなく、グランさんレヴィさんと呼んでいる。
そのことに対し二人はあまりよく思っていないようではあるが、二十年も経って今では何も言ってこない。きっと諦めたのだろう。
話が反れてしまったが、俺が魔法を初めて使ったあの日に俺の元に駆けつけてきた上官はエリース・ロドリウスという人物で第一騎士団魔物討伐部隊団長をしているかなりすごい人だ。俺の元に駆けつけた時が二十七歳だったらしく、今では四十七歳といったベテラン騎士となっている。当時から上官という立場だったらしく、俺の転生前の年齢と同じであることを考えるとそのすごさに拍車がかかる。
そんなエリースは俺の魔法の才能に惚れこみ「騎士にならないか」とほぼ毎日オルシルク家へ訪れては俺とグランにレヴィに勧誘をする事態に発展していた。
しかし当時の俺は一歳であり、この世界について何も理解していなければ、まだまともに話すこともできないそんな状態だったため、俺だけではなくグランもレヴィも毎日困惑していたのを覚えている。
しかしエリースはそんなことをお構いなしに家に訪れたり、俺を訓練所に連れて行ったりと、何としてでも騎士に育て上げたかったようだ。そんな俺も五歳になりある程度のことは自分だけでこなせるようになると、なぜか本格的に訓練所で騎士候補生として訓練を受けることとなった。
当時の俺は知らなかったが、この世界で騎士になるということはかなり有望らしい。騎士は元の世界でいうところの軍人的な立ち位置だと思っていたが、そうではないらしい。一応軍人的なこともするにはするのだが、どちらかと言えば狩人に近いようだ。
この世界には魔物が蔓延っており、魔物から人々や国を守る存在が騎士のようだ。だからと言って魔物を食したりはしないらしい。魔物は討伐すると灰のように体が崩れ、その姿が消えてなくなってしまうため、食べたりすることはできないのだとか。
俺がどうしてこんなにも他人行儀なのかというと、結論として俺は騎士になることはできなかったからだ。魔法の才能には恵まれたものの、剣の才能は微塵もなく、剣を使って魔物に切りかかるどころか、剣を振ることすらままならないほど向いていなかった。
それでもエリースは俺に親身になって剣術を教えてくれた。俺もそんな彼の期待に応えたくて努力はしたものの、努力ではどうしようもないことは世の中にはあるモノで、諦めざる負えなかった。
そんな俺を見かねたエリースはそれでも諦めきれず、騎士として魔物討伐部隊に入ることはできないが、魔法の才能を活かし、サポート部門に入らないかと提案を受けたのだ。
サポート部門とは騎士が所属する騎士団の部門の一つで俺はそのサポート部門の魔法付与課に配属されることとなった。俺がサポート課に配属されたのが十歳のころのため、今年で配属されて十一年目になる。
実は十歳ほどで騎士団に所属することは珍しい話ではないらしく、元の世界でいうところの学校のような形で騎士団の騎士候補生コースのような部門で騎士になるための勉強だけではなく、文字の読み書きや一般的なマナーなど様々ことを学ぶのだ。
マナーや物質の構造、数学の考え方などは元の世界とは一切の乖離はなかったものの、流石に文字だけは異なっていたようで、覚えるのに苦労したのを今でも覚えている。元いた世界と考えると俺は三十七歳で新しい言語を学んだことになる。もう少し若ければ、もしかしたらこんなにも苦労しなかったのかもしれない。
「トーラス、これが今日の分だが頼めるか?普段よりも少し量が多いのだが……」
そんなことを考えていると、エリースが俺のもとに今日の仕事で使用する大量の剣を部下の人たちと一緒に運んできた。
「エリースさんお疲れ様です。サジさんもありがとうございます。それにしても最近多いですね……。というか団長と副団長が持ってこなくても、他の方にお願いされてもいいんじゃないんですか?」
「すまんな……ここ最近魔物の動きが活発で剣の消耗が激しいんだ。それに疲弊している騎士に荷物運びをさせるわけにもいかんだろ。」
「エリースさんはほんとに素敵な上司ですね。」
「トーラスにそう言ってもらえるだけ私は嬉しいよ。」
「いえ、本当のことですから。それで今日の内訳ってどんな感じですか?」
俺は第一騎士団サポート部魔法付与課に配属されているのだが、魔法付与課では騎士が使用する剣に様々な魔法を付与する業務をメインに行っている。魔物にはそれぞれ弱点となる属性があり、その属性を剣に付与することで、より簡単にその魔物を討伐することができるのだが、魔法は付与となるため永続的にその魔法効果が発動されるわけではない。
そのため討伐遠征では何本もの剣を持っていくことになるのだが、そのたびに再付与をする必要はあるし、剣に関しては消耗品のため、刃毀れしたりする場合もある。そんなときに俺の魔法が活躍するのだ。
本来であれば魔法付与課は剣に魔法を付与するだけの部署ではあるのだが、俺の使う魔法は武器の修理を行うことも出来る。そのため俺の元には魔法付与をする剣だけではなく、折れた剣や刃毀れした剣も運ばれてくるのだ。
「各属性が三十本ずつ。修理が……さ、三百本なんだがいけるか?」
「さんびゃくぅ?多くないですか?」
「すまない……。討伐遠征直後だったのと、その間の訓練で使用したものをまとめて持ってきた。」
「ちなみに納期っていつですか?」
「………………明日とかっていける?」
エリースは俺の顔色を伺いながら、少し怒られるのを覚悟したような笑みを浮かべ、顔の前で両手を合わせながら問いかけてきた。それは一緒に剣を運んできた副団長のサジも同じようなポーズを取っており、こちらも申し訳なさそうに何度もペコペコと頭を下げていた。
俺も鬼ではないし、エリースには恩があるため出来ることなら力になりたいのだが、流石にこの量を明日までに終わらせることはほぼほぼ不可能に近いのだ。それは自身の魔力量が底をついてしまうというのもあるのだが、一番の問題は俺しか武器の修理をすることができないと言うことだ。つまりは俺一人でこの量をこなさなければならないということだ。
「すみません。正直全部は魔力的にも体力的にも難しいかもしれません。付与に関しては明日までで問題ないですが、修理に関しては一日百本を上限に最低でも三日間はいただけないですかね……。」
「そうだよな……申し訳ない。それで頼めるかい?」
「わかりました!」
正直この手の依頼には慣れている。割と重労働だとは思うのだが、元いた世界との労働と比べるとこっちの世界での仕事の方が俺に合っていると思う。
元いた世界ではエンジニア職についていた。エンジニアと言っても様々だが、俺はインフラエンジニアではなく、所謂システムエンジニアというものをしている。その中でも社内SEと呼ばれる自社開発のシステムを管轄する部署についており、社外のシステムを管轄する同期と比べると比較的楽な方であったが、それでもほぼ一日中パソコンの前に座っているのは体に来るものがあった。しかし現在の職は魔法付与と武器や備品の修理だ。魔力の消費と同時に自身の体力も削られていく。それも大変ではあるのだが、魔法を使用すると運動したかのような体力の消費を感じられるため、嫌な疲れではないのだ。
おそらくこれがこの仕事が俺にあっている理由なのだろう。
元々体を動かすことは嫌いではなかったし、何と言っても疲れ切った後の体を癒やすためにお風呂に浸かるのが本当に好きなのだ。むしろお風呂でゆっくり過ごしたいがために体を動かしていたまである。
まあ俺はお風呂に浸かるのが趣味なのだ。
俺は今日からの三日間、仕事終わりに浸かるお風呂が楽しみになる魔法を掛けられた感覚に陥りながらも、エリースの脚の動きに若干の違和感を覚えた。
「……エリースさん、脚どうしたんですか?」
「ん?あぁ恥ずかしい話、魔物相手に少し遅れを取ってしまったな。少しだけ攻撃を受けたんだ。」
そう言ってエリースはパンツの裾を持ち上げ、傷を俺に見せてくれた。
傷口はそこまでひどくないものの、それでもおそらく遠征先でテキトーに巻いたであろう包帯は血が滲んでおり、痛々しく思えた。
「討伐遠征には医療班も付いてくるんじゃないですか?」
「そうなんだが、この程度のかすり傷は後回しにして、重症の騎士から順に対処していくからな。あとはこの程度の怪我で医療班に治療を依頼するのは団長として恥ずかしいだろ。」
「……何も恥ずかしくないですよ。馬鹿なこと言わないでください。少し脚に触りますね。」
俺はそう言い、エリースの前に跪くようにしゃがみ込むと傷口に触れ、魔法を発動するための呪文を唱える。その英語で唱える御経のような呪文を唱えると、俺の触れているエリースの脚が蛍のような温かい薄い緑色に包まれた。
「……これである程度は問題ないと思います。ただちゃんと医療班の方に診てもらってください。」
「……トーラス、お前回復魔法も使えるのか?」
「え、はい。言ってませんでしたっけ?でも医療班の方ほどのモノは使えないですよ。できて簡易回復くらいです。かすり傷程度であれば問題なく回復できますが、骨折などの大怪我や毒などの状態異常は俺では治せないですね。」
「ほう……なるほど。いや、本当に助かったよ。トーラスの言う通り医療班にはこの後顔を出すことにするよ。」
「はぁ……すみませんトーラス。では依頼の分、対応お願いしますね。」
サジはそう告げると、エリースを少し引っ張っていくような形で俺の仕事部屋を後にする。
その後姿が見えなくなるのを待ってから俺は「やるか」と両手で頬を叩き気合を入れ直した。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
エリースとサジはトーラスのしごと部屋を後にした後、医療室へ向かう道中で静かに会議を始めていた。
「サジ、トーラスの魔法をどう思う?」
「……サポート部に置いておくのはもったいない人材だとは思いますよ。この国に他に使用者のいない修理系の魔法を扱えるだけではなく、簡易的な回復魔法まで使えるとは。他の騎士団がこのことを知ったら誘拐してでも、自身の騎士団に勧誘しにくるでしょうね。」
「サジもそう思うか。やはり俺の行動は間違ってなかったな。」
「トーラス騎士団長は彼が幼子のころから目をつけていたんでしたっけ?もしかしてショタコンなんですか?」
「……なぜそうなる。トーラスは息子みたいなもんだ。変な感情は抱かんよ。」
「どうだか……。それでどうするんですか?このままサポート部に置いておいて、彼の本領を発揮させないつもりですか?」
それを聞いたエリースは鼻を鳴らし、嘲笑うかのように微笑んだ。
「俺に考えがある。次の——」
実は俺がこの体に転生してベッドで目覚めたときにはすでに一歳の誕生日を迎えた後だったらしく、グランが離乳食を温め直そうかとエヴィに提案をしていたときには気がつくべきだったのだろうが、あの時はそれどころではなかったため、もしも俺以外が転生していたとしても自身の年齢に気がつくことはなかっただろう。
そんなことはさておき、現在二十一歳である俺が初めて魔法を使ったのは一歳の頃、レヴィに訓練所に連れて行ってもらったとき、見様見真似で呪文を唱えたことがきっかけだ。
当時は魔力が体力であることを知らなかったため、魔法を発動した瞬間に俺は意識を失ってしまったが、今は様々な魔法を同時に行使しても倒れることはないほどの体力を手に入れていた。というのもあの時俺のもとにいち早く駆けつけた上官らしき人物は”らしき”ではなく本当に上官だったようで、俺の魔法を見た上官騎士は俺を騎士団にスカウトするために何度もオルシルク家へと足を運んだのだ。
オルシルクというのは俺の苗字でもあり、グランとレヴィの苗字でもある。この世界ではファーストネームというべきだろうか。
つまり俺はグランとレヴィとの間にできた子どもなのだが、転生して二十年経っても正直まだ二人に対して親という感情が芽生えたことはない。それもそうだろう。俺は元の世界で二十七年ほど生きていたわけで、当然その世界で両親はいたのだ。そう考えるとこのグランとレヴィを生みの親を認識するのは転生者である俺に取っては難しく、二人のこともお父さんやお母さんではなく、グランさんレヴィさんと呼んでいる。
そのことに対し二人はあまりよく思っていないようではあるが、二十年も経って今では何も言ってこない。きっと諦めたのだろう。
話が反れてしまったが、俺が魔法を初めて使ったあの日に俺の元に駆けつけてきた上官はエリース・ロドリウスという人物で第一騎士団魔物討伐部隊団長をしているかなりすごい人だ。俺の元に駆けつけた時が二十七歳だったらしく、今では四十七歳といったベテラン騎士となっている。当時から上官という立場だったらしく、俺の転生前の年齢と同じであることを考えるとそのすごさに拍車がかかる。
そんなエリースは俺の魔法の才能に惚れこみ「騎士にならないか」とほぼ毎日オルシルク家へ訪れては俺とグランにレヴィに勧誘をする事態に発展していた。
しかし当時の俺は一歳であり、この世界について何も理解していなければ、まだまともに話すこともできないそんな状態だったため、俺だけではなくグランもレヴィも毎日困惑していたのを覚えている。
しかしエリースはそんなことをお構いなしに家に訪れたり、俺を訓練所に連れて行ったりと、何としてでも騎士に育て上げたかったようだ。そんな俺も五歳になりある程度のことは自分だけでこなせるようになると、なぜか本格的に訓練所で騎士候補生として訓練を受けることとなった。
当時の俺は知らなかったが、この世界で騎士になるということはかなり有望らしい。騎士は元の世界でいうところの軍人的な立ち位置だと思っていたが、そうではないらしい。一応軍人的なこともするにはするのだが、どちらかと言えば狩人に近いようだ。
この世界には魔物が蔓延っており、魔物から人々や国を守る存在が騎士のようだ。だからと言って魔物を食したりはしないらしい。魔物は討伐すると灰のように体が崩れ、その姿が消えてなくなってしまうため、食べたりすることはできないのだとか。
俺がどうしてこんなにも他人行儀なのかというと、結論として俺は騎士になることはできなかったからだ。魔法の才能には恵まれたものの、剣の才能は微塵もなく、剣を使って魔物に切りかかるどころか、剣を振ることすらままならないほど向いていなかった。
それでもエリースは俺に親身になって剣術を教えてくれた。俺もそんな彼の期待に応えたくて努力はしたものの、努力ではどうしようもないことは世の中にはあるモノで、諦めざる負えなかった。
そんな俺を見かねたエリースはそれでも諦めきれず、騎士として魔物討伐部隊に入ることはできないが、魔法の才能を活かし、サポート部門に入らないかと提案を受けたのだ。
サポート部門とは騎士が所属する騎士団の部門の一つで俺はそのサポート部門の魔法付与課に配属されることとなった。俺がサポート課に配属されたのが十歳のころのため、今年で配属されて十一年目になる。
実は十歳ほどで騎士団に所属することは珍しい話ではないらしく、元の世界でいうところの学校のような形で騎士団の騎士候補生コースのような部門で騎士になるための勉強だけではなく、文字の読み書きや一般的なマナーなど様々ことを学ぶのだ。
マナーや物質の構造、数学の考え方などは元の世界とは一切の乖離はなかったものの、流石に文字だけは異なっていたようで、覚えるのに苦労したのを今でも覚えている。元いた世界と考えると俺は三十七歳で新しい言語を学んだことになる。もう少し若ければ、もしかしたらこんなにも苦労しなかったのかもしれない。
「トーラス、これが今日の分だが頼めるか?普段よりも少し量が多いのだが……」
そんなことを考えていると、エリースが俺のもとに今日の仕事で使用する大量の剣を部下の人たちと一緒に運んできた。
「エリースさんお疲れ様です。サジさんもありがとうございます。それにしても最近多いですね……。というか団長と副団長が持ってこなくても、他の方にお願いされてもいいんじゃないんですか?」
「すまんな……ここ最近魔物の動きが活発で剣の消耗が激しいんだ。それに疲弊している騎士に荷物運びをさせるわけにもいかんだろ。」
「エリースさんはほんとに素敵な上司ですね。」
「トーラスにそう言ってもらえるだけ私は嬉しいよ。」
「いえ、本当のことですから。それで今日の内訳ってどんな感じですか?」
俺は第一騎士団サポート部魔法付与課に配属されているのだが、魔法付与課では騎士が使用する剣に様々な魔法を付与する業務をメインに行っている。魔物にはそれぞれ弱点となる属性があり、その属性を剣に付与することで、より簡単にその魔物を討伐することができるのだが、魔法は付与となるため永続的にその魔法効果が発動されるわけではない。
そのため討伐遠征では何本もの剣を持っていくことになるのだが、そのたびに再付与をする必要はあるし、剣に関しては消耗品のため、刃毀れしたりする場合もある。そんなときに俺の魔法が活躍するのだ。
本来であれば魔法付与課は剣に魔法を付与するだけの部署ではあるのだが、俺の使う魔法は武器の修理を行うことも出来る。そのため俺の元には魔法付与をする剣だけではなく、折れた剣や刃毀れした剣も運ばれてくるのだ。
「各属性が三十本ずつ。修理が……さ、三百本なんだがいけるか?」
「さんびゃくぅ?多くないですか?」
「すまない……。討伐遠征直後だったのと、その間の訓練で使用したものをまとめて持ってきた。」
「ちなみに納期っていつですか?」
「………………明日とかっていける?」
エリースは俺の顔色を伺いながら、少し怒られるのを覚悟したような笑みを浮かべ、顔の前で両手を合わせながら問いかけてきた。それは一緒に剣を運んできた副団長のサジも同じようなポーズを取っており、こちらも申し訳なさそうに何度もペコペコと頭を下げていた。
俺も鬼ではないし、エリースには恩があるため出来ることなら力になりたいのだが、流石にこの量を明日までに終わらせることはほぼほぼ不可能に近いのだ。それは自身の魔力量が底をついてしまうというのもあるのだが、一番の問題は俺しか武器の修理をすることができないと言うことだ。つまりは俺一人でこの量をこなさなければならないということだ。
「すみません。正直全部は魔力的にも体力的にも難しいかもしれません。付与に関しては明日までで問題ないですが、修理に関しては一日百本を上限に最低でも三日間はいただけないですかね……。」
「そうだよな……申し訳ない。それで頼めるかい?」
「わかりました!」
正直この手の依頼には慣れている。割と重労働だとは思うのだが、元いた世界との労働と比べるとこっちの世界での仕事の方が俺に合っていると思う。
元いた世界ではエンジニア職についていた。エンジニアと言っても様々だが、俺はインフラエンジニアではなく、所謂システムエンジニアというものをしている。その中でも社内SEと呼ばれる自社開発のシステムを管轄する部署についており、社外のシステムを管轄する同期と比べると比較的楽な方であったが、それでもほぼ一日中パソコンの前に座っているのは体に来るものがあった。しかし現在の職は魔法付与と武器や備品の修理だ。魔力の消費と同時に自身の体力も削られていく。それも大変ではあるのだが、魔法を使用すると運動したかのような体力の消費を感じられるため、嫌な疲れではないのだ。
おそらくこれがこの仕事が俺にあっている理由なのだろう。
元々体を動かすことは嫌いではなかったし、何と言っても疲れ切った後の体を癒やすためにお風呂に浸かるのが本当に好きなのだ。むしろお風呂でゆっくり過ごしたいがために体を動かしていたまである。
まあ俺はお風呂に浸かるのが趣味なのだ。
俺は今日からの三日間、仕事終わりに浸かるお風呂が楽しみになる魔法を掛けられた感覚に陥りながらも、エリースの脚の動きに若干の違和感を覚えた。
「……エリースさん、脚どうしたんですか?」
「ん?あぁ恥ずかしい話、魔物相手に少し遅れを取ってしまったな。少しだけ攻撃を受けたんだ。」
そう言ってエリースはパンツの裾を持ち上げ、傷を俺に見せてくれた。
傷口はそこまでひどくないものの、それでもおそらく遠征先でテキトーに巻いたであろう包帯は血が滲んでおり、痛々しく思えた。
「討伐遠征には医療班も付いてくるんじゃないですか?」
「そうなんだが、この程度のかすり傷は後回しにして、重症の騎士から順に対処していくからな。あとはこの程度の怪我で医療班に治療を依頼するのは団長として恥ずかしいだろ。」
「……何も恥ずかしくないですよ。馬鹿なこと言わないでください。少し脚に触りますね。」
俺はそう言い、エリースの前に跪くようにしゃがみ込むと傷口に触れ、魔法を発動するための呪文を唱える。その英語で唱える御経のような呪文を唱えると、俺の触れているエリースの脚が蛍のような温かい薄い緑色に包まれた。
「……これである程度は問題ないと思います。ただちゃんと医療班の方に診てもらってください。」
「……トーラス、お前回復魔法も使えるのか?」
「え、はい。言ってませんでしたっけ?でも医療班の方ほどのモノは使えないですよ。できて簡易回復くらいです。かすり傷程度であれば問題なく回復できますが、骨折などの大怪我や毒などの状態異常は俺では治せないですね。」
「ほう……なるほど。いや、本当に助かったよ。トーラスの言う通り医療班にはこの後顔を出すことにするよ。」
「はぁ……すみませんトーラス。では依頼の分、対応お願いしますね。」
サジはそう告げると、エリースを少し引っ張っていくような形で俺の仕事部屋を後にする。
その後姿が見えなくなるのを待ってから俺は「やるか」と両手で頬を叩き気合を入れ直した。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
エリースとサジはトーラスのしごと部屋を後にした後、医療室へ向かう道中で静かに会議を始めていた。
「サジ、トーラスの魔法をどう思う?」
「……サポート部に置いておくのはもったいない人材だとは思いますよ。この国に他に使用者のいない修理系の魔法を扱えるだけではなく、簡易的な回復魔法まで使えるとは。他の騎士団がこのことを知ったら誘拐してでも、自身の騎士団に勧誘しにくるでしょうね。」
「サジもそう思うか。やはり俺の行動は間違ってなかったな。」
「トーラス騎士団長は彼が幼子のころから目をつけていたんでしたっけ?もしかしてショタコンなんですか?」
「……なぜそうなる。トーラスは息子みたいなもんだ。変な感情は抱かんよ。」
「どうだか……。それでどうするんですか?このままサポート部に置いておいて、彼の本領を発揮させないつもりですか?」
それを聞いたエリースは鼻を鳴らし、嘲笑うかのように微笑んだ。
「俺に考えがある。次の——」