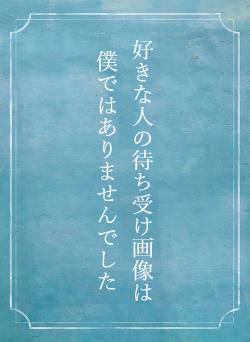動かしているのは自分自身である感覚はあるが、どう見ても自分のものではないその小さな手に俺は驚きのあまり声を出す。しかし俺の声は自動的に泣き声へと変換され、部屋中に赤ちゃんでも泣いているのかと思うほどの声が響き渡った。
その声を聞いたからなのか、何やら俺に近づいてくる足音が聞こえてくる。
(誰かが近づいてくる!医者か看護師さんだろう。その人に状況を聞けば何かわかるかもしれない……!)
しかし俺の予想に反し、俺に近づいてきた人物でどう見ても白衣を着ているわけでも、スクラブを着ているわけでもない、一人は白のワイシャツに紺色のチノパンといったシンプルな服装の黒髪の男性でもう一人は白のブラウスにカーキのロングスカートを穿いた茶髪の女性であった。
女性は俺に近づくと、俺を軽々しく持ち上げると優しく背中をさすりながらゆっくりと俺を揺らしていく。それはまるで赤子をあやすような動作であった。
「どうしたのトーラス?何か怖い夢でも見たの?」
トーラス?横にいる男性の名前だろうか?
と、いうか二人とも日本人の顔ではない。ではどこの国の顔なのかと問われればパッとは回答することはできないが、アジア系ではなく、どちらかと言えばヨーロッパ系の顔と答えるしかない。
それにしてもこの女性は俺を軽々しく持ち上げていたが、この女性は怪力の持ち主なのだろうか。二十七歳の男性をこうも簡単に抱きかかえることが出来る女性はそうはいないだろう。さらにこの女性は標準体型に見える。服で隠れていてよくわからないが、きっと筋肉量も標準に違いない。それにもかかわらず俺を持ち上げるとはどういうことだろうか。
別に俺はかなり痩せているわけではない。二十七歳にしては至って標準体重だと感じている。そのためこの女性にこうも軽々と持ち上げられたことに若干の違和感を覚えていた。
「さすが俺たちの子だ。レヴィが抱きかかえた途端に泣き止んだぞ。やっぱり赤ん坊でも親は分かるんだな。」
「グランも抱きかかえてみる?笑顔になってくれるかもよ?」
「いや俺が抱きかかえたら泣き出しそうだ……。今日は止めておくよ。」
どうやら会話の内容的に、男性は「グラン」。女性は「レヴィ」という名前らしい。つまりこの二人は日本人ではないということだ。しかし俺は日本語以外の言語の読み書きをすることはできない。大学で中国語の授業を受けていたが、卒業してから一度も中国語に触れてこなかったため、あんなにも高い学費を払って受けた授業にもかかわらず、記憶としては全く残っていないのだ。
あとはエンジニアという職業についているからか、英語であれば多少は読み書きをすることが出来るが、あくまで多少だ。流暢な英語の前では俺は何一つとして聞き取ることは出来ないだろう。
そのはずなのだが、二人の会話は問題なく聞き取ることが出来る。
それであれば二人が日本語で話しているのではないかと思うかもしれないが、おそらく同郷であろうこの二人がわざわざ日本語で話している理由が分からない。更に言えば動いている口が俺の知っている日本語の動きではないのだ。つまりこの二人が話している言語は日本語ではないものの俺が理解することができる言語ということだ。
もしかしたら交通事故の影響で新しい才能に目覚めたのかもしれない。事故の影響で何かしらのギフトを得ることがあるというのは聞いたことがある。
例えば雷に打たれた後に急に数学の才能を開花させるとか、交通事故にあいその後驚異的な記憶力を手に入れるだとかそういうものだ。もしかしたら俺もそういったものと同じような感じで言語に関するギフトを手に入れたのかもしれない。
しかし今考えなければならないのはそんなことではない。
グランの言っていた「さすが俺たちの子だ」と言うセリフだ。これはこの男女が夫婦であり、その間に生まれた子どもがいた場合にのみ発言することが出来るものだろう。加えて言えばそのセリフをあろうことか俺に向かって言い放ったのだ。
つまり俺がこの二人の間にできた子どもであることを意味している。
「何かトーラスが難しい顔をしてるぞ。」
「あら、お腹でも空いたのかしら?」
「離乳食温めなおしてこようか?」
「うんそうね。私もリビングに行くわ。」
グランとレヴィはそんな会話をすると俺を抱きかかえたまま移動を始めた。
その時俺の視界に鏡が目に入った。それはグランとレヴィと俺の三人の姿が完全に映り込むほどの大きな全身鏡であった。
そんな全身鏡に映っていたのはグランとレヴィとそしてレヴィに抱きかかえられている赤ん坊の姿であった。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
どうやら俺は異世界転生というものをしてしまったのかもしれない。
最初は夢だと思ったが、どうやら何度寝て起きてを繰り返してもこの姿であるため、認めざる負えなかった。
最初にグランが口にしていた「トーラス」というのは俺の名前らしく、俺の容姿は二人から綺麗に半分ずつの遺伝子を引き継いでいるようであった。髪色は赤毛に近い茶髪で、目は二重のクリクリとした大きな瞳。まだ自分の力で動くことは難しいが、言語を理解出来ているのは転生者だけに与えられる何かしらの効果なのだと言い聞かせた。
俺が転生したであろうこの世界は所謂剣と魔法の世界らしく、ファンタジー作品によく出てくるような設定の世界だ。そのことに気づいたのはグランとレヴィが日常的に魔法を使用しているところを見ているからなのと、グランの腰には常に日本に近い細さのロングソードが刺さっているからである。
そのため最初はグランを騎士か何かだと思っていたがそうではなく、騎士団寮にて食事を作っているシェフであることが判明した。騎士ではないものが剣を持ち歩くなんてきっとこの世界はある程度危険な世界なのだろうと勝手に考え込む。
レヴィはというと、グランと同じく騎士団寮でご飯を作っているのかと思っていたが、レヴィの仕事は騎士団寮の掃除や洗濯などをする寮母的な立ち位置の仕事をしているらしい。そんな二人の仕事を知ったのは、俺が二人に連れられて職場である騎士団寮に行ったことがあるからである。一応育児休暇というものはこの世界にもあるらしいのだが、人手が足りていないのか俺が生まれてからそんなに日が経っていないというのに二人とも職場復帰を果たしたらしい。
俺はレヴィに抱っこ紐のようなもので固定され、レヴィの肩越しに様々な情報を得ながら一日を過ごす日が続いていた。
情報は本当に様々なものがあり、この世界の文字やこの世界の住人の容姿。さらにはある程度のマナーや魔法までもを勝手に学ばせてもらった。
中でも一番の収穫は魔法だ。
俺の元居た世界には魔法なんてものは当然存在していなかったため、ひどく興味がある。
この世界の魔法は所謂発動するのに呪文を唱える必要があるモノとそうでないモノが存在しているらしく、レヴィの使う日常生活で使用するような魔法は呪文を唱える必要がないらしい。現に俺はレヴィが呪文を唱えているところを一度も見たことがない。レヴィが指をひょいと動かせば箒は自ら勝手に掃き掃除を始めるし、食器もスポンジが勝手に食器を洗っていく。洗濯物も洗濯機の無いこの世界では魔法によって服が自ら洗われに行き、勝手に干されていく。
(あ、魔法で乾かすわけじゃないんだ。)
魔法は全てができるほど万能ではないのだと思いつつも、次はレヴィに連れられ騎士たちの訓練所を見に行く。レヴィは訓練所でも仕事があるらしく「ここで大人しくしててね」近くのベンチに俺を座らせると、このだだっ広い訓練所の清掃を始めた。
その間俺は騎士たちの訓練を見学することとなった。騎士たちの訓練は体力づくりを目的としたランニングや筋トレに加え、剣技や魔法の訓練までもが行われていた。
間近で見る剣技はかなりの迫力があり、訓練とはいえ本物の剣を使っているからか剣同士がぶつかると激しく火花が散り、かなりの臨場感を味わうことができる。
そして何より魔法だ。
魔法はレヴィが使用しているものとは全く異なっており、騎士たちが使用する魔法は呪文が必要になるタイプのモノだ。魔法には属性があり、火・水・風・氷・土の魔法をこの目で確認することができた。おそらく属性を用いる魔法には呪文が必要なのだと推測をする。
呪文は俺が聞き取ることの出来る言語ではなく、強いて言えば英語で話すお経のような感じの言語だ。俺が想像していた呪文とは少し異なっていたが、これはこれでかっこいいと思う。
しかし魔法と言えば魔力を消費するようなイメージがあるが、魔力は一体いつから身につくものなのだろうか。体力イコール魔力といったものなのだろうか。まだこの世界の赤ん坊である俺はまともに話すことが出来ないため、この疑問を誰かにぶつけることが出来ず、若干モヤモヤする。
(……でもこの呪文なら今の俺にも言えるんじゃね?)
呪文は英語のようなイントネーションではあるが、その話し方はお経そのもの。見よう見まねであれば俺にも使えるかもしれない。
そう考えた俺はまだ思い通りには動かせない右腕を前に出し、近くの騎士が唱えている呪文と同じものを唱える。
——シャリン!!
呪文を唱え終えると同時に大きな音を立てたかと思えば、俺の目の前は雪景色に姿を変えていた。訓練所全体の地面は凍り、騎士たちの吐く息は白く濁って目視で確認することができる。空気中の水分も凍り付き、まるで雪が降っているかのように錯覚するほどだ。
なるほど。俺には魔法の才能があるのかもしれない。
あまりの突然のことに訓練所にいた騎士たちは瞬時に反応できずにいたが、異常を察した訓練中の上官らしき人物が俺に走って近寄ってくるのが見える。
しかしその上官が俺の元にたどり着く前に俺の視界はゆっくりと薄れていき、ベンチから凍り付いた地面へと頭から落ちていった。
やはり魔力は体力とイコールらしく、赤ん坊である俺の体力では自分の魔法に体力が追いつかないみたいだ。
その声を聞いたからなのか、何やら俺に近づいてくる足音が聞こえてくる。
(誰かが近づいてくる!医者か看護師さんだろう。その人に状況を聞けば何かわかるかもしれない……!)
しかし俺の予想に反し、俺に近づいてきた人物でどう見ても白衣を着ているわけでも、スクラブを着ているわけでもない、一人は白のワイシャツに紺色のチノパンといったシンプルな服装の黒髪の男性でもう一人は白のブラウスにカーキのロングスカートを穿いた茶髪の女性であった。
女性は俺に近づくと、俺を軽々しく持ち上げると優しく背中をさすりながらゆっくりと俺を揺らしていく。それはまるで赤子をあやすような動作であった。
「どうしたのトーラス?何か怖い夢でも見たの?」
トーラス?横にいる男性の名前だろうか?
と、いうか二人とも日本人の顔ではない。ではどこの国の顔なのかと問われればパッとは回答することはできないが、アジア系ではなく、どちらかと言えばヨーロッパ系の顔と答えるしかない。
それにしてもこの女性は俺を軽々しく持ち上げていたが、この女性は怪力の持ち主なのだろうか。二十七歳の男性をこうも簡単に抱きかかえることが出来る女性はそうはいないだろう。さらにこの女性は標準体型に見える。服で隠れていてよくわからないが、きっと筋肉量も標準に違いない。それにもかかわらず俺を持ち上げるとはどういうことだろうか。
別に俺はかなり痩せているわけではない。二十七歳にしては至って標準体重だと感じている。そのためこの女性にこうも軽々と持ち上げられたことに若干の違和感を覚えていた。
「さすが俺たちの子だ。レヴィが抱きかかえた途端に泣き止んだぞ。やっぱり赤ん坊でも親は分かるんだな。」
「グランも抱きかかえてみる?笑顔になってくれるかもよ?」
「いや俺が抱きかかえたら泣き出しそうだ……。今日は止めておくよ。」
どうやら会話の内容的に、男性は「グラン」。女性は「レヴィ」という名前らしい。つまりこの二人は日本人ではないということだ。しかし俺は日本語以外の言語の読み書きをすることはできない。大学で中国語の授業を受けていたが、卒業してから一度も中国語に触れてこなかったため、あんなにも高い学費を払って受けた授業にもかかわらず、記憶としては全く残っていないのだ。
あとはエンジニアという職業についているからか、英語であれば多少は読み書きをすることが出来るが、あくまで多少だ。流暢な英語の前では俺は何一つとして聞き取ることは出来ないだろう。
そのはずなのだが、二人の会話は問題なく聞き取ることが出来る。
それであれば二人が日本語で話しているのではないかと思うかもしれないが、おそらく同郷であろうこの二人がわざわざ日本語で話している理由が分からない。更に言えば動いている口が俺の知っている日本語の動きではないのだ。つまりこの二人が話している言語は日本語ではないものの俺が理解することができる言語ということだ。
もしかしたら交通事故の影響で新しい才能に目覚めたのかもしれない。事故の影響で何かしらのギフトを得ることがあるというのは聞いたことがある。
例えば雷に打たれた後に急に数学の才能を開花させるとか、交通事故にあいその後驚異的な記憶力を手に入れるだとかそういうものだ。もしかしたら俺もそういったものと同じような感じで言語に関するギフトを手に入れたのかもしれない。
しかし今考えなければならないのはそんなことではない。
グランの言っていた「さすが俺たちの子だ」と言うセリフだ。これはこの男女が夫婦であり、その間に生まれた子どもがいた場合にのみ発言することが出来るものだろう。加えて言えばそのセリフをあろうことか俺に向かって言い放ったのだ。
つまり俺がこの二人の間にできた子どもであることを意味している。
「何かトーラスが難しい顔をしてるぞ。」
「あら、お腹でも空いたのかしら?」
「離乳食温めなおしてこようか?」
「うんそうね。私もリビングに行くわ。」
グランとレヴィはそんな会話をすると俺を抱きかかえたまま移動を始めた。
その時俺の視界に鏡が目に入った。それはグランとレヴィと俺の三人の姿が完全に映り込むほどの大きな全身鏡であった。
そんな全身鏡に映っていたのはグランとレヴィとそしてレヴィに抱きかかえられている赤ん坊の姿であった。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
どうやら俺は異世界転生というものをしてしまったのかもしれない。
最初は夢だと思ったが、どうやら何度寝て起きてを繰り返してもこの姿であるため、認めざる負えなかった。
最初にグランが口にしていた「トーラス」というのは俺の名前らしく、俺の容姿は二人から綺麗に半分ずつの遺伝子を引き継いでいるようであった。髪色は赤毛に近い茶髪で、目は二重のクリクリとした大きな瞳。まだ自分の力で動くことは難しいが、言語を理解出来ているのは転生者だけに与えられる何かしらの効果なのだと言い聞かせた。
俺が転生したであろうこの世界は所謂剣と魔法の世界らしく、ファンタジー作品によく出てくるような設定の世界だ。そのことに気づいたのはグランとレヴィが日常的に魔法を使用しているところを見ているからなのと、グランの腰には常に日本に近い細さのロングソードが刺さっているからである。
そのため最初はグランを騎士か何かだと思っていたがそうではなく、騎士団寮にて食事を作っているシェフであることが判明した。騎士ではないものが剣を持ち歩くなんてきっとこの世界はある程度危険な世界なのだろうと勝手に考え込む。
レヴィはというと、グランと同じく騎士団寮でご飯を作っているのかと思っていたが、レヴィの仕事は騎士団寮の掃除や洗濯などをする寮母的な立ち位置の仕事をしているらしい。そんな二人の仕事を知ったのは、俺が二人に連れられて職場である騎士団寮に行ったことがあるからである。一応育児休暇というものはこの世界にもあるらしいのだが、人手が足りていないのか俺が生まれてからそんなに日が経っていないというのに二人とも職場復帰を果たしたらしい。
俺はレヴィに抱っこ紐のようなもので固定され、レヴィの肩越しに様々な情報を得ながら一日を過ごす日が続いていた。
情報は本当に様々なものがあり、この世界の文字やこの世界の住人の容姿。さらにはある程度のマナーや魔法までもを勝手に学ばせてもらった。
中でも一番の収穫は魔法だ。
俺の元居た世界には魔法なんてものは当然存在していなかったため、ひどく興味がある。
この世界の魔法は所謂発動するのに呪文を唱える必要があるモノとそうでないモノが存在しているらしく、レヴィの使う日常生活で使用するような魔法は呪文を唱える必要がないらしい。現に俺はレヴィが呪文を唱えているところを一度も見たことがない。レヴィが指をひょいと動かせば箒は自ら勝手に掃き掃除を始めるし、食器もスポンジが勝手に食器を洗っていく。洗濯物も洗濯機の無いこの世界では魔法によって服が自ら洗われに行き、勝手に干されていく。
(あ、魔法で乾かすわけじゃないんだ。)
魔法は全てができるほど万能ではないのだと思いつつも、次はレヴィに連れられ騎士たちの訓練所を見に行く。レヴィは訓練所でも仕事があるらしく「ここで大人しくしててね」近くのベンチに俺を座らせると、このだだっ広い訓練所の清掃を始めた。
その間俺は騎士たちの訓練を見学することとなった。騎士たちの訓練は体力づくりを目的としたランニングや筋トレに加え、剣技や魔法の訓練までもが行われていた。
間近で見る剣技はかなりの迫力があり、訓練とはいえ本物の剣を使っているからか剣同士がぶつかると激しく火花が散り、かなりの臨場感を味わうことができる。
そして何より魔法だ。
魔法はレヴィが使用しているものとは全く異なっており、騎士たちが使用する魔法は呪文が必要になるタイプのモノだ。魔法には属性があり、火・水・風・氷・土の魔法をこの目で確認することができた。おそらく属性を用いる魔法には呪文が必要なのだと推測をする。
呪文は俺が聞き取ることの出来る言語ではなく、強いて言えば英語で話すお経のような感じの言語だ。俺が想像していた呪文とは少し異なっていたが、これはこれでかっこいいと思う。
しかし魔法と言えば魔力を消費するようなイメージがあるが、魔力は一体いつから身につくものなのだろうか。体力イコール魔力といったものなのだろうか。まだこの世界の赤ん坊である俺はまともに話すことが出来ないため、この疑問を誰かにぶつけることが出来ず、若干モヤモヤする。
(……でもこの呪文なら今の俺にも言えるんじゃね?)
呪文は英語のようなイントネーションではあるが、その話し方はお経そのもの。見よう見まねであれば俺にも使えるかもしれない。
そう考えた俺はまだ思い通りには動かせない右腕を前に出し、近くの騎士が唱えている呪文と同じものを唱える。
——シャリン!!
呪文を唱え終えると同時に大きな音を立てたかと思えば、俺の目の前は雪景色に姿を変えていた。訓練所全体の地面は凍り、騎士たちの吐く息は白く濁って目視で確認することができる。空気中の水分も凍り付き、まるで雪が降っているかのように錯覚するほどだ。
なるほど。俺には魔法の才能があるのかもしれない。
あまりの突然のことに訓練所にいた騎士たちは瞬時に反応できずにいたが、異常を察した訓練中の上官らしき人物が俺に走って近寄ってくるのが見える。
しかしその上官が俺の元にたどり着く前に俺の視界はゆっくりと薄れていき、ベンチから凍り付いた地面へと頭から落ちていった。
やはり魔力は体力とイコールらしく、赤ん坊である俺の体力では自分の魔法に体力が追いつかないみたいだ。