本当に、衝動的だった。
この衝動に伴っていた感情を、僕は初めて知った。
期末テスト前期間の最後の土曜日の午後、テスト勉強のために国分さんの家を訪れた。
この間のお礼にと、母から持たされたゼリーの詰め合わせと、祖父から持たされた畑の夏野菜を手土産に。
国分さんの部屋へと通される。
雨に濡れて泊めてもらった日に来た時は、余裕がなくて気にも留められなかったが、整然としていて綺麗な部屋だ。
飲み物を用意すると言って国分さんが部屋を出た間に、鞄から勉強道具を取り出し、ローテーブルに置いた。
そのままその場に座って待とうか、それとも…ぐるりと部屋を見渡した。
教科書や参考書が並ぶ本棚の端には、一枚の写真が飾られていた。
陸上のユニフォームを纏った国分さんを含めた数人の男子が、一本のたすきを手に笑っている。
僕の知らない国分さんの姿だ。
写真に気を取られている間に、国分さんが部屋に戻った。
僕が写真を見ていることに気付くと、国分さんはそれを手に取った。
「これ、中学の駅伝大会の時のだな。」
「国分さん、陸上部だったんですか?」
「そう。中長距離やってたんだよ。」
「中長距離?…なんというか、意外です。」
「言ったな?これでも割りと体力あるんだからな。」
訝しげに顔を見遣る僕の額を軽く小突かれ、お互いに顔を見合わせて笑う。
「皆、良い顔してますね。国分さんも…」
「そうだな。中学生活で唯一、コイツらと陸上やってる時が一番充実してたかもな。
…俺のこと、偏見の目で見たりもしなかったし」
「そうだったんですね……」
途端に、身体の奥から言い表し様の無い感情が沸き上がってきた。
これは嫉妬心…それとも、独占欲?
国分さんが心を許すのは、僕だけがいいだなんて。
国分さんの優しさが、僕だけに向けられてほしいだなんて。
僕だけが、一人占めしたい……
まさか自分がこんなにも欲深いだなんて、思ってもみなかった。
国分さんは懐かしげに写真に見入っている。
「今でも…交流あるんですか?」
「いいや…
コイツらはそれぞれに、陸上の名門校に進学した。
大路に来たのは俺だけで、陸上辞めたのも俺だけだ。
それ以来は…なんとなく、それっきり……」
「ご、ごめんなさい…僕、無神経なこと聞いちゃって……」
「いや、水澄が気にすることない。
これは俺が選んで決めたことだから。
それより、そろそろ勉強始めるぞ。」
広げた参考書と教科書を前に、国分さんが解き方を説明してくれる。
正直、学校の授業よりもずっと解りやすい。
国分さんの説明を聞いて、問題を解いて…を繰り返す。
そのうちに、基礎的な練習問題なら一人でも解けるようになってきた。
最後の応用問題を解いたあと、国分さんがまた回答をチェックしてくれた。
ノートを覗き込む国分さんの横顔が、僕の間近にきた、ただそれだけのことだった。
そんなこと、先程から何度となくあったはずなのに。
それなのに……
ピアスが光る左耳に吸い寄せられるように、僕は唇を寄せてしまった。
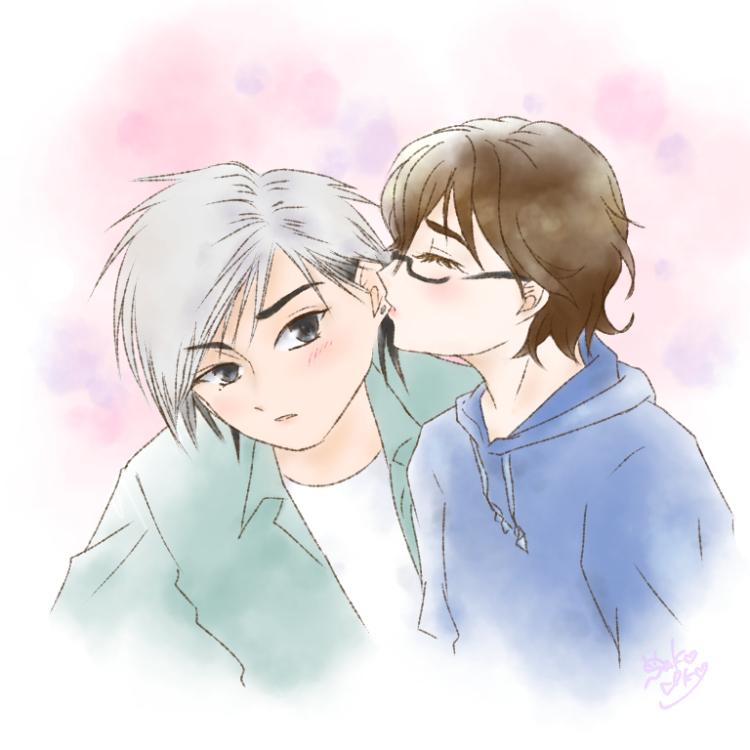
当然、耳に触れた感触に国分さんは驚いた。
「水澄…?」
「あ、あれ…僕、今……?!
ご、ごめんなさい!」
慌てて立ち上がりその場を離れようとした僕を、国分さんは逃がさなかった。
「待て!
待て、水澄…逃げるなよ……」
国分さんに腕を掴まれて逃げられなくなった僕は、再びその場に腰を下ろす。
「水澄、誤魔化さずに答えてほしい。
多分俺たち、気持ちは同じだと思うから...」
真っ直ぐに僕の目を見つめられて、もう逃げようなんて考えられなくなった。
「水澄、今のはどういう意味だ?」
「ご、ごめんなさい。
…意味なんて…なくて、ただホントに衝動的に……」
「謝らなくていいから。
ただ…それ、同じ状況で他の奴にもするのか?」
「し、しない!…です…」
「だよな?
俺も、他の奴にはしてほしくない。」
なんて答えたら良いんだろう。
国分さんは、この先何を言うんだろう。
…怖い。
僕のしたことで、国分さんと友達でいられなくなってしまったら……
「水澄は…俺が好きか?」
「えっ…と…好き、です。
でもそれは、友達としての……」
「違う、よな?」
「違わないです。」
「いや、違う。
なら、俺が今…こうしたら水澄は嫌か?」
そう言って国分さんは僕を抱き寄せると、首筋に唇で触れた。
ズキンと重く苦しく、それでいて甘やかな衝撃が身体を駆け抜けた。
嫌なんてことなかった。
ギュッと目を閉じ、国分さんの肩口に額を押し付けたまま動けない。
好き…友達?…それとも恋愛感情?
踏み出していいの?…わからない。
「水澄…」
まただ。
あの時と一緒だ。
感情ばかりが先走って、よくわからない行動に出て、国分さんを困らせてしまっている。
早く離れなきゃいけないことは解っているのに、今どんな顔をしているのか怖くて顔を上げられない。
国分さんは優しいから僕を突き放したりしないけれど。
それなら『気持ちは同じ』って言ってくれたのは…?
「水澄…
俺の方こそ煽っておいて…今更こんなことを言うのは、すげぇ狡いのはわかってるんだけどさ……」
「……」
「テストが終わったらちゃんと仕切り直すから。
このままだと、俺も水澄もなし崩しになってしまう。
それに、せっかくここまで勉強も頑張ってたのに、今ここで無駄にはしたくないから…」
「…ごめんなさい」
お互いに黙って身体を離す。
恐る恐る国分さんの顔を見遣ると、切な気に眉を下げて僕の頭を撫でた。
狡い。
「よし、良い子だ。
とりあえず休憩。一息入れたら次は化学の対策な」
用意してくれていたお茶とお菓子で気持ちを切り替える。
大丈夫。
今はテストに集中しよう。
首筋を一撫で、先程触れられた唇の感覚を思い出す。
同時に耳の奥に残る『気持ちは同じ』の言葉が僕を惑わせる。

