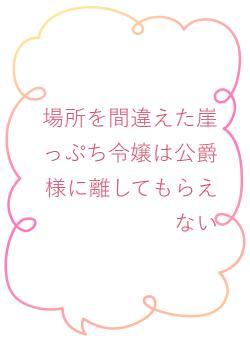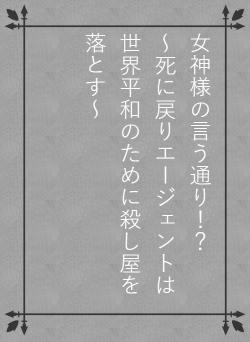ママチャリに乗っているのは、スーツの上にくたびれたコートを羽織った白髪の男だ。寒がりなのか、手袋をはめ、耳当てまで付けている。
ふさふさした真っ白な髪に、ベージュ色の耳当てがなんともアンバランスではあるが、見方によっては可愛くもなり得るだろう。
だが、眼鏡の奥の目は死んだ魚のようで、全体的にあまりいい印象とはいかない。
律儀にも一時停止できちんと止まる。左右を確認して、また自転車を漕ぎ出す。真面目なのか神経質なのか、取り方次第で印象も変わるが、あえてそこに触れる者はいない。
都会の片隅、自転車通勤。中小企業の窓際族。とはいえ、従業員は両手で余る人数しかいない弱小会社だ。一般的な窓際ほど、自由な時間は得られないのが現状だった。
「おはようございます」
自転車置き場で顔を合わせたのは、同じ職場で働くベテラン事務員、遠藤ふさ子。昔で言うところの“お局”であるが、面倒見の良さからか、特に煙たがられる要素はない。
「ああ、高梨さんおはよう。今日も相変わらず覇気がないわねぇ?」
ケラケラと笑いながら、男……高梨晃の背を叩いた。
「こないだの喧嘩は、決着ついたの?」
ふさ子が言っているのは、高梨晃と、娘あんずの親子喧嘩のことである。まるで親戚のおばさんのように、他人の家庭事情を熟知しているのだ。
「ああ、結局、また俺が謝りましたよ……」
「えええ? なによあんた、この前は『ガツンと言ってやる!』って息巻いてたじゃないのよ?」
「最初はそう思ったんですけどね、相手は世界最強とも謳われるJKですからね。敵うわけがなかったんですよ」
しょぼくれた口調で返すと、ふさ子が大笑いする。
「あはは、まったく、どうしようもないねぇ。嫁の尻に敷かれる駄目亭主みたい」
「……当たらずしも遠からずな気がします」
苦笑いで肩を竦めた。
「まったくもう、そんなんだから年寄臭いって言われちゃうのよ? まだ若いんだから、シャンとしなさいよ!」
「そう言われましてもね……」
自分が若いなどとは、微塵も思ってはいなかった。今年で四十五歳になる。もう充分にオッサンであり、あとは朽ちて去っていくだけの老害予備軍だと自負している。
「ああ、そういえば今日は珍しく外回りなんだって?」
ふさ子に言われ、溜息を吐く。
「そうでした。すっかり忘れてましたけど」
「若社長の考えそうなことよねぇ。高梨さんに営業やらせるだなんて、やめておけばいいのにさ」
ふぅ、と息を吐きつつそう口にするふさ子に、高梨は小さく頷いた。
「賛同、痛み入ります。出来ればそのまま社長を説得してほしいのですが」
「それは無理でしょ」
「……ですよね」
社長が交代になったのは、ほんの数か月前のこと。それまで社長を務めていた北見新造が七十歳を迎えたのを機に、息子である三太に社長を譲った。
穏やかな性格である新造に比べ、息子の三太は野心家だ。現状維持に興味などなく、手広く商売をしていこうと思っている節があり、内勤の晃に外回りさせようというのもその一端だ。晃にしか手に入れることができないものを、商売の目玉にしようと考えているのである。
「それにしても、高梨さんが異世界で勇者やってた、なんて……私はいまだに信じられないわ~」
ふさ子はそう口にすると、晃を上から下まで眺め、そのまま事務所へと入っていった。
◇
遡ること二十年前──。
その日、晃は大学の卒業式だった。就職も決まり、これからは社会人として世の中の荒波に揉まれることになる。その期待と不安を胸に、仲間たちとの別れを惜しんでいた。
サークルの同期と飲み周り、すっかり遅くなった帰り道。
「……ん? なんだ?」
公園の方でなにかが光っていることに気付き、ふらりと立ち寄った。
公園のど真ん中にあったのは、光る輪。今や「魔法陣」という言葉は一般常識である。もちろん晃も、それが魔法陣であることは理解出来た。
しかし、理解できたとしても、魔法陣を生で見たのは初めてだ。遊びで誰かが描いたのだろうと思いたかったが、なにせ目の前で光っている。酔っていたこともあり、中に入ってみたいと思うことを咎める者はいまい。
「すげぇ。キラキラだ」
誰かが出てくる気配はないので、出口ではなく、入り口なのだろうと勝手に推測する。足を踏み入れるとどうなるのか? それは、
「百聞は一見に如かず、ってな」
ぷぷ、と肩を震わせ一呼吸置くと、プールにジャンプするかの如く、輪の中へ飛び込む。なんの覚悟もなかった。そこには当たり前に地面があり、光る輪の中から公園の景色が見えるはずだったのだから。
現実が、そうではなかっただけだ。
「ふぇっ?」
飛び込んだ先に、地面の感覚がない。重力に従って、落ちた。
「は? なにっ? マンホールだったっ?」
晃は浮遊感に鳥肌を立てながら、落ちた。不思議の国のアリスの気持ちが、少しだけわかった気がしたが、追いかけるべきウサギもいないのに、穴に飛び込んだ自分を悔いてもいた。
手を伸ばしてもなにも掴めず、薄暗さからなにも見えず、ただひたすらに浮遊感だけを感じている。もしかしたら落ちていると思い込んでいるだけで、実際は巨大な扇風機で風を浴びているだけなんじゃないかと考え始めた瞬間、視界が開けた。
「うわっ」
細い穴から巨大な空間へ押し出されるかのように、急に目の前に見たこともない景色が現れる。山と、森と、海。広大な大地のはるか向こうに見える、町のような建造物。どう考えても、自分の知る「どこか」ではない光景。
「どうなってんだぁぁ!」
夢だと思いたい。酔った勢いで穴に落ち、気を失って見ている夢だと。しかし、頬に感じる風も、鼻をくすぐる木々の匂いも、どこからか聞こえる聞いたこともないなにかの鳴き声も淡い希望を「否」と完全拒否の構えだ。
重力に従い落ち始めてどのくらい経つのか。そろそろ命の危険を感じ始める。このまま地面に衝突すればまず助からないだろう。空でも飛べれば別だが。
そう、頭の片隅で考えた瞬間、脳内にある言葉が浮かんだ。どうしてかはわからないが、無意識にその言葉を口にしていた。
「転移、だ!」
その言葉にどんな意味があったかはわからない。が、晃の願いは聞き届けられた。シュッと乾いた音と共に、空中から地上へと転移したのだから。
「……地面、だ」
まだ体はふわふわしているが、足の下には陸がある。少なくとも、落ちてはいない。
何度も目を瞬かせ、呼吸を整える。
「あなた……なに?」
背後から急に声を掛けられ、驚く。
「うわぁぁ」
「ひゃぁぁ」
声を掛けた誰かもつられて声を張り上げる。
振り向くと、そこに立っていたのは――エルフと思われる見た目の、少女だった。
ふさふさした真っ白な髪に、ベージュ色の耳当てがなんともアンバランスではあるが、見方によっては可愛くもなり得るだろう。
だが、眼鏡の奥の目は死んだ魚のようで、全体的にあまりいい印象とはいかない。
律儀にも一時停止できちんと止まる。左右を確認して、また自転車を漕ぎ出す。真面目なのか神経質なのか、取り方次第で印象も変わるが、あえてそこに触れる者はいない。
都会の片隅、自転車通勤。中小企業の窓際族。とはいえ、従業員は両手で余る人数しかいない弱小会社だ。一般的な窓際ほど、自由な時間は得られないのが現状だった。
「おはようございます」
自転車置き場で顔を合わせたのは、同じ職場で働くベテラン事務員、遠藤ふさ子。昔で言うところの“お局”であるが、面倒見の良さからか、特に煙たがられる要素はない。
「ああ、高梨さんおはよう。今日も相変わらず覇気がないわねぇ?」
ケラケラと笑いながら、男……高梨晃の背を叩いた。
「こないだの喧嘩は、決着ついたの?」
ふさ子が言っているのは、高梨晃と、娘あんずの親子喧嘩のことである。まるで親戚のおばさんのように、他人の家庭事情を熟知しているのだ。
「ああ、結局、また俺が謝りましたよ……」
「えええ? なによあんた、この前は『ガツンと言ってやる!』って息巻いてたじゃないのよ?」
「最初はそう思ったんですけどね、相手は世界最強とも謳われるJKですからね。敵うわけがなかったんですよ」
しょぼくれた口調で返すと、ふさ子が大笑いする。
「あはは、まったく、どうしようもないねぇ。嫁の尻に敷かれる駄目亭主みたい」
「……当たらずしも遠からずな気がします」
苦笑いで肩を竦めた。
「まったくもう、そんなんだから年寄臭いって言われちゃうのよ? まだ若いんだから、シャンとしなさいよ!」
「そう言われましてもね……」
自分が若いなどとは、微塵も思ってはいなかった。今年で四十五歳になる。もう充分にオッサンであり、あとは朽ちて去っていくだけの老害予備軍だと自負している。
「ああ、そういえば今日は珍しく外回りなんだって?」
ふさ子に言われ、溜息を吐く。
「そうでした。すっかり忘れてましたけど」
「若社長の考えそうなことよねぇ。高梨さんに営業やらせるだなんて、やめておけばいいのにさ」
ふぅ、と息を吐きつつそう口にするふさ子に、高梨は小さく頷いた。
「賛同、痛み入ります。出来ればそのまま社長を説得してほしいのですが」
「それは無理でしょ」
「……ですよね」
社長が交代になったのは、ほんの数か月前のこと。それまで社長を務めていた北見新造が七十歳を迎えたのを機に、息子である三太に社長を譲った。
穏やかな性格である新造に比べ、息子の三太は野心家だ。現状維持に興味などなく、手広く商売をしていこうと思っている節があり、内勤の晃に外回りさせようというのもその一端だ。晃にしか手に入れることができないものを、商売の目玉にしようと考えているのである。
「それにしても、高梨さんが異世界で勇者やってた、なんて……私はいまだに信じられないわ~」
ふさ子はそう口にすると、晃を上から下まで眺め、そのまま事務所へと入っていった。
◇
遡ること二十年前──。
その日、晃は大学の卒業式だった。就職も決まり、これからは社会人として世の中の荒波に揉まれることになる。その期待と不安を胸に、仲間たちとの別れを惜しんでいた。
サークルの同期と飲み周り、すっかり遅くなった帰り道。
「……ん? なんだ?」
公園の方でなにかが光っていることに気付き、ふらりと立ち寄った。
公園のど真ん中にあったのは、光る輪。今や「魔法陣」という言葉は一般常識である。もちろん晃も、それが魔法陣であることは理解出来た。
しかし、理解できたとしても、魔法陣を生で見たのは初めてだ。遊びで誰かが描いたのだろうと思いたかったが、なにせ目の前で光っている。酔っていたこともあり、中に入ってみたいと思うことを咎める者はいまい。
「すげぇ。キラキラだ」
誰かが出てくる気配はないので、出口ではなく、入り口なのだろうと勝手に推測する。足を踏み入れるとどうなるのか? それは、
「百聞は一見に如かず、ってな」
ぷぷ、と肩を震わせ一呼吸置くと、プールにジャンプするかの如く、輪の中へ飛び込む。なんの覚悟もなかった。そこには当たり前に地面があり、光る輪の中から公園の景色が見えるはずだったのだから。
現実が、そうではなかっただけだ。
「ふぇっ?」
飛び込んだ先に、地面の感覚がない。重力に従って、落ちた。
「は? なにっ? マンホールだったっ?」
晃は浮遊感に鳥肌を立てながら、落ちた。不思議の国のアリスの気持ちが、少しだけわかった気がしたが、追いかけるべきウサギもいないのに、穴に飛び込んだ自分を悔いてもいた。
手を伸ばしてもなにも掴めず、薄暗さからなにも見えず、ただひたすらに浮遊感だけを感じている。もしかしたら落ちていると思い込んでいるだけで、実際は巨大な扇風機で風を浴びているだけなんじゃないかと考え始めた瞬間、視界が開けた。
「うわっ」
細い穴から巨大な空間へ押し出されるかのように、急に目の前に見たこともない景色が現れる。山と、森と、海。広大な大地のはるか向こうに見える、町のような建造物。どう考えても、自分の知る「どこか」ではない光景。
「どうなってんだぁぁ!」
夢だと思いたい。酔った勢いで穴に落ち、気を失って見ている夢だと。しかし、頬に感じる風も、鼻をくすぐる木々の匂いも、どこからか聞こえる聞いたこともないなにかの鳴き声も淡い希望を「否」と完全拒否の構えだ。
重力に従い落ち始めてどのくらい経つのか。そろそろ命の危険を感じ始める。このまま地面に衝突すればまず助からないだろう。空でも飛べれば別だが。
そう、頭の片隅で考えた瞬間、脳内にある言葉が浮かんだ。どうしてかはわからないが、無意識にその言葉を口にしていた。
「転移、だ!」
その言葉にどんな意味があったかはわからない。が、晃の願いは聞き届けられた。シュッと乾いた音と共に、空中から地上へと転移したのだから。
「……地面、だ」
まだ体はふわふわしているが、足の下には陸がある。少なくとも、落ちてはいない。
何度も目を瞬かせ、呼吸を整える。
「あなた……なに?」
背後から急に声を掛けられ、驚く。
「うわぁぁ」
「ひゃぁぁ」
声を掛けた誰かもつられて声を張り上げる。
振り向くと、そこに立っていたのは――エルフと思われる見た目の、少女だった。