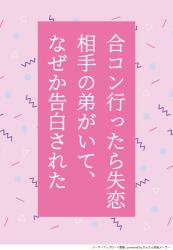「夏目って、彼女いるんだったよな?」
昼休み、クラスメイトのひとりが興味津々に夏目に聞いていた。
夏目の呼吸が一瞬だけ止まる。俺だけが気づく程度の、ほんのわずかな一瞬。
「彼女っていうか、……恋人っぽいやつならいる」
歯切れの悪い返事に、周りは大袈裟にざわめいた。
「やば、こいつぜってぇセフレじゃん!」
「違うっつの。失礼な」
夏目は人当たりのいい笑顔を浮かべながら、クラスメイトの言葉を冗談っぽく流す。
俺よりは小さいが、すらりと背の高い体に、雑誌から抜け出してきたような整った顔立ち。肩まである金髪は、いつも無造作にセットされていて完璧だし、歩くだけで男も女も見とれる。そんなふうに派手な見た目をしているから、夏目を遊んでいるやつだと思う人間もいるようだが、実際はまったく違っていた。
なんか無理して笑ってんな、とこういう時、『恋人っぽいやつ』の俺は思う。
「夏目、行くぞ。今日はふたりでメシ食おう」
俺は立ち上がって、強制的に夏目の肩を軽く引き寄せた。
「……はぁ? まあ、いいけど」
一瞬、眉間にしわを寄せた夏目が、昼飯を片手に俺についてくる。
教室を出ると、廊下には生徒たちの騒がしい声が響いていた。俺は迷わず三階の奥へと足を向ける。
もう何年も使われていない音楽室の重い扉を開けてすぐ、埃っぽい匂いが鼻をつく。さび付いた譜面台や、カバーをかけられてまるで眠っているようなピアノがひとつ真ん中に置かれていた。
夏目は端にあった椅子に座るなり、じっと俺を見上げてきた。
「さっき……嫌な顔したけど、全然嫌じゃないから」
どこか申し訳なさそうな表情で、夏目がぽつりとつぶやく。
「言わなくてもわかるって」
俺は苦笑しながら、夏目の手を取った。
「こっち、座れよ」
床に直接腰を下ろし、俺は自分の隣を軽く叩く。
「……でも、みんなに見られたら、変に思われるだろ」
「思わねぇよ」
「俺は少しでもお前が、……俺のせいで悪意にさらされたら生きていけない」
真剣な表情でそう言う夏目を見て、思わず噴き出してしまった。
夏目って、けっこう俺のこと好きなんだよな。むずがゆさをどうにもできなくて、くすくすと肩を揺らして笑った。
「……笑ってんなよ、鳳」
「いや、笑うだろ。こっちは誰かになんか言われて、行動変えるような、そんな生半可な男じゃねぇから」
「それは……わかってるけど」
悪態をつきながら、結局夏目は俺の隣に座った。
おそらく俺のほうが夏目を先に好きになったのだが、夏目はいつも『俺が先だった』とぶつぶつ言う。
駆け引きとは無縁で、言いたいことがあればすぐに言ってしまう性分の俺は、高一の夏、クラスメイトだった夏目に告白した。
――夏目、俺と付き合わねぇ?
今でも忘れられない、夏目はその場で泣いた。ガチでぼろぼろと泣いた。『……うれしい』って小さい声で何度も言いながら。
俺は今まで生きてきた中で、こんなにかわいい生き物を見たことがなかった。恐ろしくなるくらい夏目のことがかわいいと思った。そして、そんなんで大丈夫かよ、とも思った。
夏目を見ていると、フライパンの上のバターを思い出す。
最初は塊だったものが、じわりじわりと熱を受けて、ゆっくりと形を変えていく。そして、トロトロに溶けた瞬間、何物にも代えがたい恍惚を感じる。
普段は凛としていて、近寄りがたいほど格好いい夏目は、俺だけにしか見せない表情を持っていた。
「なぁ……そろそろ、する? 俺ら」
俺は夏目の髪をそっと指で梳きながら、低い声でささやく。
今のところ焦ってはいないが、のんびりと待ってもいない。夏目が俺を求める気持ちと、俺が夏目を求める気持ちが、どこかで交差するタイミングを探っていた。
「む、無理……」
そう言う夏目の頬が、かわいそうなくらい赤く染まった。
「鳳に体許したら、……たぶん、もっと依存しちまうし、ぜったいお前が逃げる」
か細い声で、でもはっきりとそう言った夏目を見て、胸がぎゅっと締め付けられる。
こいつ、そんなこと考えてたのか。
「……逃げねぇよ」
俺は夏目の手を取って、その細い指を一本ずつ撫でる。むしろ追いかけまくるだろ。どう考えたって。
夏目が俺に依存してくれるなら、俺だって喜んで夏目の虜になってやるってのに。
「俺、めんどくさいもん。逃げるよ、お前……」
夏目が自嘲的に笑って、うつむいてしまう。
だから逃げねぇって言ってんだろ。まったく、本当にめんどくさい。
俺は夏目の顎を上げて、キスをした。
最初は軽く、唇を重ねるだけ。でもそれだけじゃ足りなくて、促すように舌で押し進めると、夏目がゆるゆると、躊躇いがちに唇を開く。
「んっ……ふぅ……」
捩じ込むように舌を割り込ませれば、夏目の舌がおずおずと俺に応えてくる。ん、ん、と鼻にかかった吐息と、水っぽい音が耳に届く。
夏目の手が、俺の制服の袖をぎゅっと掴んでいる。まるで溺れる人が藁にすがるみたいに、必死に俺にしがみついている。
ああ、マジでたまんねぇ……。
唇を離すと、頬を桜色に染め、とろんとした瞳で俺を見つめる夏目がいた。息が乱れて、唇がわずかに開いている。
こんなにかわいくてさ、ほんとどうすんのお前。
「でも、まぁ、……夏目は、俺のキスだけでこんなとろとろになっちまうから、ゆっくりでもいいかもな」
俺は本気でそう思った。キスだけで泣きそうになってしまう夏目が、それ以上できるだろうか。唇についた俺の唾液を制服の裾で拭ってやると、夏目の頬がさらに赤くなる。
「……反論できなくて、むかつく」
小さく抗議する声も、どこか甘えるような響きがあって。
「どっちがいいの、お前」
俺は夏目の耳元に唇を寄せて、低い声で尋ねる。
「……タチかネコか」
「き、聞くなよ」
夏目が顔を真っ赤にして、俺の胸を軽く叩いた。その仕草がかわいくて、思わず笑ってしまった。
「俺に抱かれてぇの?」
まっすぐに見つめて問いただすと、夏目の瞳が潤んで、唇がわずかに開く。
「……ん」
甘い声で、小さくうなずく夏目。
「なに、お前。かわい……」
思わずそう口にした途端、夏目はむっとしたように睨みつけてきた。
「鳳以外には、『かっこいい』としか言われないし」
拗ねたような口調で、夏目がぼそりとつぶやく。たしかに、夏目は誰から見ても完璧にかっこいい。
「だろうな。でも、俺にはかわいいよ」
俺のキスだけで、あんなに溶けてしまうんだから、かわいくないわけがない。
「……なぁ、鳳」
「ん?」
「めんどくさい俺のこと、見捨てないで」
はっ、と声を出して笑った。
「見捨てねぇから。お前こそ、俺を見捨てんなよ?」
どれだけおあずけを食らっても、どれだけめんどくさいことを言われても、夏目からは逃れられない。
夏目は俺の指をぎゅっと握り返してくると、意を決したように言ってきた。
「……明日、家に俺だけなんだけど……来る?」
遠回しなんだか、近道なんだか、とにかくかわいい夏目の誘いの文句に、みっともないくらいわかりやすく唾を飲み込んだ。
ああ、マジで。もっと。もっと困らせてくれ、俺の夏目。
昼休み、クラスメイトのひとりが興味津々に夏目に聞いていた。
夏目の呼吸が一瞬だけ止まる。俺だけが気づく程度の、ほんのわずかな一瞬。
「彼女っていうか、……恋人っぽいやつならいる」
歯切れの悪い返事に、周りは大袈裟にざわめいた。
「やば、こいつぜってぇセフレじゃん!」
「違うっつの。失礼な」
夏目は人当たりのいい笑顔を浮かべながら、クラスメイトの言葉を冗談っぽく流す。
俺よりは小さいが、すらりと背の高い体に、雑誌から抜け出してきたような整った顔立ち。肩まである金髪は、いつも無造作にセットされていて完璧だし、歩くだけで男も女も見とれる。そんなふうに派手な見た目をしているから、夏目を遊んでいるやつだと思う人間もいるようだが、実際はまったく違っていた。
なんか無理して笑ってんな、とこういう時、『恋人っぽいやつ』の俺は思う。
「夏目、行くぞ。今日はふたりでメシ食おう」
俺は立ち上がって、強制的に夏目の肩を軽く引き寄せた。
「……はぁ? まあ、いいけど」
一瞬、眉間にしわを寄せた夏目が、昼飯を片手に俺についてくる。
教室を出ると、廊下には生徒たちの騒がしい声が響いていた。俺は迷わず三階の奥へと足を向ける。
もう何年も使われていない音楽室の重い扉を開けてすぐ、埃っぽい匂いが鼻をつく。さび付いた譜面台や、カバーをかけられてまるで眠っているようなピアノがひとつ真ん中に置かれていた。
夏目は端にあった椅子に座るなり、じっと俺を見上げてきた。
「さっき……嫌な顔したけど、全然嫌じゃないから」
どこか申し訳なさそうな表情で、夏目がぽつりとつぶやく。
「言わなくてもわかるって」
俺は苦笑しながら、夏目の手を取った。
「こっち、座れよ」
床に直接腰を下ろし、俺は自分の隣を軽く叩く。
「……でも、みんなに見られたら、変に思われるだろ」
「思わねぇよ」
「俺は少しでもお前が、……俺のせいで悪意にさらされたら生きていけない」
真剣な表情でそう言う夏目を見て、思わず噴き出してしまった。
夏目って、けっこう俺のこと好きなんだよな。むずがゆさをどうにもできなくて、くすくすと肩を揺らして笑った。
「……笑ってんなよ、鳳」
「いや、笑うだろ。こっちは誰かになんか言われて、行動変えるような、そんな生半可な男じゃねぇから」
「それは……わかってるけど」
悪態をつきながら、結局夏目は俺の隣に座った。
おそらく俺のほうが夏目を先に好きになったのだが、夏目はいつも『俺が先だった』とぶつぶつ言う。
駆け引きとは無縁で、言いたいことがあればすぐに言ってしまう性分の俺は、高一の夏、クラスメイトだった夏目に告白した。
――夏目、俺と付き合わねぇ?
今でも忘れられない、夏目はその場で泣いた。ガチでぼろぼろと泣いた。『……うれしい』って小さい声で何度も言いながら。
俺は今まで生きてきた中で、こんなにかわいい生き物を見たことがなかった。恐ろしくなるくらい夏目のことがかわいいと思った。そして、そんなんで大丈夫かよ、とも思った。
夏目を見ていると、フライパンの上のバターを思い出す。
最初は塊だったものが、じわりじわりと熱を受けて、ゆっくりと形を変えていく。そして、トロトロに溶けた瞬間、何物にも代えがたい恍惚を感じる。
普段は凛としていて、近寄りがたいほど格好いい夏目は、俺だけにしか見せない表情を持っていた。
「なぁ……そろそろ、する? 俺ら」
俺は夏目の髪をそっと指で梳きながら、低い声でささやく。
今のところ焦ってはいないが、のんびりと待ってもいない。夏目が俺を求める気持ちと、俺が夏目を求める気持ちが、どこかで交差するタイミングを探っていた。
「む、無理……」
そう言う夏目の頬が、かわいそうなくらい赤く染まった。
「鳳に体許したら、……たぶん、もっと依存しちまうし、ぜったいお前が逃げる」
か細い声で、でもはっきりとそう言った夏目を見て、胸がぎゅっと締め付けられる。
こいつ、そんなこと考えてたのか。
「……逃げねぇよ」
俺は夏目の手を取って、その細い指を一本ずつ撫でる。むしろ追いかけまくるだろ。どう考えたって。
夏目が俺に依存してくれるなら、俺だって喜んで夏目の虜になってやるってのに。
「俺、めんどくさいもん。逃げるよ、お前……」
夏目が自嘲的に笑って、うつむいてしまう。
だから逃げねぇって言ってんだろ。まったく、本当にめんどくさい。
俺は夏目の顎を上げて、キスをした。
最初は軽く、唇を重ねるだけ。でもそれだけじゃ足りなくて、促すように舌で押し進めると、夏目がゆるゆると、躊躇いがちに唇を開く。
「んっ……ふぅ……」
捩じ込むように舌を割り込ませれば、夏目の舌がおずおずと俺に応えてくる。ん、ん、と鼻にかかった吐息と、水っぽい音が耳に届く。
夏目の手が、俺の制服の袖をぎゅっと掴んでいる。まるで溺れる人が藁にすがるみたいに、必死に俺にしがみついている。
ああ、マジでたまんねぇ……。
唇を離すと、頬を桜色に染め、とろんとした瞳で俺を見つめる夏目がいた。息が乱れて、唇がわずかに開いている。
こんなにかわいくてさ、ほんとどうすんのお前。
「でも、まぁ、……夏目は、俺のキスだけでこんなとろとろになっちまうから、ゆっくりでもいいかもな」
俺は本気でそう思った。キスだけで泣きそうになってしまう夏目が、それ以上できるだろうか。唇についた俺の唾液を制服の裾で拭ってやると、夏目の頬がさらに赤くなる。
「……反論できなくて、むかつく」
小さく抗議する声も、どこか甘えるような響きがあって。
「どっちがいいの、お前」
俺は夏目の耳元に唇を寄せて、低い声で尋ねる。
「……タチかネコか」
「き、聞くなよ」
夏目が顔を真っ赤にして、俺の胸を軽く叩いた。その仕草がかわいくて、思わず笑ってしまった。
「俺に抱かれてぇの?」
まっすぐに見つめて問いただすと、夏目の瞳が潤んで、唇がわずかに開く。
「……ん」
甘い声で、小さくうなずく夏目。
「なに、お前。かわい……」
思わずそう口にした途端、夏目はむっとしたように睨みつけてきた。
「鳳以外には、『かっこいい』としか言われないし」
拗ねたような口調で、夏目がぼそりとつぶやく。たしかに、夏目は誰から見ても完璧にかっこいい。
「だろうな。でも、俺にはかわいいよ」
俺のキスだけで、あんなに溶けてしまうんだから、かわいくないわけがない。
「……なぁ、鳳」
「ん?」
「めんどくさい俺のこと、見捨てないで」
はっ、と声を出して笑った。
「見捨てねぇから。お前こそ、俺を見捨てんなよ?」
どれだけおあずけを食らっても、どれだけめんどくさいことを言われても、夏目からは逃れられない。
夏目は俺の指をぎゅっと握り返してくると、意を決したように言ってきた。
「……明日、家に俺だけなんだけど……来る?」
遠回しなんだか、近道なんだか、とにかくかわいい夏目の誘いの文句に、みっともないくらいわかりやすく唾を飲み込んだ。
ああ、マジで。もっと。もっと困らせてくれ、俺の夏目。