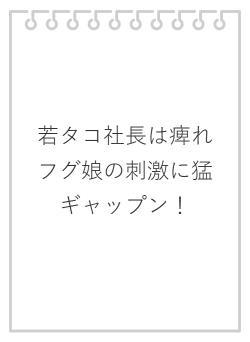平凡な日常、退屈な毎日を送る少年ノベマ(仮名)は、ある日、自分とは正反対な誰かと出会った。
「君は、誰なの?」
「マベノだよ」
ただ単に名前が反対になっただけでは……と思ったが、実際にマベノはノベマと全く違う存在だった。両者は異なる世界の住人だったのだ。例えば、ノベマの世界は色彩がなかった。ノベマの世界に暮らす人間の目には、色を感知する細胞が存在しないためである。光の明るさを検出する細胞があるだけなので、見える世界は白黒だった。それがノベマにとって、普通のことだったのだ。
しかしマベノにとって、それは異常だった。
「これ、つけてみ」
「何それ?」
「カラコン。これを目につけたら、色が認識できるようになるから」
カラーコンタクトレンズで色が検知できるわけないだろ……と思うのは日常に囚われている証左である。マベノと会うことで非日常的な要素に触れることへの抵抗感が減ったノベマは、躊躇なく色を認識できるようになるカラコンを装着した。
「あ、色が見えるようになった。凄い、これ、凄いね!」
世界の美しさに目覚めたノベマは色彩豊かな光景を夢中になって見続けた。
そんなノベマにマベノは注意した。
「そろそろ第63回キャラクター短編小説コンテストを書き始めろよ」
ノベマはコンテストのことを、すっかり忘れていた。
「そうだった。でも、今はカラーの世界を見ている方が楽しいなあ」
やる気を示さないノベマにマベノは苛立った。
「出すって決めてたんだろ? ちゃんと書けよ」
普段なら、誰に言われずとも書き始めるノベマである。この時も、いつも通り書き出そうと思うには思うのだが、色鮮やかな世界を見ている方が楽しかった。そんなわけで彼は、こんなことを言った。
「僕の代わりに君が書いてよ」
言われたマベノは戸惑った。
「え、そんなの書いたことないよ」
ノベマと違い、マベノは文章を書く習慣がなかった。それなのに、いきなり小説を書けと言われても困る。
そう言って断ろうとするマベノに、ノベマは執筆を強要した。
「絶対に書けるよ、頑張って!」
やがて締切の日が過ぎた。ノベマはマベノに、どんな作品を投稿したのか、尋ねようとした。しかし連絡が取れない。
「どうしたんだろ?」
心配になったノベマはマベノに会おうとしたが、着信拒否で相手にしてもらえない。
「嫌われたのかな……」
悲しく思うノベマ。涙が溢れる。カラコンが、ぽとりと落ちた。世界は再びモノクロームに変わる。ノベマは、マベノのいない世界は白黒なのだと気付いた。自分とは正反対だが気の合うマベノがいないと、寂しくて仕方がないのだ。
会いに行こう。マベノが会ってくれないのなら、彼がいる世界へ行って、会おう!
しかし! どうやって別の世界へ行けるのか、それが分からない!
隔てられた二つの世界を超える方法が、ノベマにはどうしても分からなかった。二人の関係性を妨げる非日常的な要素が彼を苦しめる!
ノベマが困り果てていたら、マベノが同じく困った様子で現れた。それに気付いたノベマが喜びの声を上げる。
「マベノ、君に会いたかったんだよ!」
マベノは苦笑いした。
「僕も何だけど……会いにくくてさ」
「どうして?」
「書けなくて、第63回キャラクター短編小説コンテストの作品」
そう言ってマベノは頭を下げた。
「本当に、ごめん!」
ノベマは首を横に振った。
「悪いのは僕だよ。君に全部を押し付けてしまった。ごめんなさい」
頭を深々と下げたノベマは、顔を上げると、こう言った。
「それじゃ、これから書こうよ」
マベノは頷いた。
「そうだね。締め切りには間に合わなかったけど、二人で書こう!」
そして共同執筆が始まったのだが、何もかも正反対の二人は好みのストーリーも逆だったので、話の概要をまとめる段階で揉めに揉めた。執筆作業は開始早々、暗礁に乗り上げたのだ。仕方がないので、第三者の私が、二人の出会いから現状までの概要をまとめ、投稿することにした。揉めるくらいなら共同での創作活動なんてしなければいいと思うのだが、二人の絆は強く、喧嘩しながらも離れようとはしないのだった。めでたしめでたし。
「君は、誰なの?」
「マベノだよ」
ただ単に名前が反対になっただけでは……と思ったが、実際にマベノはノベマと全く違う存在だった。両者は異なる世界の住人だったのだ。例えば、ノベマの世界は色彩がなかった。ノベマの世界に暮らす人間の目には、色を感知する細胞が存在しないためである。光の明るさを検出する細胞があるだけなので、見える世界は白黒だった。それがノベマにとって、普通のことだったのだ。
しかしマベノにとって、それは異常だった。
「これ、つけてみ」
「何それ?」
「カラコン。これを目につけたら、色が認識できるようになるから」
カラーコンタクトレンズで色が検知できるわけないだろ……と思うのは日常に囚われている証左である。マベノと会うことで非日常的な要素に触れることへの抵抗感が減ったノベマは、躊躇なく色を認識できるようになるカラコンを装着した。
「あ、色が見えるようになった。凄い、これ、凄いね!」
世界の美しさに目覚めたノベマは色彩豊かな光景を夢中になって見続けた。
そんなノベマにマベノは注意した。
「そろそろ第63回キャラクター短編小説コンテストを書き始めろよ」
ノベマはコンテストのことを、すっかり忘れていた。
「そうだった。でも、今はカラーの世界を見ている方が楽しいなあ」
やる気を示さないノベマにマベノは苛立った。
「出すって決めてたんだろ? ちゃんと書けよ」
普段なら、誰に言われずとも書き始めるノベマである。この時も、いつも通り書き出そうと思うには思うのだが、色鮮やかな世界を見ている方が楽しかった。そんなわけで彼は、こんなことを言った。
「僕の代わりに君が書いてよ」
言われたマベノは戸惑った。
「え、そんなの書いたことないよ」
ノベマと違い、マベノは文章を書く習慣がなかった。それなのに、いきなり小説を書けと言われても困る。
そう言って断ろうとするマベノに、ノベマは執筆を強要した。
「絶対に書けるよ、頑張って!」
やがて締切の日が過ぎた。ノベマはマベノに、どんな作品を投稿したのか、尋ねようとした。しかし連絡が取れない。
「どうしたんだろ?」
心配になったノベマはマベノに会おうとしたが、着信拒否で相手にしてもらえない。
「嫌われたのかな……」
悲しく思うノベマ。涙が溢れる。カラコンが、ぽとりと落ちた。世界は再びモノクロームに変わる。ノベマは、マベノのいない世界は白黒なのだと気付いた。自分とは正反対だが気の合うマベノがいないと、寂しくて仕方がないのだ。
会いに行こう。マベノが会ってくれないのなら、彼がいる世界へ行って、会おう!
しかし! どうやって別の世界へ行けるのか、それが分からない!
隔てられた二つの世界を超える方法が、ノベマにはどうしても分からなかった。二人の関係性を妨げる非日常的な要素が彼を苦しめる!
ノベマが困り果てていたら、マベノが同じく困った様子で現れた。それに気付いたノベマが喜びの声を上げる。
「マベノ、君に会いたかったんだよ!」
マベノは苦笑いした。
「僕も何だけど……会いにくくてさ」
「どうして?」
「書けなくて、第63回キャラクター短編小説コンテストの作品」
そう言ってマベノは頭を下げた。
「本当に、ごめん!」
ノベマは首を横に振った。
「悪いのは僕だよ。君に全部を押し付けてしまった。ごめんなさい」
頭を深々と下げたノベマは、顔を上げると、こう言った。
「それじゃ、これから書こうよ」
マベノは頷いた。
「そうだね。締め切りには間に合わなかったけど、二人で書こう!」
そして共同執筆が始まったのだが、何もかも正反対の二人は好みのストーリーも逆だったので、話の概要をまとめる段階で揉めに揉めた。執筆作業は開始早々、暗礁に乗り上げたのだ。仕方がないので、第三者の私が、二人の出会いから現状までの概要をまとめ、投稿することにした。揉めるくらいなら共同での創作活動なんてしなければいいと思うのだが、二人の絆は強く、喧嘩しながらも離れようとはしないのだった。めでたしめでたし。