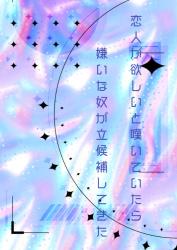申し込んでいた冬コミは落ちてしまい、来年は受験で漫画どころではなくなるので幼馴染の漫画をSNSに投稿した。
すると瞬く間にお気に入り登録してもらえ、僕のホーム画面には流星群のようにハートマークが飛んでくる。
隣で見守ってくれていた唯斗くんは目を丸くした。
「すごい人気だね」
「ちょっと怖いけど」
「藍の漫画にはそれだけの魅力があるってことだよ。でも残念だな〜せっかく俺だけのサワリーマンだったのに」
唯斗くんは背凭れに体重を預けると椅子がギシギシと悲鳴をあげた。風呂上りで湿った髪がきらりと反射している。
「転校生の方はどう?」
「あんまり筆が進んでなくて」
「残念だな。早く読みたいのに」
僕は俯いてスケッチブックの表紙を撫でた。そこには体育祭でもらった金ぴかのシールが貼ってある。
唯斗くんから告白されて三か月が過ぎ、十二月に入った。
いままでと変わりなく日常が過ぎているせいで、告白されたことを忘れてしまうくらい穏やかな日常だ。
このままでいいんじゃないか。
唯斗くんといるのは楽しい。BLの話をしても偏見はないし、一緒に出かけたり、ご飯を食べたりしていると落ち着く。
それだけじゃだめなのかな。
「体操服、また買ったの?」
唯斗くんの机の上に新品タグのついた体操服とズボンのセットが広げられている。
僕が指摘すると唯斗くんは後頭部を掻いた。
「……なくしちゃって」
「この前も同じこと言って買ってたよね。シャープペンとか教科書とか」
唯斗くんはここ数カ月ほど物をよくなくしていた。真面目でしっかり者の唯斗くんらしくないミスの連続だ。
体操服にしっかりと名前を書いた唯斗くんは丁寧に畳んだ。
「期末の疲れが出てるのかも」
「確かに頑張ってたもんね」
唯斗くんはなにかに憑りつかれるように勉強に取り組んでいた。
でも前と同じように僕も教えてもらったけど、元気がなかった気がする。もしかして無理させちゃったかな。
ーーコンコン
扉がノックされて、僕と唯斗くんは顔を合わせた。
「はーい。誰だろ?」
「もう点呼はすんだのにね」
時刻は夜の八時だ。点呼は済み、完全消灯の十時までは自由時間と決まっている。
『宇梶、いるか?』
「はい」
寮監である担任の声に唯斗くんが慌てて扉を開けた。僕の位置からは二人は見えないけど、声がわずかに漏れ聞こえる。
でもなにを話しているかまではわからない。
少ししたら戻ってきた唯斗くんの顔は壁に同化しそうなほど白い。
只事ではないと察し、僕は椅子から立ち上がった。
「どうしたの?」
「……冬休みになったら東京戻るね」
「おばあさんになにかあった?」
「いや……その」
言いにくそうに唯斗くんは続けた。
「実は文化祭で俺が海南にいるってことをSNSで書かれちゃったみたいで」
「嘘……」
女の子たちにはSNSには投稿しないでと念を押したのに。人の口にはカギを締められないとよく言ったものだ。
そこで僕はまた気がついた。
「もしかして最近ものがなくなるのって」
「誰かに盗られてるっぽい」
唯斗くんは困ったように笑った。
海南高校はスポーツ強豪校ということもあり、校内のプライバシーは徹底的に守れている。
僕たちが授業中のときは校門を締められ、守衛さんが常に警備してくれていた。
だから侵入することは不可能に近い。
ということは生徒の誰かが唯斗くんの私物を盗んでいる可能性がある。
「先生に相談しよう」
「実は何度も相談してたんだ。でも証拠もないし、誰が盗ったのかわからない。学校に監視カメラ付けるわけにもいかないでしょ」
「そんな……酷い」
どうしてそんなことができるのか。盗人と同じ釜の飯を食べているかと思うと吐き気がした。
唯斗くんは一度唇を結んだあと、無理やり引っ張るように開いた。
「東京の学校に戻ろうと思うんだ」
「え」
「ここだとセキュリティの問題とかあるし、なにより部活頑張ってる山岸たちに迷惑かけたくない」
「それじゃなにも解決にならないよ」
「でもどうすることもできない」
唯斗くんはキレイに整えられた髪を乱雑にかきあげた。まだ彼の中でも納得していない部分があるのかもしれない。
全校生徒の荷物を調べても、外部に渡っていたら意味がない。なにより唯斗くんが学校のみんなを疑うのが辛いだろう。
この部屋から唯斗くんがいなくなる。転校するとなったらもう二度と会えないのではないか。
いままで当たり前にそばにいてくれた存在がぽっかりと穴が空き、冷たい風が通り過ぎていく。
「転校するにしても親と話さなくちゃいけないから、明後日の冬休みには実家に帰るよ」
「そっか」
「だから、えっと」
唯斗くんはまた髪をかき混ぜた。
「告白の返事はいらないよ。なかったことにして」
僕は頭をがんと殴られたような衝撃を受けた。高く積み上げたつみきの城を目の前で壊されたような絶望感だ。
ショックで口の中が乾き、僕はどうにか喉を鳴らした。
「……ん。わかった」
「さて、終業式終わったらすぐ帰れるように荷物まとめておくかな」
唯斗くんはぱっと画面を切り替えるように笑った。
その笑顔に僕の胸はぎゅうと締めつけられて、苦しい。
唯斗くんは終業式が終わると慌ただしく教室を出て行った。
もう冬休みに入ったところもあるのか、校門の前には制服を着た女の子たちがちらほらいて、守衛さんが追い返している。
唯斗くんは裏門から帰ったので鉢合わせなくて済んだだろう。
「ありゃヤバいな」
同じように窓の外を見ていたシンタは口笛を鳴らした。
「全然気づかなかったよ」
「ま、おまえら寮生は裏門使うことの方が多いしな。駅からだったら表門の方が近いし」
「唯斗くんってすごいんだね」
「そりゃ歴代人気ナンバーワンだからな」
さすがシンタは詳しい。
僕は唯斗くんがモデルだと知っても、彼のことをネットで調べようとは思わなかった。
自分の目の前にいる唯斗くんを信じているから、雑音をいれたくなかったのだ。
「じゃ藍も気をつけて帰れよ」
「うん」
僕が寮に戻ると部屋に唯斗くんの姿はない。今朝まで玄関に置いてあったスーツケースもなくなっている。
「もう行っちゃったんだ」
でも冬休みが明ければ戻って来るはずだ。転校するにしても手続きがあるし、そんなすぐにできることじゃないだろう。
そうやって自分を慰めてみても全然心が晴れてくれない。
唯斗くんがいなくなった部屋はがらんどうだ。温度も音もなにもない。
夏休みと同じだ。
でもあのときは僕が体調を崩しから、唯斗くんはすぐ帰って来てくれたんだよね。
唯斗くんが帰って来るとわかれば怖くない。けれどいまはどうだろう。
もしかしたらこのまま二度と会えなくなってしまう可能性の方が高い。
不安が足元から這い上がってきて、僕を飲み込もうとする。逃げるように僕はスマホを取り出して写真フォルダを見返した。
唯斗くんがポーズを決めてくれたものや壁ドンしてもらったもの。ハグしてもらったものが画面上に溢れる。
「いま思うと僕はすごい大胆だったな」
唯斗くんの気持ちを知らなかったとはいえ、あまりに接触が多すぎる。よく唯斗くんは怒らず付き合ってくれたものだ。
ふとお気に入りフォルダの存在を思い出して、僕はタップした。
「唯斗くん……」
そこには僕を眩しそうにみつめる唯斗くんの顔があった。あまりにカッコよくて思わず撮ってしまったけど、いまならわかる。
「僕のこと好きだって言ってくれてる」
この笑顔を宝物のように大切にして、誰にも見せないようにしていた。
これは僕だけのものだ。
いままで味わったことのない独占欲に、自分の声が蘇る。
唯斗くんと「これ恋」の話をしたときだ。
ーー『受けが嫉妬しちゃうんだよね』
いまならわかる。
お気に入りフォルダに無意識に入れた行為こそが、僕の無意識の気持ちを代弁していたのだ。
「よし……決めた」
僕は椅子に座り、タブレットとスケッチブックを取り出した。
僕はバスと電車を乗り継いで静岡駅へ行き、そこから東京まで一時間ほど新幹線に揺られ、無事に東京駅に着いた。
問題はここからだ。
「……迷った。ここからどうしよう」
改札を出たらホームには人がごった返している。
大晦日のせいだろうか。それともなにかイベントでもやっているのだろうか。
初めて来る東京に右往左往しながら、僕はどうにか壁際に落ち着けることができた。
ダウンのポケットからスマホを出して、唯斗くんのアイコンをタップする。
東京に来る前に連絡するつもりだったのに、作業がギリギリまで終わらず、移動中は死んだように寝ていたのでメッセージを送れなかったのだ。
通話ボタンを押して、耳に当てるとプルルという機械音がいやに長く聞こえる。
『もしもし、藍?』
「久しぶり。元気?」
『うん。藍は?』
「僕も元気だよ」
電波越しの唯斗くんの声は少しかすれていた。でも懐かしい声音に疲れが吹っ飛ぶ。
『もしかして外にいるの? 随分騒がしいけど』
「いま東京駅にいるんだ」
『え』
「唯斗くんに会いに来たんだ。いまから会えないかな?」
僕はスマホをぎゅっと握りしめた。緊張で頬に汗をかいているのか画面がズレそうになる。両手で支えて、どうにか耳に当てられた。
『東京駅のどこにいるの?』
「お土産屋さんがいっぱいいるところ」
『お店の名前わかる?』
僕の目の前にある店名を何個か言うと「そこで待ってて」と通話を切られてしまった。
「どうしよう。怒ってたのかな」
でも声音は怒ってなかったような気がする。それとも僕の希望でそう聞こえただけかな。
僕は壁に背中を預け、流れ行く人をぼんやりと眺めていた。
「藍!」
遠くから名前を呼ばれて顔を上げると、人混みを掻き分けて唯斗くんが走ってきてくれた。
これだけたくさんの人がいるのに、唯斗くんの周りだけキラキラとした粒子が飛び、くっきりと浮かび上がっている。
「王子様みたい」
靡く髪も広がるコートの裾も全部が絵になっていた。
僕の目の前で止まった唯斗くんは、「ちょっと待って」と膝に手をついて、息を整えている。
「ビックリした……いきなり、電話きたかと思ったら、はぁ……東京駅って」
「ごめん。途中で連絡しようかと思ってたんだけど寝ちゃってて。にしても来るの早いね」
「俺もたまたま東京駅にいたんだ。おばあちゃんのお見舞いに行ってて」
唯斗くんは額に浮かんだ汗を乱暴に手の甲で拭った。
「どうしたの?」
「……白馬の王子様みたい」
僕の元に走って来てくれるなんて王子様みたいにかっこいい。
僕が見惚れていると唯斗くんは首を傾げた。
「王子様?」
「あ、ごめん。妄想してた」
「なにそれ」
唯斗くんはくしゃっと笑った。久しぶりに見る笑顔に胸が甘く疼く。
僕はデイバックの持ち手をぎゅっと握った。
「漫画ができたから一番に唯斗くんに読んでもらいたくて」
「転校生のやつ?」
「うん」
「データで送ってくれたよかったのに」
「それじゃだめなの」
「ん?」
「僕の前で読んで欲しい」
「いま? ここで?」
唯斗くんは素っ頓狂な声を上げて、地面を指さした。僕は力強く頷く。
僕たちの周りにはたくさんの人が行きかっている。人目がある中、BL漫画を読むのは勇気がいるだろう。
でも僕は一秒でも早く読んで欲しかった。待っていることなんてできない。
僕はデイバックからA4サイズのコピー本を出した。
「表紙は描いてないから、外側からならわからないと思う」
「わかった」
唯斗くんは僕の隣に立ち、ゆっくりとページを開いた。その間、僕は自分の手元をもじもじと見下ろす。
転校生の話には唯斗くんとの思い出を綴っていた。
転校してきた日から腐男子とバレたこと、海岸掃除や文化祭などの思い出を大切に描いている。
けれど結末は受けが告白して終わるようになっていた。
本を閉じた唯斗くんはきらりとした瞳を僕に向けている。
「これってもしかして」
「唯斗くんに向けた告白本、です」
僕はじわじわと頰が熱くなるのを感じたけど、唯斗くんから目を逸らさなかった。
「言葉にするのが苦手で、漫画なら伝わるかなって思ったんだけど……どうだった?」
「すっごい伝わったよ」
唯斗くんの腕が伸びてきて、僕の小指と絡めてくれる。ショッピングモールでもされたとき、初めての体温に胸が高鳴った。
嬉しくて指をきゅっと曲げると唯斗くんも絡めてくれる。
「返事もらえないからだめだと思ってた」
「自分の気持ちがわからなくて……唯斗くんがいなくなって、やっと気づいたんだ」
遅くなってごめんね、と言うと唯斗くんは絡めた指に力を入れた。離さないと言われているようで嬉しい。
「俺も好きだよ」
「うん……僕も。その、す、すす……好き」
言葉にするのは恥ずかしいけど、その分重みがある。
「藍、顔真っ赤だよ」
「初めてで恥ずかしい」
「こんな可愛い藍をこれから独り占めしていいんだ」
「これ以上変なこと言わないでよ。致死量の羞恥心で死んじゃう」
「それは困る」
勇気を出して顔を上げると唯斗くんの顔も真っ赤だ。可笑しくて同時に笑った。
小指だけ絡まっていた手が僕の手を包み込んでくれる。温かくてほっとした。
唯斗くんは繋がれた手をブランコみたいに揺らしている。
「じゃあいまこの瞬間から俺は藍の彼氏だね」
「そういうことになりますね」
「藍は照れると敬語になるんだ」
「恥ずかしいの!」
僕はぷりぷり怒ると唯斗くんは残念そうに眉を寄せた。
「……もう帰らないとやばい?」
「今日は姉ちゃんの家に泊まるからあとちょっと大丈夫だよ」
姉ちゃんは都内で一人暮らしをしている。多分いまごろ冬コミから戦利品を抱えて帰宅途中だろう。
「よかった」
唯斗くんは目を細めて、僕の耳元に顔を寄せた。
「まだ帰したくない」
僕の顔が真っ赤になったのは言うまでもない。
さすが東京生まれ、東京育ちと言うべきか。唯斗くんは人混みを避けながら魚のようにスイスイと歩いている。唯斗くんの足が長いので自然と僕は早足になっていた。
それに気づいた唯斗くんは振り返って目を丸くしている。
「ごめん、歩くの速かったね」
「僕が慣れてないから大丈夫」
「浮かれすぎてるわ。まさか大晦日に藍と会えると思ってなかったし、付き合えるなんて夢みたい」
「僕も」
目が合わせてふふっと笑いあった。なんというバカップルだ。でも付き合ったばかりだから許して欲しい。
電車に乗って移動する間、唯斗くんはさりげなく僕のデイバッグを持ってくれた。
車内は思っていたより混んでいなくてつり革に並んで捕まる。
姉ちゃんの家に泊まるつもりだったが、電車のトラブルで国際展示場から帰れなくなってしまったらしい。
だからオタ友の家に泊まるらしく、僕も来ないかと言われたけど断った。
さすがに見ず知らずの女性の家で寝泊まりできるほど図太くない。
でも未成年が一人でホテルに泊まることはできないらしく、困っていると唯斗くんが「うちに来なよ」と誘ってくれたのだ。
お互いの両親に許可を取り、僕たちは唯斗くんの家へ向かっている。
僕は車窓を流れる夜景を見つめた。どこもかしこも明るい。地元の夜空よりキラキラしているビル群に目を奪われる。
「年明けたらすぐ修学旅行だよね」
「うん、東京観光」
二人で笑った。
「唯斗くんは地元だから新鮮味がないよね」
「そんなことない。藍と回れるならどこだって楽しい」
「……そういう恥ずかしいこと言わないでよ」
僕はつり革をぎゅうと掴んで顔を俯かせると、頭上ではクスクスと笑い声が落ちてくる。どうやら揶揄われているらしい。
でもはたと大事なことに気づく。
「転校の話はどうなったの?」
「親は東京に帰ってこいって言ってるけど、俺は海南に残りたい」
「うん」
「だから説得してた。事務所のマネージャーも引っ張って、連日話し合いしてたよ。盗まれてるのは証拠がないからわからないけど、事務所も学校と相談して声明出してくれるって」
「そっか、よかったぁ」
「それに元々、卒業までしつこく藍にアピールするつもりだったんだ」
「えぇ。忘れてって言ってたのに?」
「そうやって印象残しておけば、藍なら食らいついてくれるかなって。腹黒いでしょ?」
「策略家だな」
唯斗くんの駆け引き上手に舌を巻いた。でもそのお陰で自分の気持ちに気づけたから、感謝しなくちゃ。
唯斗くんに向けられる笑顔に胸がきゅんと苦しくなる。これが好きって気持ちなのだ。
嬉しくて、苦しくて、時々泣きそうになる。
恋ってたくさんの感情を詰め合わせた集合体みたいだ。
「着いたね。ここで乗り換えだよ」
唯斗くんはスマートに電車を降りて、僕は後ろからついて行った。
「ここだよ」
「え……ここ? 本当に?」
僕は夜空に届きそうな建物を見上げた。
近隣のマンションも十階建て以上はありそうだけど、唯斗くんが指さしたマンションはその倍はある。
「唯斗くんちってお金持ち?」
「普通だよ」
「いやいや、田舎者を莫迦にしてもらっちゃ困る。普通はこんなところ住めないって」
「まぁ見た目だけだから」
そう言って唯斗くんはエントランスの自動ドア潜った。コンシェルジュのお兄さんが恭しくお辞儀し、「おかえりなさいませ、宇梶様」と言うのにも驚いてしまった。
ボタンもなにもない黒いパネルに唯斗くんがカードキーをかざすと、エレベーターの扉が開く。それに乗るとボタンを押さなくても勝手に動き出した。
まるで未来に来たかのようだ。
ガラス張りのエレベーターがぐんぐんと上がっていく。車のテールランプが遠ざかり、人がゴマ粒ほどになる。
ぽんと音がして扉が開くと重厚そうな鉄扉が目の前にあった。真鍮の表札には「宇梶」と書かれている。
こ、これは想像以上じゃないか。
僕がガチガチに固まっていると、唯斗くんがそっと指を絡めてくれた。
そのやさしい熱に背筋が伸びる。すぐに離れてしまったけど、僕はようやく落ち着けることができた。
唯斗くんが扉を開けるとパタパタと小走りする音が聞こえてくる。
「ただいま」
「おかえりなさい」
「……お邪魔します」
出迎えてくれたのは唯斗くんのお母さんだ。亜麻色に染められた髪が肩口でウェーブを作り、ぱっちりとした目が唯斗くんとそっくりである。デコルテが見えるワインレッドのニットがよく似合っていた。
圧倒される美人な奥様だ。
唯斗くんのお母さんはにっこりとした笑みを向けてくれた。
「あなたが唯斗のお友だちのーー」
「寮で同室の沢渡藍です。こんな遅い時間に突然押しかけてすいません」
「大丈夫よ。話は唯斗から聞いてるわ。どうぞ中に入って」
にこやかな笑顔にほっとする。僕は靴を脱いで揃えるという普段しないことをしたけど、指先が緊張でプルプルと震えた。
てかいまは友だちではなく恋人だ。変な言動をして嫌われないように、細心の注意を払わなければならない。
二重のプレッシャーに眩暈がした。
お父さんは仕事でいないらしい。長い廊下を歩いている間、お母さんが嬉々として話してくれる。
一つの扉の前でお母さんが振り返った。
「外は寒かったでしょ? 先にお風呂をどうぞ」
「ありがとうございます」
「タオルは用意してあるし、他のものも好きに使ってね」
「はい。じゃあ唯斗くん、行こう」
僕が唯斗くんの袖を引っ張ると「え?」と驚きの声が降ってきた。なにか間違ったことがあったかな?
唯斗くんが眉をハの字にさせている。
「ここは寮じゃないから、藍一人で入っていいんだよ」
「あぁ! そうだった」
ついいつもの癖で唯斗くんを誘ってしまった。恥ずかしい。
顔が熱くなって俯いていると唯斗くんのお母さんはくすぐったそうに笑った。
「随分、仲良くしてくれてるのね」
「いえ……いつも迷惑かけてます」
「ふふっ、寮とは違って狭いけどよかったら二人で入る?」
「お先に失礼させていただきます!」
僕は唯斗くんのお母さんから逃げるように洗面所に飛び込んだ。
扉越しに二人の笑い声が聞こえて、恥ずかしてしばらく洗面所から出られそうもない。
お風呂はホテルみたいにピカピカで、シャンプーやボディソープも全部いい匂いがする。薬局で売っている見慣れたボトルが一つもなく、英語で書いてある容器を確認しながらちょっとだけ使わせてもらった。
「すごい、浴槽で足が伸ばせる。うわー泡がぶくぶくしてきた」
こういうのジャグジーというんだっけ。僕が浴槽に入るとセンサーが感知したのか左右から炭酸みたいな泡が出てくる。
ちょっとだけ擽ったい。
僕は冷えた身体を充分に温まらせてもらい、持参したスウェットに着替えた。
羞恥心もだいぶ落ち着いてきたし。
リビングに行くと唯斗くんとお母さんがお茶をしている。
ソファに座っているだけなのに絵になる二人だ。
「お風呂ありがとうございました」
「温まれたかしら?」
「はい。ちょっと熱いくらいです」
スウェットをすぐに着たせいでちょっとだけ汗ばんでいる。でもお陰で身体の芯までポカポカだ。
「風呂から出たら髪乾かしなっていつも言ってるでしょ」
唯斗くんはソファから立ち上がって、僕の頭を拭いてくれた。やさしい手つきにうっとりと目を細めてしまう。
猫が撫でられてゴロゴロ喉を鳴らす気持ちがわかる。唯斗くんの手は心地いい。
僕たちのやりとりを見て、唯斗くんのお母さんが擽ったそうに笑った。
「唯斗が誰かのお世話をするところなんて初めて見たわ」
「別に。いままでやる機会がなかっただけ」
「つまり僕は手のかかる弟ってこと?」
僕の問いに唯斗くんはニヤっと笑った。
「じゃあ俺も風呂入るね。母さん、藍に変なこと吹き込まないでよ」
「はいはい」
唯斗くんが浴室へ行ってしまうとお母さんと二人きりだ。
どうしよう、彼氏の家でいきなりお母さんとだけなんて。
粗相はしないように細心の注意を払って動くぞ、と気合いを入れる。
「沢渡さん、オレンジはお好きかしら?」
「はい!」
「じゃあちょっと待っててね」
お母さんはハンドジューサーを使い、目の前でオレンジを絞ってくれる。かなり堅そうだけど涼しい顔をしていてすごい。
「どうぞ」
ワイングラスみたいなやつになみなみと注がれたオレンジジュースが芳醇な香りをしている。まさに絞りたてだ。
「いただきます」
一口飲むとオレンジ本来の苦みがあるけど、あとから甘さが追いかけてくる。鼻に抜ける豊かな香りに僕はうっとりと目を細めた。
「美味しい。いつも飲んでるのと全然違います」
「気に入ってもらえてよかった。唯斗が子どものころから好きで、よく作ってたの」
お母さんはグラスの中のオレンジジュースを懐かしそうに見つめている。
その目には唯斗くんと築いてきた思い出がたくさんあるのだろう。とても唯斗くんを大切にしているのが伝わってくる。
だからこそ唯斗くんのことをちゃんと伝えなくちゃ。
僕は居住まいを正した。
「唯斗くんがモデルだって聞きました」
お母さんは驚いたように目を見開いた。
「でも唯斗くんは芸能人だからって威張ることなく、仲良くしてくれました」
唯斗くんはみんなにやさしかった。
頼まれれば勉強を教えてあげたり、文化祭を盛り上げるために王子様の恰好をしたり。
普通の高校生として、学校生活を楽しんでいた。
「唯斗くんと友だちになれたから、僕は自分の夢に一歩近づけたんです。だからその……」
うまく言葉にできないのがもどかしい。
漫画だったらうまく表現できるのかな。
僕ははっと思いだし、バックからスケッチブックを取り出した。
「学校での唯斗くんです。よかったらご覧になってください」
僕はお母さんにスケッチブックを渡した。一枚一枚丁寧にページを捲り、お母さんは眩しそうに目を細めている。
「唯斗はこんないい顔してたのね」
「体育祭のときすごかったですよ! 野球部のエースを抜いて一位になって、あと海岸掃除のとき寮のおばちゃんたちから帽子とか借りてて。ほら、これです」
走っている姿や海岸掃除のときのへんてこな恰好をしている唯斗くんがページいっぱいに描いてある。
唯斗くんに内緒で描き溜めていたものだ。
お母さんは愛おしそうにページを撫でている。
「いまの学校がすごく楽しいのね」
「だと思います」
唯斗くんが学校を生き生きと過ごしていると知ってもらえただろうか。
「二人でなに見てるの?」
お風呂から出てきた唯斗くんは、お母さんが持っているスケッチブックを覗いた。これは一度も見せたことがない、僕の秘蔵コレクションだ。
「だ、だめ! 唯斗くんは見ちゃだめ」
「これ全部俺でしょ? 見る権利はあるじゃん」
「これは違うの!」
「ちょっと見せてよ」
「あぁ!」
唯斗くんは僕の制止を無視して、お母さんからスケッチブックをひったくってしまった。
この一冊すべては唯斗くんしか描いていない。
唯斗くんは一枚ずつページを捲り、目尻を下げた。
「海岸掃除のとき、俺こんな恰好だったんだ」
「すごく似合ってたよ」
「この文化祭の王子はカッコ良く描きすぎ。ちょっと盛ってない?」
「もっとカッコよかったよ」
僕たちがスケッチブックを覗きながら話しているとお母さんはくすっと笑った。
「唯斗、学校楽しい?」
「楽しいよ」
「そっか……なら卒業まで頑張んなさい」
「うん」
「よかったね!」
僕は嬉しくて抱きつきそうになったけど、こぶしを握って耐えた。さすがに友だち同士で抱き合うのは変だよね。
お母さんは僕に頭を下げた。
「沢渡さん、このノート貰えるかしら?」
「写真もありますよ」
「これがいいの。唯斗のことを大切に思ってくださる人が描いてくれた絵だから」
僕のイラストを通して、唯斗くんが学校を楽しんでいるのを伝わってくれたようだ。
「はい」
「ありがとう、一生大切にするわ」
お母さんはしばらく嬉しそうにスケッチブックを眺めてくれていた。
しばらく三人でスケッチブックや写真を見返していると、「時間がない!」と背中を押され、僕は唯斗くんの部屋に押し込まれた。 床にはすでに布団が敷かれている。
唯斗くんは机の上の時計を見て、悲鳴をあげた。
「あぁ、もう十一時五十七分だ!」
「初詣行きたかったの?」
「じゃなくて、今日藍の誕生日でしょ?」
「あ」
唯斗くんに想いを伝えることばかり考えていたから、今日が何日という感覚がすっぽり抜けていた。
唯斗くんは布団の上で正座になったので、僕も向かい側に座ると、膝同士がちょこんと当たる。
「急だったからプレゼント用意できてないんだけど……誕生日おめでとう!」
「ありがとう」
「目瞑って」
「なんで?」
「いいから、時間なくなっちゃう!」
「わかったよ」
僕は言われるがまま瞼を閉じた。一体なにが始まるのだろうか。
ドキドキしていると唯斗くんの大きな手のひらが頰に添えられる。呼吸が肌に触れて擽ったい。
もしかしてーー
「まっ……んぅ」
僕が目を開くと同時に唇が触れた。睫毛の際までわかるほど唯斗くんの顔が近い。
一瞬だけ触れた唇が火傷したみたいにじんじんした。そっと指でなぞると甘さが咥内に広がってくる。
「誕生日おめでとう。藍と出会えてよかった」
こつんと額同士がぶつかる。唯斗くんのおでこが熱くて、このまま一つになってしまいそうだ。
僕の視線が唯斗くんの唇に固定される。桜色のきれいな唇と重なったんだという実感がじわじわ込み上げた。
「わっわぁ〜ちゅうしちゃった」
「嫌だった?」
「嬉しくて……どうしよう。最高な誕生日プレゼントだよ」
「よかった」
背中に腕を回されてぎゅっと抱きしめてくれた。唯斗くんの心音が僕と同じくらい速い。きっと唯斗くんも僕と同じくらい緊張していたんだろう。
心地よい体温に欠伸を噛み殺すと、唯斗くんはクツクツと笑い声を漏らした。
「長時間移動したし、疲れたよね? もう寝よっか」
「うん。もうちょっと話したかったけど」
「また明日もいるよ」
「そうだね」
僕がうつらうつらしていると唯斗くんが布団に寝かせてくれた。なぜかするりと猫のように僕の隣に潜り込んでくる。
「なんで入ってくるの」
「だって寮のベッドは狭いから二人は無理じゃん。ちょっとだけ」
「ふふっ、唯斗くんは甘えん坊さんかな?」
「そうかも。お兄ちゃん、甘やかして〜」
唯斗くんの頭をぐりぐりと押しつけられる。撫でろと要求する様が可愛い。
僕は触り心地のいい髪を撫でながら目を瞑った。
「唯斗くんの髪、サラサラでいい匂いがする」
「今夜は藍も同じだよ」
「そう……だね」
もう眠くて仕方がない。
意識が落ちていきそうになる直前に瞼に柔らかいものが触れた気がした。