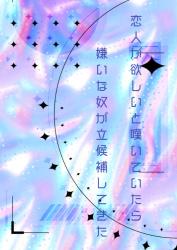夏休みが明けるとあっという間に文化祭が始まった。
海南高校は、スポーツ強豪ということもあり、毎年全国から来場者が来てくれるので結構盛り上がる。
僕たち二年四組は「王子様喫茶店」をやることになった。唯斗くんを始めとしたイケメンに王子様のコスプレをさせて、お客さんに給仕するのだ。
喫茶店らしくメニューはホットケーキとアイス、飲み物は紅茶とコーヒーに絞っている。
文化祭当日、衣装に着替えた給仕係がぞくぞくと教室に入ってきて、教室がいっきに華やいだ。
唯斗くんは一目散に僕の方に来てくれて、「どう?」とくるりと回ってくれる。
「ふぁ〜かっこいい」
「変じゃない?」
「完璧。どこからどう見ても王子様だよ」
「よかった」
唯斗くんがふわりと笑うと埃っぽい教室が薔薇の香りに変わるから不思議だ。
唯斗くんは真っ白い軍服みたいなジャケットとスラックスで、至るところに金糸で刺繍されている。動くたびに肩章が揺れた。
髪型も後ろに撫でつけられ、毛先をちょっとだけ巻いている。
誰が見ても二次元から飛び出してきた王子様だ。
衣装を手がけた演劇部の子が、唯斗くんを見上げて嬉しそうに目尻を下げた。
「宇梶くんはカッコいいし、スタイルもいいからつい凝っちゃったよ」
「ありがとう。動きやすいし助かるよ」
唯斗くんにお礼を言われて、演劇部の子が頰を赤く染めている。男子も惑わすイケメン、恐ろしい。
「開店するぞ」
開場を知らせるチャイムが鳴り、文化祭実行委員の子が声を張り上げる。みんなそれぞれの持ち場に散らばった。
僕は教室の一角をキッチンにして、そこでホットケーキを焼く係を任されている。所謂裏方だ。
僕が急いで暗幕で仕切られた裏に行こうとすると唯斗くんに呼び止められた。
「当番が終わったら一緒に回ろうね」
「もちろん。王子様頑張ってね」
「頼まれたからにはやり切るよ」
唯斗くんが親指を立てたので、僕も同じポーズを返した。
洋画のワンシーンみたいに息ぴったりである。
唯斗くんが乗り気でよかった。
僕もホットケーキを焦がさないようにしようと気合いが入る。
「王子様喫茶店」は瞬く間に人気になり、廊下に長蛇の列ができている。列に並んでいるのは同世代の女子高生ばかりだ。
来場者は多いとはいえ、今日は生憎の雨である。海南高までのアクセスの悪いから客足が減ると踏んでたけど、想像以上に大盛況で交代して休憩をとる暇すらない。
クラス三十人が一丸となって捌いている。
だが昼過ぎあたりから様子が変わった。
「はいっ、ホットケーキ三枚ね」
僕がホットケーキののった紙皿をカウンターに置くが、給仕係の王子様が誰一人来ない。そのせいでカウンターには窮屈そうに紙皿が並んでいた。
「外なにやってんだ?」
「どうしたんだろうね」
同じく裏方のシンタが首を傾げている。飲み物のカウンターにも紙コップが並びすぎて、置き場がない。
注文も入らなくなり、僕たちはホットケーキを追加で焼いていいのかわからなくなってきた。
「教室見てくるね」
「頼む」
僕はシンタに頷き返し、暗幕を潜った。
「おねがーい、写真撮って」
「困ります」
「いいじゃん! インスタにはあげないし」
唯斗くんを始めとした王子様たちが、女子高生たちに囲まれ写真を強請られていた。
プライバシーの関係で校内の写真撮影は禁止されている。そのことはパンフレットや学校のホームページにも記載され、校門の前にもポスターが貼ってあるくらい周知されているはずだ。
彼女たちはわかっているだろうに、唯斗くんたちをどうしても残しておきたいのだろう。
女の子を無下にすることもできず、唯斗くんたちは途方に暮れていた。
受付から長蛇の列が見え、行列に並んでいる客からの不満の眼差しが突き刺さっている。
こういうときに限って担任は校内の見回りに出かけてしまった。
「どうしよう」
裏方の誰かを呼ぼうか。でも誰がいい? 文化祭実行委員の子も間に入ってるけど、全然聞き入れてないし。かといって僕が入っても事態がよくなるとは思えない。
僕がオロオロしていると、ピンクのインナーカラーの子が唯斗くんを指差した。
「てか、この人「かじゆー」じゃない?」
「えっ!」
「まじだ! 確かにかじゆー!!」
女の子たちは目を爛々と輝かせ、唯斗くんを「かじゆー」と親しげに呼んでいる。
教室中の注目が唯斗くんに集められ、彼の表情は可哀想なくらい引きつっていた。
唯斗くんにいつもの笑顔がなくなり、なにかに怯えているかのように肩が小刻みに震えている。
かじゆーがなにを示すのかわからない。でも唯斗くんが困っているのだけははっきりとわかった。
「あの、お客様!」
僕はいままでの人生の中で一番大きな声を張り上げると、みんなの視線が僕に向けられる。その顔が「なんだこいつ」と書いてあったけど負けじと前に一歩出た。
「学校の決まりで写真はだめですが、絵はどうですか? こんな感じなんですけど」
僕はスマホでいままで描いたイラストを見せた。
「みなさんと一緒にいるところを無料で描かせてもらいます。今日の思い出にいかがですか?」
最後は自信がなくてしどろもどろになってしまった。顔が熱い。女の子たちの視線をいくつも受けると背中を向けて逃げ出したくなる。
でも困っている唯斗くんを放っておくことはできない。
女の子たちはこしょこしょと相談し合い、「それならいいよ」と唯斗くんと話すときよりワントーン低く返してくれた。
「ありがとうございます! ここだと他のお客様の迷惑になるので端で。えっと……唯斗くんもそれでいい?」
僕が訊ねると唯斗くんは頷いてくれた。
思ったよりイラストを描くのが大盛況となり、これなら金を取ればよかったと文化祭実行委員の子に言われてしまった。
数十枚も描いたので手首が痛い。
最後は唯斗くんたち給仕係とではなく、友だち同士やカップルで来た客を描くただの似顔絵屋になっていたけど。
でもみんな喜んでくれたから結果オーライだろう。
「はぁ~疲れた」
似顔絵屋として店を盛り上げた功労者として後片付けは免除してもらえた。教室じゃ邪魔になるから僕は中庭のベンチに座っている。
これから後夜祭があるので、片付けが早く済んだクラスが体育館へと向かっていた。
来場者はみんな帰り、少しずついつもの空気が戻ろうとしている。
僕は炭酸を煽り、オレンジ色に染まった空を見上げた。どうやら雨は午前中で止んだらしい。
「こんなところにいたんだ」
「なにか急用?」
振り返ると制服姿の唯斗くんが中庭に入ってきた。僕が慌ててスマホを確認したが誰からも着信がきていない。
唯斗くんは左右に首を振った。
「さっきのお礼を言おうと思って」
「そんなこといいよ。結局断り切れなかったしさ」
「でもデフォルメっぽく描いてくれたでしょ? 言われなきゃ俺だとわからないよ」
「だといいんだけど」
彼女たちにはSNSには投稿しないでと訴えたけど、あまり納得してなさそうだった。
見回りから戻ってきた担任に事情を説明したら、「申し訳ない」と謝られてしまった。来年はもっと周知するよと約束もしてくれ、大事にはならなかったはずだ。
唯斗くんは僕の隣に座り、オレンジ色に染まる雲を眺めている。
その横顔がなんだか物悲し気で僕はじっと唯斗くんを見上げた。
しばらくしてから唯斗くんがゆっくりと口を開く。
「……俺、実はモデルなんだ」
「モデルって雑誌とかに出る人のこと?」
「そう。去年まで「初めての恋を始めました」っていう恋愛リアリティ番組にも出てた」
海岸掃除のとき、一部の男子が「はじ恋」の真似として海辺を走っていたのを思い出す。
確かモデルやインフルエンサーの高校生たちが旅行に出かけ、本物の愛を探すという趣旨の番組だった。
「えっ……唯斗くんって芸能人なの?」
「休業してるけどね」
空に固定されていた視線がふいに僕の方に向けられた。顔に影が入り、唯斗くんは殴られたかのように顔を歪めた。
「でもモデルとして全然人気でなくて、それで名前を売るために「はじ恋」に出演したんだ」
一つ一つ箱を開けて中身を確認するように、唯斗くんは言葉を慎重に選んでいるように感じる。
僕はただじっと黙って耳をすませた。
「女の子にやさしくして、笑顔を振りまいて、まるで好意があるように装って……俺ね、ゲイなんだ。だから女の子を好きになることなんてない。それでもそういう演技をしなくちゃいけない。すごいきつかった」
きんと耳の奥で高い金属音が鳴る。唯斗くんがゲイ? なにかの間違えなんじゃないか。
僕がじっと見つめると唯斗くんは困ったように眉をハの字にさせた。
「こんなこと急に言われたら困っちゃうよね」
「ビックリはしたけど」
「さらに驚かせちゃうこともあるんだけど、言ってもいい?」
「これ以上のものがあるの?」
唯斗くんは一度唇を湿らせた。
「番組の方針が辛くて落ちこんでたとき、一枚の絵に出会ったんだ」
唯斗くんの表情が柔らかくなる。大切な思い出なんだとすぐにわかった。
「男子高校生たちの一枚絵。ぎゅっと抱き合ってて幸せそうなやつ」
唯斗くんがスマホの待ち受け画面を見せてくれた。それは僕が初めてSNSで投稿した作品だ。
「嘘……」
「たまたま流れてきて、でもすぐに鍵付きになっちゃってさ。必死でパスワード解除したよ。ヒントは誕生日って書いてあったから一月一日から順にいれてさ」
くしゃっと笑う唯斗くんはそのときをとても楽しんでいたように明るい。
「まさか大晦日が誕生日だと思わなかったよ。解くのに一週間もかかった」
「なんか……ごめん」
「ううん。でもこれでいつでもサワリーマンの絵が見れると思うとすごく嬉しかった」
「ずっと見ててくれたの?」
「うん」
閲覧数一をカウントしていた人がいま目の前にいる。自分の中の熱量が膨張して、弾けそうなほど嬉しい。
僕の絵を見てくれていた世界にただ一人のファンが、転校してきて同室になるなんてどのくらいの可能性だろうか。
「藍が腐男子ってことにはすぐ気づいた。だってクローゼットの裏にBLアニメのポスター貼ったままなんだもん」
「あ」
部屋を取り繕うのに必死で、クローゼットの中は確認不足だった。最後のツメが甘いのがなんとも情けない。
でもそのお陰で唯斗くんと距離が縮まったのだ。
「俺がモデルってことも気づいてなかったでしょ」
「BL漫画しか読まないからね」
「東京じゃ、ちょっと歩いてるだけですぐ「かじゆー」だって追いかけ回されてばかりで、友だちと遊ぶこともできなかったよ」
「だから「逃げて来た」って言ってたんだね」
唯斗くんは山岸くんたちを見て、「夢を追いかけてきた人」と眩しそうにしていた。唯斗くんの立場からすれば自分を「夢を捨てた人」と卑下していたのだろう。
唯斗くんの目には周りが眩しく映っていたのかもしれない。
「こっちはみんな俺のこと知らなくて過ごしやすかった。自分が普通になれたみたいで、ずっと楽しかったよ」
「体育祭、海岸掃除、今日の文化祭とかいろんなことあったよね。唯斗くん、ずっと楽しそうだった」
ただ真面目だから行事に手を抜かないんだと思ってた。
でも唯斗くんの本音を聞いたいまは、参加できることが純粋に嬉しかったんだろう。
「……そんな俺の気持ちまでわかってくれるんだね」
「友だちだもん」
「そういうところがさぁ。もうね」
「どうしたの?」
唯斗くんの長い睫毛が伏せられる。泣くのを我慢しているように見えて、僕の胸がきつく絞られた雑巾みたいに苦しくなった。
「唯斗くん」
そっと肩に触れると唯斗くんが瞼を開けた。星空を詰め込んだような瞳が僕を射貫く。
「好きだよ」
「え」
「藍のことが、好き」
まっすぐ向けられた言葉に僕は心臓が止まってしまったのかと思った。ゆっくりと息を吐くと体内を巡る血潮が高速で動くのがわかる。
だから思考がどんどんクリアになった。
これは友だちに対する「好き」じゃないことだと。
「なにかの間違いじゃない?」
「俺が藍を好きな気持ちを疑わないでよ」
「だって……全然釣り合わないじゃん」
モデルで女の子たちから騒がれる唯斗くんとオタクで腐男子の僕では、傍から見てもギリギリ友人だと思ってもらえる程度だろう。
僕の返答に唯斗くんは首を傾げた。
「釣り合いって大事?」
「大事だよ」
「じゃあ藍に釣り合うようにするにはどうすればいい?」
「そうじゃなくて僕が唯斗くんと釣り合ってない」
「遠回しに振られてる?」
「いや、そういうわけじゃ」
「可能性があるってこと?」
「そういうのでもないんだけど」
「ごめん、困らせてるよね」
「……どう言えばいいのかわからない」
唯斗くんとは友だちで、恋愛的な意味の好意を持たれてるなんて思ってみなかった。それに僕は異性愛者だ。
あれほどBL漫画を読んできたのに、最適な返答がなにひとつ思い浮かばない。
唯斗くんの眼光が鋭くなる。
「考えて。俺とのことを」
「でも」
「こんなに押しが強くて引かれてるのもわかってる。でもこのまま諦めるなんてできない」
痛みを伴う声に僕は心臓を鷲掴みされたように息苦しくなった。
唯斗くんは必死に僕を求めてくれている。だけど荒れ狂う海を鎮めるように自分の中で折り合いをつけているのがわかった。
ガラス玉みたいなきれいな気持ちを無碍にすることなんてできない。
僕はちゃんと向き合わなくちゃいけないんだ。
「わかった。考えてみる」
「ありがとう」
そのとき笑ってくれた唯斗くんの顔がしばらく瞼の裏にこびりついていた。
唯斗くんと話しているうちに後夜祭は終わってしまい寮へ帰ると、玄関でちょうど山岸くんたち野球部とかち合った。
唯斗くんを認めると山岸くんはぱっと目を開ける。
「おー芸能人!」
からかいの籠もる言葉に唯斗くんの動きが止まったのがわかった。
でも山岸くんは気づいていない。唯斗くんを指さしてアスファルトにくっついたガムみたいな粘っこい笑みを浮かべている。
ぎりっと山岸くんを睨みつけるが、僕の目力に怯むはずもない。
山岸くんは僕を押しのけて唯斗くんと肩を組んだ。
「なんでモデルだって言ってくれなかったんだよ。そしたら自慢しまくったのに」
山岸くんは笑顔なのに言葉がどんどん鋭くなる。まるで遅効性の毒のように唯斗くんの心に染み込ませようとしていた。
こんな扱いをずっと受けるんじゃ東京から逃げ出したくなる。
きっと唯斗くんは同じように揶揄われて、辛い思いをしてきたのだろう。
胃が捻れるような怒りが僕のこぶしを震わせる。
なにも知らないくせに唯斗くんを傷つけるな。
どうして唯斗くんの肩書きだけを見て、彼の価値を決めつけてしまうのだろう。
僕が前に出ようとすると唯斗くんは片手で制した。大丈夫、と黒い瞳が語っている。
「自慢できるほど売れてないよ。それに「はじ恋」も最初に脱落しちゃったしさ」
「でも番組一イケメンって言われてたじゃん」
「それしか言うことないからだよ。他の子は表紙飾れる有名モデルだったり、ドラマに出演してるような子ばかりだからさ」
「あ〜確かにそうなのかも?」
「他になにも書けないからイケメン枠にされただけだよ。ダサイだろ」
唯斗くんはからっと笑うと山岸くんの顔が痛ましそうに変わる。揶揄ったつもりが、相手の予想外の反応に困っているのがわかった。
唯斗くんは自分を落としながら護ってきたのだろう。
そんな処世術が身についてしまうくらい、唯斗くんの味方がいなかったんだと透けて見えてしまったから、僕は泣きそうになった。
山岸くんと別れて部屋に戻ると「疲れた〜」と唯斗くんが珍しく制服のままベッドに突っ伏した。
「ずっとそうやって誤魔化してきたの?」
「そう。ダサイでしょ」
「唯斗くんはカッコいいよ。素敵だよ。どうして自分を貶めるようなことを言うの」
唯斗くんは困ったように笑った。そうしないといけなかったのはわかってる。
自分を護る術を知らない唯斗くんを悲しいと思った。
「あ~今日はさすがに疲れちゃったな。藍、着替えさせて」
「え!?」
まるで弟たちみたいに甘える姿に目を剥いた。
さっきまでちょっと落ち込んでませんでした?
でもちょっと可愛いかも。いやいや同い年の子を着替えさせるなんて変だろ。
僕が葛藤していると唯斗くんは声を出して笑った。
「なーんてね。ちゃんとやりますよ」
唯斗くんはベッドから起き上がり、仕切りになっているカーテンを閉めた。
風呂から戻ると唯斗くんはクラスメイトの部屋に行くと言い出した。
「どうして? 疲れてるなら休んだ方がいいよ」
「だってさすがに気まずいでしょ?」
「なにが? あっーー」
そこで僕はようやく唯斗くんから告白されたことを思い出した。山岸くんとのことがあったのですっかり忘れていたのだ。
確かに告白直後に二人っきりは気まずいかも。
僕の百面相で察したらしい唯斗くんは困ったように眉を寄せた。
「ね。今夜はあっちに泊めてもらう。点呼のときには帰って来るから」
「うん。ありがと」
唯斗くんは柔らかく笑み、スナック菓子を持って部屋を出て行った。
山岸くんとのことがあって落ち込んでいるだろうに、僕の気持ちを敏感に察してくれた唯斗くんはやっぱりやさしい。
僕は一人になり、ベッドの上で悶々と唯斗くんとのことを考えた。
唯斗くんの過去を知って衝撃を受けたけど、嫌いになるなんてことはない。むしろ知れたことが嬉しいとすら思っている。
でもこの感情は友だちだからなのか、好きな人に対する気持ちなのかわからない。
「僕は唯斗くんをどう思っているんだろう」
考えても考えても答えが出てこない。ぐるぐる同じところを回っているような気がする。
「こういうときは気分転換だな」
僕はタブレットの電源ボタンを押して、お絵かきアプリを立ち上げた。
幼馴染とのストーリーは無事にトーンまで終わっている。納得いく出来上がりになり、冬コミに受かれば本にできる。
でも転校生との話がなかなかうまくまとまらない。
僕はプロットを最初から見直した。
田舎の高校生である受けの元にイケメンの転校生がやって来る。隣の席になり、なにかと面倒を見ているうちに転校生のことが気になるという展開だ。
「でもこれって僕と唯斗くんの話だよね」
出会って、恋をして、付き合う。恋愛漫画もBL漫画も大筋は一緒だ。
「恋ってなんだろう」
数多な恋愛漫画を読んできたのでわかっているつもりでいたが、ちゃんと理解できてなかったんだろうな。
好かれて嬉しい。
でもそこから一歩友情から恋に方角が変わるには、なにかが決定的に足りない気がする。
それはなにか。
自分に問いかけても答えがみつからず、雲の中に手を入れて掻き混ぜているような手応えのなさだけが残った。
結局漫画のことを考えているつもりでも、唯斗くんのことを思い出してしまう。
頭を抱えて唸っているとスマホが鳴り、画面を見るとシンタからの電話だった。
「どうしたの?」
『あのあとどうなったのかなってな』
唯斗くんがかじゆーだと知られ、校内ではちょっとした騒ぎになっていた。でも文化祭の真っ最中だったせいか、いまのところ大事になっていない。週明けからどうなるかだ。
僕は山岸くんたちの話をすると「あいつら」とシンタは苦いものを食べたように低く唸った。
でも僕の一大事もある。少し濁して訊いてみようかな。
「あのさ……相談があるんだけど」
『とうとう宇梶に告白されたか』
「な、なんでわかるの!?」
『あいつ、隠すつもりなかったもんな。オレにめっちゃ牽制してくるし』
ケタケタと笑うシンタはなにもかもお見通しだったのだろう。めっちゃ面白かった、とどこかネタっぽくされる。
「どうして唯斗くんが僕を好きってわかったの?」
『そりゃ藍にだけ異常にやさしいからな。あと声のトーンが違う』
「全然気づかなかった」
『藍は昔からニブいもんな。で、どうするの?』
「どうすればいいと思う?」
『そんなこと自分で考えろよ』
シンタは呆れたように息を吐いた。同時にカチャカチャと音がするから、ゲームをしているのかもしれない。器用な男だ。
「好きってどんな気持ち?」
『おまえの本棚に溢れるほど答えは書いてあるだろ』
「わからないんだよ」
答えを知って頭では理解しても、実感を持てない。
友だちの好きと恋愛の好きはどう違うんだ。
僕は唯斗くんをどう思っているのだろう。
唯斗くんとどうなりたいんだろう。
シンタは答えがわからない生徒に飽きれるように息を吐いた。
『よく言うのは一緒にいると楽しいとか独り占めしたいとかじゃん?』
「確かによく見かけるかも」
『もっとよく考えてやれ。宇梶はいい奴だと思うぜ』
「僕もそう思う。だから気まずくなるのは嫌なんだ」
『嘘吐いてまで付き合おうとするなよ。それこそ宇梶が可哀想だ』
「うん」
鋭いシンタの指摘に内心ひやりとする。考えがまとまらなくても、付き合うしかないと思っていたからだ。
だって卒業まで同室なのに気まずいままあと一年半も過ごせるとは思えない。
でもそれは唯斗くんの気持ちを踏みにじることになる。
シンタはなおもカチャカチャと激しいボタン操作をしていた。
『オレから言えるのは、藍はもっと素直になればいいと思うよ』
「素直?」
『周りの目を気にしないで自分を優先するんだよ』
「かっこいい台詞」
『この前読んだ少年漫画に描いてあった』
「なんだよ、パクリじゃん」
『せっかく人が相談に乗ってやってるのに』
もう知らねえ、と一方的に切られてしまった。向こうからかけてきてくせに自分勝手な奴だ。
でも気にかけてくれたやさしさは充分に伝わる。
僕は温かくなったスマホを見下ろした。
「もっと素直に」
ぼそりと呟いた言葉は誰の耳に届くことなく消えていった。